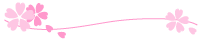
【拾壱】
私宛に再びさくらさんから手紙が届いた。
今度は呼び出しではなく、さくらさんが身請けされることになったというお知らせであった。手紙の節々から反省していない、ざまーみろ風な意味で伝わってきた。
彼女はやったことを反省しておらず、最後に捨てゼリフを投げつけたくて私宛に手紙を送りつけただけみたいだ。
したたかすぎる人だ…
私が夢見ていたヒロイン像はことごとく崩れ去り、今ではトラウマ化している。彼女は私を憎んでいるようだが、今では私も彼女を許せそうにない。
身請けされたとのことなので、どこかで会うかもしれないが…その時は恨み言の一つくらいぶつけてやりたい気分でもある。
…こうして、遊女さくらは途中退場することになった。まだあのドラマの時間軸は終わっていないというのに。
忠お兄様の運命の人は別の男性を選んで消えた。
……そしたら、私は……
私は気づいていた。抑え込んでいた恋心が日に日に大きくなって隠せなくなっていることを。
だけど伝えられずにいる。
私がマッチ役だから?
ううん。それもあったけど今は別の理由がある。
──戦争が始まるからだ。
これから日本は戦争に巻き込まれる。時代が変わるのだ。
彼が戦争へ出陣する前に自分の想いを伝えるべきか私は葛藤していた。
告白したら少しは楽になるかもしれない。…だけど戦争に向かう彼の重荷になるのではと思うと何も言い出せずにいた。
頻繁に遊びにいらしていた忠お兄様は忙しくされているようで、うちに立ち寄らなくなってしまわれた。
そして街でも町人の耳に戦争が始まるとの噂が流れ、街に不安な空気が流れた。
本土にいる人には影響が出ないと思われがちだが、これまで入荷していた輸入品が入ってこなくなって物価が上昇したりして、庶民の生活にも影響はあった。
当然のことながら、身内が軍関係の仕事をしている人は気が気じゃない。家で下宿している忠お兄様のお母様はそのうちの一人だ。
息子の武運長久を祈るおばさまから、千人針で祈念するべく、ひと針頼まれた。これはただのおまじないだと私もわかっていた。だけどおまじないに頼るしか出来ない。
私はこの戦争の行方を知っている。
だけどそれを止める術はない。
見送るしか出来ない私にはお守りに願いを込めるしか出来ないのだ。
──会いたい。
だけど忙しい彼の邪魔になってしまう。
会ってしまったら、行かないでと引き止めてしまうかもしれない。
勢いに任せて告白するかもしれない。
それならいっそ会わないほうがいいのかもしれない。生きるか死ぬか、日の本の運命が決まる戦争前に色恋ごとで彼を悩ませたくない
彼の邪魔になるくらいなら、最後まで会わないほうがいいのではないかと、敗走兵な私が囁いたのだ。
■□■
「最近あの人来ないですね」
吹雪さんの言葉に、ページを捲っていた私の指が止まった。
先程からページを捲っていたけど、私は内容を全く理解していなかった。目で文字を追っても、全然頭に入ってこないのだ。
「…今日の夕刻に出港でしたっけ。…戦争に行っちゃうんですね」
吹雪さんは庭池で飼っている鯉に餌をあげながら私に問いかけてくる。
そう、だから今日は忠お兄様のお母様はお休みを取って、息子の見送りに行かれたのだ。私にも一緒に来ないかと声を掛けてくださったけど、母子の別れの場面に私がいたら邪魔になるからと遠慮した。
……私はお兄様のお気持ちを考えてと言い訳をしながらも、実は情けなく彼に縋って行かないでと叫びそうになってしまいそうだったから行かなかったのだ。
今彼の顔を見たら間違いなくそうする。確実に。
それは彼の士気に関わる。もしかしたらあのドラマの流れと変わる可能性だって生まれる。怪我をしながら帰ってきた彼が、ここでは帰ってこなくなるかもしれない。
私は運命を変えてしまうのが今更になって恐ろしくなっていたんだ
「亜希子お嬢さん」
本のページを睨みつけていた私の目の前が陰った。私が顔を上げると、そこには吹雪さんが太陽の明かりを遮るかのように立ちふさがっていた。
「どうし」
「好きです」
吹雪さんの口から飛び出してきた言葉に、私は思考停止した。
「好きです、俺は亜希子お嬢さんをお慕いしています」
「えっ、え……」
告白……!?
え、吹雪さん、私と結婚して逆玉の輿に乗りたかったんじゃなくて、私のことを好きだったの?
私はほうけた顔で彼を見上げていた。
まさか、規格外のガリ勉女子な私を好きという男性が現れるとは思わず、呆然とするしかなかった。
吹雪さんの腕がこちらへ伸びてきて、私の身体をそっと包んだ。
「素直で優しくて勉強家のお嬢さんが俺は好きですよ。夢見がちなところも、お転婆なところもひっくるめてあなたをお慕いしております」
「ふ、吹雪さ…」
男性に抱きしめられ慣れていない私は固まってしまった。
それと同時に「違う」と思った。
先日助け出された私が忠お兄様に抱き上げられた時は、もっと逞しくて、体温も高くて……私が求めているのはこの腕じゃないと。
こんな時まで私はあの人を想うのか。
吹雪さんに失礼もいいところだ。
「あの……」
「わかってますよ。お嬢さんの心は決まっているのでしょう? 後悔してはいけませんよ」
亜希子お嬢さんらしくない。と吹雪さんは泣きそうな顔で苦笑いを浮かべていた。
彼は、恋敵に塩を送るのか。
まるで、ドラマの中の吹雪と同じだ。
好きな女性のために、心から血を流しながらも背中を押す彼。
吹雪さんは「ほらほら急いで」と言って、私を立たせると玄関まで送り届けた。
「いってらっしゃい。ちゃんと言いたいこと伝えてから帰ってくるんですよ」
彼はそう言って私の背中を押す。
私は後押しされて、歩いていたが、だんだん気が急いてきた。いつの間にか足は早歩きになり、小走りに変わった。
頬を伝う涙が止まらない。
私は馬鹿だ。
マッチ役だ、運命の相手がいる人だからって自分の気持ちから逃げて。
やっぱり私は敗走兵だ。
もう二度と会えなくなるかもしれないのに、わけのわからない言い訳をして、ただ自分が傷つきたくないだけ。
今伝えなきゃ。
いってらっしゃいって。
無事をお祈り申し上げますって。
…あなたをお慕いしておりますって。
鼻緒が足の股をこすって血が出ていそうだったが、私は構わずに走り続けた。
目的地にたどり着くと、港では立派な戦艦がずらりと並んでいた。これ全部、戦争に向かう戦艦なのか…と圧倒されるところだが、今はそんな事している場合じゃない。
戦へ向かう軍人らが家族と別れを惜しんでいる姿がちらほらあった。
今生の別れになるかもしれないと、涙を流す母親、日本のために戦い、錦を飾れと息子を叱咤激励する父親。はたまた幼い乳児を抱えたお嫁さんと離れがたそうにしている若い水兵の姿も。
私は辺りを見渡して彼の姿を探した。
早くしなきゃ。
もう時刻は夕刻。
彼が行ってしまう。
「──亜希ちゃん?」
その声に私はバッと振り返る。
私が見上げた先には、さっぱり髪が短くなった忠お兄様の姿があった。彼の顔色は悪く、緊張にこわばっているように窺える。
「お兄様っ!」
その姿を目に映した私は感情が昂ぶり、外だと言うのに彼の胸に飛び込んだ。
はしたないと眉をひそめられても構わない。絶対に後悔したくないのだ。
「ずっとずっとあなたが好きでした! あなたに近づきたくて認めてもらいたくて私は勉学に励んできたんです」
私の告白に案の定、忠お兄様はびっくりした顔をしている。
これをわかっていた。動揺させたくなかった。
だけどこのまま見送るなんて無理だ。
あなたの負担になるかもしれない。応えようとしなくてもいい。せめて私の想いをわかってほしい。
「勉強ばかりの私を賢い子だと褒めてくださって嬉しかった。あなたの笑顔が好きです、あなたの特別になりたい。…あなたは私を妹のように思われているかもしれません。ですけど私はっ」
私の言葉を封じるかのように、白い手袋をした忠お兄様の人差し指が私の唇の上に乗せられた。
「参った…先を越されちゃったな」
彼は照れくさそうに苦笑いを浮かべていた。
「亜希ちゃんに求婚しようと思った矢先に戦争が勃発してしまったから…君の負担にならぬよう何も言わずに行こうと思ったのだけど…」
私の目からひっきりなしに流れている涙を彼に拭われるが、拭っても拭っても止まりそうにない。
「…君を待たせることになるんだよ? もしかしたら俺は帰って来られないかもしれない」
その言葉に私の涙はブワッと溢れた。
この目にしっかり彼の顔を焼き付けておきたいのに、視界が滲んで歪んで見える。
「…それでも、待ってます。私にはあなたのいない人生は考えられない」
あなたはわかっていない。
私の恋心は着火されて燃え盛っているのだ。マッチ役を自称していた私は抑えていた恋心を自らの火種で更に大きくしてしまった。
私がどれだけあなたを愛しているのかわかってないのだろう。
「お兄様は私の唇を奪ったのです。責任を取って貰わねば困ります!」
私はあなた以外の男性に抱かれたくない。ワガママと言われても構わない。
それで嫁き遅れてオールドミスと後ろ指さされても、それが私の選択だから後悔しない。
私のワガママに、忠お兄様は泣きそうな顔をしていらした。「全く、仕方のない子だね」と私を窘めるように言ってるが、その言葉は震えていた。
お兄様は軍人だ。この日の本のために戦うという覚悟を持って行かれるのだ。
彼は私の左手を持ち上げると、手の甲に口づけを落とした。そして私の手を頬に押し当てると手のひらにもキスをされた。
忠お兄様の唇が当たった部分が熱く痺れる。自分の顔に一気に熱が集まったのがわかった。
「待ってて、必ず帰る。……帰ってきたら俺と夫婦になってほしい」
覚悟を決めた顔でお兄様は私に言った。
飾られた言葉じゃない。戦争へ旅立つ彼から言われたそれは遺言にも似ている。
たけど私も覚悟を決めねば。
「待ってます、ずっと待っていますから必ず帰ってきてください」
私達は周りの目を気にせず、抱き合った。
離れたくない。彼と一緒にいたい。
だけど彼は行かねばならない。
彼は運命の人とは結ばれなかった。
だけど戦争という運命だけは変わらなかった。
彼が軍艦に乗り込んで行き、出港する姿を私は涙を流して見送った。
私だけじゃない。見送りに来た人は皆そうしていた。日の丸の旗を振って、声が枯れるまで激励を送っている人もいた。
私は艦艇が見えなくなっても、そこに佇んでいた。
いつまでも、何年経っても彼を待ち続けると誓って。
|