故意に伏せられた紙の表側
「そこまで言うなら任せるが…」
先日のこと。突然火影室に現れた日向ヒアシの言葉に耳を傾けていた綱手は、難しい顔を浮かべてはいたが分かったというようにゆっくりと首を縦に振った。ヒアシが綱手に伝えたこと…それは白魚ハヤの右眼についてだった。彼女はまだ自身の置かれた"運命"の全てを知らない。それは綱手自ら伝えるはずであったが、ヒアシから伝えると直々に申し出にきていたのだった。
「それにしても誰から聞いたんだ?日暮硯コトメに過去を話したことを…」
「正直な所は感でした。最近抜忍も多いと聞いていましたし、その理由が封印の器である可能性があるなら話すのは今ではないかと…」
「…大丈夫なのか。はっきり言わせてもらうがアイツは日向のことを良く思ってないだろう。ヒナタとは仲が良いみたいだが…ちゃんと受け止められてもらえるか分からんぞ」
「それでも…ハヤを"守る"為とはいえ"嘘"を重ねていたのは私ですから」
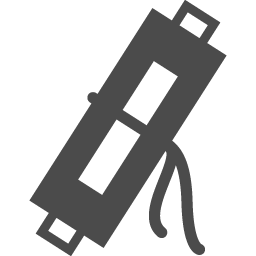
「…」
シンとする自室に篭ったまま布団に潜り込んで静かに風が吹く外の音を聞きながら私はぼんやりとしていた。時計を見るともう明け方の3時を過ぎていて、それでも目は冴えたまま眠れずにいる。
昨日、ネジに自分勝手な言葉を投げて病院から飛び出してしまった。折角お見舞いに行ったのに、…でも、私のせいではありませんよね…?だって…ネジまで私のことを好きだなんて……もちろん、私もネジと同じ気持ちだしネジの気持ちが嬉しくないわけじゃない。むしろ非常に嬉しいというのが本音だ。それでも日向という名をふと思い出すと、私はネジと一緒にいてはいけないのだと感じてしまう。何度も言うが日向一族は特有の血継限界を持つ一族で、ネジは一族でもずば抜けた天才児だ。それなのに私と一緒になること等あっていいわけがない。一時の幸せが訪れても、その幸せはきっと一瞬だから。
「……ネジ…」
愛しいと感じれば感じる程苦しい。じわりとこみ上げてくる涙を枕に押し付けると、ぎゅっと強く瞼を閉じた。
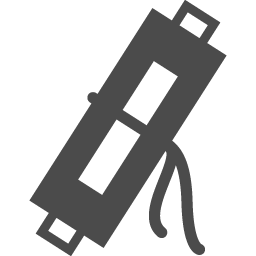
「おはよう、ハヤちゃん」
「おはようございます、ヒナちゃん」
「これから修行に…あれ…ハヤちゃん隈が」
結局一睡もできずにいつもの起きる時間にのそりと起き上がった私は、丁度ヒナちゃんの部屋の前で彼女と鉢合わせしていた。寝間着に身を包んだヒナちゃんはもちろん可愛いんだけど、それよりもなによりも眠気の方が優っているのは間違いない。
「どうしたの?珍しいね…眠れなかったの?」
「あ…はい。少し考え事をしていたので…」
「今日も任務、だよね?大丈夫…?」
「ええ。今日は確か里内任務だったと思いますし…心配してくれてありがとうございます」
「無理しないでね…?頑張りすぎは駄目だよ。あ、ごめんなさい、私今日は」
「今日は1人で修行したい気分なので気にしないで下さい」
心配そうに眉を寄せるヒナちゃんににこりと笑いかけると、いつものように修行へ向かった。日向一族の人と僅かにすれ違うのはほとんど玄関先である為に、行きや帰りに玄関へ向かう時はなるだけ急いでその場を離れている私は今日も相変わらず忙しないように靴を履いて扉を開ける。
「ハヤ」
「……?」
その瞬間、背後から威厳を持った人物の声が響いて足を止めた。呼び止める時はいつもいつも…この眼絡み。朝っぱらから嫌な仕事をしないといけないのか…なんて小さく溜息を吐いていると、私を呼び止めた人物・日向ヒアシ様は考えていた予想とは違う言葉を告げた。
「少し私と話しでもどうだ」
「…癒無眼のことでしたらすぐに対応いたします」
「いや、そういうことではない。…言い方を変える。お前と少し昔話がしたい。今から修行に行くつもりだったはずだ、時間はあるだろう」
「昔話…?」
「そうだ」
ヒアシ様の意図が全く読めなくて困惑するように眉間に皺を寄せて首を傾げた。それを見てフッとほんの少しだけ笑みを零した顔にネジの面影がよぎる。叔父、とはいえやはり似ている部分があるのは否めない。それでも私はこの人が苦手だった。しかし、ヒアシ様が私の前で笑みを零すのは珍しいことで、何か思惑でもあるのかと無意識に1歩後ろへ後ずさった。
「そろそろ己を知ってもいい頃だろう…ここでは話しにくいことだ。私の部屋に来なさい」
「…どういうことですか…?私のことは何も知らないと、仰っていたではないですか…」
そうなのだ。幼い頃、何故自分は実の親でもない日向一族に住んでいるのかとヒアシ様に何度か聞いたことがあった。が、ヒアシ様は「何も知らない、ただお前は日向にとって利用価値のある存在だから引き取った」と言うばかりで、もちろんそれを私も鵜呑みにしているのだ。何故それを何故今更…「己を知っていい頃」って…。私の発言にピクリと反応を示したヒアシ様は数秒の静止の後に何も言わず自室へと戻っていく。
私が何者かなんて…もうとっくに興味なんてないのに。それでも、ついて来いとでも言われているような背中に私の足はゆっくりと廊下を踏み出していた。
2014.05.18
prev || list || next
先日のこと。突然火影室に現れた日向ヒアシの言葉に耳を傾けていた綱手は、難しい顔を浮かべてはいたが分かったというようにゆっくりと首を縦に振った。ヒアシが綱手に伝えたこと…それは白魚ハヤの右眼についてだった。彼女はまだ自身の置かれた"運命"の全てを知らない。それは綱手自ら伝えるはずであったが、ヒアシから伝えると直々に申し出にきていたのだった。
「それにしても誰から聞いたんだ?日暮硯コトメに過去を話したことを…」
「正直な所は感でした。最近抜忍も多いと聞いていましたし、その理由が封印の器である可能性があるなら話すのは今ではないかと…」
「…大丈夫なのか。はっきり言わせてもらうがアイツは日向のことを良く思ってないだろう。ヒナタとは仲が良いみたいだが…ちゃんと受け止められてもらえるか分からんぞ」
「それでも…ハヤを"守る"為とはいえ"嘘"を重ねていたのは私ですから」
「…」
シンとする自室に篭ったまま布団に潜り込んで静かに風が吹く外の音を聞きながら私はぼんやりとしていた。時計を見るともう明け方の3時を過ぎていて、それでも目は冴えたまま眠れずにいる。
昨日、ネジに自分勝手な言葉を投げて病院から飛び出してしまった。折角お見舞いに行ったのに、…でも、私のせいではありませんよね…?だって…ネジまで私のことを好きだなんて……もちろん、私もネジと同じ気持ちだしネジの気持ちが嬉しくないわけじゃない。むしろ非常に嬉しいというのが本音だ。それでも日向という名をふと思い出すと、私はネジと一緒にいてはいけないのだと感じてしまう。何度も言うが日向一族は特有の血継限界を持つ一族で、ネジは一族でもずば抜けた天才児だ。それなのに私と一緒になること等あっていいわけがない。一時の幸せが訪れても、その幸せはきっと一瞬だから。
「……ネジ…」
愛しいと感じれば感じる程苦しい。じわりとこみ上げてくる涙を枕に押し付けると、ぎゅっと強く瞼を閉じた。
「おはよう、ハヤちゃん」
「おはようございます、ヒナちゃん」
「これから修行に…あれ…ハヤちゃん隈が」
結局一睡もできずにいつもの起きる時間にのそりと起き上がった私は、丁度ヒナちゃんの部屋の前で彼女と鉢合わせしていた。寝間着に身を包んだヒナちゃんはもちろん可愛いんだけど、それよりもなによりも眠気の方が優っているのは間違いない。
「どうしたの?珍しいね…眠れなかったの?」
「あ…はい。少し考え事をしていたので…」
「今日も任務、だよね?大丈夫…?」
「ええ。今日は確か里内任務だったと思いますし…心配してくれてありがとうございます」
「無理しないでね…?頑張りすぎは駄目だよ。あ、ごめんなさい、私今日は」
「今日は1人で修行したい気分なので気にしないで下さい」
心配そうに眉を寄せるヒナちゃんににこりと笑いかけると、いつものように修行へ向かった。日向一族の人と僅かにすれ違うのはほとんど玄関先である為に、行きや帰りに玄関へ向かう時はなるだけ急いでその場を離れている私は今日も相変わらず忙しないように靴を履いて扉を開ける。
「ハヤ」
「……?」
その瞬間、背後から威厳を持った人物の声が響いて足を止めた。呼び止める時はいつもいつも…この眼絡み。朝っぱらから嫌な仕事をしないといけないのか…なんて小さく溜息を吐いていると、私を呼び止めた人物・日向ヒアシ様は考えていた予想とは違う言葉を告げた。
「少し私と話しでもどうだ」
「…癒無眼のことでしたらすぐに対応いたします」
「いや、そういうことではない。…言い方を変える。お前と少し昔話がしたい。今から修行に行くつもりだったはずだ、時間はあるだろう」
「昔話…?」
「そうだ」
ヒアシ様の意図が全く読めなくて困惑するように眉間に皺を寄せて首を傾げた。それを見てフッとほんの少しだけ笑みを零した顔にネジの面影がよぎる。叔父、とはいえやはり似ている部分があるのは否めない。それでも私はこの人が苦手だった。しかし、ヒアシ様が私の前で笑みを零すのは珍しいことで、何か思惑でもあるのかと無意識に1歩後ろへ後ずさった。
「そろそろ己を知ってもいい頃だろう…ここでは話しにくいことだ。私の部屋に来なさい」
「…どういうことですか…?私のことは何も知らないと、仰っていたではないですか…」
そうなのだ。幼い頃、何故自分は実の親でもない日向一族に住んでいるのかとヒアシ様に何度か聞いたことがあった。が、ヒアシ様は「何も知らない、ただお前は日向にとって利用価値のある存在だから引き取った」と言うばかりで、もちろんそれを私も鵜呑みにしているのだ。何故それを何故今更…「己を知っていい頃」って…。私の発言にピクリと反応を示したヒアシ様は数秒の静止の後に何も言わず自室へと戻っていく。
私が何者かなんて…もうとっくに興味なんてないのに。それでも、ついて来いとでも言われているような背中に私の足はゆっくりと廊下を踏み出していた。
2014.05.18