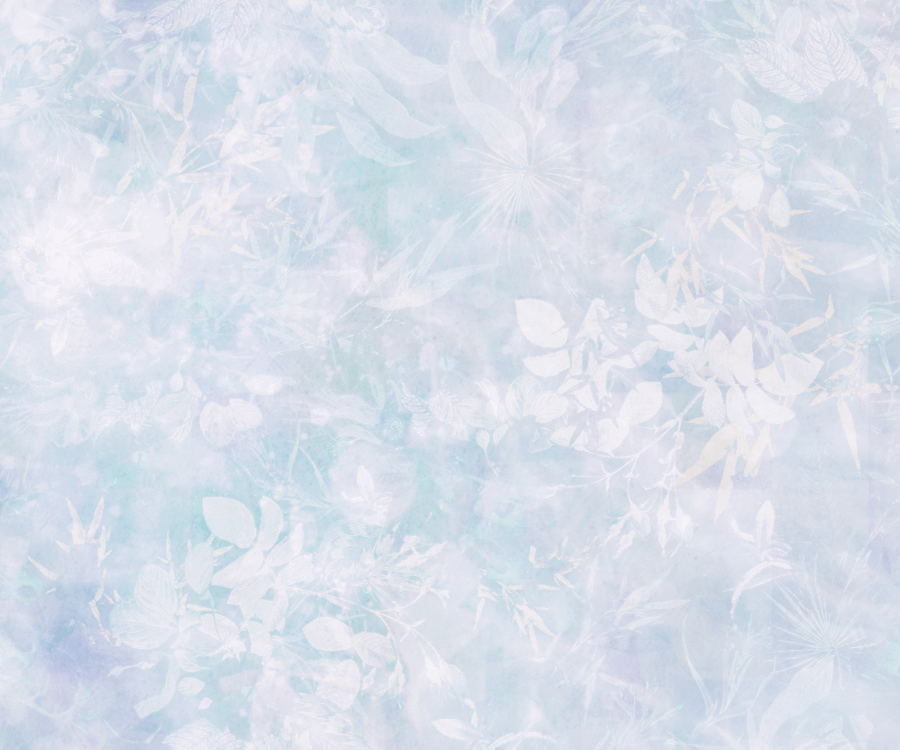春と戯れるきみ
「やっぱり自分でやるのは無理があったのでは……」
そう不安そうに呟いたなまえの声が部屋に響く。しかしひとりきりの空間では当然ながら返事などはなく、しんと静まり返っていた。白を基調としたキッチンに、製作途中の“それ”と山積みになった片付け待ちの器具たち。それらを見つめ、なまえはキッチンの真ん中で唸り声を上げながら腕を組んだ。
三月。大学生活も一年が過ぎようとして、再び新たな春が訪れた日本。すっかり大学にも慣れたなまえは、近ごろ空いた時間が出来ては難しそうな顔を浮かべ携帯を見つめていた。理由は、今月の中旬に訪れるとある人の誕生日のせい。せい、と言うと聞こえが悪いが、しかしなまえにはもう正解がわからず本当に困っていた。
「駄目だ……本当にわからない」
「なにが?」
「っ、うわあ! い、い、いつから……」
「え? 今来たばっかりだけど」
広い学食の端の方に座りながらぶつぶつとひとりごとを呟いていたなまえは近付いて来ていた気配に一切気付かず、突然隣から降ってきた声に椅子を揺らすほど驚いた。
「びっくりしたー……」
「随分と考え込んでたみたいだけどどうしたの?」
「ああうん、いや……」
「あ、もしかして彼氏だ。あのイケメンの」
高校生のときから付き合いがある彼女はなまえの事情をよく知る数少ない友人だ。現在なまえはオメガだと隠してはいないけれど、番の話はほとんどしたことがないし、ましてや相手のことなどは一切ない。容姿や性格もそうであるし、事情が事情なのでどこまで話していいのか分かりかねるからだ。その点彼女は卒業式に偶然白蘭と顔を合わせたことから相手についての話もしやすく(もちろんマフィアのことなどについては話していない)、相談に乗ってもらうことも多かった。
「実は、今月彼の誕生日があって」
「ほう」
「でもあの人、わたしと違って大人だし、欲しいものはなんでも自分で手に入れられるというか……あげるものが全く浮かばなくて」
「ちなみに何日なの?」
「十四」
「ホワイトデーだ」
「うん、そう」
去年は誕生日のことを全く知らず、後日白蘭本人から聞かされたなまえはショックでしばらく立ち直れなかった。そのときは二人で過ごした時間もまだ浅く、また白蘭が日本の観光地を巡りたいと言ったことから“案内すること”をプレゼントとして(無理やり白蘭が納得させた)、様々なところへ出かけた。近所の商店街に行くこともあれば、水族館やプラネタリウム、また遠くの地まで旅行に行くことも。しかしそういうときは基本的に白蘭が全てを払っていたし、また現地で小さなものから大きなものまで本当に様々な贈り物をされた。これじゃあお祝いどころか結局自分だけがいい思いをしているだけなのでは? となまえは何度も白蘭に言っているのだが、イタリアではこれが普通と返されてしまえば、文化のわからないなまえはなにも言えなくなってしまったのだった。
そして先月、バレンタインデーもそうだ。日本であれば女性からチョコレートを贈るのが主流であるが、イタリアにはそのような文化はなく、恋人と共に時間を過ごし、贈り物も男性から渡すことの方が多い。もちろんそれは白蘭も例外ではなく、チョコレート(有名なチョコレートショップで購入したもの)を用意したなまえに、彼は愛の花言葉がつまった春の花束を贈ったのだった。
うんうんと唸るなまえに友人はしばし考え込むように宙を見上げると、「いいこと思いついた!」とパッと顔を明るくさせた。そしてそれをなまえに告げ、「こういう方が意外と喜ばれるかもよ」と肩を叩いた。そのときは確かになまえも納得したのだが、実際用意してみると本当にこれで大丈夫だろうかと不安でいっぱいになった。
◇◇◇
やってきた当日。三月十四日。この日、白蘭は月に何度か行われているユニたちとの定期連絡のため、午後四時ごろまで帰って来ないということは把握済みである。白蘭を送り出してから準備を始め午後二時すぎ、ようやく完成が見えてきたところ。しかしその出来栄えに、なまえは思わず不安の声を漏らした。
「やっぱり買ってきた方がよかったんじゃ……」
友人の言う“いいこと”とは、自分で誕生日ケーキを作ってみる、ということだった。それも白蘭の好物であるマシュマロを乗せて。なまえは普段料理は作っているものの、お菓子はほとんど作ったことがないため買ってきたものを食べたり贈ったりすることが多かった。先日のバレンタインもそう。しかし友人は「だからこそ手作りがいいんだよ」となまえの背中を押した。確かに料理を作ったときもいつも喜んでくれるし、よく強請られるが、お菓子……ましてやケーキだなんて一度も作ったことがなかったので不安でしょうがなかった。
そして案の定、完成間近ではあるケーキはなんとも言えない出来だった。初めてにしては、まあ……悪くない、くらい。しかしよく見れば形は少し歪だし、側面もそれほど綺麗ではないし。見れば見るほど不安になってくる。
それとは別に夕食の準備もしておいた。日本の家庭料理、ホームパーティで出てくるようなメニューではあるが、以前白蘭が美味しいと言っていたのでこちらは問題ないだろう。あとは目の前にあるこのケーキを仕上げて、部屋の準備をして……。そう思っていた矢先だ。ガチャン、と玄関扉が開いた音がしたのは。
「あれ? なんか甘い匂いがする」
廊下を歩きながらそう呟いた白蘭の声がして、なまえは慌ててそちらの方へ向かった。大抵定期連絡のときは時間通りに帰ってくるはずなのに、今日は一時間以上も早かった。
「びゃ、白蘭!」
「わ、エプロン着けてる。なあにー? なんかいい匂いするー」
「ああ待って、まだ入っちゃだめ」
「えーなんでよ、僕には内緒なの?」
「まだ、内緒……」
後ろ手に閉めたリビングの扉の前に立ち、白蘭の侵入を防ぐ。しかし彼は必死に足止めするなまえを見下ろしてから、にっこりと笑みを浮かべてその体を抱き上げた。
「でも入りまーす」
「あああ!」
抵抗も虚しく呆気なく突破される。白蘭はなまえを片腕で抱いたままリビングへと入り、甘い匂いのする方へ誘われるように奥へと進んで行った。そうしてキッチンの前に辿り着き、ぴたりと足を止める。
「わー! ケーキだ!」
「うう、まだ完成してないのに……」
「作ったの?」
「うん……」
キッチンの作業台に置かれた白いケーキ。その大きなフォルムの上には切りそろえられたフルーツとマシュマロが半分ほど乗せられていて、作業途中だということがわかる。
子供のように抱きかかえられたままについては、なまえももう慣れてしまったせいかなにも言わなかった。表情を明るくさせて白蘭がきょろきょろと左右からケーキを覗く。そんなにたくさん見られると不格好なのが余計に恥ずかしくなり、なまえは最後の足掻きで目元に手をかざしてみた。
「見えないよー」
「綺麗じゃないから、だめ」
「えー、そんなことないのに。僕のために作ってくれたんでしょ? ありがとう」
そっと手のひらの奥からなまえを覗く白蘭が微笑む。その甘ったるい声で言われると、なまえはどうしても逆らえなかった。視線が絡むと、やさしくキスをされる。二人の関係は、あの夢で見たものよりもずっとずっと良好だった。
◇◇◇
なんでこんなことになったんだっけ。と、なまえは熱に浮かされた朧気な意識のなかでそう思った。ふわふわと心地よい感覚と甘く痺れるような刺激に揺られながら、目の前で何度も自分にキスを落とす白い男を見やる。
「あ、う……びゃく、らん」
「気持ちいい? 蕩けた顔してる」
白蘭の前でケーキを完成させてから、先に少しだけ食べようということになって……。なまえはひとつずつ最初から記憶をなぞるように、これまでの経緯を思い返した。美味しいと言ってケーキを食べてくれて、それで上に乗っていたマシュマロも口に放り込んで。ああ、そうだ。「なまえチャンもはい、あーん」と、白蘭が自分の口のなかにフルーツやマシュマロを放り込んだところがきっかけだった。クリームがついた唇を舐めて。それから長い長いキスに変わっていって。気がついたら現在のようにソファに押し倒されながらキスの雨を降らされて、大きな手に頬や首、腕、腰、足まで、様々な場所をたくさん撫でられているのだった。
エプロンはいつの間にか取り外されていて、服も少しだけはだけていた。白蘭は快感に震えるなまえを見下ろしながら、口角を緩ませる。その唇はなまえの唾液でわずかに艶めいていた。
「あ……」
「まだキスしたい?」
「……したい」
すると白蘭は仕方ないといったように「僕の番は本当にかわいいね」と言って顔を寄せた。鼻先がぶつかって、ラベンダー色の瞳がなまえを射抜く。未来では恐ろしさまで感じていたはずなのに、今は少しもそんな感情は湧かなかった。むしろ愛おしくて、もっと見ていて欲しいと思う。引き寄せられるように腕を伸ばせば、白蘭もまた唇を重ねて、ぬるりと舌を這わせた。
「んっ、ぁ……」
白蘭が以前なまえのキスを甘いと思ったように、またなまえも白蘭のキスを甘いと感じていた。それはケーキを食べたせいというわけではなく、もう何度もそう思うのだ。あつい舌が口内を回って、吸い付く。その度に、なまえはどんどん白蘭が欲しくなった。
「このままここでするか、ベッド行くか、どうする?」
唇を離した白蘭が耳元で囁く。しない、という選択肢はないらしい。しかし彼もまたわずかに呼吸を乱していて、あつい視線をなまえに送っていた。
「ここで、する」
吐息混じりで呟く。その瞬間、がぶりと首元に噛みつかれ、白蘭の大きな手が素肌の上をなぞった。