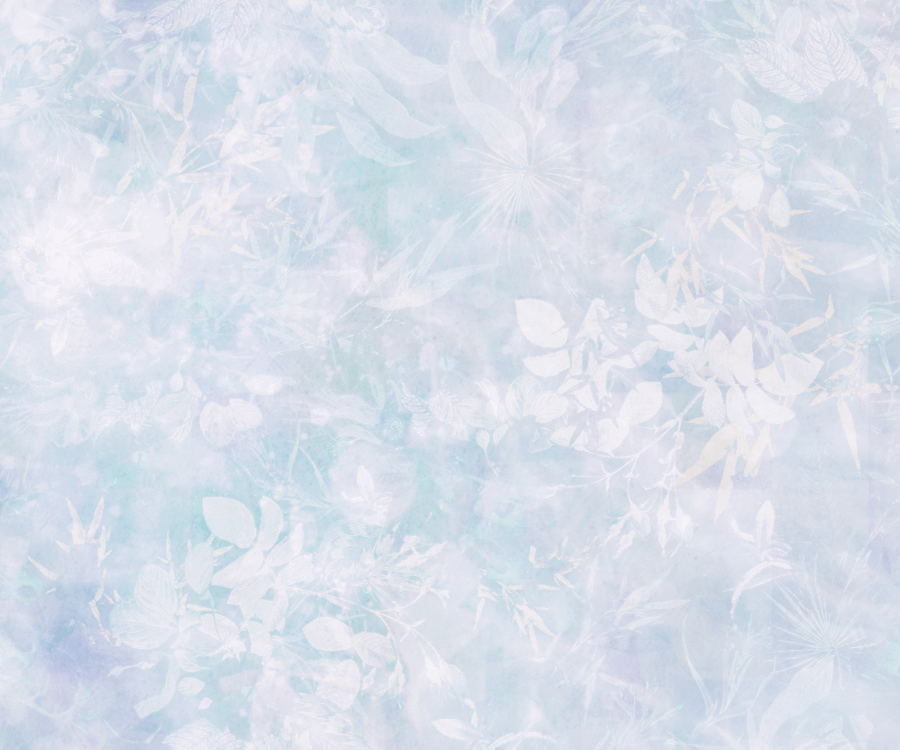ユーデモニクスの亡霊
あの人がいないヒートを何度過ごしただろう。季節は移り行き、秋から冬へ、そして年を越して冬から春へと変わろうとしている。1月と2月は酷く冷たい冬を過ごし、無事受験も終えて、希望の大学へと進学出来ることが決まった。残るは卒業式のみ。
「こうして登校するのも残り数日だね〜」
「卒業旅行とかしたくない?」
「あ、それいい!」
今日から3月が始まり、授業のない私達が登校するのは残り僅かな日数だけである。友人達も希望の進路に進めたようで、安心して私達はこの残り少ない高校生活を送っていた。
「お、おいこの匂い」
「……まさか」
朝のホームルームが終わり、卒業式の予行練習のために体育館へ向かう途中、クラスメイトが何やらざわざわと騒ぎ始める。私にはクラスメイトが言う“匂い”は全く分からなかったが、どうやら友人達もその異様な匂いに気付いたらしい。
「もしかしてこれがそうなの?」
「え、誰?!」
オメガだ、と言ったクラスメイトの言葉に私は一気に血の気が引いたような気がした。まさか、いやそんな筈はない。ヒートまでは暫く日数もあるし、内側から燃え上がるような熱も、体のだるさも今は全く感じていない。それに、隣にいる友人達も私の方は一度だって見ていない。ならば、オメガというのは私ではなく他の誰か。
アルファだと公言していたクラスメイトがその場で蹲る。周りにいた違うクラスの人達も数名が同じようにしゃがみ込んだり、胸元を押さえて苦しそうにしている人が数名。きっと、あの人達はアルファだ。そして、私には分からないその香りに惹かれるようにして、彼等は真っ直ぐにある一人の人物へと向かっていく。
「いや……いやだ……!」
叫んだのはクラスメイトの男の子だった。彼はうなじを噛まれないように、首元に両手を添えている。まさか彼がオメガだと誰も思っていなかったようで、私を含めたクラスメイトは皆、驚いたように彼を見た。
「え、あいつが……?」
「……知らなかった」
恐怖で腰を抜かしてしまったのか、その男の子はその場で座り込むと、迫り来るアルファに怯え、助けを求める。だが、周りのクラスメイトは突然の出来事に誰一人として動けずに、ただ目の前で起きている出来事を遠巻きに見ているだけ。
彼の恐怖を私は知っている。そう思ったらいても立ってもいられずに、私は彼の元へと駆け出した。
「え?!なまえ?!」
友人達も私が走り出したことに驚きを隠せず、私の名を呼び叫ぶ。無我夢中で走って、彼の手を取った。
「こっち!」
「君は……」
「早く!」
何となく私は前に踏み出せている気がした。あの嫌いな男に言われた言葉を思い出し、あの星空の下であの人が漏らした本音を思い出して、何ヶ月もの日々を過ごして、私は一つ決めたことがある。
「何処に行くの?!」
「とりあえず保健室に!」
勢いよく扉を開ければ、中に居た保健医は驚いたように体を飛び上がらせる。どうみても普通じゃない私達の様子と、彼から香る微かな匂いに、ベータである保健医も事情を察したようで、棚の奥から抑制剤を探し出した。
「あの、みょうじさんは大丈夫なの?その、俺の匂い……」
「大丈夫。私もオメガだから」
その言葉にクラスメイトの男の子は目を見開く。校内でもその事を知る人物はここに居る保健医と、担任の先生のみ。私は初めて自分の口からオメガであることを告げたが、不思議と気持ちが少しだけ軽くなったような気がした。
◇◇◇
あの男の子は抑制剤を服用した後、直ぐに落ち着いたようで、そのまま自宅へと帰ったらしい。クラスメイトはオメガであった彼のことが気になっていたようだが、私は何も答えなかった。
「じゃあ卒業旅行計画の続きはメッセージで!」
受験も終えた私達は、少し前と同じように放課後にファストフード店に寄って卒業旅行の計画を立てた。友人達もあの男の子のことが気になっていたようだが、クラスメイトに何一つ答えなかった私を見て、聞くことを諦めたようだった。
3月であれど、春になるのはまだ少し先のようで、空気はまだ冷たく、暗くなるのも早い。このまま高校生活が終わるのかと、何処か寂しさを感じながら帰路に着けば、突然背後から誰かに腕を引かれる。
「えっ?」
振り向く間もなく、背後から襲いかかった腕は私の口元へと回り、そのまま押さえ込まれるように口元に何かを押し付けた。咄嗟に息を吸ってはいけないと頭の中で警報が鳴っても、時は既に遅く、私は意識が次第に薄れていくのを感じた。
◇◇◇
初めに見えたのは、暗い部屋に明かりのついていないライトが天井に一つ。どうやら両手足を縛られているらしく身動きはとれないが、幸い視界は何も遮られていないため、首を動かし辺りを確認する。窓が一つあり、そこから星空が見えたところ、連れ去られてそこまで時間が経っていないか、はたまた数日間眠っていたか。
「お目覚めか」
扉が開く音がすれば、やや大柄な中年の男が口を開く。状況が分からぬまま黙って相手を見つめていると、男は私の胸元部分の服を掴み上げ、ギラギラとした目で私を見た。
「お前に罪は無いがボンゴレにちょっとばかり用があってな」
「え?」
「ボンゴレ10代目と関わりがあることは知ってんだ」
ということは目の前にいる男もマフィアということなのだろうか。服を掴む手から解放されると、私は少しずつ後ろへと下がる。そんな私を嘲笑うかのように笑みを零しながら、男は見慣れぬ色の液体が入った瓶を取り出した。
「お前、オメガなんだってなあ」
「え……どうして」
もしやと思い、男が手にする瓶が途端に恐ろしい物だと分かると、自然と体が震える。きっとあれはヒートの誘発剤だ。逃げようとしても手足を縛られている為、中々思うように動くことが出来ずに必死に這うようにして動き回ることしか出来ない。
高笑いをしながら男が私を追って腕を掴む。抵抗さえも出来ぬまま、男は瓶の蓋を開け、私の口に無理矢理押し込む。必死に口内に入る液体を飲み込まないように我慢するが、次々に注がれるそれに私は意図せずに少しだけ飲み込んでしまった。
「ぐ……がはっ……げほっ、」
「吐き出すんじゃねえ!!」
床に投げ捨てられ、咳込みながらも、いつか来るであろう内側からの熱に今から恐れを感じながら必死に耐える。お願いだから広がらないで。
願いも虚しく、次第に燃え上がる筈のない熱が徐々に広がっていくのを感じる。変わり始めた私の反応に、男はニヤリと口角を上げた。
すると部屋に数人の男達が入ってくる。誘発剤のせいで敏感になった私の鼻は、瞬時に数人の男の中にアルファが混じっていることに気付く。目の前の男と同じように、ニヤニヤと笑みを浮かべて私を囲むようにして立ち塞がると、その中の一人のアルファの男が私を抱きかかえた。
「やめて!離して!!」
部屋の片隅にある小さなベッドに男は私を降ろした。これから始まる悪夢を想像して、私は叫び声を上げる。今ならあの人が出てきた夢が幸福のように感じられる。オメガとして一番最悪の結末が訪れようとしている事に私は震えが止まらない。
「ひっ………やだ……やっ……」
縛られていた足枷を解かれる。その際、少し肌に指が触れられただけで、私は嫌でも体が反応してしまう。
手枷はそのままに、アルファの男が私の服を脱がそうと、スカートに触れる。嫌だと泣き叫んでも、目の前の男達は寧ろ嬉しそうにしているだけ。
内側からの熱はどんどん大きくなっていき、息が上がっていくのが分かる。そして目の前のアルファもそれに誘発されるように、同じく息が上がっていった。それでも私が求めているのはあの人だけ。あの人しか考えられないし、それ以外は要らないの。
「やだ……お願い……」
泣きじゃくったって意味が無いことは分かってる。それでもこの最悪な状況を誰でもいいから打破して欲しかった。
刹那、建物に衝撃が走る。何事かと全員が慌ただしく視線を彷徨わせると、部屋の扉が勢いよく開けられ、目の前の男達の仲間であろう男が叫んだ。
「ボス!!ボンゴレが!!」
「何だと?!彼奴らに教えたのは向こうであろう?!」
「それが同時に襲撃されまして!」
中年の男が舌打ちをする。どうやらこの男がボスらしい。
すると激しい音が鳴り響いたかと思えば、見知らぬ少年達と共にリボーンくんが現れる。私はその姿を捉えただけでほっとして、再び涙が零れた。
「おっと、忘れんなよ?!」
だが近くにいた別の男が私の腕を掴めば、何処から取り出したか分からないナイフを私の首筋に当てる。目の前の少年達は武器を構えて身動きが取れずにいた。誘発剤のせいで火照る体と、殺される恐怖が混ざり合って、訳もわからず固く目を瞑る。
しかし私は微かに香るあの匂いに気付いて、思わず目を見開いた。そんな筈無いと思っていても、体はあの人の香りだと確信している。何処からだと視線を彷徨わせれば、背後にある窓ガラスが割れる音が響き、何かが私を捉えていた男の腕を貫いたのが分かった。
「おせーぞ!!」
少年の一人が叫んだ。恐る恐る振り返ると、見えたのはやはりあの夢の中の人。どうして。
「あいつ……」
リボーンくんが小さく声を漏らしながら眉を顰めたのが分かった。それもそうだろう、夢の中のあの人の視線は恐怖で震えそうなほど冷たく、私の背後にいる男を真っ直ぐと射抜いているのだから。
あの人は一瞬で私達の前まで移動すると、あっという間に男から私を奪った。安心出来る体温と香りにほっとしたが、あの人は私を押さえつけていた男に近付くと容赦なく攻撃を放った。既に腕からは血が溢れ、額からも零れるその赤色に私は背筋がぞっとした。
「ま、待って……」
正直もう目の前から香る匂いに頭がくらくらとしてきているが、それよりも目の前で起きたこの悲惨な現状が私の理性を引き戻す。
無言のまま私に視線を向けたあの人は、何故止めるのだと言わんばかりの表情をしていた。
「だめ……っ」
私の声は届いていないのか、あの人は再び男に近付いて振りかぶる。今度こそあの男は殺されてしまうと、恐怖に怯えると、あの人と男の間に銃弾が飛び込んだ。
「っ……?!」
「白蘭。最初に言ったことを忘れんなよ」
声の主はリボーンくんだった。まさか彼が今の銃弾を放ったというのか。あの人はその言葉で我に返ったような表情を見せると、小さく舌打ちをしてから「あとはお願い」と呟いて、私を抱いて瞬く間に宙へと浮いた。