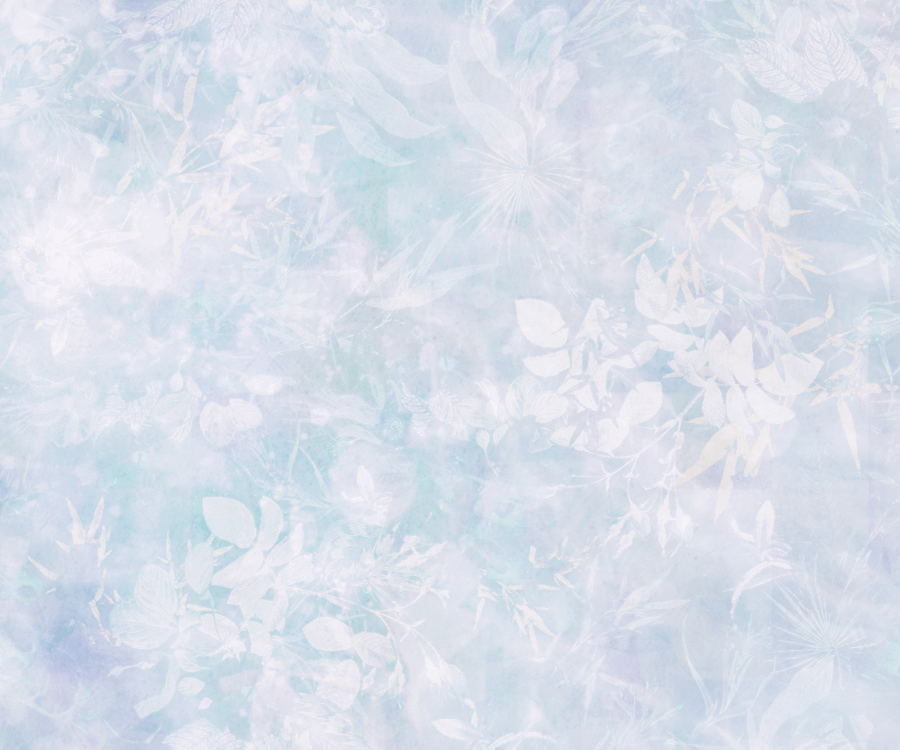夢と夢と夢から覚めた夢
誰かに撫でられている気がした。夢の中のあの人もたまにこんな風に優しく撫でてくれて、その瞬間だけは隣にいることが心地よくて、この暖かさがずっと続けばいいのにと、何度思ったことだろう。
「目が覚めましたか」
瞼を何度か瞬かせ、私はゆっくりと声の主の方へ顔を向けた。
「ろくどう、むくろ……」
「君は本当に阿呆ですね」
そう思っても彼は約束を守り、私を守ってくれたのだから、甘んじて彼の言葉を受け止めるべきであろう。
抑制剤のお陰で体の熱は既に治まっている。上体を起こしてから、彼の言葉に何も言えずにいる私を見かねた六道骸は溜息をついた。
「言ったでしょう、正夢になると」
「うん……言ってた」
「同じことを繰り返したいんですか?」
「……ごめんなさい」
「謝って欲しい訳では無い。君のその捻くれた性格をどうにかして欲しいだけです」
そう言われても仕方が無いだろう。自分でさえ、自分のことが分からない。分からないまま行動するから、同じことを繰り返す。
あの夢の中の私のように、私は自分が怖くなった。ヒート時にあの人を目の前にしてしまえば、簡単に理性など何処かへと飛んで、欲を求める。まるで、獣のように。
「泣くのはやめなさい」
零れ落ちそうになる瞬間に浴びせられた言葉は随分と冷たく感じる。六道骸は下を向き続ける私の顎を掬うと、目線を合わせるように上へと向かせた。身長もそこそこある彼の目線に、古びたソファに座ったままの私が合わせようとすれば、当然首は痛いし、零れそうになった水は目尻から頬を伝っていく。
「僕が言う、同じことを繰り返すというのは、今の状況のことを言っているんですよ」
もっと分かりやすく説明しましょうか。と、態とらしく息を吐き出してから、彼は赤い瞳を見せ付けるように顔を寄せた。すると瞳に映る数字は六から一に変わり、ふとした瞬間に周りの景色は先程とは全く違う、酷く暗い闇に包まれる。
「周りの視線や世間体に囚われ、自分の心にも嘘をつく。そして心とちぐはぐになった言動にまた嘘を重ねて、涙を流し、自分は不幸なのだと、生まれた性のせいだと、悲観的なことばかりを考える」
「ちが……」
「そうして、目の前の欲に抗えずにまた君は涙を流しながら同じことを言うんです。運命のせいだと」
「だって、それは本当に……」
「本当に?」
暗闇からじわじわと迫るように現れたのは蔦のようなもの。ソファに座るつま先から、重力に従って下に落ちる腕の指先から、するりと巻き付くように登るそれは、私の動きを縛り付けるようにひどく苦しい。
「痛っ……」
「君はいつも考えているようで大事なことには蓋をして見ようともしない。自分が不幸だと思っているから」
「……っく、ちが……」
「違わないでしょう。未来の君も、今の君と同じように悲観しては泣いて、また求めて、同じことを繰り返していた」
「そんなの、貴方にはっ……」
「分からないと?そうでしょうね、何せ君はオメガで僕はアルファだ」
「だったら……!!」
「君、それ以外で他人のことを考えたことがありますか?」
六道骸の言葉に私は何も言うことが出来なかった。抵抗しないと分かったのか、きつく巻きついていた蔦は少しずつ力を緩め、先端の蕾が膨らんだかと思えば、隙間からピンク色の花びらが見える。
「縛り付けているのは他の誰でもない、自分自身だと、少しは理解してもらえればいいのですが」
この蔦がそうだと言いたいのだろうか。下を見てみれば、花は咲き誇ることはなく、開きかけたままである。
「僕は君が嫌いです。見ていると腹立たしくなる」
「…………私も貴方が嫌い」
「嫌いで結構」
「……でも、助けてくれて、ありがとう」
六道骸は一瞬こちらに視線を寄越したかと思えば、煩わしそうな表情を浮かべる。
「僕は借りを返したまで。それと、貴方々のセックスには全く興味無いので毎度最中に呼ぶのはやめてもらえますか?」
それは未来だというあの夢の中の出来事のことを指しているのであろう。私は居た堪れずに視線を逸らす。きっと耳まで赤くなっている筈だ。
「すみませんでした……」
「もういいです。これで貴方への借りは返しましたから」
赤い瞳に映る数字が一から六へ戻ったかと思うと、周りの景色も先程まで見ていたものと同じになる。何も無い古びた部屋に、傷んだソファ。そもそも一体ここは何処なのだろうか。
「さあ、さっさと帰ってください」
「帰るって、ここ、何処?」
「君って人は本当に……」
うんざりとした表情で睨まれたが、こればっかりは仕方が無いだろう。場所も分からないのに帰れだなんて、無理な話である。
◇◇◇
帰って来れたのは夜も遅く、暗闇に包まれている時間。六道骸はなんだかんだ並盛まで送ってくれて、私が知っている通りまで来ると「じゃあこれで」と早々に踵を返した。嫌いと言う癖に律儀に送ってくれる所を見ると、彼は案外優しいのかもしれない。
今日は満月らしく、雲ひとつない空にまん丸とした月が見え、外は思ったよりも明るい。
「はあ……」
溜息をつきながら、自室の扉を開ける。窓は開けっ放しになっており、月明かりと共に秋の涼しい夜風と何故かあの甘い香りが入り込んでいる。まさかと思い窓際に寄れば、月明かりに照らされてきらきらと輝く小さな白い翼が見えた。
「嘘……」
私の部屋は2階だ。白い翼を持つあの人は2階より広い1階部分の屋根に座り込んでおり、私が帰ってきたことに気付いている筈なのに振り返ろうとしない。
怖い。もうあんな思いはしたくない。以前であればきっと逃げ出していただろう。だが先程六道骸から言われた言葉を思い出す。彼の言う通りになるのは癪だが、それでも彼の言っていることは間違ってはいなかった。……正しいと言えないのは、私がまだ今までの自分を否定出来ないからであろう。
「白蘭……」
名を呼べば、あの人の肩が少しだけ揺れたような気がした。
「中……入る?」
その言葉に未だ彼は振り返ること無く、首に横に振る。
「何で来なかったの」
それは彼が昼間に来た時と同じ台詞であった。あの日、彼は私のことをずっと待っていてくれたのでろうか。
「……ごめんなさい」
「本当は会いたくなかった?」
「ううん、違う、違うの。本当にごめんなさい」
やっと振り向いたかと思えば、彼は苦しげな表情を見せる。まただ、またあの表情で私を見つめている。触れたいのに、触れてしまえば壊れると分かっているような顔。
「あの」
手を差し出した私に、あの人は無言で見つめ返す。
「秋の夜は寒いから……それに、私はまだ貴方のこと何も知らない」
あの人は少しだけ間を置いて、視線を彷徨わせた後にそっと私の手に触れた。
ああ言ったものの、私は何を話せばいいのか分からず、そしてあの人も何も話さないまま時間は過ぎる。けれど優しく抱きしめられているからか、沈黙でもいいような気がした。
鈴虫が鳴く音と、あの人の心臓の音、そしてあの甘い香りに包まれて、それだけで私は多幸感で胸がいっぱいだった。もしかしたら抑制剤で抑えているとはいえ、ヒート時だからかもしれない。それでも、優しくあの人が頭を撫でてくれるから、そんなことどうでも良くなって私はこの一瞬だけの甘い時間に、全ての悪い考え投げ出して、あの人の胸に体を預けた。
「もう行かなくちゃ」
長い沈黙の後に、小さくあの人は呟いた。
「あの、今度は絶対」
「ううん。もうこれで最後だ」
「……え」
「イタリアに帰るんだ」
イタリアに帰る?私は彼の言っている意味がよく分からなかった。いや、分かりたくないのだ。
「僕のこの心臓は偽物だ。ついこの間、移植出来ることが決まってね」
偽物。その言葉に私はどん底に突き落とされたような気がした。先程まで私が安心しきっていたあの音もニセモノ。そうだ、彼は、戦いで心臓を失っていて……。
「またいつか会えたらいいね、なまえチャン」
そう言ってあの人は窓の外へと羽ばたいた。
私は何も言えなかった。