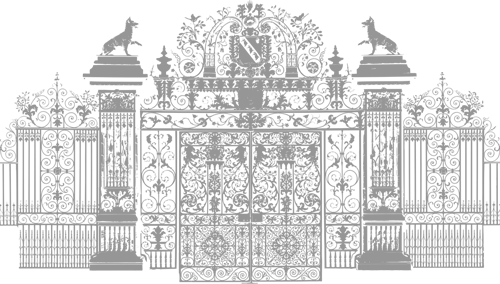▼ 白百合と庭薔薇の記憶
――――あれは、良く晴れた七月のことだった。
学校から帰宅したわたしを、両親の死体が出迎えた。
まるで見せつけるように、通りに面した窓からよく見えるように、『それ』は配置されていた。
リビングのソファに腰掛ける、首のない父。まるでキッチンに立っているかのように見せかけて天井からフックで吊された、内臓を零れさせた母。その姿は、加工途中で放棄された食肉用の家畜みたいな有様で。わたしは暫く、目の前のものを現実として理解出来なかった。
近所の人の通報で警察が来て、わたしは護送の名目で覆面パトカーに乗せられた。けれど、その車が覆面パトカーを装った、警察とは全く無関係の車だと気付いたのは、友人の家に運ばれたときだった。
「百合ちゃん……?」
お伽噺に出てくるような立派な洋館に住んでいる、わたしの親友。
保育園からお嬢様学校に通っていてもいいような家柄なのに、わたしと同じがいいからって家の近くの公立中学に通っている、ちょっと変わった子だ。
真っ直ぐに伸びたサラサラの黒髪と宝石みたいな黒い瞳、お庭に咲いている百合の花弁みたいに白くて綺麗な肌と、艶のある形の良い唇。お伽噺の白雪姫みたいな彼女は、わたしを出迎えるなり思い切り抱きしめた。
「ごめんなさい、姫花さん……あなたのご両親を助けて差し上げられなくて……」
言葉の意味がわからなくて、説明を求めるように回りを見ると、普通に暮らしてきたわたしにも一般人じゃないってわかるオーラを持った、金髪の男の人と目が合った。
「
「畏まりました」
その人に指示を出すと、百合ちゃんはわたしをアンティークソファに座らせた。
窓の外は綺麗に整えられた庭園と青空が広がっていて、お伽噺の世界に来たみたいだった。
ルーと呼ばれていた人が持ってきてくれたお茶を一口飲んだら、凍り付いていたような胸の内が少しだけ温度を取り戻した。
わたしが一つ息を吐いたのを見て、百合ちゃんが言葉を選びながら話し始める。
その内容はあまりにも突飛で。けれど頭の片隅で何となく予感していたことの回答篇のようにも思えて。わたしは驚きとかショックとか通り越して。
「……そっか」
そう、納得した。
「驚かないのですね。それとも、その段階は通り過ぎてしまったのかしら」
「うん……たぶん。たまに、スーツの男の人と話してるのを見たし。わたしは、会社の人かなって思ってただけど……それもきっと、そう思いたかっただけなんだろうな……」
わたしの両親は、ヤクザの構成員だった。しかも、小さいながら組を一つ持つような。それで、最近は成果を上げてきて、両親のすぐ上に位置する組の人が成績を抜かれそうになったのを恐れて両親を殺したのだという。百合ちゃんはお父さんの周りを嗅ぎ回っている人に気付いてルーさんに探らせていたけれど、尻尾を掴んだのとほぼ同時に殺害計画を実行されてしまったと言った。
もしかしたら自分が調べたせいで焦らせてしまったかも知れないと謝る百合ちゃんに、わたしは心から「百合ちゃんのせいじゃない」って答えた。
「わたし、これからどうすればいいんだろう……家には住めないし、学校も……行ってる場合じゃなくなっちゃったな……」
百合ちゃんと同じ高校に行きたくて受験勉強をがんばってきたけれど、それも無意味になった。中卒でも雇ってくれるようなところってあるんだろうか。
この期に及んで、天涯孤独になった実感もまだぼんやりとしたもので、何とかバイトを探すしかないのだろうなと思っていると、百合ちゃんの家の呼び鈴が鳴った。
「お迎えが来たようですわね」
「お迎え……?」
いったい誰の? いったい誰が?
言葉にならない両方の疑問に、百合ちゃんは来客を通すことで答えた。
「お迎えに上がりました、姫花お嬢様」
その人は、髪も瞳もスーツもネクタイも靴も手袋も、全てが真っ黒で影のような姿をしていた。
「本日よりお嬢様の世話役を仰せつかりました。真赭慎十朗と申します」
これが、わたしの転機。
日常が壊れて、非日常が日常に成り代わった日。
良く晴れた七月の、夏休み前の出来事だった。