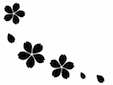いつまでも待つよ
※Painfulの続きです。先にこちらを読まないと話が分からないです。
俺がストーカー男に襲われたのは、もう三日前のことだ。
襲われて皆が助けに来てくれた後、俺が落ち着きを取り戻した頃合いを見て赤司っちが家まで送ってくれた。
ストーカー男は青峰っちたちが警察に連れて行ったらしい。
家に帰ってそのまま寝込み、今日具合が直ったので久しぶりに登校する。
赤司っちたちに会えるのを楽しみにしていたのだが、一つ問題があった。
いや、問題が出来ていた。
「黒子っちおはよー!久しぶりっス!」
下駄箱で上履きに履き替えている黒子っちを見つけ、笑顔で話しかける。
俺に気づくと、黒子っちは一瞬目を見開いた後苦し気に眉を寄せる。
「あ、黄瀬君…!おはようございます。…もう大丈夫なんですか?」
「うんもう平気っスよ」
「ならよかったです」
「心配してくれて嬉しいっス!」
黒子っちに後ろから抱きつく。
いつもならこの後に文句を言ったり抵抗する黒子っちだったが、今日はそれがなかった。
「あれ?嫌がんないんスか?離してください、とか」
「…あんなことがあった後なので、変わらない黄瀬君がいて安心しました」
「黒子っち…」
片眉を下げながら優しく言われ、本当に心配してくれていたのだと伝わる。
内心泣きそうになりながらも、笑みを作って黒子っちを抱き締めている腕に力を入れる。
「じゃあ今日はずっと黒子っちに抱きついてるっス!もう離さないぜっ!」
「それは止めてください。イグナイトお見舞いしますよ」
「じ、冗談っスよ!冗談!」
「あれ、黄瀬じゃねーか!もう学校来て大丈夫なのかよ!」
「っ!あ、青峰っち…」
いつの間にか隣に来ていた青峰っちに声をかけられて思わずビクッと体をはねらせる俺に、青峰っちは怪訝そうな顔をする。
「どうした?」
「…あ、いや…。久しぶりっス青峰っち。…あの、俺ちょっと用があるから教室行くっスね!じゃ!」
「は?おい黄瀬っ?」
青峰っちの方は向かずに言い、二人を置いて教室に向かう。
「…教室も駄目だ」
教室に着いたのだが扉の前で足を止め、踵を返す。
人のいない場所を頭で考え、結局屋上に行く。
ホームルームの始まる時間なので、誰もいないだろう。
案の定屋上には誰もいなくて、思わず安心してため息をついた。
「…黒子っちは大丈夫だったのに、青峰っちはダメだった…」
制服を捲り、腕を見る。
そこには鳥肌が沢山立っていて、一向に治まる気配がない。
登校している時に気付いたのだが、どうやら俺は男性恐怖症になってしまったらしい。
触れられる距離に男がいると、鳥肌が立って冷や汗が出てきて、震えが止まらなくなる。
男と言っても、俺より身長や体格が大きかったり、俺を簡単に組み敷ける様な人以外は大丈夫なようで、子供などには鳥肌は立たなかった。
だから黒子っちも大丈夫だったのだろう。
青峰っちがダメだということは、それより身長が高い緑間っちや紫原っちも多分ダメだ。
赤司っちはどうなのだろうか。
一応俺よりは身長低いし、体格も俺の方がいい。
でも、組み敷くのは赤司っちなら出来ると思う。
そう考えると五分五分で、どちらなのか判別出来ない。
赤司っちは恋人だし、大好きだからできれば大丈夫であってほしい。
でなければ、触れることは愚か、話すことも難しくなってしまう。
「…昼食の時、確かめてみよう」
そう決心して、教室に戻ることにした。
席は窓際の一番後ろだし、近くの席の男子は皆俺より身長が低い。
警戒してれば大丈夫だ。
******
昼休みになり、俺はまた屋上へと来ていた。
赤司っちにもメールで『屋上でお昼食べよう』と送ったので、もう少しで来るだろう。
弁当を広げて待っていると、扉が開いて赤司っちが入ってくる。
「待たせたか?」
「ううん、大丈夫っスよ」
…今のところはまだ鳥肌は立っていない。
このまま何もありませんように…。
しかし、赤司っちが俺の隣に腰を下ろした瞬間、ぶわっと一気に鳥肌が立ち始めた。
「…っ!」
「…涼太?どうしたんだ?」
「…ぁ、…いやっ、なんでもないっスよ…っ」
「…?」
飲み物を取る振りをして、急いで赤司っちから離れる。
そして隣ではなく、弁当を挟んだ向かいに座り、これ以上症状が出ないようにした。
震えたりなんかしたら赤司っちには絶対バレてしまうし、何より傷つけてしまうかもしれない。
これくらい離れていれば、鳥肌は立ったままだが、冷や汗や震えは出てこない。
自然に治るまで、なんとか隠さなければ。
「久しぶりだね涼太。もう大丈夫なのか?」
「あ、うん。もう平気っスよ。というか、皆同じこと聞いてくるんスね」
「それはそうだろう。あの後なんだから…」
表情を曇らす赤司っちに気付き、俺は場を和ませるために目一杯笑顔を作る。
「ホントにもう大丈夫っスから!それより、今日も赤司っちの弁当美味しそうっスね!」
「そうか?欲しいものがあったら食べていいからな」
「やった!じゃぁこの玉子焼きもらうっス!」
「あぁ」
あの出来事を思い出させて赤司っちに暗い顔をさせたくなかった。
その表情を見ると、必死に忘れようとしてることを思い出してしまうから。
「あ、そうだ赤司っち。明日からも屋上で昼食べないっスか?」
「分かった。なら昼はここに集合だな」
「了解っス」
この時俺は、もうあの悪夢のような出来事は過ぎたこととして処理して頭の隅に押し込めていた。
まだ終わってないということに気付かされるとは知らずに。
******
「…はぁ…、疲れた…」
帰宅してすぐに俺はベッドに寝転がった。
いつもより疲労感が半端じゃない。
常に警戒して、気付かれないように振る舞って。
部活では黒子っち以外には近づかないで、赤司っちたちがこちらに来たらさり気なく一歩下がって距離を取る。
青峰っちがふざけて肩パンしてきた時は叫んでしまったが、笑ってどうにか誤魔化した。
帰りは赤司っちが送ってくれたのだが、距離を取る俺を聞かれはしなかったが不信がっていた。
これではバレるのは時間の問題かもしれない。
うつ伏せに休んでいると、携帯の着信音が聞こえてきた。
「メール…。…誰だ?」
携帯を開きメールを確かめる。
差出人は不明で、タイトルには『おかえり』の文字。
誰だか分からずに本文を読み、愕然とした。
『おかえり涼太君。久しぶりの学校はどうだった?さっき疲れたって呟いてたけど、何か嫌な事でもあったのかな?僕でよければ相談に乗るよ。この前涼太君のお友達の赤髪君に殴られた顔の腫れも、やっと引いてきたんだ。腫れが引いたらまた近いうちに会いに行くね。返事、待ってるよ』
これは、どう見てもあのストーカー男からのメールだ。
確か青峰っちたちが警察に連れて行ったはずなのに。
それより、何で俺が今さっき呟いていた内容をこいつは知っているんだ。
「…まさか…っ」
盗聴されてる…!?
俺は急いで自分の部屋に盗聴器がないか隈なく探した。
だが、それらしい物はなく、変わった物は一つもない。
あるはずなのに、いくら探しても見つからなかった。
いつから盗聴されてたんだ…!?
いつ盗聴器を付けられた!?
部屋に入られたってことだよな…!?
心の内でパニックを起こしていると、また携帯の着信音が鳴った。
開いて見ると思った通り男からで、『返事遅いけど、どうかしたの?』と書いてあった。
鳥肌と冷や汗が一緒に出てきて、体も震え始めてくる。
あの時の悪夢のような出来事が、男の終始ニヤけた顔が、頭の中をループする
。
「…ぅ…っ」
気分が悪くなってきて、吐き気もし出した。
俺は口を手で覆い、急いでトイレに向かう。
ポケットに入れた携帯から五月蝿いほど着信音が鳴る。
こいつはどれだけ俺を追い詰める気なんだ。
あれだけ赤司っちが仕返しをしたのにまだ諦めてないなんて、完全に頭がイカレてる。
「…気持ち悪い…っ」
その日は一睡も出来なかった。
携帯は一向に鳴り止まないので電源を落として鞄に放り投げた。
盗聴されているかと思うと下手に動いて音を立てたくないし、もしかしたら盗撮もされているかもしれない。
本当に地獄のような一晩だった。
朝になってジャージに着替えて、まだ早いが学校へ向かった。
家から早く出たかった。
皆の顔を見ていくらか安心出来たが、男性恐怖症の所為で黒子っち以外には近づけない。
朝練が終わって教室に行って授業を受けていたが、じっとしてると男の顔ばかり思い出して震えが止まらなかった。
四時限目終わりの合図のチャイムが鳴り、俺は一目散にトイレに向かった。
吐き気が収まらなくて、昨日の夜から何も食べてない空っぽの胃から、ひたすら胃液を吐き出す。
昨日今日で、一気に老けた気がする。
顔は血の気が引いてるし、目の下には薄らと隈もできている。
気を引き締めるために顔を洗い、昼食を食べに屋上に向かう。
赤司っちの顔を見れば思い出さないでいれるかもしれない。
屋上の扉を開けた先には、何故か赤司っちだけでなく、黒子っちや青峰っち、緑間っちに紫原っちの五人がいた。
わいわいと楽しそうに弁当を食べていて、俺に気付くと青峰っちが開口一番に文句を言う。
「おっせーぞ黄瀬!」
「え、す、すんませんっス…?」
皆がいる理由は分からないが、一応謝って黒子っちの隣に座る。
「…えっと、何で皆居るんスか?」
「昨日、夜に『部活のことで話したいことがあるから昼に屋上集合』と赤司からメールがきたのだよ」
「涼太にも送ったと思うんだが」
俺の問いに緑間っちが答え、赤司っちが首を傾げる。
夜はもう携帯の電源を落としてしまっていた。
「あっ、電源落としてて見てなかったっス…!今確かめるっスね…っ」
携帯をポケットから取り出し、慌てて電源を入れる。
しかし、入れた瞬間にものすごい数のメールが受信され、着信音も鳴り始めて止まらない。
「…っ!」
「…受信341通…?何ですか…これ」
携帯のディスプレイが隣にいた黒子っちに見えてしまったようで、深く眉を寄せて言われる。
「341通!?三桁とかマジかよ!」
「ち、違うんス!なんか昨日から迷惑メールが沢山きてて…!」
「迷惑メール?」
「そうなんス!だから気にしないで!ねっ?」
「…………」
電源をすぐに落とし、ポケットに隠すようにしまう。
皆、特に赤司っちが納得のいっていない顔をしていたが、部活の話をするように促して話題を変える。
赤司っちに問い詰められたら、嘘をつける自信がない。
話が終わるのと同時にチャイムも鳴り、俺は適当に理由をつけて先に教室に戻った。
皆の視線を背中に感じたが、振り返らずに階段を下りていく。
「…黄瀬ちん、なんかおかしくなかった?」
「だな。なにかを隠しているのがバレバレなのだよ」
「メールの受信数も、迷惑メールであの数なんて有り得ないですし…」
「明らかに疲れた顔してたしな、黄瀬の奴。どうすんだ?赤司。黄瀬に直接聞くか?」
「……いや、涼太から言ってくれるまで、もう少し待ってみよう。ただ仕事と学校で疲れているだけかもしれないしな」
「そうだな」
******
「…赤司っち、今日も送ってくれてありがとうっス。じゃ、また明日」
「…また明日」
赤司っちの背中が見えなくなるまで手を振り、家の中に入る。
自室に行って鞄を置き部屋着に着替えようとした時、机の上に紙が置いてあるのに気づく。
こんなもの置いた覚えはないので手に取って確認すると、その紙には見覚えのある字で
『メール返ってこないみたいだから、手紙をまた書いてみたよ。メールは嫌いだったのかな?いきなりだけど、明日涼太君が学校終わった後にデートしようよ。僕、迎えに行くから待っててね。今から楽しみだよ』
と書いてあった。
「…っ!?これ…っ」
あの男がこの部屋に入ってこれを置いて行ったのか。
家にはずっと母がいたはずだし、玄関からは入って来れないだろう。
だとしたら、どこから?
部屋の窓を全て確かめてみると、一つ鍵の開いている窓があった。
どうやって開けたのかは分からないが、ここから入ってきたようだ。
開いている鍵を閉め、男からの手紙をぐしゃぐしゃに丸めてごみ箱へ投げ捨てる。
目の届く場所にあると気持ち悪くてしょうがない。
それより、手紙には迎えに行くと書いてあった。
どこまで迎えに来る気なのだろうか。
まさか学校まで来ようとしているのか?
前みたいに帰り道に待ち伏せしているのか?
ストーカーとデートなんかする訳ないのに、こいつはどれだけ狂っているんだ。
勝手に人を恋人にしたり、襲ってきたり、盗聴器とかつけたり、部屋に入ってきたり。
本当に気持ち悪い。
食欲もないし疲れているために、まだ早いが寝ることにした。
しかしベッドに横になってもあいつが鍵開けて入って来るんじゃないかとか色々考え込んで、結局一睡も出来なかった。
そしてまた眠れないまま、トボトボと学校へ行く。
もう体力的にも精神的にも限界だった。
どうにか四時限目の授業までは受けたが、完全に動けない程ダルい。
それにすぐにでも目が閉じてしまいそうだ。
これじゃ赤司っちと昼食なんか食べていられない。
「……どこか人目のつかない場所で寝よう…」
ふらふらと危ない足取りで赤司っちの教室まで向かう。
人が沢山いても目立つ赤髪を探し、扉の横から手を振る。
「…赤司っち、ちょっといい?」
俺にすぐ気付いてくれた赤司っちは、鞄から弁当箱を取り出し早足で来てくれた。
「すまない、遅かったか?」
「ううん、そうじゃなくて、俺今日ちょっと用あるからお昼一緒に食べれないんスよ。それを言いに来ただけっス」
「用が終わるまで待ってるよ」
「ごめん、いつ終わるか分かんないし、遅くなるから」
「…そうか」
少し残念そうに言い、俺の顔をじっと見る赤司っち。
「…酷いな」
「…え?」
「昨日より顔色が酷い。それに少し痩せたんじゃないか?」
「そ、そうかな?仕事で疲れてるのかもしれないっスね」
「…あんまり無理はするなよ。もし何か困ったことがあれば言ってくれ。力になるから」
「…赤司っち」
「涼太には笑顔が一番合うし、僕が一番好きな表情だからな。最近見ていないから心配なんだ」
「…うん。ありがとう赤司っち、心配してくれて…」
…やばい。
涙出てきそう…。
「じ、じゃぁ俺もう行くっスね。また放課後部活で」
「…あぁ」
笑顔を向けて、急いでその場を後にする。
あれ以上赤司っちの顔を見てたら泣きそうだった。
気が参ってる分、優しくされるとじわりと心まで染みてくる。
縋ってしまいたくなる。
助けてほしい、そう言ってしまいたくなる。
******
俺は寝る場所に部室を選んだ。
部室なら放課後まで絶対誰も来ない。
考えて、安心して寝られるところがここしかなかった。
壁際にある長椅子に寝転がり、目を閉じる。
するとすぐに眠気が襲ってきて、意識を手放した。
気付いたら、俺は知らない道を必死で走っていた。
『…はぁ…っ、来るな…っ』
…あれ?
何で俺走ってるんだ?
何から逃げてるんだ?
『…っ、…やだ…っ』
…この場面、どっかで見た気がする。
『…待ってよー、…涼太くーん…』
こいつ…!
『来るなって言ってんだろ…!』
『…つーかまえた』
『!?』
いやだ…。
『鬼ごっこはもう終わりにしよう?僕疲れちゃったよ』
『は、なせ…!』
『早く僕の家に行こうよ。そんなに照れなくてもいいよ』
嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ。
『離せって言…っひ…!』
『…ねえ涼太君、キスしていい?いいよね?』
『…や…っ!』
――――っ!
「――は…っ!」
目を開けると、部室の天井が広がっていた。
夢だったようで安心していると、横から視線を感じた。
「…涼太?」
「…ひっ!?」
声のした方に顔を向けると、隣に誰かがいた。
起きたばかりの所為で視界がぼやけていて、誰だか分からない。
男だということは分かって、先ほどの夢と被って体が震えてくる。
目をぎゅっと瞑り、横にいた男を思い切り突き飛ばす。
「…っ!」
「や、やだ…っ!来んな…!」
椅子から転げ落ちるようにして離れ、隅に逃げこむ。
「……涼太…?」
「き、黄瀬君?」
「いきなりどうしたんだよ…?」
「あ…、赤司っち…皆…」
聞き覚えのある声によく見ると、突き飛ばしてしまったのは赤司っちだった。
その後ろに驚いた顔の皆もいる。
「ご、ごめん赤司っち!俺、寝ぼけてて…!」
「いや、大丈夫だ」
「すごい汗ですよ黄瀬君。それに涙も…。これ、ハンカチです。使ってください」
「え…、ホントだ…。ありがとう黒子っち」
扉の近くにいた黒子っちがハンカチを持って俺の隣に渡しに来てくれた。
ハンカチを受け取り、涙を拭く。
そんな俺たちを見ていた赤司っちが、眉を寄せながら近くに来ようとする。
一歩手前でそれに気づいた俺は、顔色を変えて赤司っちを止める。
「ま、待って!こっち来ないで!」
「…涼太?」
ピタリと足を止めた赤司っちは、一層眉間に皺を寄せていた。
「…どうしたんだ?最近テツヤ以外には近づかなくないか?避けているようにも見える」
「……それは…」
「言ってくれ、涼太」
赤司っちに悲しい顔させたくなかったから黙っていたのに、結局させてしまった。
俺をじっと見る赤司っちと視線を合わせ、ゆっくりと口を開く。
「…俺、男性恐怖症に、なっちゃった…んだよね…」
「……男性恐怖症」
「男性恐怖症ってなんだ?」
「恐怖症のひとつなのだよ。男に触られると強い不安感に駆られたり、一緒に居るのが耐えられないといった病的な心理だ」
「でも、僕は黄瀬君に近づけてますけど…」
「…黒子っちは大丈夫なんスよ。俺より身長や体格が大きかったり、俺を簡単に組み敷ける様な人以外は大丈夫みたいっス」
「それってさー、あのストーカー男の所為なの?」
「…うん」
俺の返事に、皆は苦い顔をして口を噤んだ。
暫く重たい沈黙が辺りを包んでいたが、それを破ったのは赤司っちだった。
「…他にも、何か僕たちに隠してる事はないのか?」
「…な、ないっスよ…?」
「…本当か?」
「…本当っス」
赤司っちの鋭い目つきに、耐えられなくて思わず目を逸らす。
それをどう受け取ったのかは分からないが、少し微笑むと背を向けて言う。
「…ならいい。涼太、今日はもう帰るんだ。疲れきった顔してる」
「…分かったっス」
ハンカチを黒子っちに返し、体を立たせる。
皆に『また明日』と挨拶をして部室を後にした。
「…真太郎」
黄瀬が部室を出て行ったあと、赤司は視線を扉から放して低い声音で言った。
「どうしたのだよ赤司」
「僕も今日はもう帰るよ。後は任せてもいいかな」
「…追いかけるのか?」
「まぁ、ね。じゃぁ任せたよ」
「…あぁ」
赤司は床に置いていた鞄を持つと、真剣な面持ちのまま帰っていった。
*******
どこであの男が待ち伏せしているか分からないため、俺は周りに注意しながら家路を歩いていた。
眠ったお陰でいくらか体が軽くなった。
前の様に体調は崩していないから、今日は自分でなんとか出来るはず。
二発ぐらい殴ってすぐに逃げよう。
ぎゅっと拳を握り、そう決意する。
男に襲われた神社を通りすぎようとした時、いっそ恐怖を覚えそうなほどの甘い声が俺を呼んだ。
「涼太君、おかえり」
声のした方へと顔を向けると、あの時と全く同じのニヤついた表情の男がそこにいた。
男の姿を確認した瞬間、十分離れているのに全身一気に鳥肌が立った。
冷や汗も震えも同時に出始める。
「約束通り、迎えに来たよ」
俺に手を伸ばしながら近づいてくる男を強く睨みつける。
「アンタ頭おかしいんじゃないの?約束なんてした覚えないんだけど」
「忘れちゃったの?一緒にお出かけしようってお話ししたよね?」
「だからしてないって言ってんだろ。そろそろ妄想だって気づけよ。アンタの所為で俺めちゃくちゃなんスけど」
「…僕の涼太君はそんな悪い口調で話さないよ」
「勝手に決めんな」
震えの止まらない体を無視して、顔を顰め始めた男を睨み続ける。
男が一歩近づいてくるたびに、俺も一歩下がる。
そうして殴る瞬間を伺う。
「…そっか、お出かけが嫌なの?じゃあ僕の家に行こうよ」
何を思ったのか、パッと笑顔になった男は早足でこっちに来た。
「ちょ…!こっち来んな…!」
それに驚いて自分も後ろに逃げようとしたが、足元を見ていなかったために落ちていた拳サイズの石に躓いて転げてしまう。
「―っい…!」
「ああ、大丈夫?涼太君、怪我してない?」
「く、来るなって…!や…っ」
俺と男の距離があと数センチに迫った瞬間、見覚えのある赤い髪が間に入ってくる。
いとも簡単に男の両腕を後ろにひねり揚げると、彼は俺の方に振り向いた。
「大丈夫か?涼太」
「あ、赤司っち…!」
「いだだだ…っ!!」
「…こいつは、前の強姦の…」
赤司っちは男の顔を見るなり顔色を変えた。
俺に笑いかけていた目には鋭い怒りの色が灯り、額に血管も浮き出ていた。
男を掴んでいる手からはギリギリと鈍い音が鳴っている。
「お前は確か青峰たちが警察に届けたと聞いたが…。まあいい、懲りずに涼太に近づいたってことは、覚悟は出来ているんだろうな?」
「腕、が…っもげる…!」
「涼太が寝不足になったのも、最近笑わなくなったのも全部お前の所為か。二度目はもう遠慮はしてやらない」
「――ぁ゙あ゙あ゙あ゙っ!?」
ゴギっという音と共に、男が高い悲鳴を上げた。
そのまま勢いよく地面に倒れる。
気絶したようだ。
「…その人、大丈夫なんスか?」
「片腕を折っただけだ。命には別状ない。それより、立てるか?」
手を差し出され思わずビクリと肩を震わせた俺に、赤司っちは悲しそうに「すまない」と小さく呟いて手を引いた。
助けてもらってこんな態度じゃダメなのに、俺の体は俺の意思を無視してビクビクと震えたままだった。
そんな俺にいつもの優しい笑みを向けて、「怪我はないか?」と話かけてくれる。
ゆっくり頷くと、「良かった」とまた笑いかけてくれた。
きゅぅぅ…と自分の胸が締め付けられるように痛み、じわりと涙が滲み出てくる。
気が付けば俺は震えなど気にせずに、赤司っちに抱きついていた。
「…っ!…涼太?そんな震えてるのに、抱きついたりなんかしたら…」
「いいんス。今すごく赤司っちに抱きつきたいんス。もうちょっとこのままでいさせて」
「…分かった」
そう言った後、少し戸惑いがちに抱き締め返してくれた。
久しぶりの赤司っちの体温に、心が和らぐ。
「…好きっス。赤司っち、大好き」
「…僕もだよ。だから何かあったら何でも僕に言ってくれ。涼太に何かあったら…、多分僕は狂ってしまうから」
「はは…、狂うってなんスか。…次からは、ちゃんと言うっスね」
「そうしてくれ」
その後、離れてから赤司っちはどこかに電話をかけ始めた。
五分後くらいに、黒い見るからに高級そうな車が俺たちの目の前で止まって、中から複数の黒いスーツを着た人たちが出てきた。
まだ気絶しているストーカー男を担いで車に乗せると、赤司っちに一礼して忙しなく車はどこかに走っていった。
「…さっきの人たち、誰っスか?」
「僕の家の使用人だ。あの男には、ちゃんと相応な罰を与えなければならないからな」
「…さすが赤司っちっスね」
何をするのか気になったが、ニヒルな笑みで言う赤司っちにそんな事聞ける雰囲気ではなかった。
「送ってくよ」
「うん、ありがとう赤司っち」
男性恐怖症はまだ治っていないので、少し距離を開けて赤司っちと家路を歩く。
「ごめんね赤司っち…。距離取って。これよく調べてなるべくすぐ治すから」
「ゆっくりで大丈夫だよ。治るまで、いつまでも待ってるから」
「…うん」
─END─
少し中途半端なところで力尽きました(´`)
もう少しだけ続きを考えていたのですが、諦めます←)ω()ω()ω(
ないとは思うのですが、続きが読みたいと言ってくださる方がいましたら、書くかもしれません←←←