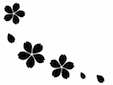Painful
「…はっ…は…っ」
視界が霞む。
何度も足がもつれそうになるが、踏ん張ってそれをどうにか留める。
足を止めてはいけない。
こんなに走るのが辛く感じる日が来るなんて思ってなかった。
「…待ってよぉー…涼太くーん…」
「…やだ…っ、来るなっ」
…くそっ、いつもならあんな奴ぶん殴ってでも追い払うのに…!
なんでこんな日に限って体調崩すんだよ俺は!
やっぱり誰かと一緒に帰ればよかった…!
学校を出る前の自分を恨みながら必死に止まりそうになる足を動かす。
事の始まりは二週間前のことだ。
家のポストに名前も住所も書かれていない封筒が入っていた。
中には一枚の手紙が入っており、内容は『いつも見てる』だの『好き』だの『僕の涼太君』だの、気色悪いものだった。
いつ誰がお前のものになったんだよ、とツッコみながらその手紙を封筒ごとシュレッダーに入れた。
ただの悪戯だと思い特に気に留めていなかったが、それから毎日のように気持ち悪い言葉がびっしりと書かれている手紙がポストに入っていて、さすがの俺もだんだんと気が滅入ってきた。
けれど、今日の朝いつも通りにポストの中を確認したが封筒は入っていなかった。
無意識に出ていたため息に、そんなに張り詰めていたのかと思い知った。
それに、安心したからかぐっと体が重くなった気がする。
「…学校行こ」
今日は確か朝練があったはずだ。
みんなの顔見れば元気が出るだろう、と早足に学校へ向かった。
「おっはよーっす」
「ん、あぁ、おはよう涼太」
「おはよー黄瀬ちん」
「おはようございます」
「…あれ?青峰っちはともかく緑間っちがいないのは珍しいっすね」
「そういえばそうですね。寝坊でしょうか?」
「そんなまさかー。青峰っちじゃあるまいし」
あはは、と笑いながら言うと、急に赤司っちが真剣な顔で俺を見た。
「涼太、顔色悪くないか?」
「あー、ホントだー。黄瀬ちん具合でも悪いの?」
「え?別に普通っすけど」
「ならいいが」
「遅くなったのだよ」
声のした方へと目を向けると、眉を寄せてる緑間っちがいた。
「緑間っちおはよー」
「…あぁ」
「…?どうしたんすか?そんなにデコにシワなんか寄せて」
「さっきそこで変な奴を見つけた」
「変な奴…?」
「そこの扉から男が体育館の中を覗いていたのだよ。邪魔で入れないから声をかけたら悲鳴を上げて逃げて行った。失礼にも程があるのだよ」
「緑間っち身長高いし、しかもそのぶっちょう面だからヤクザとでも間違って怖がったんじゃないっすか?」
「……殴るぞ」
「ごめんなさいすいません」
「どんな男だったんだ?」
「マスクをつけていて、それに…」
「よーす」
「あ、青峰っち」
緑間っちの台詞を遮って入ってきたのは青峰っちだ。
「さっきよー、校門で変な男と思いっきりぶつかったんだよなー。肩いってー」
「変な奴、ですか?」
「それはマスクをつけて帽子を深く被っている上下黒いジャージを着ている男か?」
「そうそう、そいつ。てかなんだよ緑間、そいつの知り合いか?」
「そんな訳ないだろう。さっきその男が体育館を覗いていたのだよ」
「なんだぁ?不審者か?」
「格好からしてもろ不審者だけどねー」
「誰かの親という可能性もあるんじゃないか?」
「親でしたらまず職員室に行くはずですが…」
「それもそうっすね。道に迷って学校に入ってきちゃった、とか?」
「そりゃねーだろ。誰かのストーカーだったりしてな」
「…え」
ストーカーという言葉に、手紙のことが頭を過った。
…まさかね。
「まぁいい。練習を始めるぞ」
「はーい」
短い朝練の時間が終わり、午前の授業も全て終わって昼の時間になった。
…食べる気がしない。
というか食欲がない。
頭も痛いし、気分も悪い。
思いっきり体調崩しちゃったな…。
「…だるー…」
「やっぱり体調悪いのか?」
「へ?あ、赤司っち…」
伏せていた顔を上げると、弁当箱を持った赤司っちが目の前にいた。
弁当箱といっても、黒と金のすごく高そうな重箱だ。
何でここにいるんだろうと思っていると、それを察したのか赤司っちが俺の机の上に重箱の弁当を置く。
「昼食はいつも一緒に食べているだろう?」
「…あー…そういえば…」
「……涼太」
「なんすか?…っ!」
いきなり赤司っちの顔が近づいてくる。
え、まさかキス!?
てか待ってここ学校だし、しかも教室で人がたくさんいるのに…!
「…熱があるじゃないか」
「…え、あ…」
…何だ、おでこで熱計っただけか…。
「大丈夫っすよ赤司っち、ちょっと疲れてるだけだから」
「…本当か?」
「本当っすよ」
にこりと笑うと、赤司っちも少しだけ微笑んだ。
「昼食、食べようか」
「はいっす」
弁当なんか食べる気しないし、そもそも体が受け付けないのだが、心配かけまいと無理矢理口に放り込んだ。
昼の時間が終わり、赤司っちが帰っていった後、すぐにトイレに駆け込む。
「…はぁ、昼飯食べた意味なかった…」
昼に無理して食べた分を全て吐き出してしまい、胃の中は空っぽだ。
さすがにもう保健室に行こう…。
午後の授業はそっちのけで、とぼとぼと保健室に行った。
保健医に渡された体温計で熱を計ってみたら、39度を超えていた。
「39度って…ダルいはずだよな…」
ベッドを借りて少し眠ることにした。
放課後の部活には出たいから、ちょっとでも体調が回復するように。
─────。
「……ん…、あれ、今何時…?」
まだ頭が起きていないが、時間を確認するために携帯を開く。
「…はぁっ!?やばっ、部活始まってるじゃん!」
部活が始まってもう15分は経っており、一気に覚めた体を立たせる。
「──っ!?」
立ち上がった途端、酷い目眩がして目の前がぼやけた。
頭痛も気分も、何もかも寝る前より明らかに悪化している。
「…全然…善くなってないし…っ」
フラフラしながらも、何とか体育館へ向かった。
「…お、遅れてすいません」
「おっせーよ!黄瀬ぇ!」
「青峰っち声大きいっす…」
頭に響くから今日だけは大声を出さないでほしいんすけど…。
「今まで何していたんだ?」
青峰っちの後ろから赤司っちが顔を出す。
「えっと…保健室にいて…」
…あ、口が滑った…!
「保健室?何で保健室にいたんだ」
「…ちょっと昼寝しに…」
「…僕に嘘が通じると思っているのか?」
目を細めてギロリと睨まれ、その威圧感にビクッと体が跳ねる。
隣にいた青峰っちまで小さく肩が跳ねていた。
「…き、気分が悪かったから保健室に…」
「熱計っただろう、何度あった?」
「………39度…です…」
「……はぁ…」
赤司っちは深いため息をつき、俺の手を握って歩き出した。
「帰るぞ涼太」
「いや、俺バスケやりた…」
「僕は帰るぞって言ったんだが…?」
「わ、分かったっすよ!でも俺一人で帰れるっすから!」
「…途中寄り道しないと約束するか?」
「約束します!」
「真っ直ぐ家に帰ると約束するか?」
「約束します!」
「…なら許す」
握られていた手を離してくれた赤司っちに背を向け、顔だけ振り向く。
「心配してくれてありがとう、赤司っち。じゃ、また明日」
「…あぁ」
赤司っちの返事を聞いて、俺は体育館を後にした。
「いいのか?黄瀬一人で帰らせて。めっちゃフラフラしてんぞあいつ」
「…涼太が大丈夫と言うんだから大丈夫だろう。それに、僕がいると逆に気を使わせたり無理に笑おうとするだろうしな」
「まぁ、お前がいいならいいんだけど。…あ、扉に顔面ぶつけたぞあいつ。本当に大丈夫か?」
「…大丈夫…だろう」
そして今にいたる。
帰り道にいきなり声をかけられたのだが、知らない男に構ってる余裕など微塵もなかった俺は適当にあしらって男の横を通りすぎた。だが、男は俺を追いかけてきたのだ。
息を荒げながら追いかけてくる様子は気持ち悪いことこの上ない。
「何で逃げるのー?涼太くーん」
「…はぁ…っ、来るなって…言ってんだろ…っ!」
…もう、無理…っ。
やっぱり一発殴って気絶させようか…。
いや、今の俺じゃ気絶どころかまず当たらないだろう。
…どうしよう…、もうこれ以上走れない…っ。
霞む目で周りを見ると、少し先に神社を見つけた。
とっさに俺は神社へと入り、一番奥の寺の中へと隠れる。
息を整えながらポケットから携帯を取り出して震える手でボタンを押す。
電話帳の最初に登録してある赤司っちへと電話をかける。
数コールですぐ繋がった。
「赤司っち…!」
『は?黄瀬?俺赤司じゃねーぞ?』
「その声は…青峰っちっ?」
急ぎすぎて、どうやら赤司っちの次に登録してあった青峰っちにかけてしまったようだ。
でもかけ直している暇はない。
「青峰っちでもいい!助けて!」
『はあ!?助けてって、どうしたんだよ?お前家に帰ってるんじゃねーの?』
「帰ってる途中で男に追いかけられて!でも俺そいつ追い払う力今ないから走って逃げて!もう走れなくてっ!」
『ちょっと待てって!もう少しちゃんと説明しろって!』
「とにかく助けて!」
『黄瀬、お前今ってうお!?何すんだそれ俺のケータイ!』
「青峰っち…っ?」
『涼太、今どこにいる?話は隣で聞いていた』
「赤司っち!今、帰り道にある神社に…!」
「みーつけた」
「…っ!?」
声に振り向くと、すぐ後ろにニヤけた顔の男がいた。
振り向いた時に携帯を取られてしまった。
「ダメだよ涼太君。友達なんか呼んじゃ」
「く、来るな!近づくな!」
「どうして?涼太君は僕の恋人なのに」
「いつ誰がアンタの恋人に…っ!…あれ?これ前にも…あ!」
パッと手紙の事を思い出す。
「…あの手紙、アンタが…?」
そう問うと、男は嬉しそうに答える。
「気付いてくれたんだ。さすが僕の涼太君」
「だからアンタのものになった覚えはないし、そもそも俺ちゃんと恋人いるから!」
「…え」
俺の言葉に男は目を見開いた。
けどそれは一瞬で、すぐに目を細めて俺を押し倒した。
「…なっ!?」
俺の上に馬乗りして、両手を頭上で一つにまとめられた。
「浮気はダメだよ。一生僕だけを愛してくれるって言ってくれたじゃないか」
「それはアンタの妄想だろ!離っ…う…っ」
暴れて大声を出しすぎたせいで頭がズキズキと痛みだし、体も力が出せない程にダルい。
「あれ?涼太君顔赤いし息も荒いね。具合が悪かったの?」
「いいから…離せ…!」
「僕が介抱してあげるね。そのネクタイ苦しいよね。外してあげるね」
「!?」
男は俺のカーディガンを器用に脱がせ、ネクタイを外した。
そのネクタイで俺の両手首を柱と結びつけられる。
「シャツのボタンも開けよっか」
驚く俺を余所に、ボタンも全部開けられてしまった。
…こいつ、本当にヤバい…っ!
「涼太君の体、すごく綺麗だよ」
「や…っ、触るな!」
腹を撫でられ、鳥肌が立ちそうになる。
気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い…!!
この酷い寒気は、具合が悪いからではなくコイツのせいだとだんだん思えてきた。
「…恋人だから、いいよね?」
「は?…んっ!?」
意味の分からない言葉に思わず聞き返すと、いきなり口唇を塞がれた。
「んぅ…、やっ…ふ…っ」
少し開けた隙間から、男のザラザラした舌が入り込んでくる。
気持ち悪くて吐きそうで、苦しさに涙が出てくる。
それから地獄の様で、胸を撫でられたり舐められたり、首筋に顔を埋めてきたりと、俺の体に跡を残していく。
「……っ…」
「可愛い声、聞かせてよ」
いつまでもニコニコとニヤついた顔の男を、目一杯睨む。
「何でそんなに怒ってるの?気持ち良くない?」
女の子じゃあるまいし、気持ちいい訳がない。
それに、赤司っちならまだしも、好きでもない男に触られても気持ち悪いだけだ。
赤司っちとはこんなことまだしていないから余計だ。
「もう、こっちもいいかな」
ベルトを抜き取られ、ズボンを下着ごと脱がされる。
「ひ…っ!」
後ろに指が入ってきて、喉の奥から小さく悲鳴が上がる。
時間をかけて2本3本と増やされて掻き回されて、感じたことない感覚に腰が抜けていく。
「入れるよ?」
「い…や…ぁ…っ」
暫くして指が抜かれ、変わりに男のそれが突き入れられる。
「あぁっ、ん…!や、め…っ!」
下から聞こえてくる卑猥な水音に耳を塞ぎたい衝動に駆られた。
…もう、死にたい。
知らない男に自分の体を好き勝手にされ、赤司っちといつか、なんて考えてた“はじめて”を簡単に奪われた。
赤司っちに会わす顔がない。
「…ふ…っあ、かし…ちぃ…っ」
抵抗も何も出来ない自分に涙が溢れて止まらない。
その時、複数の足音が聞こえてきた。
音はどんどん大きくなっていき、俺が今いる寺の前で止まった。
それと同時に、襖が勢いよく開けられた。
「涼太…!」
「黄瀬!」
「黄瀬君!」
「…み、な…っ!」
襖から入ってきたのは赤司っちと青峰っち、それに黒子っち、緑間っち、紫原っちの5人で、俺と男を見ると目を見開いた。
「てめぇ!黄瀬に何して…!」
バキッ!
青峰っちが叫ぶよりも早く、赤司っちが男の顔面を思い切り殴った。
「ぐあ…っ」
殴られた男はバランスを崩して後ろに倒れた。
そのお陰で俺の中から男のものが出ていく。
「おいっ、大丈夫か?黄瀬!」
「これ、着てください」
青峰っちと黒子っちが急いで駆け寄ってきてくれて、心配そうに見つめられる。
縛られている両手を解放してもらい、黒子っちが肩にかけてくれたブレザーをぎゅっと握って無理に笑顔を作る。
「だ、大丈夫っすよ…。あり、が、とう…」
「無理して笑わなくていいです」
「顔ぐちゃぐちゃだぞ」
ぶっきらぼうながらも、青峰っちが服の裾で顔を拭いてくれた。
「ひいぃ…っ!ぁぐっ!」
男の悲鳴に視線を向けると、赤司っちが男の上に乗り、何度も顔を殴っていた。
「がっ、は…!やめ…っぐ!」
「僕の涼太を……殺す…っ」
赤司っちの顔はいつもの静かな表情だが、目は完全に瞳孔が開いていた。
人ひとり殺せそうなその迫力に、みんな止めるのを忘れて息を飲む。
「……は…、赤司、それ以上は本当に死んでしまうのだよ…!」
我に返った緑間っちが、赤司っちの腕を掴んで止めに入る。
「………くそ…」
赤司っちは息を整えてゆっくりと気絶している男から退き、俺の前に片膝を立てて座った。
「……遅れてすまない、涼太」
「…赤司っちのせいじゃないっすよ…。俺が…っ、俺のせいっす、から…」
1人で帰った俺が…、抵抗出来なかった俺が全部悪いんだ…。
「お前は悪くない…」
震える俺を、力強く抱き締めて安心させようとしてくれる。
しばらく赤司っちに体を預けていると、赤司っちの口唇が俺の口唇と重ねられた。
「…ん…、ぅン…」
「おい!?お前ら俺たちがいること忘れてねーか!?」
「…デリカシーがなさすぎますよ、青峰君」
「空気読もうよ峰ちんー」
「俺たちは外に出てるのだよ」
みんなは俺たちを気遣ってか、外に出ていってくれた。
そのあとしばらく、お互い無言のまま何度も深いキスを交わした。
赤司っちの口唇から、塩の味がしたような気がした。
─END─
続くかもしれません)ω()ω()ω(