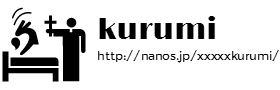trash(R18,パロ,グロごちゃ混ぜ,極めて乱文,)
▼ _ ChanBaek
目が覚めると白い天井があった。白い天井に、白い壁。それだけでなく、窓から入ってきた朝焼けの光に照らされて、より一層シーツも白く光っていた。
少し体を起こして明るくなり始めた窓の外を眺めると、まだうまく働きださない頭を使って、今日は何をして時間を潰そうか、と考えた。
毎日、毎日、これが僕の日課になっていた。いつにしても僕は退屈で、ここから出られることはないからだ。
初めの頃はただ、風邪かなんかだろう、と思っていたのに。
頭を振る。いけない。こんなこと、考えたって仕方が無いじゃないか。僕はふうっと息を吐いた。あれこれ、考えていたって治るわけでもないし、気分が暗くなるだけだからやめよう。
そのとき、窓の外へちょうど二羽のすずめがやってくるのが見えた。兄弟か、友達か、はたまた恋人か、ということはわからないが、二羽は戯れるようにして仲良く飛んでいた。窓越しからでも、ちゅんちゅん、とわずかに小高い鳴き声が聞こえる。その遊ぶすずめたちがあまりにも愛くるしいものだからつい、かわいいなあ、と自然に笑みが浮かんできた。
けれども眺めだしてしばらくすると、すずめはどこかへ飛んで行ってしまった。再び窓の外には味気のないビルの街が広がった。白けた空は灰色のコンクリートばかりが乱立していた。ここに寝ている間に次々と増えたその灰色。景色を見るには視界が悪かった。眺めているだけでどこか取り残されたような、見放されたような心地がしてくる。
窓の方に顔を向けたまま、僕はベットに倒れた。ぎし、という音がわずがに病室に響いた。けれどもそれ以外の音は他にせず、なんとなく、感傷的な気持ちになった。
ベットサイドの時計を見ると、まだ5時を指していた。いつもながら時が進むのは遅いと感じた。することもない僕からすると、それは非常に焦れったかった。
頭の上で手を組みながら、もしも時間というものを自由に触れるとしたならば、僕はいったいどうするだろうかと考えた。マイペースに回る長針や短針に耐え切れずに、自分の手でくるくると回してしまうのだろうか。やがて僕へと訪れる"その時"を、自らの手で迎えに行ってしまうのだろうか。
別段、特に眠気もしなかったが僕はもう一度目を閉じた。起きていても、することがない。看護師が体温を計りに来るまでの間、少し眠ることにした。
「キョンくん、……ベッキョンくん、起きてくださーい」
優しいふんわりとしたその声に、ゆっくり目を開いた。ぼやけた視界が徐々にはっきりとしてくると、柔和にほほえむ彼女が見えた。担当の看護師、ユナヌナだった。相変わらず、彼女の笑顔は眩しかった。目をこすりながら差し出された体温計を受け取って、それを脇に挟みこんだ。何やら紙へ記入しながら、いつものようにヌナが問診を始めた。
「体調はどう?」
「いつもどおりです」
「そう、よかった」
これまた特にこれといって取り止めもない日常。まあ、問診なのだから仕方がない、というか、当たり前なのだけれども。
そうして、いくつかの冷めた問診に答えているうちに、高い電子音が鳴った。平熱を示した体温計を渡しながら、それにしても早くなったもんだなあ、と感心した。以前は最低でも二、三分くらいは待たないと熱は測れなかったのに、今ではものの一分ほどで測れてしまう。技術の進歩って偉大だ、なんてぼんやりと考えた。そして同時に恐怖を感じた。進歩する時代の中、ここで寝てばかりいる自分は一体大丈夫なものなんだろうか、と思った。
最後に学校行ったのはいつだったか。授業を受ける自分の姿は遥か彼方の遠い思い出のようだった。しばらく、友達にも会っていない。おぼろげながら浮かぶ顔たちは、中学生のままで止まっている。
ぽすり、と後ろへ倒れた。
僕は、何をしているのかな。
見上げた天井は相変わらず白かった。
そのうち、ヌナはやることを終えて出て行って一人きりになった。しかしそうかと思えば、またしばらくするとごはんが運ばれてきた。
味の薄いごはんにも慣れてしまって、もはや文句すら忘れて平らげた。きっと慣れすぎて、ピザとかラーメンとか、万が一、そういう味の濃い食べ物が出てきたとしても全て食べられないだろうと思う。
といっても、食べる機会が無いから、目の前にそれが置かれたら食べてしまうのかもしれないけれど。
後ろ手で腕を組むと、瞼を下ろした。
けれど目をつぶってみたものの結局眠りに落ちることはなかった。今日の診察が午後からだったので、外に出ることにした。外と言っても病院にある庭のようなところだ。病院の中屋上にも似たようなところがあるが、今日は病院の敷地内のところに行った。やはり部屋にいるよりは幾分もましである。何よりも、自分の中の最近のマイブームでもあった。
一歩、一歩と足を踏み出すと、空からの暖かな陽を感じた。見上げると、空はすっかり青く染まっていた。あとひと月もすると夏が来るらしい。僕にはてんで時の流れがわからないけれど、カレンダーがそう言っていた。
婦長さんの趣味で植えられた花たちに囲まれ、しおりの挟まった本を開いた。ひさしのついたベンチに座って、時折風に撫ぜられながら読書をするのはこの上なく気持ちがよかった。温もりを感じる日差しや風は僕の身体をやんわりと包み込む。
こんな時くらいだろうか、幸せを感じるのは。
そう思った途端、急にぴゅうっと強い風が吹きつけてきた。持っていたしおりはするりと手をすり抜けて飛んでいってしまった。
赤色のしおり。いくらか前に、母からもらったものだった。どこかで買ってきたのか、それとも自分で作ってくれたのかはわからないが、シンプルなデザインでかわいらしいものだった。
退屈な病室に、数冊の本とその赤いしおりを持って見舞いに来てくれた母が、なんだかすまなそうな顔をしていたのを覚えている。いや、確かに笑ってはいたのだが、予定外に伸びていく僕の単調な生活を申し訳ないと思っているようだった。寝言ではごめんなさいと言っていた。健康に産んであげられなくて、ごめんなさい、と。
一度も責めたことはないのに。そんな風に思ってほしくなかった。誰かのせいにしたいなら、そんなものは神様のせいにすればいいのだから。
ぴゅうっと飛んでいった赤いしおりは花壇のほうへ消えたみたいだった。やれやれ、と肩を落としつつ立ち上がると、ぐらりと視界が歪んでバランスを崩す。慣れたもので、反射的に倒れないように足が踏ん張った。嘆息をついて頭を振った。
しおりはどうやら大きな花壇の中に入ってしまったようで、取るのが難しそうだった。
「どうしよう……、一輪でも花踏んだら、ぜってー怒られる……」
色とりどり咲き乱れる花たちが光に照らされて、輝かしいほど眩しかった。そんなに見つめないでくれ。僕はしおりを取りたいだけなんだから。けれども、顔を真っ赤にしながらきんきんと高い声で怒る婦長さんを思うと、どうしても足がすくんで踏み出せなかった。
「俺がとってあげるよ」
「え?」
はっと、顔を上げた時にはそこに男がいた。背が高い、けれども見知らぬ若い男だった。その身体を見たが、右足にギブスをはめ、松葉杖さえついているのに、いったいどうしようというだと思った。
けれども、そんな声すらかける暇もなく、彼は松葉杖を置くとひょいひょいと花壇に入っていった。そうして、笑顔で戻ってきた。
なんてことを! とっさに花壇に目をやった。しかし、見事に一輪も花は踏まれていなかった。ほっと胸をなで下ろした。けれどそれと同時に、何なんだこいつは、という気持ちが湧いてきた。
じろじろと疑心の目でもって彼を見ると、男は松葉杖も拾わず、真っ先にしおりを差し出してきた。
「これだよね、はい。どうぞ」
きらりと光った白い歯。その、まるで王子様のような姿は女の子には抜群に有効だろうが、あいにく僕は男の子であったので、てんで無効だった。むしろ不信感のようなものがむくむくと湧き上がった。
一応礼をしてしおりを受け取った。彼が払ってくれたのか、土は着いていなかった。指を挟んでいたページにしおりを挟み込んだ。
「ありがとう、わざわざ」
いまどきこんな若者いないだろうな、と考えながら、自分も若者だろうが、と心内ひとり突っ込んだ。
彼は、いいよ、ぜんぜん、と満面の笑みを浮かべ、照れくさかったのか、頭をかいた。
彼を見上げるに、必然とその、やけに整っている面立ちに目が行った。ぱちりと大きな瞳に、すらりと高い鼻、そして形の整った唇。えてしてイケメンは心すら綺麗なのか、と思った。
けんけんと片足で移動して松葉杖をとった彼は、口を開いた。何か言うのかと思えば、しかし僕から視線をはずして開閉を繰り返すばかりで、あー、とか、うー、とか言ってまともな言葉がでてこなかった。
なんだこいつ。
「あの、なんか、あるの?」
「えっ。あ、え、あー……」
「……なに?」
「あ、いや、そのえええーっと……っ」
べつに特別僕が威圧するように言ってるから彼が口をこもらせているわけではないことを留意してほしい。ごくごく自然に、むしろ優しく聞いているのに、僕らの間には風しか通り抜けない。
「僕ベッキョン。名前、なんていうの」
いよいよ耐えかねて僕は助け舟を出した。図体でかいのに何をためらっているんだか知らないが、イケメンがそんなんじゃだめだろうよ。
「あっ、俺っ、……チャニョル! 俺、パクチャニョルって、いうの」
「……チャニョル。うん。よろしくな」
いままで外れていた視線が急に僕を捉えると、きらきらと目を輝かせて男は握手を求めた。やや勢いに身を引きながらもその手を握り返した。なんだこいつ。変な奴。彼の後ろにぶんぶんと振れるしっぽが見えた気がした。
「あ、そういえば何歳なの?」
ふと、なんとなく聞いたそんな質問を皮切りに、僕らはそれから長い間おしゃべりをした。
最初に抱いていた不信感のようなものなんて僅かなもんで、豪快に笑い、声を上げて大袈裟に手を叩くチャニョルと仲良くなるのに時間はかからなかった。病院にはおじいさんやおばあさんばかりで、こんなに気の合う話し相手がいなかったせいかもしれない。彼と話しをしているとすうっと心が晴れていく感じがした。
チャニョルはどうやら僕と同い年で、つい最近、入院したらしい。交通事故にあって、派手に車に吹っ飛ばされたのだが、奇跡的に右足の骨折だけで済んだという。自身のことを「ハッピーウィルス」と称していたが、あながち嘘でもなさそうだと思った。にこにこ笑う彼には、神様だってきっと、こいつを悲しませたくない、と思うだろう。
「ベッキョニは、何で入院したの?」
ベンチに座って前をまっすぐ見ながら、チャニョルがそう言った。隣を向くと、風にふわりと浮いた彼の髪が柔らかそうにうねるのが見えた。何気なく、手を組む。
「んー、とねー」
僕は唸りながら、さてなんと答えようか、と考えた。絡めた指の間を眺めながら、どう言ったら彼は普通に受け流してくれるだろうかと答えを探したが、なかなか見つからなかった。
「うーん……ちょっと、風邪の菌が肺に行っちゃって、べつに、……まあ大したことないんだけどね」
チャニョルの顔を見たら、ついに口から嘘が出てきた。そうなんだ、と彼は頷いてくれたけれど、こんなの真っ赤な嘘だった。原因不明なんです、理由は見つからないけれど、体が弱っていくんです、……なんて。さっき会った人間に言えるわけがなかった。それも、やっと出来た、"友達"。尚更言えるわけがなかったし、言いたくなかった。
なんとか笑って嘘を繕う。こうして気持ちを隠して笑うのは、母譲りなのだろうか。
「はやく良くなるといいね。そんで、良くなってさ、退院したら俺ら海行こうよ」
ししし、といたずらっぽくチャニョルが笑った。そうだね、と曖昧に答えたが僕はもちろんそれが叶わないことを知っていた。
海かあ……、いいなあ……。
笑みがこぼれた。きっと、楽しいだろう。白く、薬品の匂いが染みついた狭い部屋ではなくて、青く、塩の匂いが鼻腔をくすぐる大きな、雄大な海。
僕は、ベンチから立ち上がった。
「チャニョラ、診察の時間だから行くね」
「そうなの? うん、じゃあ、またね」
診察は午後からだった。また嘘をついた。彼の笑顔が眩しくて、見ていられない。夏の予定なんて立てたところで出来るわけないのだ。ぶんぶんと手を振った彼に背を向ける。病院に入ろうとしたころ、俺の病室305だからあ、と声が届いた。振り返ると、大きく手を振り返すもんだから、バランスを崩して倒れそうになっていた。ばかなやつめ、と心の中で思ったが、すぐに自身の頬が緩んでいたことに気がついた。
病室へ戻ると、母がいた。
「ベッキョナ」
「わ、母さん、どうしたの。パートは」
決して裕福でない家庭なもんだから、僕の入院費用がかさむため、入院してしばらくすると母はパートを始めた。その頃はまだ自分のこともよくわかっておらず、「すぐに退院するから、ごめんね」と言っていたが、結局、いまに至る。
母が少し小さくなった顔で笑った。そして手に持った袋を掲げた。黄色が透けて見えた。
「夏みかん、食べる? もらったの。まだ、なつじゃないんだけどね」
僕は頷く。
母は夏みかんを剥き始めた。その光景を見ると自然と口の中に唾液がじわじわ染みてきた。僕はなんとなく、口を開いた。
「母さん、僕、いつ治る」
言葉は響くことなく消えた。
母の手は止まらなかった。自分で言っときながら、言葉にしたことを後悔した。なんでもない、と小さな声ではぐらかして、夏みかんを一房口へ放り込んだ。
砂糖もなしに食べるのが好きだった。噛みしめるたびに、粒から飛び出す酸味が舌に広がり、からからに乾いていた口に染み込んでいく。いつもはそれだけで心がすうっとするのに、今はどうしてか酸っぱさが口内にとどまり続けた。
母が夏みかんを全て剥き終える。手を洗いに行って、タオルで丹念に拭き取りながら僕に微笑んだ。
「大丈夫だから」
「……うん」
母のそれは、むしろ祈りのようにも聞こえた。が、やはり母の言葉には力があった。じんわりと心が温まる。くすぐったくて、なんとなく、今日出会った「友達」について僕は話したくなった。
ふふふ、と母が笑う。僕は少しだけ大袈裟に話しをする。母が笑ってくれる。それが嬉しかった。
母は本当に、楽しそうに聞いてくれた。そう、そうなの、そうなんだ、と時折相槌を打ちながら、夏みかんを口にする。僕はいつも母に外の話を聞くばかりだったから、こうして彼女に物事を話すのは久しぶりだった。母も、嬉しそうだった。
続きが浮かばない┗(^o^ )┓三