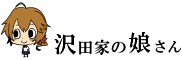私は一度だけ父さんと二人でイタリアに行った事があった。
確か七、八年前くらい。七歳になった頃だろうか。まだ「ゆりかご」の事件が起きる、ちょっと前。よくは覚えていないが、私は「おじいちゃん」に会いに行ったのだ。
その時私は、無駄な好奇心を発揮してしまい、お父さん達からこっそりと離れて探検を始めた。
広すぎる家と、そこに初めて来た子供の組み合わせがどうなるか。
答えは簡単。私はおじいちゃんの家で迷子になってしまい、一人途方にくれて泣いていた。
そんな時、私の前に現れたのは一人の少年だった。
「Che cosa ci fai qui?」
金髪の男の子は壁にもたれ掛かりながら小首を傾げて、私を見ていた。年齢は多分私と同じくらい。前髪が長くて目は見えないけど、口や鼻は整った形をしていて、綺麗な子だというのは分かった。
「えっ、何?」
男の子が何を言ったのか分からず、私は酷く戸惑ったのを覚えている。
「日本語かよ。お前ジャッポネーズィ?」
「じゃ、ぽ?」
「日本人か聞いてるんだよ、ばっかじゃねーの」
そう言って男の子は歯を見せて笑う。その時私はバカにされてるのもよく分からず、つられて笑った。年の近い子がいたのと、日本語が飛んできて安心したのもあったと思う。
「そういや家光がガキ連れてきたって、ボスが言ってたな。お前がそれ?」
「えっと、多分、そう。私のお父さん、家光って言うの。あなた、お父さんの事知ってるの?」
「知ってる」
ししし、と男の子は不思議な笑い方をする。
「お前迷子だろ」
「……うん」
「家光絶対怒るぜ。あいつ、離れるなって言ってただろ」
「う、うん」
「やっぱしねー。あーあ、じゃあお前、家光におしおきされんだろーな」
「……」
男の子の笑みが濃くなる一方、私は再び泣きそうになっていた。悪いことだと分かっていたのに、勝手に離れて迷子になったのだ。お父さんが探しに来る前に戻って「ずっとここにいたよ」って誤魔化そうと思ったけれど、道が分からず元の場所には戻れなかった。怒られたらどうしようと思ったら怖くなって、泣いていた所で出会った少年から追い討ちをかけられる。
そんな状況で、私は絶望的な気持ちになっていた。
「王子が助けてやるよ」
「え?」
私が泣くのを確認してから、男の子は言った。なんとも意地が悪いと思う。
「王子なら、お前がそんなに怒られないように出来んぜ」
「ほんと?」
「うん」
男の子はにんまりと笑う。
「お前これから王子と遊べ」
「は?」
「そうすりゃ怒られないから」
なんとも腑に落ちない提案だった。けれど、その時の私は藁にでもすがりたい気持ちだったので、その提案を受け入れるしかなかった。
「わ、分かった……遊ぶ。あの、王子って?」
「俺」
「あなた王子さまなの?」
「うん」
相変わらずの笑みを見せながら、男の子は自身の頭にあるティアラを指差した。
「わあ、キレイ」
「王子の証」
「すごいねえ、王子さまなんだね」
私がきらきらした瞳で見ていたら男の子は気を良くしたらしい。機嫌良く、跳び跳ねるように歩き始めた。
「こっち」
私は彼の後ろを着いていき、その日は彼と楽しく遊んだ。正直何をしたかよく覚えていないけど、ろくな事をした気がしない。うん、覚えてないけどそれは間違いないと思う。だって相手が相手だし。
暗くなってきた辺りで、黒い髪をした顔の怖い男の人が私達の前にやって来た。その人は私を見るなり、何故か王子君を怒鳴り付けた。私も怒られるんじゃないかと終始どきどきしていたけれど、黒髪の人は私には怒らなかった。王子君は怒られている間、謝りながらもニヤニヤとしていて全く悪びれた様子がなかった。
しばらくして黒髪の人がお父さん達を呼んできて、私は王子君から引き離された。
怒られるんじゃないかとはらはらしたけれど、やっぱり怒られる事はなかった。話を聞いていたら、王子君が私をお父さんから引き離し、無理矢理連れ回していたと言う事になっていた。
「だって面白そうなのがいるから。王子暇つぶししたかったし。別に殺した訳じゃねーから良いじゃん」
何やら物騒な事を言って王子君は笑っていた。
結局、私が勝手に探検して迷子になった事は、誰にもばれなかった。
「よう」
「王子さま」
その夜。皆が寝静まる頃。王子君が私の元にやってきた。バルコニーの外から、身を乗り出してこちらを見ている。
私はお父さんを起こさないようにベッドから出て、慌ててそちらに向かった。王子君はバルコニーの外側から柵に肘をついて、にやにやとしていた。
「お仕置き、なかっただろ」
「うん。王子さまの言うとおりだった」
「当たり前じゃん。だって俺王子だもん」
ししし、と例の笑い声。
「明日帰るんだろ」
「うん」
「見張りが着いてるから、俺がお前と会えるのはこれが最後」
「そうなの?」
「うん」
何だか大変な事をしてしまったんじゃないだろうか。私がまた泣きそうになっていると、王子君は歯を見せて笑う。
「あの、ごめんなさい」
「別に。王子にはこんなの迷惑のレベルに入らないし。お前つまんなかったけど、暇つぶしにはなったしな」
「……」
「じゃー。家光が黙ってるうちに、王子帰る」
肘を下ろし、彼は外側へと踵を返す。
「王子さま」
「ん」
「王子さまの名前は?」
「どうせお前とは、もう会わねーと思うけど。ベルフェゴール。ベルで良い」
「私は」
「沢田ソラだろ」
知ってる、と言う声と共に、王子君、もといベル君は二階に位置するバルコニーから飛び降りた。
その時以降。
私の中で王子と言えば、金髪でティアラで黒コートにボーダーシャツの男の子という変なイメージが定着した。