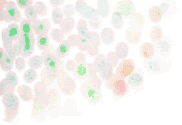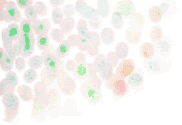
ろく
夢を見たような気がする。
まだ1歳になったばかりの悟天を背負いながら、悟飯と並んでパオズ山を散歩する夢。
小鳥の囀り。
獣の息。
虫の鳴き声。
悟天がきゃらきゃら笑う声。
悟飯の優しい笑み。
お母さんが遠くで呼んでいる。
大きく手を振るお父さん。
私は……………
「………」
ふと目を覚ます。一瞬ここがどこだかわからなくて真上からの木漏れ日をぼーっと眺めた。けどすぐに自分の今の状況を思い出して飛び起きるけど、腕に走った激痛に再び地面に逆戻りとなった。
「いってぇー…!な、なんでこんな痛いの…」
戦ってる時は痛みはあれどこれほどじゃなかった。こんなに痛くはなかった。恐らく、アドレナリンがどっばどば出て痛覚麻痺してたんだと思う。
…まぁ、動かせないほどではないんだけどね。
「あぁーッ!!シュエちゃん起きたぁぁあああ…!!」
「ぜ、善逸く、ぶほッ」
「うわぁぁああああああんよかった…!よ"か"っ"た"よ"ぉぉおおおお!!!」
「ぢょ、善逸ぐ、マジかッ…!ぐるじッ…!」
私を絞め殺さんばかりに締め上げてくる善逸くんに軽く殺意が湧いた私は決して間違っていない。湧いてもいいはずだ。
「ええい、離せ!!」
「ぎゃッ」
ぎゃッ、じゃないっての!こっちがぎゃッ!って言いたいわ!!
息を整えながら半目で善逸くんを睨みつけていると、我に返ったらしい彼は申し訳なさそうに眉を垂らした。
そ、そんな顔しても許してやんないんだからね?!
「ご、ごめん、安心してつい…!てか、シュエちゃんその腕大丈夫なの!?一応布は巻いたけどちゃんと消毒してるわけじゃないから早く手当てしてもらわないと…!あ、そ、それと!なんか気付いたら夜が明けてる上に鬼がいなくなってたんだけど、もしかしてシュエちゃんが倒してくれた…!?」
「へ、」
「うわーんさすがシュエちゃんありがとぉぉおおおお…!君のおかげで命拾いしたよぅ!最初ぶん投げられたときマジでどうしようかと思ったけど、ちゃんと守ってくれたんじゃんんんん…!」
「な、何言って…あの鬼は善逸くんが倒したんだよ…?」
「は?いやいやいやいやいや!!ないから!絶対にありえないから!俺があんな鬼倒すとか無理無理の無理だから!!あれはシュエちゃんが倒してくれたんだろ!?謙遜してんの!?またまたぁ」
えー…、と…一体どういうことだろうか…
あの鬼は確かに善逸くんが倒していた。私の意識もまだはっきりしてたし、彼が放ったあの鋭い一閃を私はよく覚えている。だけど本人はその自覚が一切ないどころか記憶の片鱗もないらしい。
…どういうことだ。
改めて考えを巡らせる。…善逸くん、もしかして自分がビビりキャラだっていうのを確立させんがために演技してる…?いや、もし演技だとしてもあんなアホみたいな汚い悲鳴をあげれるわけじゃないし。
じゃあ何か。彼は眠っている時だけが本来の力を発揮できるというの。確かに眠ってしまえば恐怖も何もわからないけれど、まさか…
じぃ。善逸くんを見上げると、彼はなぜかぽぽッとほっぺを赤くして目線を彷徨わせた。いや、なんでだよ。
「そ、そんな見つめられると俺照れちゃう…はッ…!も、もしかして結婚」
「いやしないけど!?はぁー…なんか、考えるのが面倒になってきた…」
「え、何が?」
「…うーうん、何でもないよ」
立ち上がり、太陽の位置を確認する。日が昇って約2時間…ってところだろうか。善逸くんの話と照らし合わせると今日はちょうど7日目。つまり、最終日だ。今夜を乗り越えれば私たちは最終選別を生き残ったことになる。
長かった…とても…
見えてきた終わりに胸が震えた。
「シュエちゃ、本当に大丈夫…?!もうちょっと休んでた方がいいんじゃない…?」
「ん、善逸くんが手当てしてくれたおかげで思ったより平気。ありがとうね」
「!ふ、ふへ…ウィッヒッヒ」
え、何その笑い声ちょっと引くわ。
未だ座り込む善逸くんの手を引いて、朝霧燻ぶる木々の隙間に身を滑りこませた私たちであった。
そして、約束の7日後。
「「おかえりなさいませ」」
出発前の白黒のこけしちゃんたちに出迎えられ、私たちは藤の花生い茂る広場に足を踏み入れた。
どうやら帰って来たのは私たちが一番最後だったらしく、広場にはすでに何人か帰ってきていた。
そして驚くことに、この最終選別を生き残ったのは私を善逸くんを含めてたったの6人。なんだけど…1人いなくない?
「死ぬわ。死ぬ死ぬ死ぬ死ぬ。ここで生き残っても結局死ぬわ俺」
「(またそんなこと言って…)もったいないなぁ…」
この子は私が思っているよりずっと実力も才能もあった。ただ、自覚していないからこうやって自嘲したり卑屈になったりする。
白髪と黒髪のこけしちゃんたちの言葉を聞きながら隣でぶつぶつネガティブなお経を唱える善逸くんを半目で見つめた。
「さらに今からは鎹鴉を付けさせて頂きます」
いつの間にか話がだいぶ進んでいたらしい。
ぱんぱん。白髪のこけしちゃんが手を鳴らすと同時に現れる鴉たち。私の肩に止まった鴉は尾っぽの先だけ白い鴉で、その子は「カァ」とひと鳴きすると頬にすり寄ってきた。かわいいかよ…
そしてなぜか善逸くんだけが鴉ではなく雀ちゃんだった。…ねぇ、お願いだからこっち見ないで。見られても困るし交換しないよ!?
「どうでもいいんだよ、鴉なんて!!」
唐突にバシッと鈍い音が響いた。見れば、目つきの悪いモヒカンの子が白髪のこけしちゃんの髪を掴みあげ、怒鳴り散らしている場面で。
「刀だよ刀!今すぐ刀を寄越せ!!鬼殺隊の刀!!色変わりの刀!!」
「ちょッ、あんた…!」
止めるべく足を踏み出した私よりも先に、耳飾りを付けた子がモヒカンの子の腕を掴みあげた。
「この子から手を離せ!」
手が緩んだその隙に白髪のこけしちゃんを彼から遠ざける。
「だ、大丈夫?痛かったでしょ…」
「いえ、お構いなく」
「お、おう…」
とりあえず乱れた髪を直してあげた。か、感情が読み取れないぞぅ…!?
「お話は済みましたか?」
すると、何事もなかったかのように黒髪のこけしちゃんが話を進めた。君の片割れだろうに、いいのかそれで。果てしない疑問であった。
「ではあちらから、刀を造る鋼を選んでくださいませ。鬼を滅殺し、己の身を守る鋼はご自身で選ぶのです」
白髪のこけしちゃんを黒髪のこけしちゃんの方へ行かせ、私は並べられた岩礫みたいな鋼を眺める。
うーん…どれも同じに見える…
「…選ぶ基準とかって、あるの?」
「いいえ。皆様直感でお選びいただいております」
「な、なるほど…」
直感…野生の勘…言い方はなんかやだけど、こういう時、お父さんならどうするか。
…多分、なんとなくこれだと思うものを選ぶんだろうなぁ
各々が悶々と悩んでいる横をすり抜けた私は一歩、前に出る。
「じゃあ、私一番手」
「え、シュエちゃん決めたの!?」
「ん、まぁね」
「では、お選びください」
「うん。私はねぇ…」
そうして私が手に取ったのは、右端の少し大きめの鋼だった。
「おーい!シュエちゃーん!」
隊服を受け取り、後日家に刀鍛冶師が刀を届けてくれると言うので遠慮なく帰路を辿っていたのだが、不意に後ろの方で名前を呼ばれた。
「善逸くん」
「ぜ、ぜぇ…け、怪我してんのに歩くの早くね…!?急いでんのか競歩してんのかどっち!?」
「いや、どっちもしてないけど…。どったの?」
「べ、別に何か用があったわけじゃないけど…帰る方向が同じみたいだったから、せっかくだし途中までって思って…」
「わざわざ追いかけてくれたんだ?」
「だ、ダメだった…?」
「ダメじゃないです」
ち、ちくしょうなんだよ今の顔!うるうるおめ!子犬かッ!悟飯もよくそんな顔してたよ!あの子は確信犯だったけど!
「そっか、よかった」
「(む、無自覚さんだぁあああ…!!)」
まさかの事実に驚愕でしかない。ほわほわと笑う善逸くんが眩しすぎて目を細めているとめっちゃ怪訝な顔された。解せない。
「どんな色になるんだろうね、刀」
「…色が変わろうが死ぬ運命には変わりないよ…」
「またそんな卑屈言う…善逸くん強いんだから、もっと自信持ちなよ」
「はぁ?俺が強い?ないない、魚が地べた這うくらいありえない。俺超絶弱いよ。見てただろ?」
「見てたけど…うーん、なんて言うべきか…。でもさ、そうやって卑下するのもいいけど、ほんのちょっとでもいいから自分のこと信じてあげてよ」
「ぅ…」
ぽんぽん。頭を撫でると善逸くんは顔を真っ赤にして、戸惑いながら目線をあらぬ方向に向けていた。
「…シュエちゃんってさ、よく人の頭撫でるよな」
「え、ダメ?」
「ダメじゃないです…!」
「ならよかった。…あ、それじゃあ私こっちだから」
「え、もう行っちゃうの?」
「じっちゃんに早く報告したいから。…もぉー、そんな寂しそうな顔されちゃ行きにくいじゃんよ…。大丈夫だって、同じ鬼殺隊にいるならどこかの任務でまた会えるよ。その時はよろしくね」
「…うん。じゃあ」
「またね」
別れ道に差し掛かり、私は右に、善逸くんは左に曲がる。時々ちらっと振り返れば、遠くの方でぶんぶんと善逸くんが大きく手を振っていたから、私も思いっきり振り返した。
お互いがついに見えなくなった頃、日が沈む前に帰るべく周りに誰もいないのを確認して空を飛んだ私であった。
だって、楽したい。
じっちゃんの小屋に辿り着くと、私を見るなりじっちゃんは泣きながら抱きしめてきて「よく、頑張った…!」と消え入りそうな声で呟き、それに感化された私が泣き出すという事態が起こったのはまた別の話。
▼ ◎