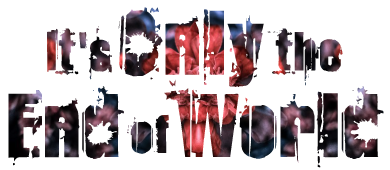BARブルズアイは相変わらず趣味のいいマスターの選曲によって気の利いたサウンドが響いていた。
そのロックに耳を傾けながらダンテはカウンターで頬杖をついて暮れていく空の色を眺めていた。溶け始めたストロベリーサンデーの器からつう、と水滴が落ちる。
「デザート、口に合わなかったかい?」
グラスを拭きながら心配そうにマスターが尋ねてくる。
「いや、美味いぜ、ちゃんと」
ただイチゴが少しばかり酸っぱすぎるなと思い、メアが作ったイチゴのカスタードパイを思い出してしまっていた。また食いたい、あの味が。違う誰かでは同じ物は作れないだろう。シンプルなストロベリーサンデーでも味が微妙に変わるのと同じように。
ダンテは溶けたアイスを口に運んだ。
外からドタバタとした足音が聞こえ、ドアベルの音と共にエンツォが飛び込んでくる。
「すまねぇ、遅くなった」
「おお」
「んだよ、五徹したみてぇなシケたツラしやがって」
実際メアが消えて一週間が過ぎようとしていたのでエンツォの指摘は凡そ正しかった。メアと眠る時だけ不思議と悪夢を見ないことに気がついてしまってから、ダンテはますますの睡眠不足に陥っていた。だからといって睡眠薬に頼る気にもなれず漫然と夜を過ごしている。
隣の椅子に腰を落ち着けてビールを注文しながら、エンツォは小脇に抱えていた茶封筒をカウンターの上に差し出した。
「頼まれたレッド・ラムの資料だ。木っ端みたいな情報が腐るほど出て来て選別に手間取っちまった」
「……レッド・ラムはマフィアの名称なんだよな」
しょぼつく目で資料を追いかけながらダンテはメアが持ち去ったゴシップ誌の内容を思い出していた。ベラルディの逮捕と共に彼の裏社会での動きも記事にされていたのだ。組織名は書かれていなかったが、あの舞踏会の晩にベラルディが叫んだ"レッド・ラム"というワードが怪しいと踏んだダンテはエンツォに情報収集の依頼をかけた。情報屋界隈でもレッド・ラムは決して無名ではないようで、あんまり近付かねえ方がいいぞ、とエンツォからも真っ先に警告はされていた。
ビールのジョッキを煽りながらエンツォはニヤリと笑ってダンテの背中を強く叩く。
「とかなんとか言って、どうせお前のことだからあの子に愛想尽かされるようなことしただけなんだろ?」
「うるせぇな……マジで耳から鉛玉食わせるぞ」
あまり実りの無さそうな資料の束をうんざりとめくっていたが、ダンテはふと手を止めた。
「この写真は?」
「あー、レッド・ラムのメンバーが入れてる識別タトゥーだ」
殺人現場の死体写真のズームだった。死体の脇腹に、頭蓋骨に血の滴るハートマークが絡みついたような意匠のタトゥーが入っている。どこかで見覚えがある気がしてダンテは寝不足の頭をもたもたと回転させる。
「ああ……あの悪魔か」
漁村で倒した"ノスフェラトゥ"と呼ばれていたやつの脇腹にも似たような図柄が入っていた気がする。それをメアが発見していても何らおかしくはない。
もう少しで埋まりそうなパズルのピースが上手くまとまらず、ズキズキとし始めた頭痛にたまらずダンテはこめかみを揉みながらマスターにアルコールを頼んでいた。
「自虐行為だろ」
「病は気からって言うだろ」
言葉まで通じなくなったのか、と呆れるエンツォを横目にボンベイ・サファイアのショットを一気に流し込む。
ーーもしもメアの父親がレッド・ラムの関係者、ないしは"掃除屋"だったら?
酒に喉を焼かれながら頭に浮かんだそのifの端を離さぬように、さらに資料の紙を繰る。
「主な資金調達の方法は薬か……マフィアの常套手段だな」
「"キル・デビル"とか言うブツだったかな。よくトブつって最近人気らしいぜ。俺はやりたかねえけど」
「なんだその馬鹿げた名前は……」
なんでも禁断症状がやばいらしい、とエンツォは肴のピスタチオの殻を割りながら言った。
「化け物みてぇに暴れ出すとかなんとか」
「そんなんで薬は流行るのか?」
理解出来ねえ、とボヤきながらダンテは溜め息を吐く。
「それだけキマってる時が最高なんだろ」
エンツォのうろんげな声を聞きながら、ダンテはぼんやりと目を通していた項目ではたと手を止めた。ベラルディが資金提供していた製薬会社の開発者レポートだった。警察からの流出書類らしく黒塗りで潰されている行も多かったが、欠片を拾い上げていくと、
「……このモイラ・スカーレットって科学者がキル・デビルの元となる向精神薬を開発したってことか」
スカーレット、そのファミリーネームにダンテは背筋がぞくりと粟立つのを感じた。たまたま、だろうか。メアのファミリーネームもスカーレットだ。
額に手を当てて考え込んでいるとエンツォが横合いから手を出して資料をパタパタと繰る。
「ベラルディも出資してた民間軍事会社が、その薬を自社の傭兵に使おうとしてたらしい。PTSDの抑制だとか戦力向上だとか何とかこの辺に書いてあったけど、めんどくさくて読んでねえや」
化け物、キル・デビル、傭兵、戦力向上……怒涛のようになだれ込んで来たキーワードが脳内で散らかって上手くまとまらない。あまり小難しいことを考えるのはダンテの性分に反していた。ただ、兎角イヤな予感がする事だけは確かだった。
「まあ一番重要なのはこれだな」
ビールで喉を湿らせてからエンツォが封筒の中に残っていた一枚の写真を引っ張り出してダンテの前まで滑らせた。
そこには走り書きの住所と人物の名前も添えられている。
「ジェイド・ハジェンズ……」
隠し撮り写真の中の男は粗暴な顔つきをしており軽薄そうな笑みを湛えていた。写真内のクラブらしき薄暗い室内と走り書きの住所に記された店名を擦り合わせる。
「そのハジェンズって男がレッド・ラムの幹部クラスの一人らしいんだが、そいつしか足取りが今のところは掴めなかったんだ。そのクラブによく出入りしているらしい」
「隠れんぼが大層お上手みたいだな」
「そいつをふん捕まえてアレコレ聞き出してみればいいんじゃないか」
酔いの回ってきた目付きでエンツォがポリポリと頬をかく。
こいつがメアの父親の件をあっさり吐いてくれれば話が早いんだが、とダンテは眉間を曇らせる。
「そうカンタンに行くかな。俺は"生体処理"は苦手なんだ」
ドロドロに溶けたストロベリーサンデーの器を煽って、ダンテはマスターへ飲みの料金とエンツォへの情報量をそれぞれに差し出した。
「おい、お前がツケねえのは珍しいな」
「怒るやつがいるんだよ」
「お嬢ちゃんか」
「まあな」
封筒を脇に抱えて礼を言いながらダンテは踵を返しかけて、あ、と声をもらした。
「エンツォ、また車貸してくれないか」
「いい加減てめぇで車買えよ」
俺より乗ってるじゃねえか、と渋い顔でエンツォが投げ渡して来た車のキーをキャッチしてダンテはニカッと歯を見せて笑った。
「サンキュ」
ドアベルを鳴らして出て行ったダンテの背中に溜め息を吐くエンツォを見て、マスターはふっと微笑んだ。
「あんた、ダンテのあの笑顔に弱いんだろ」
「……まあな」
父から逃げることは難しいが、足取りをこちらから追いかける分にはそう難しくないことをメアは知っていた。
漁村を離れてレンタカーを借り、父が昔働いていた民間軍事会社を訪れれば良いのだ。
"こんにちは、私はメア・スカーレットです。昔こちらでお世話になっていたアダム・スカーレットの娘なんですが、父をご存知の方はいらっしゃいますか?"
受付の女性にそう尋ね、父と既知の社員を引きずり出せば勝手に裏社会に繋がり父に連絡が行く。父は会社に勤めていた頃から"レッド・ラム"の専属掃除屋だったからだ。父が母のモイラと出会った経緯をメアは知らない。知ろうとも思わなかった。母は毎日父に怯えて暮らしていたからだ。もっと私が強ければ母を救うことが出来たんだろうか、と度々後悔の念が過ぎる。製薬会社で研究員をしていたこともあった母はメアの妊娠をきっかけに職を退いたらしい。聡明だった母がもし健在だったら、今の自分はこんな"出来損ない"になんてなっていなかったはずだ。
メアはそこまで虚ろに考えてから腹部にめり込んできたワークブーツの爪先の重さに背中を折って息の塊を吐き出した。
安モーテルの薄い壁に体がぶつかる。幸か不幸か隣の部屋には宿泊客は居ないようだった。もしくは父が念を入れて二部屋借りているのかもしれない、と考えた。仕事の時の父はとても慎重だ。
息を荒らげているアダムに乱暴に髪の毛を掴まれて歯を食いしばる。右の頬に強い張り手が飛んできて鼓膜が破れるかと思った。殴られた痕がジンジンと熱を持って痛む。
「自分から帰って来たと思えば巫山戯たことぬかしやがって」
首根っこを掴まれて壁に押し当てられ、体が宙ぶらりんになりかける。爪先が床に付くか付かないかギリギリのラインに呼吸ができず、メアはアダムの手に爪を立てて抗った。
「もう、逃げないから……っ」
「信用できる訳がないだろ」
母親にそっくりだ、とアダムは吐き捨てるように言った。血走った目がメアの母譲りの青い瞳をじっと睨みつける。
「あいつも組織のことを洗いざらい暴露してやるって、ある日突然キレやがった」
メアの体をソファーに放り出すとアダムはイライラとその場を往復し始めた。禁断症状でも起こしているのだろうか、父は薬だけはやらない人間だったはずだが。キレ易い面は兼ねてより抱えていたが、それにしてもいつもより気性が荒かった。
メアはゲホゲホと咳き込んでから、掠れた声を絞り出す。
「お父さんのことをバラしたりはしない。私はレッド・ラムを潰したいだけ。あの忌まわしい薬をこの世から消さないといけない」
だから幹部メンバーのリストが欲しい、とメアは懇願した。それがメアがようやく見つけた自分が向き合うべき問題だと思った。発作的に家を飛び出し、ダンテに縋り、自分一人の身を守って自由を掴めればいいと最初はそう思っていた。けれど間違いだったのだ。自分の家族が撒いた種が思わぬ被害を産んでいる、それをあの漁村で実際に目にして知ってしまったら無視なんて出来ない。
「お父さんの実力ならあんなマフィアに固執しなくても仕事していけるでしょう……?」
アダムは足を止めると怖々とこちらを見上げているメアをもう一度不満げに突き飛ばしてから、どかりと反対側のソファーに身を埋めた。短く刈り上げたブルネットを掻きながら、煙草に火をつけると、仕事用のバッグをあさって書類ホルダーをメアの前に投げて寄越す。
「一件俺の仕事を代わりにやれ。殺しの仕事だ。お前なら出来る」
そうしたらリストを渡してやる、とアダムは紫煙を吐き出しながら感情の読めない冷たい目で言い放った。メアはひくりと喉を鳴らして、そのホルダーをめくる。
「組織の金に手をつけたとかで、制裁の処分になった裏切り者だ。名前はジェイド・ハジェンズ」
男の顔写真と出入りする店名を記憶してメアは静かに息を吐いた。
「この男を殺すだけでいいの?」
「ああ」
そこへ追加で投げ渡された封筒の中身を見てメアは苦々しく唇を噛み締めた。そこには事務所の傍で買い物をしているメアの姿や、ダンテと一緒に仕事へ向かう様子、漁村で車に乗っている二人の姿などが写っていた。
「どんな関係だか知らないが、お前が変な気を起こせばコイツも巻き添えを食うことになるかもな」
「……判った」
やっぱりこの男から逃れることは無理だったんだなと一瞬打ちのめされかけたが、どうせそんなことだろうさ、とメアは開き直った。父の仕事の実力だけは信頼しているからだ。
メアは一週間ぶりに見たダンテの顔に泣きそうになりながらも涙を堪える。ダンテならばちょっとやそっとじゃ死なないことは判っていたが、だからといって迷惑をかけていい理由にはならない。
「仕事の準備をしろ」
小綺麗にしてターゲットの気を引いてやれ、と投げ渡された現金を受け取ってメアは静かに頷いた。
護身用にガンホルスターを身につけていると、一瞬服の影から痕が見えたのかアダムが歩み寄ってきて服の裾を捲り上げる。
「……自分で焼いたのか」
メアは脇腹の火傷を指でなぞってから、かつてよく判らないままに入れられたレッド・ラムのタトゥーを思い出していた。自分で皮膚を焼いた時よりもインクを刺された時の方が何十倍も痛かった。
「私はもうあの組織の人間じゃない」
アダムの手を払い落としてメアは仕事の準備に取りかかった。
クラブ『サッカー・パンチ』とライトアップされた安っぽい木製の看板を見上げてダンテは小さく溜め息を吐いた。
「"不意打ち"ねぇ……」
店名の意味に今一度呆れてから入店した。こっちから不意打ちを仕掛けるつもりだが、仕掛けられるのはお断り願いたいものである。
このクラブが件のジェイド・ハジェンズが頻繁に出入りしているという店だった。
色鮮やかなフラッシュライトに照らされた鏡張りの廊下を進みながらダンテは写真の人相をもう一度確認した。
薄暗いダンスホールは重低音の音楽と人で溢れ返っていた。
カウンターで酒を注文するついでに店員に聞き込んだところ、ハジェンズはやはりお得意様扱いらしく週末の夜には必ず来るようだ。ちょうど今日もその夜である。
出てきたロックのジンをあおりながら、店内に目配せをしていると、
「お兄さん、一人なの? 良かったら一緒に踊らない?」
どう見ても成人しているとは思えない少女が声をかけてきた。メアと同じくらいかもっと若い年頃かもしれない。スタイルは良く、タンクトップにプリントされた星条旗が今にもはち切れそうな急カーブを描いている。長いブロンドを子どもっぽいツインテールに結っているのが何とも言えない大人と子供の境界線の揺らぎを感じさせた。
カルーアミルクらしきグラスをちろちろと舐めながら隣に座って来たかと思うとダンテを上目遣いで見つめてくる少女の誘いに、以前の自分なら何の躊躇いも持たなかっただろうな、とダンテはふっと鼻で笑ってしまった。
「なーに? 一人で笑っちゃって」
「いや、悪いな。今忙しいんだ。他の男を当たってくれ」
少女はムッと眉を潜めてダンテの腕に腕を絡ませてきた。押し当てられた柔らかい胸の感触にげんなりと溜め息を吐きそうになる。
「全然忙しそうに見えないんだけど!お兄さんくらいしかカッコイイ人いないんだもん。つまんないから遊んでよ」
どうやら酔っ払っているらしく少女は頬を赤らめて駄々を捏ね始めた。
ダンテはとうとう溜め息をつくと、少女の手からカルーアミルクを奪って一息に飲み干すと、店員に声をかける。
「この子にコーラを」
「はぁ?」
「それで酔いさまして帰れ。子どもは家で大人しく寝るもんだ」
腕をやんわりと振りほどいて頭をポンポンと撫でてやると、少女はぽかんと口を開けて石のように固まってしまった。
そのまま席を立って店内をうろつき二階席に行く。
初対面の時、まだ飲める年じゃないからと酒を断ったメアの様子を自然と思い出していた。そうだ、あいつ変なところで真面目で頭が固いんだった、と熱の篭ったダンスホールを見下ろしながら思い出に浸りかけてしまう。
「"どうか私のことは探さないで"、か」
置き手紙の文面を呟いてダンテはくしゃりと前髪を握った。置き手紙に従い、つい二、三週間前まで知りもしなかった少女が突然いなくなったくらいどうってことない、と最初は自分に言い聞かせて忘れようとしたのだ。でも無理だった。彼女がいなくなった穴は意識していたよりも遥かに大きく、ダンテの胸は空虚さに苛まれてしまった。
結局耐えられなくなって探している。それをメアが望まないのだとしても、今はもうどうでもよかった。
その時、ぼんやりと階下に彷徨わせていたダンテの視界に真っ赤なドレスが横切る。
「……メア?」
ホルターネックのタイトなカクテルドレスを纏って、男の手を引いていた。暗闇でも判る赤いルージュと紫色の扇情的なアイシャドウが濡れたように光っている。男の方に目を向けると、当のハジェンズその人だった。取り巻きが三人、彼の後ろを少し距離を置いて追いかけていく。どういう因果か。
呆気に取られながらもダンテは静かに一階へと戻り、取り巻きたちの背中を追いかけた。尾行なんてガラじゃないが、した事がない訳でもない。
メアとハジェンズたちは近くの立体駐車場に入って行くようだった。車に乗られると厄介なんだがどうしたものか、と考えていたダンテだったがその心配は杞憂に終わりそうだった。
一向の動きが止まったので柱に寄りかかって身を隠す。ハジェンズはメアの体を車のボンネットに押し倒すと、首筋に顔を埋めた。太い指が白いメアの太ももを這い上がっていくのをダンテは虚ろな瞳で見ていた。
彼女が体を売るなんて可能性は考えられないし、本当に襲われているのだとしたら自力で捩じ伏せられるはずだ。可能性としてあるのはメアもダンテと同じくレッド・ラムの関係者を何らかの理由で追っている、ということか。
下手に手出しはしない方がいいかな、とダンテはしばらく傍観を決め込むことにした。綯い交ぜになった感情は無視して。
ハジェンズの唇がドレス越しにメアの胸をなぞり、下腹部にたどり着こうとした時だった。メアの太ももがハジェンズの首にきつく絡みついた。狼狽えた取り巻きたちにメアはレッグホルスターからハンドガンを抜くとトリガーを引く。サプレッサー付きの押し潰した銃声が響き、男三人の体がどうと倒れた。
黒いハイヒールを履いた爪先でハジェンズの顎先を蹴りあげ、よろめいた男の両膝を撃ち抜く。情けない絶叫が駐車場内に響き渡り、呆気なくうつ伏せに倒れたハジェンズの隣に膝を抱えてゆっくりとしゃがみ込むと、メアは静かに尋ねた。
「"掃除屋"に貴方の処分指示が入った。心当たりはある?」
「ねえよ、そんなもん……このアバズレめ……!」
「そう」
後頭部に向かって二度トリガーを引くとハジェンズは静かになった。
そこへ一台の車が滑り込んでくる。ヘッドライトの逆光の中で顔に飛んだ返り血を拭ってからアップにしていた髪の乱れを整えるメアを見て、ダンテは思わず足が動いていた。
「メア」
サファイアブルーの瞳が大きく見開かれる。
何事かを言おうとした赤い唇が凍りついた。
車から降りてきたのは四十代ほどの屈強な男だった。ダンテを一瞥してから、何も言わずに四つの死体をネイビーのピックアップトラックの荷台へと詰め込んでいく。
ダンテは静かにメアへと手を差し出した。何を言うか数瞬躊躇った後に、
「帰ろう」
メアの顔がくしゃりと歪んだ。
「探さないでって言ったのに」
その時、ダンテの胸の真ん中を三度衝撃が貫いた。口から溢れた鉄臭い血の塊を吐き出しながら顔を上げると唖然としているメアの背後であの男が銃を構えていた。撃ち込まれたのは大口径のマグナム弾だったがその程度でダンテは死なないし、死ねない。そのまま前に進もうとすると銃を掴んだ手がメアの後頭部に振り降ろされた。鈍い音が響きメアの体から力が抜ける。
「メア!」
叫んだ喉に間髪入れずに銃弾がめり込み、思わず後ろにたたらを踏む。怯んでしまった、とダンテは自分が大きく動揺していた事に遅れて気がついた。
男は気絶したメアを車に乗せると、ダンテに向かって数度引き金を引きながらタイヤを甲高く鳴らして立体駐車場を下って行った。
その後ろ姿と車のナンバーを頭に焼き付けながら、ダンテは追いかけることも出来ずにじっと立ち尽くしていた。
「……何やってんだ俺は」