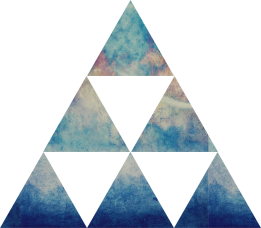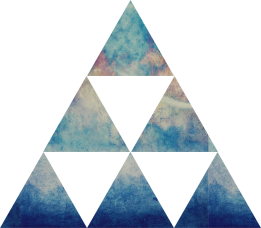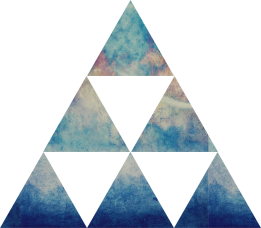
その頃、マフィアの拠点のある場所にて。
男、中原中也は自分の執務室の椅子に寄りかかりながら、深い溜め息とともに舌打ちをした。片手にあるのは、失踪したその男の部下について書かれた一枚の書類。
「まだ見つかンねえのかよ……彼奴」
一人でそうぼやいてしまうほどには、彼奴──さゆりの居所の捜索は困難を極めていた。
本来なら、失踪した構成員の捜索なんてマフィアであれば1日で見つけ出せるくらい容易なはずなのだが、何せ彼奴が回収し損ねた情報が情報だ。それが公表されてしまったことへの処理にかなり手間取っているらしく、さゆりの捜索に割ける人手がないらしい。
俺も独自で調べを進めてはいるのだが、やはり人手が少ないと情報収集には限界がある。今のところ分かっているのは、関東より遠くには出ていないらしい、ということのみだ。
矢張り、もう少し範囲を絞らないと見つけるのは厳しい。今度信頼できそうなやつに頼んでみようかと考えながら、他の仕事があるため席を立つと、ことん、と机の上で何かが倒れる音がして動きを止めた。何だろうと思って音がした方に目をやると、きらりと光る三日月を象った女物の髪飾りが目に留まる。
手に取ってみると、蛍光灯の光を受けて瑠璃色に輝くそれは、まさに星が瞬く夜空のよう。
実は俺は、この髪飾りに少しばかり思い入れ──いや、正確に言うと心残りがあった。丁度、先刻の失踪した部下、橘さゆりという女に関することだ。
それは、任務帰りのある日のこと。肌を刺すような寒さの冬の日、まだ俺がさゆりのことを「橘」と呼んでいた頃のことだった。
俺は、任務を終えた後の帰りで橘と待ち合わせをしていたので街に訪れていた。街を歩いていると、ここ最近はクリスマスというイベントで店は明るく彩られていて、その店の灯りの眩しさに少し顔を顰めつつ、待ち合わせ場所へと足を運んでいく。
そして、予定通り待ち合わせの場所に着き橘も既にそこにいたので声をかけようとした、その時だった。
俺は、目に入った少し珍しい光景に思わず出かけていた言葉を引っ込めた。橘の立つ、煌びやかな店が立ち並ぶ方向に視線が吸い寄せられる。
そこに居た橘の視線は、ガラスケースの中に入っている何かに釘付けになっていた。暗い闇の色をした目が少し見開かれ、店の灯りを映してまるで宝石のように瞬いている。
その頃の橘の印象は、いつも無愛想で暗い目をした無口なやつというものだったから、そのアクセサリーをまるで子供のようなキラキラした目で見ている橘を見た時には本当に驚いた。同時に、普段との差が激しいせいか──何だか、可愛らしいと思ってしまった。
俺は、橘の視線をこれだけ引きつけるものが何なのか少し気になった。そこで、今居る場所からは動かずに角度を変えて、ガラスケースの中をのぞき込んでみると──
そこにあったのは、夜空を映したような濃い瑠璃色の、三日月の形の髪留めだった。その瑠璃色が放つ星空のような煌めきは、宝石にも少し目がある俺が見ても、確かに綺麗だ。一応年頃の娘である彼奴の目が奪われるのも、無理はないかもしれない。
年頃の娘、か──不意に、そんな言葉が頭を過ぎって俺は顔を伏せた。
橘がマフィアに入った時の様子や、普段の服装を考えると、きっと彼奴は年頃の女が持ちそうなものなど触れたこともないのではないか。だから、そういうものに憧れを感じて、こんなキラキラした目であの髪飾りを見ているのではないだろうか、と。
俺はそこで、彼奴があの髪留めを貰ってその黒髪につけ、嬉しそうに微笑んでいるところを想像してみた。
……なんだか、結構似合っていそうな気がする。いや、むしろ彼奴のために作られたのではないかという程に、あの黒髪に似合うような気がしてならない。
「……………」
俺はその時、気がついたら何も考えずに橘の方へ歩き出していた。黙ったまま橘の隣に立ち、改めて近くでその髪飾りと、それから橘の顔をじっと見遣る。すると、さすがに俺の存在に気づいたらしい橘がぎょっとしたように目を丸くし、ショーケースから離れて後ずさった。そして、焦ったように目を泳がせながらぱくぱくと口を動かす。
「……っ、あ、な、中原先輩……すみません、これは違うんです、その……」
「欲しいのか、それ」
ふと己の口をついて出た言葉に、自分自身が一番驚いた。橘も驚いたように目を見開いて固まっている。当然だろう、上司でしかも幹部である男から女物の髪飾りを見て、欲しいのか、だなんて。下手をすれば変な勘違いをされかねない発言である。俺は自分の発してしまった発言に内心羞恥を覚えつつも後戻りをする訳にもいかず、とりあえず適当に繋げようと口を開いた。
「いや、その……手前が、そういうのをそんな夢中になって見てンの、見たことなかったからよ」
ほとんど何も考えずに出てきた言葉だったので、無意識に緊張が口調に出てきてしまう。橘はそんな俺に少し訝しげな表情を残しつつも、また先程のショーケースをちらりと一瞥し、小さく溜め息を吐いた。
「あ……いえ、大丈夫です。少し、綺麗だと思っただけなので……」
そう呟いた橘は相変わらずの無表情だったが、髪飾りを見つめるその瞳はやはり切なげに揺れていて。一目で分かった。欲しいのだろう、やはり。
俺は何だかその表情がもどかしくなってしまって、別にそんなことをする理由も何もないのに、買ってやろうか、という言葉が喉元ギリギリまで出かかってしまった。しかし、ただの「部下」である女に髪飾りをプレゼントするのは流石に憚られて、その時は結局言うことができず、そのまま報告をしに街を去ったのだ。
思えば、この時だった。俺がさゆりに──惚れてしまったのは。
その感情をしっかり自覚したのは、この出来事よりももう少し後になってからだった。本当に、馬鹿げた話だ。
結局俺はその後、あの髪飾りのことが頭から離れず、態々あの街に1人で行って自腹でそれを購入した。別に買って何をしようだとか渡そうということもなかったというのに、彼奴の顔を思い浮かべたら買わずにはいられなかったのだ。
そして俺は自分の感情を自覚し、そこでようやく思い至った。そうだ。いいタイミングでどこかにさゆりを呼び出して、そしてその時に、この髪飾りを渡し──彼女に思いを伝えよう。そう決心したあの日の夜。
さゆりが俺を受け入れてくれるかどうかは正直分からなかったが、まだ暇はある、時間をかけて、彼女を少しずつ俺のものにしていこう……そう、思っていた。その時は思いもしなかった。突然さゆりが──俺の前から居なくなるだなんて。
俺は、今自らの手の中で光る瑠璃色の髪飾りを見て、深い溜め息を吐いた。今では、この髪飾りを見るたびに、後悔の念が募って仕方がない。
もっと早く、さゆりにこれを渡していれば。もっと早く──さゆりに俺のことを受け入れて貰えていれば、彼女を、守ることが、できたはずだというのに。
しかし、後悔をしているばかりでは、状況は何も変わらないし、何も始まらない。俺は、そう思いながらそっと髪飾りを掌に握り締めた。
だからこそ早く、さゆりを探し出して、救い出さなければならない。俺は決意を新たに決めて、三日月型の髪飾りをデスクの引き出しにしまった。救い出せたらすぐに、包み隠さずさゆりに俺の思いを伝えよう。もう二度と、後悔を繰り返さないように。
そう強く思い直して、俺は今日もデスクに向かい、1人愛しい彼奴の行方を追いかける。
瑠璃色の三日月
- 9 -
prev | next
back