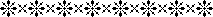 あれからあの女、ハニーの顔が頭から離れない。 あいつは僕の名前を覚えちゃいない。 僕にだって、意地がある。 絶対に名前で呼ばせてやる。 毎日僕はハニーの元へ通った。 最初はやはりあなたはだぁれ?状態だったが、こうも毎日毎日通っていればハニーも少しずつだが僕を覚えてきた。 次第に、彼女に会うのが楽しみになってきた。 よく、わからない。 ハニーと出逢ってから僕はおかしくなってしまったんじゃないか。 いや、おかしいのはハニーだ。 前に皮肉のつもりで キミは脳みそまで蜂蜜で出来てるんじゃないのか。 と言ったら それってとっても素敵ね。 と彼女はふんわり微笑んだ。 彼女の笑顔を見れば、鼓動が早まる。 やはり僕はおかしい、 授業中も、食事中も、寝ても醒めても彼女の事ばかり考えている。 * 「おい」 見慣れた蜂蜜色が湖の畔でボーッとしているのを見つけ思わず声をかけた。 「あ 、蜂蜜王子」 またハニーは僕を訳の分からない名前で呼ぶ。 「 誰だソレは 。僕はドラコ・マルフォイだ 。 いったいいつになったら覚えるんだ?」 僕はハニーの隣に腰をおろした。 「 …… 蜂蜜は、特別なの」 「特別?」 「王子だって蜂蜜なんかに興味ないんでしよ」 何だか今日の彼女は機嫌が悪い。 「…話してみろ」 ハニーは驚いた表情を見せながらも、ゆっくりと話した。 彼女の両親の蜂蜜色の恋の話。 彼女が蜂蜜色の訳 彼女がお菓子と蜂蜜好きの訳 「そうか、なら蜂蜜王子と呼ばれるのは光栄だな」 そして彼女は初めて僕の顔を見た。 「お、おい」 彼女は静かに涙を流していた。 「どこか痛いのか」 「ううん、嬉しくて」 初めて見る彼女の涙を、美しいと思った。 「ありがとう、ドラコ」 蜂蜜色の瞳に溜まる涙はまるで蜂蜜のようで思わずペロリと舐めてみる。が、やはり甘いわけがない。 「しょっぱいな」 と言えば彼女は、不思議そうにしながらも微笑んだ。 ふんわりと微笑んだ彼女を見て、また心臓がドクンッと鳴った。 嗚呼、僕は ハニーに恋をしたんだ。 キミが泣くならその涙を飲み干そう。 prev / next |