学園祭の時間
「……くくっ、あっはははははは!!」
僕を特別視か、なんて面白いんだろう!
突然僕が大きな声で笑い出したからか、学秀は不思議そうな顔で首を傾げている。近くにいた人も僕に視線を集めているのを感じた。
けど、それで恥を覚えないのが僕だ。注目を集めることには慣れているし。
って、そう言う話ではないね。
「な、何故笑う!」
「いや、君を馬鹿にしている訳じゃないんだ。気を悪くしたらすまない」
「そ、そうなのか……なら、何が面白かったんだ?」
僕の発言を疑うことなく受け入れた学秀は、その理由を問うた。
隠す理由もないため、学秀が問うた質問に答えた。
「何、君は僕を見透かしているんじゃないかって毎度思うんだ」
「僕が? そんなつもりはなかったんだが……」
「無自覚か、僕としては質が悪いね」
どのようにして見破ったのかは今でも分からない。感だったのかもしれないけど、僕の演技を見破ったのは確かなのだ。……雑なやつだったとしても、だ。
だから、どこかで僕は学秀を面白い者として見ているのだろう。E組の彼らとはまた違った面白さを、学秀から感じている。
……そんなことより、一般人に見抜かれるなんて。僕もまだまだだね。
「どちらかというと、僕が名前に対して感じている事なんだけれど」
「人間観察は好きだよ」
「……なるほど。そういうことにしておこう」
まだ僕に裏があるのではないか、と思っているんだね。ターゲットの件で僕は話せないことが多い。依頼人である政府との契約だからね。
その点を『何かまだ隠している事がある』と見ているのだろう。何かまでは分かっていないけれど、隠しているのは確かだって感じでね。
「さあ、お互いに思っている事を明かしたんだ。今、この場において懸念することはないだろう?」
「ああ、特にないよ」
「では、準備を進めよう。セッティングはもう済んでいる。後は君だけだ、名前」
僕と学秀が話し込んでいる間にドラムは移動されていたらしい。残るは僕がズボンを履くだけだ。
「先に行って、始めていると良い。途中から入る」
「ほぅ? 随分と自信があるようだな」
「当然さ。観客だけでなく、君の事も魅了してあげようか?」
「できるものならやってみると良い」
学秀はステージへ。僕は用意されたズボンに履き替えるため、簡易的な更衣室へと足を進めた。……遠くから聞こえるエレキギターの音に、どんなリズムを刻んでやろうかと考えながら、着替えを進めた。
***
男子生徒用であるズボンは、僕の身長に合わせたものを用意したようで、ぶかぶかではなかった。……まさか、目視で測ったというのか?
折角男子生徒のズボンを履いたので、軽く結んでボーイッシュ風にしてみた。人を魅せるなら、格好も大事だ。
「スティックはドラムと一緒に持って行ったって話だったな」
スティックの存在を思い出しながら、裾を捲る。ドラム及び、正式名称ドラムセットは全身を使って音を奏でるから、段々と暑くなってくるんだよね。
「結構な腕じゃないか、学秀」
学秀の奏でる音にそう呟きながら、ステージへと立つ。スピーカーに繋がれたことで、ギターの音は大きい。それに加え、観客から聞こえる黄色い声もある。だから、僕の声など聞こえていないだろう。
「……!」
なのに、学秀はステージに現れた僕に気づいた。それも、思っていたより早くだ。観客の誰かが僕に気づいて、その視線に気づいた可能性もあるが……僕の目が可笑しくなっていなければ、学秀は目を閉じていて、ギターを弾くことに夢中になっていたはずだ。
……本当、面白い奴だ。
学秀に対し、そう思いながら僕はドラムセットへと近づき、用意された丸椅子に座った。
「……」
学秀がギターを弾くのを止めた。ドラムセットの位置を調整し終え、顔を上げれば学秀と目が合った。
「……へぇ、僕から初めて良いの?」
そう問いかければ、学秀はコクリと縦に頷いた。なら、遠慮なくさせて貰おう。スティックを両手に持ち、自分の好きなビートを刻み始めた。
「! なるほど、そうきたか」
割と複雑なものを選んだつもりだったんだけど……学秀のやつ、着いてきたか。それに、あの顔は……随分と余裕そうだ。
だったら!
「これはどうかな!?」
先程まで刻んでいたリズムを大幅に変えてやった。これはさっきとはまた別の意味で複雑なものだけれど、まだ着いてこれるかい?
「ははっ、これも着いてくるか!」
パーカッションは第二の指揮者と呼ばれる。この場には指揮者は存在しない、つまり僕がリズムを決める決定権を持つ。
だから、僕の刻むリズムについて来られないのなら、この場では負けということになる。そんなこと、一言も言っていないけれど……どうやら向こうも分かっているようだ。顔に出ているんだよ、僕が今言った事がね。
「中々やるじゃないか、学秀ッ!」
「それはこちらの台詞さ、名前!」
きっと僕達が交わす言葉は観客に聞こえていない。互いが奏でる音が、メロディーが僕達の声が向こうへ届くことを阻止しているからだ。
「初めてだ、セッションでこんなにも心が高ぶったのは!」
「僕もさ! この時間がずっと続いていてほしい……!」
僕のリズムにあうビートを奏でる学秀。それに対し、僕は違和感の一つも覚えない。もしや、音楽の才能があるのか?
それとも……僕と一緒で、ここまで上り詰めた努力の人間なのだろうか?
ほら、普通の学業であれば音楽なんて触れないだろう?
こういうのを何というのか、僕は知っている___無駄な技術を習得するっていうのさ。音楽の道を目指しているのなら、話は別なんだけどね。
「いくぞ学秀、ラストだ! これに着いてこれるかな!?」
「僕を舐めないことだ、名前!!」
___僕と学秀によるセッションは、10分ほどのものだった。だと言うのに、僕にはそれがあっという間の時間に思えた。
「あーあ、バレバレな男装をしちゃって。ま、それでも違和感を覚えさせない所が、君の変装の腕が高いことを改めて実感させられるよ」
「さて、初めから撮ってたコレ、E組のみんなにプレゼントしちゃおうっと」
僕と学秀が繰り広げたセッションは大盛況で終えた。
その出来事を動画にする者がいて、かつ顔見知りのところへと送ったことなど、その時の僕は知らなかった。
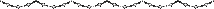
2023/12/10
prev next
戻る
×