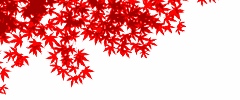 ‖片恋話 「なんだ、最近めっきり名前の嬢ちゃんは来てねぇみたいだな」 「確かにそっすねぇ。瀬名さん、大丈夫なんすか〜?」 厨房の方で料理をしている泉に、非番の夜警二人からお声がかかる。いかにもな巡査らしい、鬼の名を冠する無骨な男と、その弟分である元気のよい若者が一人。彼らもまた、泉の茶屋の常連だった。 「別に! あいつが来ないってことは、ちゃんと稼げてるってことじゃないのぉ?」 「熱っつ!! うどんを机に叩きつけるのはやめて欲しいっすよ! 散る!」 「ふんっ。知らないよぉ、文句があるなら他所に行きな!」 「苛立ってんな、瀬名の旦那。……まぁ、関西風の美味いダシが効いてる店もそうねえんだ、これからもよろしく頼むぜ」 鬼龍が苦笑しながら、ここ最近ずっと不機嫌極まりない泉を宥めた。 ――茶屋の常連が知る共通の話題。それが今、泉を最高に苛立たせる要因となっている訳だ。その話題というのは『泉の想い人』である。昼の一時だけ現れ、無償でお昼を御馳走になっている若い女性。 誰がどう見ても『想い人』にしか思えない対応なのだが、泉はムキになって否定してくる。それが面白くて、ますます常連は仮説である『泉の想い人』説を雄弁に語りだすわけだ。 あの寡黙な鬼龍でさえもが弄りだすのだから、この話題がどれほど『定番』なのかは一目瞭然だ。 「いやぁ、ほんとでも瀬名さんの料理はうまいっすよねぇ! さすがは京のお人というか」 「今更おだてたって無駄だよぉ?」 鉄虎がそろりと泉をおだててみるも、全くの無効。気まぐれな猫のようにツンとしているものだから、鉄虎は参ってしまった。 「うぐ……やっぱ今日の瀬名さん、気が立ってるっすよぉ……どうするんすか、大将?」 「どうもこうもねえな。解決できるのは、名前だけだ」 「そんなぁ」 泉も鬼龍も、取り付く島もないといった具合だ。鉄虎が、泉に睨まれながらおずおずとうどんの汁を啜ろうとしたその時、別の来客があった。 「む? なんだ鬼龍、お前も非番だったか」 「お、蓮巳の旦那。と、そちらさんは……初めて見る顔だな」 入ってきたのは二人の男だった。 片方は、この店の常連であり、煉瓦街の平和を時給十円で守る巡査の一人、蓮巳敬人だ。鬼龍や鉄虎とも同僚である。 さて、もう片方はというと。 「敬人の同僚さんかい」 「ああ。体のでかい方が鬼龍、小さい方が南雲だ」 「小さい方って言い方はないと思うんすよ、蓮巳先輩!」 「はは、すまんすまん」 「そうだよ敬人、失礼に値する」 鉄虎の非難を軽く笑い飛ばした蓮巳をたしなめ、「すみません」と柔らかく謝罪する男。見た目から判断すると、どうやら書生らしい。柔らかな黄金色の髪に、ここの店主の泉と似た水色の瞳を持っている。 「申し遅れました。僕の名前は――ええと、名乗っても引かないって約束してくれると嬉しいのだけど」 「なぁに。別に、今更。何せこの店は、鬼だの蛇だの虎だの、魑魅魍魎に獰猛な生き物が跋扈(ばっこ)してるからねぇ。今更何が出ても、怖くないけど?」 凄い言われようである。巡査三人は苦笑しながら頷いた。書生さんは、泉の皮肉に目を丸くしたあと、クスクスと笑った。 「そうですか。じゃあ名乗ろう。 僕の名前は天祥院英智、といいます。敬人とは幼馴染で、今日は当てもなく煉瓦街をぶらついていた所です」 「――へぇ、そりゃ前置きも必要だねぇ。天祥院家と言ったら、煉瓦街一のお金持ちだ」 泉の感想に、鬼龍と鉄虎も頷いた。 天祥院家。 この煉瓦街一の大富豪。いや、下手をすると、今の日の本でも一、二を争う名家ではなかろうか。新政府にも多大なる支援を施し、天祥院家に繋がりの深い者が、各省で実権を握っているともうわさされている。――とにもかくにも、ものすごい名家な訳だ。 その御曹司が、この煉瓦街に。しかも、煉瓦街にありながらも木造という、一風変わったこの茶屋兼飯屋に足を踏み入れている、この現実のあべこべさ。中々に面白いことだ。 「ま、とにかく座れよお二方。今、瀬名の旦那の片恋相手が、どうやったら店に来てくれるか話し合ってたのさ」 「何とんでもないウソを言ってくれちゃってんのかなぁ、鬼龍は?」 「それは重要な議題じゃないか。ふむ、早く名前が戻ってこなければ、おちおちうどんと茶漬けを頼めたものじゃない」 「このクソ巡査ども、出禁にしちゃうからねぇ!?」 顔を真っ赤にして否定したって、何も怖くはない。蓮巳は天祥院を連れ、鬼龍たちの隣の席に座った。「握り飯でいい。二人前」と蓮巳が泉に注文を言いつけると、彼は渋々厨房に引っ込んでいった。 さて、常連と新入り一人だけになった空間では、やはり定番の話題は広がりを見せるわけで。 「しかし、昼に来なくなったとなればよぉ、単純に勤め先でまかないが出るようになったんじゃねえのか」 「そっすよねぇ。俺も、小さいときは名家の下男やってたんすけど、普通はまかないが出るんすよ」 「ふむ。俺は寺の子だからな、そのあたりは良く分からないが。確か、名前はどこぞの名家の女中をやっていたのではないか」 巡査三人が思い思いの推測を言っていると、ふいに天祥院が声をかけてきた。 「おや、名家か。もしかすると僕の知り合いかもしれないな。どこの家か覚えていないかい」 その言葉に、巡査たちは目を輝かせた。この泉の片恋の振るわなさに、何かテコ入れがある可能性が出たからだ。色恋も賭け事も、動きがあったほうが面白いのは決まっている。 「なんでしたっけ。何回か聞いたことあるんすよねぇ」 「あー……名前に色がついてたな。あと、最近煉瓦街に新しく洋風屋敷を構えたんじゃなかったか? それで色々入用で、まかないもロクに出ない慌ただしさだって、名前が言ってたような……」 「色に関する名字で、煉瓦街に新居を構えた名家か。英智、何か心当たりはないか」 幼馴染である蓮巳が訪ねると、天祥院はさらりと答えた。 「煉瓦街だろう? それはおそらく、朱桜家だね」 「――あぁ! 確かに、朱桜と言っていたな!」 「あそこの家は、元は武家の名門でね。本家はそれはもう、広大な日本家屋だよ。……でも最近、息子のうちの一人を留学させたり、煉瓦街に新居を構えたりと、文明開化にうまいこと合わせているようだからね」 「お侍さんにしちゃ、ずいぶん器用な立ち回りだな」 「確かにそうっすね。煉瓦街をちょっと抜けた先、元武家屋敷のわびしい空き地だらけなのに」 鉄虎の言う通りだ。 江戸から東京と名を変えたとはいえ、それまで江戸にあったものが、急に無くなるわけではない。 当然、中には明治の世に馴染めず、取り残され、消え去るモノが存在していた訳だ。 「それにしても、名前さんは女中っすからねぇ。しかも、中々気立てもいいし。うーん……」 「鉄、もしかしてアレか。名前が、朱桜の御曹司に手籠めにされたんじゃないか、とか心配してる口か」 「剣呑な話っスけどね。実際、気に入った女中さんを、若君や旦那様が……ってのはよくあるし」 「……そういえば、朱桜家にはかなり子がいたな。男兄弟ばかりだとか」 「ああ、聞いたことあるよ。そういえば最近、朱桜家の息子の一人が、女中を召し抱えたとか…………」 「……」 四人は押し黙った。 まさか、とは思いながらも、一気に話が繋がっていくため、どうしても人ごとに思えない。 「どうするんすか、瀬名さんに言うんすか、この話」 「……いや。やめておけ、南雲。召し抱えられたのが名前だという確証もないだろう」 「でも、心配しているんだろう? 僕らが可能性を伝えたら、本人次第で調べられるじゃないか」 「……天祥院の旦那。頭から関西風のダシを被りたくなかったら、瀬名の旦那には何も言わねえほうがいいぞ」 「そ、そうかい」 天祥院が微妙な顔をして笑った。 どうか、どうかその女中が名前ではありませんように……。という願いを胸に宿しながら、鉄虎は残りのうどんの汁を飲み干してしまうことにした。 [*前] [次#] [戻] |