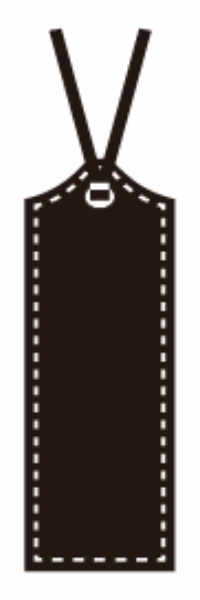2
月を見ていた
夏祭りが夜空に太陽を打ちあげていたころ、あたしたちは、月の見えない箱の中にいた。
10ケ月前── 。
人混みを避ける。
動きづらい浴衣の袖よりも、つながれる掌の熱のほうが新鮮で、あたしは彼の、ストライプの肩を必死に追っていた。白と黒の、見慣れない和装の肩を。
「高校に行こうぜ?」
「こーこーこー?」
「こ・う・こ・う」
「高校がなに?」
「探険しに」
「タケシ兄?」
「誰だよタケシって」
録音された鼓笛隊や、和装の町人が打つ柏手、呼びこみたちの情熱に遮られ、か細い声のあたしたちはこれ以上を張りあげられず、ひとまず会話を諦め、脱獄のスピードで夜店のイグジットを抜けた。
熱気を祓うように天を仰ぐ。
初めて気づく。まぁるい月が浮かんでいた。
電車の踏切を渡り、右に左にと、華奢な住宅地をさまよう。土地勘のある彼の背中に、つき従うことしか術はなかった。
蒸れる掌や、不安定なスケート靴の草履、空気と同化した体温──安定感のないあたしを支えるためのあたしの部品は、この時ばかりは、すべてが彼のものだった。もしも預け損なったものがあるとすれば、彼のために描きあげられた、いつも以上のメイクだけ。
女の武器に中庸はない。折れるか、折れないか。
風は凪ぎ、鼓笛隊のライヴはすぐに途絶えた。いや、わずかに漂ってはいる。聞こうと思えば聞こえる。でも、もう要らなかった。必要なものは、最初から、この蒸れた鼓動の奥にある。
15分でたどり着いた、しばらくぶりの高校。
鉄の門を軽快に乗り越え、内側から閂を外す彼。それからあたしも、恐る恐るに飲みこまれる。
夏休みを利用しての改装工事。蜘蛛の巣のように張りめぐらされた防音メッシュシートの胎内で、校舎の赤ちゃんが眠っている。
校庭をぐるりと半周し、足場材に覆われる第1校舎の裏、第2校舎とをつなぐ渡り廊下の真下へと回りこむ。
街の灯はあっさりと縁を絶たれ、瞬く間もなく、あたしたちは闇になった。
鉄骨の匂い、塗装の匂い、粉塵の匂い──彼の匂いが掻き消され、とたんに怖くなる。結んだ指に力を込めると、あたしは、必死になって聞き慣れた息づかいを嗅いだ。
「どっか開いてねぇかな」
勇敢に足場に乗りこんでは何度か頭をぶつけながらも、施錠の有無を確かめる彼。その都度、指が離れて怖かったけど、彼は必ず戻ってきたし、それに、少しずつ、恐怖よりも好奇心のほうが勝っていった。
「開いてない?」
「ムリっぽい」
第1校舎は絶望的だった。職員室は盤石の箱の中。
「じゃあ、第2は?」
あたしのほうがその気だったのかも。闇に向かって提案。
一瞬、わずかに指を引き攣らせるだけで、彼はなにも言わなかった。でも、その反応だけで、あたしは充分に満たされた。
不法侵入できたところで、なにもなくたっていい。それとも、なにかがあったっていい。キスだけでもいいし、エッチしたっていい。色んな意味で、なんでもできるような気がしていた。
知ってることも、知らないことも。
できることも、できないことも。
罪も、罰も。
第2校舎の裏に回りこむ。こちらには足場材はかけられておらず、でも、月の威光はますます弱まる。ぢゃく、ぢゃく、ぢゃく。玉砂利を踏む音だけが頼みのソナー。
解体された貯水槽らしき残骸の影を横目に、校舎と平行に、側溝に沿うようにして、ひとつずつ窓をくすぐっていく。
それでも、不感症の箱はびくともしない。
「これが現実?」
問いかけると、
「んー」
目の前の闇が、低く唸る。
「もしも窓が開いてたら」
ついでに問うと、
「んー?」
ついでのように唸る。
「エッチするの?」
「学校は萎えるだろ」
「ふふ。なにそれ」
「まぁ、べつにいいけど」
早口で囁き、こぼすようにして、彼は、再び指に力を込めた。
胸に風が吹いた。流されてもいいと確信。
残すところ、あと6枚ぐらいのところで、からら、難なく窓が開いた。
おーと歓声をあげて彼、
「これが現実」
たぶん自慢げ。
「致命的な凡ミス」
業者を皮肉りながら、さっそく彼は不法侵入。
しばらくすると、やや右手、侵入窓から少しズレた場所が、かしょん、軽やかに鳴る。正規の通用口か。
「行こ?」
迎えにくる彼。指を結ぶ。熱が蘇る。今まででいちばん熱い。
不思議と、校内のほうが明るいと感じた。障害物が多いぶん、跳ねかえされるかすかな外光が際立ってる。
「ホントに誰もいないの?」
「だってお盆だぜ?」
「そっか」
「民主主義」
小声なのに、1曲目のカラオケのような、血迷ったエコー。
2階へとあがる。あがってすぐ、第1校舎とを連結する細長い渡り廊下。
非常ベルの灯籠がひとつ。異世界の架け橋を紅色に染めている。
「こわい」
「足りない?」
そう言って、彼は指を解き、肩を抱いた。
耳たぶが、逞しい胸に預けられる。でも、今いち彼の鼓動が聞こえない。誰かさんのリズムに相殺されてる。
第1校舎。
作業用の導線なのだろう養生シートの敷かれる階段をあがり、3階、あたしたちのエリアへと出る。
第2校舎よりも薄暗い。厚手の防音メッシュシートが、必要なぶんの月光しか許していない。
「静か」
「凡ミスだから」
なるほど、清掃しきれていないのか、塵で床が滑り、足音を立てることのほうが難しい。
それでも、さすがに慣れた歩幅で歩く。
階段フロアから廊下へと出、1組と2組を右に見ながら、その逆を折れる。さらに、3組と4組を見すごし、5組へ。
あたしたちの主戦場。今は、なんにもない教室。
厳選された月光が、予定表の黒板の白いラインを引き立たせている。
「ねぇ」
自分の机にお尻を乗せる。彼も倣ってお尻を乗せ、背中に背中を添える。
はんぶんこの机。シンメトリィのふたり。
「なに?」
「いつまで続く?」
「なにが?」
「あたしたち」
彼の背中に深くもたれる。すると、彼ももっと深くもたれる。
暗黙の抵抗がかわいい。
「ずっと続くと思う?」
「ずっと続くと思わなくなるまで」
「それズルい」
ごん。後頭部に後頭部をぶつける。
「思っててって」
背中で抱きしめられたらいいのに。
「お願いするしかなくなるじゃん」
「お願いしてもいいよ」
「そういうふうに言われると」
「お願いしてよ」
背中に、真夏が燃えてる。そして渇いた心を突き破り、逞しい芽吹きが彼の背中に蔓を這わす。
疚しくて、でも、聖なる蔓を。
「お願いしてもいいの?」
「してる」
「まだしてないもん」
「いまお願いしたじゃん」
「えぇぇ。したかった」
「いいよ」
そう告げて、彼はお尻で90度だけ机を回り、さらに上半身を90度だけ捩ると、
「叶えてあげる」
あたしの腰を両腕で囲い、うなじにおでこを当てた。
「ずっと思ってるよ」
背もたれを失ったあたしは、だから、やっぱり彼に預けるしかなかった。
ぜんぶ、ぜんぶ、ぜんぶ、彼のものだった。
「ずっと思ってる」
ズット思ッテル。
不意に、胸がざわついた。
月は輝く。
いや、輝いてなどいないのかも知れない。
だって、あたしの目には、今、月が映っていない。そこにあると証明できない。
箱の外にとって、箱の中の出来事は、ただの確率でしかないのだから。
箱の中にとっても、箱の外の出来事は、ただの確率でしかないのだから。
ズット思ッテル。
だとしたら、この約束も……?
たちまち、不安になった。
「アメほしい」
「アメ?」
「持ってる?」
「そで」
お腹を囲う袖を探る。固形物が5つ。
「イチゴはどれ?」
「ピンク」
「どれ?」
「ぜんぶ」
手探りでビニルを開く。べべべり。ちょっと溶けてる。包み紙は机の中に投棄。
かろ。
一瞬にして、甘酸っぱいが広がった。
彼と出会ったばかりのころの、懐かしい香り。
無我夢中でいることがすべての、確信犯の香り。
彼の大好物だと、彼の十八番だと、彼の代名詞だと信じるあたしを、迎えてくれる香り。
嘘のように、胸のざわつきが止まった。
やっと、彼の中におさまった気がするから。
彼という、箱の中に。
「リンゴだ」
「イチゴ」
「リンゴだよ」
「オレにもちょうだい」
「どれ?」
「リンゴ」
「だから、どれ?」
「1個しかない」
「じゃあ、もうない」
「まだ、あるじゃん」
うなじが囁かれる。
「しょうがないな」
彼の両腕を優しく解くと、あたしもまた、90度。
彼の、顔の輪郭、その箱のまん中に、
「愛ひへる」
そっと、小さな月を浮かべた。
かろ。
やわらかい。
あったかい。
生きている。
箱の中で、あたしたちはちゃんと生きていた。
かろかろと浮かぶ月を糧にして、あたしたちは、ちゃんと生きていた。
箱の外、月はそれを知らない。
いや、あたしたちが箱なのかも知れない。
箱。
箱の中に。
キスの中に、やがてひとつになったあたしたちの中に、何度も、何度も、何度も、あたしたちは月を浮かべた。
| ≪ | 表紙に戻る | ≫ |