「おはよう、レム」
「おはよ、アウネさん! 待った?」
「いや、今着いた」
アウネンゴデムは俺の姿を認め、目を細めた。今日の薬屋は定休日。朝から薬草を補充しに森に出かけ、群生地で彼と落ち合う。すなわち逢引である。余り布で作ったシーツを敷き、早起きして作った弁当を広げれば、彼は興味深そうに箱の中身を覗き込んだ。
「綺麗なものだな」
「ふふふ、俺、子供の頃から自炊してたから、料理は結構得意なんだ」
「吾が食べても良いのか?」
「その為に作ってきたの! 一緒に食べよ、朝ご飯」
アウネンゴデムは弁当箱の上でうろうろと手を彷徨わせた後、こんがり焼いた厚切りベーコンと野菜を挟んだサンドイッチを掴む。それを上から下からしげしげと眺め、ゆっくり口に運び、咀嚼した。
「おいしい?」
「うむ!」
きらきらした明るい表情とすぐに無くなってしまったサンドイッチに、どうしようもなく嬉しくなる。久しぶりに二人きりでいられる時間なのだ、俺も堪能しなければならない。次はどれを食べようかと考えている彼の身体にそっともたれかかれば、白い尾の先が楽しそうにぴるぴる動いた。
「今日はあったかくていい天気だね、アウネさん」
「そうだな、吾は晴天を好む」
俺の定休日にだけ二人で会って、他愛もない話をして、時々少しだけ触れ合って。そういう風に二人で決めた。俺が記憶喪失だった頃より一緒にいられる時間は減ったけれど、それでちょうどいいのだと思う。
俺も彼も、たぶんまだまだ幸せの許容量が少ないのだ。一度に摂取しすぎると拒否反応を起こしてしまいそうな気がする。だから、少しずつ二人でいられる幸福に慣れていって、幸せな自分を受け入れられるようになって、それで最終的には。
「最終的には…………」
「どうした、そんなに赤い顔をして」
「な、なんでもない!」
最終的には、アウネさんの、つがいになりたい。結婚したい。そんな恥ずかしいこと言えるはずもない。少なくともまだ言えない。ふるふると頭を横に振れば、首をかしげるだけでそれ以上何を追及してくることもない。しばらく黙々と料理を食べて、不意に彼が赤い花を示して見せた。俺の方を横目で見て、そういえば、と呟く。
「この中でどの花が一番綺麗だろうか」
「え、なに、全部綺麗だよ」
「そういうことではなく、ぬしが一番好きなものはどれか教えてほしい」
「うーん……それ? 丸くてかわいい」
「分かった」
彼の顔の一番近くに咲いているものを指差せば、アウネンゴデムは頷く。どうしてそんな事聞くの、と問えば、何となく、との返答。彼は持っていたローストチキンを、咀嚼し、飲みこみ、持ってきた濡れ布巾でやたら丁寧に手を拭いた。その日はそれきりその話題に触れてこなかったから、他愛もない話の一つとして思い出の箱にしまわれた。しまわれた、のだけれど。
「この花を受け取ってはもらえぬだろうか」
――どうか、応えを。愛しいひと。
アウネンゴデムが求婚の覚悟を決めて。綺麗に取られた赤い花を、俺が一番好きだと言ったものを恭しく目の前に差し出されて。思わず泣きだしてしまった俺が、彼を酷く動揺させて。震える手で受け取れば、花をそっと髪に挿されて。静かに顔が降りてきて。そして、そして――。
それは、次の満月の夜まで誰も知らないお話。これからも続いていく、俺と彼が共にある物語、そのほんの序章に過ぎない幸せな話だ。
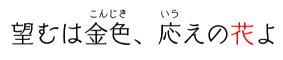
-------
人外×人間アンソロジー「まれびと」様に提出させていただきました。
2017.1110 sato91go
←
(main)
|