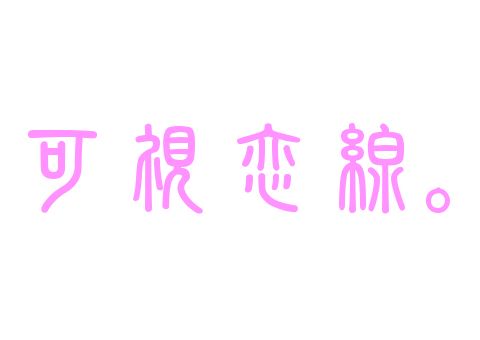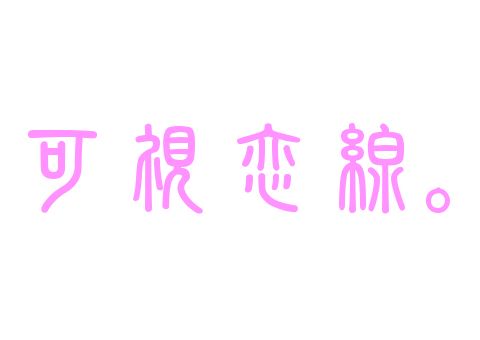人生はシンプルな方が生き易い。
品の欠片もない笑顔を晒して、その口癖を投げつけてきた女は誰だったか。
「小雀」
『小雀』と『小朱』には天と地ほどの差があると思う。呼び名の違いだけではない。
例えば何かにつけて殴り掛かって来る様な気性が激しい女は、打算で結婚した割りにはいつも幸せそうだった。
「起きなさい、小雀!」
「…あ?」
朝から元気な女だと、寝惚けながら呟けば、寝台の上から蹴り落とされた。いつか死ぬぞと怒鳴れば、煌びやかな金髪を掻き上げた女性は一言、
「その程度でおっ死ぬようなヤワな息子を産んだ覚えはない」
これだ。いや、これだけで済めばまだ良い。
「もっかい蹴られる前にとっとと起きなさい、馬鹿息子」
「うっせーな、もう少ししとやかに起こせ馬鹿女!」
「キルユー」
これが大河朱雀に残る、数少ない母親の記憶の一部だ。
単語を並べただけの下手糞な中国語は、標準語と広東語と台湾語がまぜこぜになっていて、生まれた時からそれに慣れていた自分やアジア中の言葉を理解していた父親はともかく、それ以外の誰もが混乱していただろう。
「だから大老のジジイ共に小朱と小雀じゃ一緒に聞こえるから、阿朱にしろって言ってやったんだよ」
「それ餓鬼の呼び方じゃねぇか」
「白燕もそんな事言ってたけど、こっちじゃ陳朱花で通してんだからローズで良いじゃないよ…」
「嘘つけ、アネモネだろ」
「Shout up bad boy!(お黙り馬鹿息子!)」
自分を薔薇と言って憚らない金髪女は、金髪以外は地味な容姿だったと思う。染めていたのか地毛だったのかも今となっては判らないが、記憶の中で生き続ける母親の印象の大部分が、ブロンドだった。
「何でそんな嫌がるんだよ。親父だって知ってんだろ?」
「…私が直接教えた訳じゃないんだから、ノーカン!」
「滅茶苦茶言ってる自覚はあるんだろうな」
「4歳の餓鬼がマセた事言うんじゃない。…当てつけでつけられた名前なんか、好きになるもんか」
「あん?あてつけって何だ?」
「私には同い年の姉ちゃんが居るって言ったでしょ?」
「おう」
「フリードって結構大きな家の一人娘は、豪華絢爛って意味のサニアって名づけられた。母さんはそれを知って、誕生祝いにアネモネの花束をクソ親父の元に送りつけたんだ。花言葉は色々あるらしいけど、愛の苦しみだとか、期待だとか、見捨てられただとか…あんまり聞きたくないのもあるってさ」
「良く判らんが、嫌がらせで贈った花の名前って事か」
「All right、どう思う?」
「イカれてんな」
「やっぱアンタは私の子!チューしてあげる!」
「キモい、やめろ」
記憶の母親は常に笑っていた。何がそんなに楽しいのか、言葉もろくに判らない国に嫁いできて、マフィア同然の男達が切り盛りしている中国最大組織の中枢で暮らしながら、主食はハンバーガー。おやつはフライドポテトに大量のチェダーチーズソースを溢れさせた、何処が芋なのか判らない代物。
「サニアは私が言うのも何だけど、美人で腕っぷしも強い。12歳で大学に入るくらい頭も良いのに、15歳で卒業した途端、家には内緒で軍に入った。私に会いに来てくれたのはその頃だったね。サニアの母親は日本人なのに細菌研究で褒賞された様な凄腕研究者で、中国大使館で働いてた母さんは同じアジア人として尊敬してた部分もあったらしい。そんな天才が選んだ男から誘われて、まぁ、舞い上がったんだろうね。お子様のアンタには判んないだろうけど」
「昔ユエの別荘だかに行った時に会った、目が緑のおばさんだろ?」
「アンタ覚えてんの?あれはリヒトが生まれた後だったから、アンタまだ一歳になってなかったわよ?」
「ぼんやり覚えてる気がする、ような?」
「子供の記憶力って凄いな。ま、楼月の別荘じゃなくて美麗の別荘だけどね。新年の旅行に誘われて、イタリアに行った」
「その辺までは知らねぇ」
「仕事が忙しいって言ってた筈の白燕が半日もしない内に追い掛けてきて、まー思い出したくもないくらいサニアの旦那と睨み合ってたわ。一回りくらい離れてるのにどっちも若白髪で、神経質そうな所がそっくりだったからね」
「虎柄のパンツ履いてる男が神経質なんか?」
「私達の前じゃデレデレしてるけど、かなりの神経質だっつーの。枕が変わったら眠れないわ、ドライアイが酷いからカラコンつけただけで目の色が変わるわ、酷い時は眼圧が上がり過ぎて出血までするんだからね!アンタは出かける時にコンタクトレンズを付け忘れるんじゃないよ!」
「うっせ、怒鳴るな!唾が飛んできただろクソババア!」
「誰がクソババアだって?!お育ちが知れるっての、馬鹿息子。裸眼でもそれなりに珍しい色してるんだから、どーんと奇抜なスカイブルーとかゴールドなんてのも良いんじゃない?そうだ、リヒトが宝石みたいな緑だったね。アンタら顔立ち似てるから、今度お子様用作って貰おっか」
そんな女だったからか、己の息子の眼が不気味なものだったとしても、然程深く考えていなかったに違いない。
中国国内、それも北京か上海から殆ど出る事がなかった夫とは真逆に、彼女は幼い息子を連れて何処へでも出掛けた。その度に夥しい数の警護や監視が当然の様につけられていたが、まるで意に介さず。
「サニアは自由を選んだ。私はあの子の真似をした。大学に行く頭がなければテーブルマナーも知らない私が、サニアの代わりなんか出来るもんか」
「んで、親父と結婚したのか。ババアもイカれてんな」
「全然違うね、私が白燕を選んだんじゃない。私が白燕に選ばせたんだ」
「どう違うんだ?」
「初めて会った時、白燕はまだトップではなかった。まぁ上海を任せられていたくらいだったから、頂点に近い所には居たけどね、当時の社長は強い人だった。金を通じてでも、中国統一を果たしたんだ。お前の祖父さんはそれほどの力を持っていたんだよ」
「痛ぇ、蹴るな」
「それしか選択肢がないのと、まっさら自由な状態で選ばれるのは、全然違うんだよ。お前も男だったら選べて選ばれる人間になりなさい」
「意味が判らん。ババアはまずちゃんと喋れ」
「良い事言ったつもりなんだけど?!かーっ、腹立つ!いつものパズルやるわよ、さっさと出してきて!」
「人使いが荒ぇババアだ」
子供の頃の玩具は積み木。ブロック一つ一つにアルファベットが刻まれているものと、漢字が刻まれているものがある。手っ取り早く言葉を覚える為にと白燕が特別に作らせたそれは、朱雀が生まれる前からあるそうだ。
「そこスペルが違う。言葉は早い内に覚えておいた方が絶対に良いんだ、広東語に比べたら英語なんて簡単だろ。次また間違えたら、今度は投げる」
「クソババア」
「お母様でしょうが」
「顔についてるケチャップ拭いてから抜かせ。テメェ何歳だ」
「レディに年齢を聞くな殺すぞ糞餓鬼」
「お育ちが良い事で」
「…アンタのそう言う所は白燕に似たんだ、絶対そうだ」
豪快な妻にも神経質と呼ばれた大河白燕が気を許した、ただ一人の人間。
彼女はいつもいかなる時も笑顔だった。記憶が始まった時から、死んだ最後の日ですら、息を引き取る瞬間ですら。
最期の言葉を聞いたのは、自分だけだった。
そしてその言葉は19年間、誰にも話した事がない。
大河朱雀と言う当時4歳の少年が、初めて見た真っ赤な世界で、双眸を真紅に染めたあの日。
「…アンタに怪我がなくて良かった」
「バ…っ、か、母ちゃん…!」
「私は平気だから落ち着きなさい、コンタクトしてても透けてる。アンタまで血を流したら白燕が泣いてしまうだろ?」
人間は生まれる場所も、死ぬ場所も、殆どの人間が選ぶ事が出来ないだろう。
手を離したものが戻らない事もある。アジア最強とも謳われる男が、乾き切った眼球から涙の代わりに血を流す事がある。
「強者はいつだって笑ってなさい」
「っ」
「アンタは自分が選んだ人間の前だけ、泣けば良い。…絶対に忘れるんじゃないよ、小雀」
小雀と小朱には、永遠に埋まらない違いがあった。
大河白燕はとうとう息子の前で涙を流す事はなく、間もなく息子を亡き妻の実家へ預けると、ただの一日も休まなかった家業を放り出して復讐に身を窶す。朱雀が知ったのは全てが終わった後、それも他人の口からだ。
以降、父子が顔を合わせる事は実に十年以上なかった。それだけではなく、朱雀の最後の記憶で父は、息子に銃口を向けたのだ。生気を感じさせない作り物めいた無表情、まるで蚊を見るかの様に。
今の関係が構築出来ている一番の理由は明らかに、松原瑪瑙と言う人間の影響だろう。
「ジュッチェや〜」
と言う建前はともかく、だ。
俺こと大河朱雀19歳が夜明けと共に人の気配を感じて飛び起きれば、未だ薄暗い私室の窓辺に人影を見つけた。それは人の部屋を我が物顔でつかつか歩くと、遠慮なくシャーっとカーテンを弾き飛ばし、人格を疑う様な奇抜な虎柄のチャイナドレスを翻しながら振り返ったのだ。
「起きたか小朱、我がモーニングサービスに来てやったぞ!」
「…俺はドアに内鍵をつけてた筈なんだがなぁ、5つも」
「こんな事もあろうかと、我はお前の部屋を二階に作らせたんだ。三階から梯子で降りれば天井をぶち破るだけで良く、一階から脚立を使えば床をぶち破るだけで良い」
さっと部屋中を見渡せば、ベッド以外の家具がない部屋のクローゼットの扉が空いていた。ウォークインクローゼットは6畳ほどしかないので、ドアが空いていれば中を窺える。無駄に巨大な穴が空いている事も、忌々しい事この上ないが、一瞬で理解した。
「朝ご飯は何が食べたい?汝は放っておくと飯もまともに食わんそうだのう、向こうでマーナオと暮らす様になってからは一日三食食べていたと報告を受けているが、近頃は夕食だけだと聞いておるぞ。全く今時の若者が貧弱になる筈だ。良いか小朱、」
「その小朱ってのやめろ、そして5秒で良いから黙れ」
「聞いたか天国に住まう我の愛しい朱花、我らの息子は19歳にもなって反抗期を満喫したままだ。か弱い我は、容赦なく荒ぶる息子に虐げられる哀れな余生を生きねばならんのかのう、150歳まで生きるつもりなのにのう…」
「5秒も黙れねぇのか」
此処まで接近されるまで気づかなかった腹立たしさはあるが、20平米の部屋の隅にあるベッドから最も離れたクローゼットの中で工作されては、あれほどの穴が開けられていても気づけなかった理由にはなるかも知れない。そもそも普段着と仕事着の数着以外着る用事がないので、クリーニングから戻ったものだけを着回していた事が原因だろうか。クローゼットがあった事も今思い出した様じゃ、いつから穴が開けられていたのかも定かではないと言う事だ。
「クソが、十回殺して11回埋めたい気分だ」
「おお、成程のう。爽やかな目覚めと共にパパの顔を見る事が出来たので、喜んでいるのか」
「間違えた、百回殺して千回沈めたい気分だ」
「そんな情熱的な目を実の父に向けるでない、間違いが起こってしまうではないか?」
「起きるか死ね」
クネっと恥ずかしげに目を逸らしたクソ野郎にティッシュ箱(まめことテレフォンセックスする時に使う高級品)を投げつけてやったが、鉄扇で難なく打ち返された。ぽふっとベッドに戻ってきたティッシュ箱は足元にあるので、手を伸ばして取り戻すのは面倒臭い。
自分の部屋に自分以外の人間が居ると言う最悪の状態で、シャツとパンツしか着ていない今の無防備な状態で、クソ野郎の前に立ちたくなかった。俺の中ではカルマこと遠野俊とクソ親父はほぼ同列に存在する。敵意が明確な分、洋蘭こと叶二葉やルーク=フェイン=ノア=グレアムの方が多少マシだと思っているからな。
「今すぐ出ていけ」
「だがッ、断るッ」
「何なんだこの鳴り止まねぇイライラは。全力でうぜぇ」
「この屋敷は我の屋敷、何なら上海の全てが我のものであり、中国大陸の全ても我のものだ。故に中国で暮らす人民にプライバシーなど存在せねば、我を拒絶する権利もない。くっく、そうとも!我こそがキングオブチャイナなのだ!」
「マジで俺にゃこんな糞の血が流れてんのか」
「鏡を見てみろ朱雀、汝は若かりし頃の我にク・リ・ソ・ツだぞ☆」
イラッとした瞬間、糞親父が日本語を喋っている事に気づいた。朱雀の発音だけ中国のものだったから流していたが、クリソツの部分で過去最大の殺意をマークしたと言っておこう。
「相変わらず、何にもない部屋だのう。これではマーナオが嫁いできた時に困るのではないか?」
「テメェに指図されなくても、必要なもんは必要になった時に必要なだけ用意するから良いんだよ」
「貧乏臭い事を言うでない。大河が必要なものと必要な分だけ買うなど、あってはならんケチ臭さだ。必要なものも必要でないものも必要以上に買え、これは王の命令ぞ」
「頼むから死ねよ。どうしたら死んでくれるんだ。今だったら何でもするぞ、マジで」
「馬鹿者、我が死んだらマーナオが悲しむだろうが。何せ我はマーナオの尻の穴まで見ている男だぞ」
枕元に仕込んでおいた護身用の銃を引き抜いた瞬間、満面の笑みの父親がクローゼットではなく部屋の戸口を指差した。
「石さんが来ておる」
「ああ?!…って、セキさんってのは、まさか石英の親父さんが来てんのか?!」
「部屋の外で待たしておるぞ。好調稼働中のアジア支店の視察で今回も一ヶ月ほど滞在するそうでのう、我が家を宿として使ってくれと我から申し出たのだ」
ああ、
「…よもや今此処で我が死ぬなど起こり得てしまえば、石さんはどう思うかのう?」
この男の何処が神経質なのか、生き返ってもう一度説明しやがれ、クソババア!