
魂の聖痕
「頬へのキス」「片思い」「忘れられない恋」をテーマに書いた話です。悲恋要素があります。
ーーーーーーーーーーーーーーー
*
ーーー もし、魂を震わす恋というものがあるとしたら、あたしはこの恋がそうだと思う
*
「ナナシー、3番テーブルがお呼びだよー!」
バイト仲間のナターシャに言われて、あたしの心臓がドクンと跳ねた。
ーー3番テーブルといえば、あの人がいるテーブルだ。
あたしは、トレーに乗っていた器とグラスを急いで厨房に追いやって、フロアのバックヤードに駆け込んだ。
「ねぇナターシャ私大丈夫?変な髪型してない?メイク崩れてない?マスカラは?パンダ目になってない?ライナー落ちてない?大丈夫?」
矢継ぎ早にナターシャに畳み掛ける。
「だ…大丈夫、大丈夫だって!変じゃないよ。」
「ホント?ホントだね!?嘘だったらあたし怒るからね!」
あたしの勢いに押されたのかナターシャはやや引き気味答えていたけれど、そんなのお構いなしにあたしはさらに前のめりになった。うん、大丈夫、ナターシャの瞳に映っているあたしは大丈夫、変じゃない。髪もメイクも服も完璧だ。
「そ、それより、ナナシー、いいの?3番テーブル待たせたままよ。」
その言葉を聞いて、慌てて体を起こして背筋を正す。「行かないなら私が行くわよ?」というナターシャの声を遮って、あたしはフロアの3番テーブルに急いで向かった。
ーーだめよだめ、この役は誰にも譲らないんだから!!!
そう心の中で叫びながら、あたしは窓際の王子様ーーークロロ=ルシルフルさんに向かって歩いていった。
「お、お待たせしました。ご注文はお決まりですか?」
窓際のテーブルで難しそうな本を読むクロロさんに、あたしはアルバイトマニュアルに載っている笑顔なんて目じゃないくらいの最大級の笑顔で声を掛けた。その声に、クロロさんが伏せていた目をこちらに向ける。クロロさんの黒い瞳と目があって、あたしの心臓がドキンと鳴った。
ーーや、やばい、超絶カッコいい……。クロロさん、今日も素敵です。
「あ、君は…」
「ナナシーです!!昨日も一昨日も注文伺わせて頂いたんです。ク、クロロさんですよね?」
「そうだよ、よく覚えているね。」
「もちろんです!だって、昨日、お名前教えてくれたじゃないですか!?忘れるわけありません!!」
顔を赤くして断言するあたしに、クロロさんは困ったような笑顔を返した。好意を隠さずにストレートに口にするあたしに困惑しているのかもしれない。けれどそんなことには構ってられない、『恋をしたら一直線』『全力全開超突進』で押しまくるのがあたしの恋愛必勝法なのだ。
「オーダー入ります!ブレンドコーヒーひとつ、クラブハウスサンドひとつ、お願いします!」
クロロさんから聞いたオーダーをキッチンに伝えると、あたしはコーヒーサーバーの前に立った。ポチッと、ブレンドコーヒーのボタンを押すとゴリゴリゴリと豆を引く音と共になんとも言えないコーヒーの香しい匂いが漂ってきた。珈琲豆の匂いーーーそう、クロロさんの匂いだ、なんてセンチメンタルに思ったりした。
さっきのクロロさんとの会話を思い出す。
大丈夫だったかな?変なこと喋って無かったかな?なんて一人反省会始めたあたしだけど、次から次へと思考が飛んでしまってあたしはコーヒーサーバーの前で一人表情をくるくる変えていた。
ーーーどの行動が正解かなんて分からないよ……でも一つだけ言えるのは前進あるのみってことだけ!!!
コーヒーマシーンからカップに向かってポタポタと抽出されるコーヒーを決意した瞳でじっと見る。
大丈夫、大丈夫、さっきのやりとりであたしが好意を持っているってクロロさんに伝わったはず。……もし伝わってなかったとしても名前を覚えてもらったんだから大丈夫、大丈夫、あたし前進してる!!落ち込まない落ち込まない。恋は押せ押せGO!GO!GO!!立ち止まってなんかいられないんだから!!!
ジェットコースターのように乱高下するする心臓をギュッと握って、あたしは顔を上げた。コーヒーマシーン越しに本を読んでいるクロロさんが目に入って、心臓がキュンキュンと高鳴った。
あぁ、もう、やっぱり好き。あたし、クロロさんのこと好き。好き好き、大好き、大大大好きだ!!!もー、だめだ止まんない!この恋もこの想いも誰にも止めることはできないよ!!!
*
あたしがクロロさんに出会ったのは、ちょうど5日前の雨の降る日だった。雨といってもしとしと降る雨ではなくて、突然バケツをひっくり返したように降りだした雨で、クロロさんはそのスコールに当てられて体を雨に濡らした状態で、このカフェの扉を開いたのだった。今でもその姿は脳裏にしっかりと焼き付いている。
カランカランというドアのベルで振り返れば、そこにいたのは雨で髪を濡らした体躯のいい男の人で、あたしはその均整の取れた体つきと気だるそうに髪を掻き上げるその仕草に、しばらく魅入っていたのだった。
「あー…やられた…」
と悔しげにボソリと呟いて顔を上げた彼に、あたしの目はさらに奪われてしまった。すっと通った目鼻に、吸い込まれそうな黒い瞳。キュッと引き締まった知的な唇。そして、彼の纏う近寄りがたいのに近寄りたくなる不思議な空気。
トレーを持ったまま仕事を忘れてボーッと立ち尽くすあたしに、クロロさんは追い打ちのように爽やかな笑顔を向けて「お姉さん。一人なんだけど、席、空いてるかな?」と言った。
その時にあたしが感じた衝撃をどう言葉にすればいいのか今だに分からない。頭の天辺から足の先に向けてピシャリと電流のようなものが走って、一瞬で体が硬直した。なのに、心臓の鼓動だけはドクンドクンと次第に早くなり、しまいには100mを全力疾走したくらいの早鐘を打っていた。
それは、まさしく恋の稲妻。
どれくらいの間そうしていたのか分からないれけど、こちらを訝しげに見るクロロさんの視線に気づいてあたしはハッと顔を上げると、急発進をする車のようにバタバタバタと音を立てて裏のロッカールームに駆け込み、お母さんが持たせてくれたタオルをカバンの中から勢い良く取り出すと、扉を締めるのを忘れてあたしは入口に向かった。
「ハァ…ハァ………あの、一名様ですね?」
「あ、あぁ……」
「ご、ご案内致します、こちらへどうぞ。」
そう言ってクロロさんを空いているテーブルに誘導した後、あたしは震える心臓を押さえつけるように深呼吸をしながら、手にしたタオルをクロロさんにえいと渡した。
「あ、あの!!よ、良かったら、このタオル使って下さい!!」
「いいの?これ君のじゃないの?」
「そ、そうですけど、あたしは濡れてないし、お母さんが持たせてくれたんだけどお母さん心配性だから二枚入れてくれて、あ、あたし二枚も使う予定ないし、それに、いくら8月だと言っても濡れたままだとお兄さん風邪引いちゃいますから!!」
そこまで一息で言うと、クロロさんの手に強引に置いた。すると、クロロさんは「そう?悪いね。」と言いながら受け取ってくれた。
その時、さっき見せてくれた爽やかな極上の笑顔をあたしに再び向けてくれた。心臓がキュンと音を立てる。歓喜なのか感動なのか分からないけれど、なぜか指先がふるふると震え出した。
ーーーあぁ、あたしこの人に恋しちゃったんだ。
根拠のない確信。だけどそれは間違いなく真実で、あたしは一目で恋に落ちてしまった。そして、その時から、あたしの日常はクロロさん一色になったのだった。
*
「ねぇねぇ、ナターシャ、聞いて聞いて!!」
バックヤードに飛び込んだあたしはナターシャを探してキッチンを見渡した。あ、いた。食器洗浄機の近くで洗い終えたお皿を取り出しているナターシャを見つけるとあたしはバビュンとナターシャの側に行った。
「ねぇねぇ、ナターシャ!!」
「………なによ。私、今、仕事中なんだけど。」
「あーーん、もういいじゃんそんなの。そんなの後でもやれるじゃん!!」
「はぁ………ったくもう。なに?……まぁ、聞かなくても分かるけどね。どうせまたクロロさんの事なんでしょ?」
「そうなのーー!!!あのね、あのね、ナターシャ、聞いて!!クロロさんの仕事ってなんだと思うーー??」
「さぁ?ここ最近、毎日このカフェに来ているから……大学院生とか?あ、仕事している人か……なら何かの実業家とか?」
「あーーー、惜しい!けど、違うの。あのねぇーーーー………古美術商、だって!!」
「コビジュツショウ?」
「うん、古い美術品を仕入れて売る仕事だって。世界中を渡り歩いてるんだって!!カッコいいよね!?カッコいいよねーーーー!!!!」
「………そう?この時期にヨークシンにいるんだもの、別に珍しくないでしょ。確か、最近朝のモーニングを食べに来てるちょっと太ったあの人も、確かヨークシンオークション目当てに来た人だよ。古美術商じゃないの?」
「えーー!?あの猫目の太った人が!?いやいやいやいや、全然違うよ、古美術商って感じじゃないじゃん。なんかアニメオタクっぽいじゃん。あれはただ何かのアニメグッズを競り落としに来ただけだって。クロロさんと同じ職業な訳ないじゃん。」
「ナナシー……、あんた、たまにサラッと酷いこと言うよね?」
「……そう?だって、そうとしか思えないじゃん。」
あたしに「魔法少女ミルキーメイの『レイラ』ちゃんに似てるよね?」って話しかけてきたミルキだかミルクだかって名前の人が、クロロさんと同じ仕事のわけがないのに、ナターシャったらホント何を言っているんだろう。
そんな風に考えているあたしを置いてナターシャは、一人黙々と作業に戻ってしまった。残念、まだナターシャに言いたいことがいっぱいあったのに。チェっと口を尖らして、あたしはフロアに戻る事にした。
こんなやりとりが、クロロさんと出会ってから何回あっただろうか。その回数は多すぎて、あたしはもう数を数えることすら放棄していた。
*
クロロさんと出会ってから10日が過ぎた。出会ったその日からあたしの世界は極彩色に輝き始めて、いつもと同じ風景が全くの別物に見えるほどに全てが一瞬にして変わった。たった10日なのに、今までのあたしの人生をぎゅっと凝縮したくらいの濃密な時間を、あたしは過ごしていた。
『魂を震わす恋』ーーーまさしく、そんな恋だった。
今まで恋をしたことは何度もあったけれどこんな風に感じる恋は初めてで、この10日間のあたしはナターシャに百面相ってからかわれるほどクロロさんの一挙手一投足に翻弄されていた。でも魂を震わせるほどに心の底から感じ入り、心の底から笑い、心の底から泣き、心の底から喜び、そして心の底から湧き上がる好きという感情を、心の赴くままに伝えることができて、あたしは幸せものだったと思う。
その頃のあたしの口癖は「ねぇねぇ、ナターシャ、聞いて、聞いて!」だった。その言葉の後に続くのはもちろん「クロロさんがね…」だったのだけど、今考えれば、鬱陶しいだけのこんなあたしを見限りもせずにナターシャはよく付き合ってくれたもんだと思う。
けど、その時のあたしはクロロさんの事で頭がいっぱいいっぱいで、この思いを伝えずにはいられなかったし、それにクロロさんがカッコよすぎるせいか、はたまたあたしが単純すぎるせいか、ナターシャに報告する話題には事欠かなかったのだった。
「ねぇねぇ、ナターシャ、聞いて、聞いて!!さっき、クロロさんがね、超絶カッコよかったんだよ!!私がコーヒー持って行った時にね、こう……指と指とがちょっと触れ合ったんだけど、その時に『あ、ごめん」って言いながら、あたしに笑かけてくれたんだよ。何て言うの?流し目っていうのかな?そうそう、こんな感じの艶かしい視線でさ。それが超色っぽいの!!!これってわざとなのかな?あたしのことをそんな目で見ちゃうなんて、もしかして誘われてたりするのかな!?ねぇねぇ、どう思う!?」
なんて報告する日もあったり
「ねぇねぇ、ナターシャ、聞いて、聞いて!!クロロさんがね、私と目があった時にね、小さく手を振ってくれたんだ。そう、8番テーブルを片付けている時なんだけど……。こう、小さくヒラヒラって。これってさ、あたしのこと気にかけてくれてないと出来ないことだよねー!?もしかして、あたしに気を持たれてるのかなーー!?」
なんて報告する日もあった。
そんなある日、レジで伝票整理をしているとテーブルを片付けたナターシャが手に持ったものを見せながら話しかけてきた。
「ねぇ、コレ、クロロさんの忘れ物じゃない?」
見るとそこには、確かにクロロさんが読んでいた古めかしい本があった。なんでここにあるの?と言いたかったけど、驚きすぎて言葉が上手く出てこなかった。
「え……あ……それ……」
「クロロさんのでしょ?」
「じゃぁ……今から……」
「もう、分かってるって。店長にも許可とっといたから。」
「ほ…ホント?」
「本当だって、ついでに30分の小休憩取っていいって店長言ってたよ。」
「ナターシャ!!!大好き!!!!クロロさんの次にだけど、大大大好き!!」
「全くもうナナシーったら調子いいんだから」
「ねぇねぇナターシャ……あたし………」
「はいはい、分かってるって。メイクも服も完璧だよ、髪型も大丈夫。ただちょっと笑顔が足りないかなー?ほら、笑って笑って。」
「ナ、ナターひゃ。い、痛いひょ……。」
「よっし、これでいい。ナナシーにはそんな顔は似合わないよ、笑顔が一番!!!」
「ナターシャ……」
まだ痛む頬をさすりながら、あたしはにかっと全力全開の笑顔をナターシャに向けた。すると、ナターシャがグッと親指を立てて笑顔を返してくれた。
それを合図に、あたしは「行ってくるね。」と一言告げるとくるりと背を向けて店を出たばかりのクロロさんを追いかけて走り出した。
*
「クロロさん、まだ遠くに行ってなければいいんだけど……」
いつも店を出て右に曲がるクロロさんのことだ、いつもと同じならこの道を進めば会えるはず。そう思っていたら店を出て5分と立たない内に、クロロさんを見つけることが出来た。良かった。あたしは「クロロさーーん!」と手を振りながら走りを加速させた。
「ハァハァ……ハァ…。ク、ロロさん……。」
「ナナシーちゃん、どうしたの?」
「あの……忘れ物を届けに……ハァハァ。」
大きく息を吸って呼吸を整えると、脇に抱えていた本をクロロさんに差し出した。
「わざわざ届けに……?」
「えぇ……はい、これ。」
「ありがとう。でも、予想より少し遅かったな。」
「え!?」
クロロさんがにやりと笑ってあたしに意味ありげな視線を送ってきた。ま、まさか…
「え!?あの…ワザとだったんですか!?」
「フ……どうだろうな。でも、君がこうして持ってきてくれたおかげでオレはコレを手放さずにすんだ。」
「そんな……あたし、クロロさんにコレ渡さなきゃって必死になってきたのに……クロロさん、イタズラが過ぎますよ!」
「でも、こうして持ってきてくれたおかげで、君と話す時間が出来た。」
思わず息を飲む。クロロさんの意図を理解した瞬間、あたしの顔がカーッと熱くなった。二人きりになるためにこんな手を使うなんて、やっぱりクロロさんは大人だ。あたしの周りにこんな事をしそうな男の人なんていやしない。こんなことがサラッと出来ちゃうなんてクロロさんやっぱり素敵だ、格好いい。
騙されていたと知ってもあたしのクロロさんへの想いが褪せることはなくて、むしろクロロさんへの想いはさらに加速した。目の前のクロロさんをじっと見つめる。いつも席に座っているクロロさんとしか話してなかったから目の前で向き合って話すのはとても新鮮で、「クロロさんって意外と背が高いな」とか「抱き締められたら胸の中にスポンと入っちゃうんじゃないかな」なんてことを考えていた。
クロロさんが何かを言いたげに口を開く。もしかしたらもしかしたらあたしへの告白なんじゃないかと思う自分もいたけど、そんなことはないよ期待しちゃダメだよと諌める自分もいた。でも、やっぱりこんな風に演出されちゃうと少しは期待しちゃうわけで、あたしの心臓はドキンドキンと期待で高鳴っていた。
「実は、オレ、君にお礼したいことがあって。」
「……お礼?」
「はい、これ。」
そう言ってクロロさんは可愛くラッピングされたクッキーをあたしに手渡した。なんだか告白ではなさそうな雰囲気にあたしは心底がっかりしたけれど、クロロさんにプレゼントを貰えた事実に次の瞬間にはあたしは持ち直していた。
「え……お礼?あたしクロロさんにお礼されることなんてしてないです……。」
むしろ、毎日うちを利用してくれて、あたしに姿を見せてくれて、あたしに話しかけるチャンスをくれることに、あたしの方がお礼を言わなくちゃいけないはずなのに。
「オレに気さくに話しかけてくれたじゃん。」
「でも……それは、あたしがしたくてしたことだから…。」
そのまま「クロロさんの事が好きだから」って告白したかったのに最後の一押しの勇気が足りなくて、最後の方はもごもごしてしまった。
「実はね、オレに君と同じくらいの年の妹がいてね。」
「妹……?」
「ネオンって言うんだけど、かなり小さい時に別れたっきりでね。近々会うことになったんだけど向こうはオレのこと覚えてないだろうから、ほとんど初対面みたいなものなんだ。」
「そう、なんですか…。」
「今時の女子高生と話する機会なんてないから、どんな風に話したらいいか悩んでいたけど、君が気さくに話しかけてくれたおかげで自分に自信がついたよ。ありがとう。」
クロロさんの役に立てて嬉しいと思う反面、悲しいって思ってしまったのはなぜだろうか。それは、たぶん、クロロさんがあたしと話してくれたのは全てその妹さんとの予行練習のためだったんじゃないかって勘繰ってしまったから。
その瞬間、クロロさんの妹に対する嫉妬心がブワッと湧き出した。
羨ましい。ずるい。こんなカッコいいお兄ちゃんがいるなんて。久しぶりに会うってだけでクロロさんに予行練習させちゃうなんて。羨ましくて羨ましくてたまらなかった。
だけど、そんな下衆な勘繰りで嫉妬心を燃やしているだなんてクロロさんに知られたくなくて、あたしは取り繕って返事をした。
「あたし、特別なことしてないですけど、クロロさんのお役に立てたなら嬉しいです。」
「本当に助かったよ、ナナシーちゃんありがとう。あ、そのクッキー、バイトの子たちには内緒で食べてね。君にしか渡してないから。」
そう言うとクロロさんは、初めて会った時の爽やかな極上の笑顔をあたしに向けてくれた。その笑顔を見た途端、あたしの心を曇らせていた嫉妬心が一瞬で消え去って代わりに突き抜けるような青空が心の中で広がった気がした。
ーーーなんていう破壊力。たった一つの笑顔でこうも変わるだなんて。
クロロさんのことが好きで好きで堪らない自分に自嘲の息を短く吐くと、あたしは背中を向けて歩き始めたクロロさんを呼び止めた。
「ん?どうしたの?」
振り返ったクロロさん前髪がさらりと揺れる。ごくりと唾を飲んであたしは口を開いた。
「あ、あの………クロロさん……。あたし…、クロロさんに伝えたいことがあるんです……。」
「何かな?」
「め、迷惑かもしれないんですけど、どうしてもこれだけは伝えたくて……。」
声が震える。心臓が喉から出そうなくらい激しく鳴っている。浅い呼吸のせいか、頭の中が真っ白になっていく気さえした。でもダメだ。こんなチャンス今しかないんだ。
あたしは、拳をギュッと強く握って、なけなしの勇気を振り絞った。
「あ……あたし、く…クロロさんのこと、す……好きなんです。」
絞り出すようして言う。
ああ…言った、言っちゃった。あたし、ついに言っちゃった。あたしは顔をこれ以上ないくらい赤くしながらクロロさんの反応を待っていた。風がふわりと通り過ぎる。
ーーーあぁ、ダメだ。
風が教えてくれたのだろうか、クロロさんが困った顔をした気配がした。恥ずかしくて下を向いているからちゃんと見たわけじゃないけど、そんな気がした。
「……ありがと。」
その言葉に顔を上げれば、そこにはやっぱり眉を困ったように寄せたクロロさんがいて、困らせたくなんかなかったのに困らせてしまった事実に悲しみが込み上げる。でも、溢れ出した想いは止まらなくて。
込み上げた色んな感情に鼻の先がツンとした。
「あ、あたし…クロロさんのこと…好きで好きで……」
声が詰まって言葉が途切れ途切れになる。涙を必死になって堪えるけれど、それももう限界で。
「もう……っ……んぐっ……自分でも、…っ…どうしようもないくらい好き、なの……」
そこまで言うので精一杯だった。泣いたらメイクが落ちちゃうってのに、涙がポロポロ零れてしまってもうどうしようもなかった。
好きなのに。泣きたくなんかないのに。困らせるつもりもなかったのに……。クロロさんへの思慕と困らせてしまったことへの後悔と二人っきりで話ができることへの歓喜と、そして気持ちが届かないことへの悲哀とが混ざり合って、もうどうしようもなくて、次から次へと涙が溢れては地面に落ちていった。
「……そっか。」
あたしの言葉を静かに聞いてくれていたクロロさんは、優しい声でそう言うとぐすぐす泣いているあたしの頭を軽くポンポンと叩いてくれた。
驚いて顔を上げると、そこには困りながらも優しさ溢れる顔であたしを見つめるクロロさんがいて、頭に置かれた手からクロロさんの温もりがじんわりと伝わってきた。
ーーーそんな優しい目であたしを見ないで。気持ちがさらに加速しちゃうから……
さらに、鼻の奥がツンとした。断りの言葉を言われたわけでもない。ダメだって言われたわけでもないない。でも、だけど、それだけど……あたしには分かっていた、この恋が成就する事はないって。
「……こんな可愛い子に好意を持ってもらえて、オレ………嬉しいよ。」
その言葉の後に続くのは間違いなく否定の言葉で。たぶん、色んな経験をしているであろうクロロさんの、相手を傷つけない断り方なんだと思う。
ーーーダメだダメだ、泣いちゃダメだ。クロロさんの記憶に残るのが泣き顔のあたしだなんてダメだダメ。ナターシャも言ってたじゃない、あたしは笑顔が一番だって。笑わなくちゃ。笑顔笑顔。
あたしは涙をぐっと堪えて笑顔を作った。クロロさんには、笑顔のあたしを覚えておいて貰いたい。
最高の笑顔をクロロさんに向けると、クロロさんはやっと困り顔をやめて笑い顔を向けてくれた。そうして、少し近づくと幼子をあやすようにあたしの頭をポンポンと軽く叩いた。
「よく頑張ったね。ご褒美だよ。」
その言葉が聞こえると同時にクロロさんの顔が近づいてきた。ふわりとクロロさんの香りが鼻腔をくすぐる。クロロさんの前髪がふわりと揺れるのが目の端に映ったかと思うと、左頬に温かい何かを感じて、チュッというリップ音が聞こえた。
突然の出来事に体が硬直して思考が停止する。
「ナナシーちゃん、またね。」
クロロさんにキスをされたと頭が理解したのはずいぶんと後で、理解した時にはすでにクロロさんが手を振りながら別れの挨拶を言った後だった。
「………キス、されちゃった………。」
クロロさんが通りを曲がった後、あたしはへにゃへにゃと腰を抜かしてその場に座り込んでしまった。クロロさんがキスをした左頬が熱を持ったみたいに熱かった。
*
クロロさんにキスをされてから3日が経った。この二週間毎日欠かさず来てくれていたのに、あたしが告白した日からピタリと来なくなって、あたしは常連のお客さんたちに「どうしたの?」って聞かれるほど感情がめまぐるしく動いていた。
もしかしたら、あたしが好きって言ったせいで来てくれなくなったのかもしれない。もしかしたら、あたしのことが嫌いになったのかもしれない。もしかしたら、オークションでの仕事が終わって自分のホームにさっさと帰ってしまったのかもしれない。もしかしたら、そのホームには恋人がいるのかもしれない。はたまた、もしかしたら、感動の再会をした妹さんとここではないどこかで暮らし始めたのかもしれない。
もしかしたらもしかしたらの妄想が次から次へと湧いて、その度にあたしは落ち込んだり悲しんだり涙ぐんだりしていた。でも、次の瞬間には3日前のキスをされたとことを思い出してはにやにやしたりしていた。それはまるで感情のジェットコースターのようだった。
それでも一週間経った頃にはマイナスな妄想ばかりが増えていってあたしは日に日に情緒不安定になっていった。
そして8日目の朝、裏のロッカールームで着替え終えてフロアに出たあたしに、ナターシャが声をかけてきた。今まで見たことのない、困ったような苦しいような申し訳ないような複雑な顔をしていたナターシャの手には、一枚の紙がぎゅっと握られていた。
「ごめんね。ナナシーに見せるかどうか迷ったんだけど、ずっと黙ったままではいられないと思って……」
ナターシャがその紙をおずおずとあたしに差し出した。こんな前置きを言いながらあたしに何か知らせてくるなんて、クロロさんに関することだって瞬時に理解した。どくんと心臓が跳ねる。嫌な予感に指先が震える。
「今ネットで拡散されている情報なんだけど……。ナナシー、気を確かにして聞いてね。それ、ヨークシンオークションを邪魔した集団を公開処刑した写真でね…結構グロ写真なんだけど……。その……その中にいる人が………。」
そこまで言うとナターシャは口を噤んだ。それ以上先は言葉にしたくないみたいだった。
この時期、ヨークシンには世界中のマフィアが集まってどこかで秘密裏に闇オークションをやっている。それはこのヨークシン界隈ではあたしも知っているような公然の事実で、この時期に外から来る観光客の何割かはマフィアだったりする。
そして、彼の纏う深くて底の見えない空気とオークション騒動後に姿を消したという事実が、あたしの数ある「もしかしたら」の中の一つを現実のものとしてその輪郭を浮かび上がらせた。
『彼は裏の世界の人間で、姿を消さなくてはいけないようなナニカが彼の身に起こった。』
当たって欲しくない予想に、冷や汗がジワリと噴き出す。
「ねぇ、ナターシャ。今、………何て言った?……こ、公開………処刑……って言わなかった……?」
ナターシャが気まずそうに目を反らした。手がブルブルと震えて、畳まれた紙を開こうとするけど上手に開けることが出来なかった。
「………これ…………まさか……………。」
開いた紙の中で、あたしが目にしたのは男女数人の血みどろの写真だった。そこには、血を流した無残に殺された死体がモザイクもなくあって、その中の一つがあたしの知っている人に思えた。
「あ………カハッ………ハッ………あ…………」
言葉が出なかった。こんなの嘘だ、これがクロロさんのはずであるわけがない。息をしたいのに息をすることも出来なかった。
でも、そこにはあたしがずっと見続けていた男性の姿があって。均整の取れた肉体に、すっと目鼻の通った顔。黒曜石のように黒い瞳に黒い髪。血だらけの姿で目を見開いて力なく壁に寄りかかっていたけれど、それはずっとずっとずっと夢に見るほどに思い続けていたクロロさんの姿に間違いなくて。
「………カハッ………ハッ………あ…………」
脳の許容量を超える衝撃に、頭が真っ白になってゆく。遠くでナターシャが「ナナシー大丈夫!?しっかりして!!」って言っている気がしたけれど、もう何も聞こえなかった。
ーーーこんなの嘘……誰か嘘だと言って……お願いだから……
薄れてゆく意識の中で、あたしはそれだけを必死に繰り返し繰り返し願っていた。
*
ーーーーもし、魂に刻まれた恋というものがあるとしたら、あたしはあの恋がそうだったと思う
*
「ナナシー?」
ふと名前を呼ばれ、あたしはハッと振り返った。すると、そこには心配げな顔で私の顔を見つめるマイクの姿があった。
「どうしたの?ナナシー?そんなぼーっとしちゃってさ。」
「ううん。なんでもないよ。」
力ない声であたしが言うと、マイクはあたしのおでこに手を当ててきた。数か月前から付き合っているマイクはとても心配性で、すぐにあたしのことを心配するのだ。
「熱?……はなさそうだけど。体調でも悪いの?」
「ううん。別に。ーーーーただ、ちょっと思い出しただけ。」
「あぁ、ここナナシーが前バイトしてたカフェに近いもんね。でも、そう言えば、三年以上働いていたのになんで辞めちゃったの?僕、ナナシーの制服姿結構好きだったんだけどな。大学が忙しくなったから?」
「それもあるけど。ーーーもう、区切りをつけようと思って。」
ーーーあれから三年、あたしはクロロさんの事をあのカフェで待ち続けていた。
ナターシャも店長も他のバイト仲間も「もう忘れなよ」って何度も何度も言ってくれたけど、あたしはクロロさんの事を忘れることは出来なくて、ドアのベルが鳴る度に「もしかしたら…」って淡い期待をしてしまっていた。期待をしては絶望するーーそんな日が三年もの間続いた。
高校を卒業しても新しい大学生活が始まってもあたしは待って待って待ち続けていた。けれど、ホントはもう気づいていた。この先一生クロロさんと会えることはないって。
だから、あたしはクロロさんと別れてからちょうど三年経った今年の9月2日に、あそこのバイトを辞めたのだった。ちょうど同時期にあたしの事を好きだとアプローチかけてきたマイクの存在も一役を担ったけれど、このままではいけないっていう気持ちもあったんだと思う。
すっかり木の葉が落ちた冬の並木道を、風がすうっと走り抜ける。ヨークシンの街並みを吹き抜ける冬の風は鋭く冷たいけれど、心に直接語りかけるように吹き込むそれは、あたしの心を慰めてくれた。
風に促されるようにして、あたしはあたしの歩調に合わせてゆっくりと歩いてくれているマイクを見た。あたしの事を可愛い大好きだって言ってくれる優しい優しい彼。まるで砂糖菓子のような甘い甘い愛情をくれる彼だったけれど、あたしの心が、魂が、あの時みたいに燃えることはなかった。
木枯らしの冷たい風がマフラーで隠れていないあたしの頬を撫で上げる。
風で冷えているはずなのに、クロロのさんがキスをしてくれた左頬が軽い火傷の痕のようにじくじくと痛み出した。
ーー頬。左頬。あたしの中の聖域。
そこはこの先誰にも許しはしない、クロロさんにだけ許した場所。まだ熱を持っているその左頬を、あたしはそっと優しく噛みしめるようにして触った。
『魂に刻まれた恋』
あの恋はまさしくそんな恋だった。喜びと悲しみと切なさとーーーそして溢れんばかりの愛しさを教えてくれたあの恋を、あたしは一生忘れない。
それはまるで魂に深く深く刻まれた聖痕のようで、この先一生癒えることはないだろう。
頬に当てていた手をスッと下ろす。久しぶりにあのカフェの前を歩いたせいだろうか。もう枯れたはずだと思っていた涙が、もう過ぎ去ったと思っていた感情が込み上げてきて、鼻の奥がツンとした。
立ち止まり空を見上げる。突き抜けるように青いヨークシンの空と冷たい凍えるような風が、あたしのことを包み込んでくれたような気がした。
[魂の聖痕]
ーーーーーーーーーーーーー
狩人夢企画サイト「くちづけ〜22箇所のキス〜」に「頬:親愛・厚意・満足感」で提出させていただきました。
[ *prev | back | next# ]
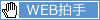
ーーーーーーーーーーーーーーー
*
ーーー もし、魂を震わす恋というものがあるとしたら、あたしはこの恋がそうだと思う
*
「ナナシー、3番テーブルがお呼びだよー!」
バイト仲間のナターシャに言われて、あたしの心臓がドクンと跳ねた。
ーー3番テーブルといえば、あの人がいるテーブルだ。
あたしは、トレーに乗っていた器とグラスを急いで厨房に追いやって、フロアのバックヤードに駆け込んだ。
「ねぇナターシャ私大丈夫?変な髪型してない?メイク崩れてない?マスカラは?パンダ目になってない?ライナー落ちてない?大丈夫?」
矢継ぎ早にナターシャに畳み掛ける。
「だ…大丈夫、大丈夫だって!変じゃないよ。」
「ホント?ホントだね!?嘘だったらあたし怒るからね!」
あたしの勢いに押されたのかナターシャはやや引き気味答えていたけれど、そんなのお構いなしにあたしはさらに前のめりになった。うん、大丈夫、ナターシャの瞳に映っているあたしは大丈夫、変じゃない。髪もメイクも服も完璧だ。
「そ、それより、ナナシー、いいの?3番テーブル待たせたままよ。」
その言葉を聞いて、慌てて体を起こして背筋を正す。「行かないなら私が行くわよ?」というナターシャの声を遮って、あたしはフロアの3番テーブルに急いで向かった。
ーーだめよだめ、この役は誰にも譲らないんだから!!!
そう心の中で叫びながら、あたしは窓際の王子様ーーークロロ=ルシルフルさんに向かって歩いていった。
「お、お待たせしました。ご注文はお決まりですか?」
窓際のテーブルで難しそうな本を読むクロロさんに、あたしはアルバイトマニュアルに載っている笑顔なんて目じゃないくらいの最大級の笑顔で声を掛けた。その声に、クロロさんが伏せていた目をこちらに向ける。クロロさんの黒い瞳と目があって、あたしの心臓がドキンと鳴った。
ーーや、やばい、超絶カッコいい……。クロロさん、今日も素敵です。
「あ、君は…」
「ナナシーです!!昨日も一昨日も注文伺わせて頂いたんです。ク、クロロさんですよね?」
「そうだよ、よく覚えているね。」
「もちろんです!だって、昨日、お名前教えてくれたじゃないですか!?忘れるわけありません!!」
顔を赤くして断言するあたしに、クロロさんは困ったような笑顔を返した。好意を隠さずにストレートに口にするあたしに困惑しているのかもしれない。けれどそんなことには構ってられない、『恋をしたら一直線』『全力全開超突進』で押しまくるのがあたしの恋愛必勝法なのだ。
「オーダー入ります!ブレンドコーヒーひとつ、クラブハウスサンドひとつ、お願いします!」
クロロさんから聞いたオーダーをキッチンに伝えると、あたしはコーヒーサーバーの前に立った。ポチッと、ブレンドコーヒーのボタンを押すとゴリゴリゴリと豆を引く音と共になんとも言えないコーヒーの香しい匂いが漂ってきた。珈琲豆の匂いーーーそう、クロロさんの匂いだ、なんてセンチメンタルに思ったりした。
さっきのクロロさんとの会話を思い出す。
大丈夫だったかな?変なこと喋って無かったかな?なんて一人反省会始めたあたしだけど、次から次へと思考が飛んでしまってあたしはコーヒーサーバーの前で一人表情をくるくる変えていた。
ーーーどの行動が正解かなんて分からないよ……でも一つだけ言えるのは前進あるのみってことだけ!!!
コーヒーマシーンからカップに向かってポタポタと抽出されるコーヒーを決意した瞳でじっと見る。
大丈夫、大丈夫、さっきのやりとりであたしが好意を持っているってクロロさんに伝わったはず。……もし伝わってなかったとしても名前を覚えてもらったんだから大丈夫、大丈夫、あたし前進してる!!落ち込まない落ち込まない。恋は押せ押せGO!GO!GO!!立ち止まってなんかいられないんだから!!!
ジェットコースターのように乱高下するする心臓をギュッと握って、あたしは顔を上げた。コーヒーマシーン越しに本を読んでいるクロロさんが目に入って、心臓がキュンキュンと高鳴った。
あぁ、もう、やっぱり好き。あたし、クロロさんのこと好き。好き好き、大好き、大大大好きだ!!!もー、だめだ止まんない!この恋もこの想いも誰にも止めることはできないよ!!!
*
あたしがクロロさんに出会ったのは、ちょうど5日前の雨の降る日だった。雨といってもしとしと降る雨ではなくて、突然バケツをひっくり返したように降りだした雨で、クロロさんはそのスコールに当てられて体を雨に濡らした状態で、このカフェの扉を開いたのだった。今でもその姿は脳裏にしっかりと焼き付いている。
カランカランというドアのベルで振り返れば、そこにいたのは雨で髪を濡らした体躯のいい男の人で、あたしはその均整の取れた体つきと気だるそうに髪を掻き上げるその仕草に、しばらく魅入っていたのだった。
「あー…やられた…」
と悔しげにボソリと呟いて顔を上げた彼に、あたしの目はさらに奪われてしまった。すっと通った目鼻に、吸い込まれそうな黒い瞳。キュッと引き締まった知的な唇。そして、彼の纏う近寄りがたいのに近寄りたくなる不思議な空気。
トレーを持ったまま仕事を忘れてボーッと立ち尽くすあたしに、クロロさんは追い打ちのように爽やかな笑顔を向けて「お姉さん。一人なんだけど、席、空いてるかな?」と言った。
その時にあたしが感じた衝撃をどう言葉にすればいいのか今だに分からない。頭の天辺から足の先に向けてピシャリと電流のようなものが走って、一瞬で体が硬直した。なのに、心臓の鼓動だけはドクンドクンと次第に早くなり、しまいには100mを全力疾走したくらいの早鐘を打っていた。
それは、まさしく恋の稲妻。
どれくらいの間そうしていたのか分からないれけど、こちらを訝しげに見るクロロさんの視線に気づいてあたしはハッと顔を上げると、急発進をする車のようにバタバタバタと音を立てて裏のロッカールームに駆け込み、お母さんが持たせてくれたタオルをカバンの中から勢い良く取り出すと、扉を締めるのを忘れてあたしは入口に向かった。
「ハァ…ハァ………あの、一名様ですね?」
「あ、あぁ……」
「ご、ご案内致します、こちらへどうぞ。」
そう言ってクロロさんを空いているテーブルに誘導した後、あたしは震える心臓を押さえつけるように深呼吸をしながら、手にしたタオルをクロロさんにえいと渡した。
「あ、あの!!よ、良かったら、このタオル使って下さい!!」
「いいの?これ君のじゃないの?」
「そ、そうですけど、あたしは濡れてないし、お母さんが持たせてくれたんだけどお母さん心配性だから二枚入れてくれて、あ、あたし二枚も使う予定ないし、それに、いくら8月だと言っても濡れたままだとお兄さん風邪引いちゃいますから!!」
そこまで一息で言うと、クロロさんの手に強引に置いた。すると、クロロさんは「そう?悪いね。」と言いながら受け取ってくれた。
その時、さっき見せてくれた爽やかな極上の笑顔をあたしに再び向けてくれた。心臓がキュンと音を立てる。歓喜なのか感動なのか分からないけれど、なぜか指先がふるふると震え出した。
ーーーあぁ、あたしこの人に恋しちゃったんだ。
根拠のない確信。だけどそれは間違いなく真実で、あたしは一目で恋に落ちてしまった。そして、その時から、あたしの日常はクロロさん一色になったのだった。
*
「ねぇねぇ、ナターシャ、聞いて聞いて!!」
バックヤードに飛び込んだあたしはナターシャを探してキッチンを見渡した。あ、いた。食器洗浄機の近くで洗い終えたお皿を取り出しているナターシャを見つけるとあたしはバビュンとナターシャの側に行った。
「ねぇねぇ、ナターシャ!!」
「………なによ。私、今、仕事中なんだけど。」
「あーーん、もういいじゃんそんなの。そんなの後でもやれるじゃん!!」
「はぁ………ったくもう。なに?……まぁ、聞かなくても分かるけどね。どうせまたクロロさんの事なんでしょ?」
「そうなのーー!!!あのね、あのね、ナターシャ、聞いて!!クロロさんの仕事ってなんだと思うーー??」
「さぁ?ここ最近、毎日このカフェに来ているから……大学院生とか?あ、仕事している人か……なら何かの実業家とか?」
「あーーー、惜しい!けど、違うの。あのねぇーーーー………古美術商、だって!!」
「コビジュツショウ?」
「うん、古い美術品を仕入れて売る仕事だって。世界中を渡り歩いてるんだって!!カッコいいよね!?カッコいいよねーーーー!!!!」
「………そう?この時期にヨークシンにいるんだもの、別に珍しくないでしょ。確か、最近朝のモーニングを食べに来てるちょっと太ったあの人も、確かヨークシンオークション目当てに来た人だよ。古美術商じゃないの?」
「えーー!?あの猫目の太った人が!?いやいやいやいや、全然違うよ、古美術商って感じじゃないじゃん。なんかアニメオタクっぽいじゃん。あれはただ何かのアニメグッズを競り落としに来ただけだって。クロロさんと同じ職業な訳ないじゃん。」
「ナナシー……、あんた、たまにサラッと酷いこと言うよね?」
「……そう?だって、そうとしか思えないじゃん。」
あたしに「魔法少女ミルキーメイの『レイラ』ちゃんに似てるよね?」って話しかけてきたミルキだかミルクだかって名前の人が、クロロさんと同じ仕事のわけがないのに、ナターシャったらホント何を言っているんだろう。
そんな風に考えているあたしを置いてナターシャは、一人黙々と作業に戻ってしまった。残念、まだナターシャに言いたいことがいっぱいあったのに。チェっと口を尖らして、あたしはフロアに戻る事にした。
こんなやりとりが、クロロさんと出会ってから何回あっただろうか。その回数は多すぎて、あたしはもう数を数えることすら放棄していた。
*
クロロさんと出会ってから10日が過ぎた。出会ったその日からあたしの世界は極彩色に輝き始めて、いつもと同じ風景が全くの別物に見えるほどに全てが一瞬にして変わった。たった10日なのに、今までのあたしの人生をぎゅっと凝縮したくらいの濃密な時間を、あたしは過ごしていた。
『魂を震わす恋』ーーーまさしく、そんな恋だった。
今まで恋をしたことは何度もあったけれどこんな風に感じる恋は初めてで、この10日間のあたしはナターシャに百面相ってからかわれるほどクロロさんの一挙手一投足に翻弄されていた。でも魂を震わせるほどに心の底から感じ入り、心の底から笑い、心の底から泣き、心の底から喜び、そして心の底から湧き上がる好きという感情を、心の赴くままに伝えることができて、あたしは幸せものだったと思う。
その頃のあたしの口癖は「ねぇねぇ、ナターシャ、聞いて、聞いて!」だった。その言葉の後に続くのはもちろん「クロロさんがね…」だったのだけど、今考えれば、鬱陶しいだけのこんなあたしを見限りもせずにナターシャはよく付き合ってくれたもんだと思う。
けど、その時のあたしはクロロさんの事で頭がいっぱいいっぱいで、この思いを伝えずにはいられなかったし、それにクロロさんがカッコよすぎるせいか、はたまたあたしが単純すぎるせいか、ナターシャに報告する話題には事欠かなかったのだった。
「ねぇねぇ、ナターシャ、聞いて、聞いて!!さっき、クロロさんがね、超絶カッコよかったんだよ!!私がコーヒー持って行った時にね、こう……指と指とがちょっと触れ合ったんだけど、その時に『あ、ごめん」って言いながら、あたしに笑かけてくれたんだよ。何て言うの?流し目っていうのかな?そうそう、こんな感じの艶かしい視線でさ。それが超色っぽいの!!!これってわざとなのかな?あたしのことをそんな目で見ちゃうなんて、もしかして誘われてたりするのかな!?ねぇねぇ、どう思う!?」
なんて報告する日もあったり
「ねぇねぇ、ナターシャ、聞いて、聞いて!!クロロさんがね、私と目があった時にね、小さく手を振ってくれたんだ。そう、8番テーブルを片付けている時なんだけど……。こう、小さくヒラヒラって。これってさ、あたしのこと気にかけてくれてないと出来ないことだよねー!?もしかして、あたしに気を持たれてるのかなーー!?」
なんて報告する日もあった。
そんなある日、レジで伝票整理をしているとテーブルを片付けたナターシャが手に持ったものを見せながら話しかけてきた。
「ねぇ、コレ、クロロさんの忘れ物じゃない?」
見るとそこには、確かにクロロさんが読んでいた古めかしい本があった。なんでここにあるの?と言いたかったけど、驚きすぎて言葉が上手く出てこなかった。
「え……あ……それ……」
「クロロさんのでしょ?」
「じゃぁ……今から……」
「もう、分かってるって。店長にも許可とっといたから。」
「ほ…ホント?」
「本当だって、ついでに30分の小休憩取っていいって店長言ってたよ。」
「ナターシャ!!!大好き!!!!クロロさんの次にだけど、大大大好き!!」
「全くもうナナシーったら調子いいんだから」
「ねぇねぇナターシャ……あたし………」
「はいはい、分かってるって。メイクも服も完璧だよ、髪型も大丈夫。ただちょっと笑顔が足りないかなー?ほら、笑って笑って。」
「ナ、ナターひゃ。い、痛いひょ……。」
「よっし、これでいい。ナナシーにはそんな顔は似合わないよ、笑顔が一番!!!」
「ナターシャ……」
まだ痛む頬をさすりながら、あたしはにかっと全力全開の笑顔をナターシャに向けた。すると、ナターシャがグッと親指を立てて笑顔を返してくれた。
それを合図に、あたしは「行ってくるね。」と一言告げるとくるりと背を向けて店を出たばかりのクロロさんを追いかけて走り出した。
*
「クロロさん、まだ遠くに行ってなければいいんだけど……」
いつも店を出て右に曲がるクロロさんのことだ、いつもと同じならこの道を進めば会えるはず。そう思っていたら店を出て5分と立たない内に、クロロさんを見つけることが出来た。良かった。あたしは「クロロさーーん!」と手を振りながら走りを加速させた。
「ハァハァ……ハァ…。ク、ロロさん……。」
「ナナシーちゃん、どうしたの?」
「あの……忘れ物を届けに……ハァハァ。」
大きく息を吸って呼吸を整えると、脇に抱えていた本をクロロさんに差し出した。
「わざわざ届けに……?」
「えぇ……はい、これ。」
「ありがとう。でも、予想より少し遅かったな。」
「え!?」
クロロさんがにやりと笑ってあたしに意味ありげな視線を送ってきた。ま、まさか…
「え!?あの…ワザとだったんですか!?」
「フ……どうだろうな。でも、君がこうして持ってきてくれたおかげでオレはコレを手放さずにすんだ。」
「そんな……あたし、クロロさんにコレ渡さなきゃって必死になってきたのに……クロロさん、イタズラが過ぎますよ!」
「でも、こうして持ってきてくれたおかげで、君と話す時間が出来た。」
思わず息を飲む。クロロさんの意図を理解した瞬間、あたしの顔がカーッと熱くなった。二人きりになるためにこんな手を使うなんて、やっぱりクロロさんは大人だ。あたしの周りにこんな事をしそうな男の人なんていやしない。こんなことがサラッと出来ちゃうなんてクロロさんやっぱり素敵だ、格好いい。
騙されていたと知ってもあたしのクロロさんへの想いが褪せることはなくて、むしろクロロさんへの想いはさらに加速した。目の前のクロロさんをじっと見つめる。いつも席に座っているクロロさんとしか話してなかったから目の前で向き合って話すのはとても新鮮で、「クロロさんって意外と背が高いな」とか「抱き締められたら胸の中にスポンと入っちゃうんじゃないかな」なんてことを考えていた。
クロロさんが何かを言いたげに口を開く。もしかしたらもしかしたらあたしへの告白なんじゃないかと思う自分もいたけど、そんなことはないよ期待しちゃダメだよと諌める自分もいた。でも、やっぱりこんな風に演出されちゃうと少しは期待しちゃうわけで、あたしの心臓はドキンドキンと期待で高鳴っていた。
「実は、オレ、君にお礼したいことがあって。」
「……お礼?」
「はい、これ。」
そう言ってクロロさんは可愛くラッピングされたクッキーをあたしに手渡した。なんだか告白ではなさそうな雰囲気にあたしは心底がっかりしたけれど、クロロさんにプレゼントを貰えた事実に次の瞬間にはあたしは持ち直していた。
「え……お礼?あたしクロロさんにお礼されることなんてしてないです……。」
むしろ、毎日うちを利用してくれて、あたしに姿を見せてくれて、あたしに話しかけるチャンスをくれることに、あたしの方がお礼を言わなくちゃいけないはずなのに。
「オレに気さくに話しかけてくれたじゃん。」
「でも……それは、あたしがしたくてしたことだから…。」
そのまま「クロロさんの事が好きだから」って告白したかったのに最後の一押しの勇気が足りなくて、最後の方はもごもごしてしまった。
「実はね、オレに君と同じくらいの年の妹がいてね。」
「妹……?」
「ネオンって言うんだけど、かなり小さい時に別れたっきりでね。近々会うことになったんだけど向こうはオレのこと覚えてないだろうから、ほとんど初対面みたいなものなんだ。」
「そう、なんですか…。」
「今時の女子高生と話する機会なんてないから、どんな風に話したらいいか悩んでいたけど、君が気さくに話しかけてくれたおかげで自分に自信がついたよ。ありがとう。」
クロロさんの役に立てて嬉しいと思う反面、悲しいって思ってしまったのはなぜだろうか。それは、たぶん、クロロさんがあたしと話してくれたのは全てその妹さんとの予行練習のためだったんじゃないかって勘繰ってしまったから。
その瞬間、クロロさんの妹に対する嫉妬心がブワッと湧き出した。
羨ましい。ずるい。こんなカッコいいお兄ちゃんがいるなんて。久しぶりに会うってだけでクロロさんに予行練習させちゃうなんて。羨ましくて羨ましくてたまらなかった。
だけど、そんな下衆な勘繰りで嫉妬心を燃やしているだなんてクロロさんに知られたくなくて、あたしは取り繕って返事をした。
「あたし、特別なことしてないですけど、クロロさんのお役に立てたなら嬉しいです。」
「本当に助かったよ、ナナシーちゃんありがとう。あ、そのクッキー、バイトの子たちには内緒で食べてね。君にしか渡してないから。」
そう言うとクロロさんは、初めて会った時の爽やかな極上の笑顔をあたしに向けてくれた。その笑顔を見た途端、あたしの心を曇らせていた嫉妬心が一瞬で消え去って代わりに突き抜けるような青空が心の中で広がった気がした。
ーーーなんていう破壊力。たった一つの笑顔でこうも変わるだなんて。
クロロさんのことが好きで好きで堪らない自分に自嘲の息を短く吐くと、あたしは背中を向けて歩き始めたクロロさんを呼び止めた。
「ん?どうしたの?」
振り返ったクロロさん前髪がさらりと揺れる。ごくりと唾を飲んであたしは口を開いた。
「あ、あの………クロロさん……。あたし…、クロロさんに伝えたいことがあるんです……。」
「何かな?」
「め、迷惑かもしれないんですけど、どうしてもこれだけは伝えたくて……。」
声が震える。心臓が喉から出そうなくらい激しく鳴っている。浅い呼吸のせいか、頭の中が真っ白になっていく気さえした。でもダメだ。こんなチャンス今しかないんだ。
あたしは、拳をギュッと強く握って、なけなしの勇気を振り絞った。
「あ……あたし、く…クロロさんのこと、す……好きなんです。」
絞り出すようして言う。
ああ…言った、言っちゃった。あたし、ついに言っちゃった。あたしは顔をこれ以上ないくらい赤くしながらクロロさんの反応を待っていた。風がふわりと通り過ぎる。
ーーーあぁ、ダメだ。
風が教えてくれたのだろうか、クロロさんが困った顔をした気配がした。恥ずかしくて下を向いているからちゃんと見たわけじゃないけど、そんな気がした。
「……ありがと。」
その言葉に顔を上げれば、そこにはやっぱり眉を困ったように寄せたクロロさんがいて、困らせたくなんかなかったのに困らせてしまった事実に悲しみが込み上げる。でも、溢れ出した想いは止まらなくて。
込み上げた色んな感情に鼻の先がツンとした。
「あ、あたし…クロロさんのこと…好きで好きで……」
声が詰まって言葉が途切れ途切れになる。涙を必死になって堪えるけれど、それももう限界で。
「もう……っ……んぐっ……自分でも、…っ…どうしようもないくらい好き、なの……」
そこまで言うので精一杯だった。泣いたらメイクが落ちちゃうってのに、涙がポロポロ零れてしまってもうどうしようもなかった。
好きなのに。泣きたくなんかないのに。困らせるつもりもなかったのに……。クロロさんへの思慕と困らせてしまったことへの後悔と二人っきりで話ができることへの歓喜と、そして気持ちが届かないことへの悲哀とが混ざり合って、もうどうしようもなくて、次から次へと涙が溢れては地面に落ちていった。
「……そっか。」
あたしの言葉を静かに聞いてくれていたクロロさんは、優しい声でそう言うとぐすぐす泣いているあたしの頭を軽くポンポンと叩いてくれた。
驚いて顔を上げると、そこには困りながらも優しさ溢れる顔であたしを見つめるクロロさんがいて、頭に置かれた手からクロロさんの温もりがじんわりと伝わってきた。
ーーーそんな優しい目であたしを見ないで。気持ちがさらに加速しちゃうから……
さらに、鼻の奥がツンとした。断りの言葉を言われたわけでもない。ダメだって言われたわけでもないない。でも、だけど、それだけど……あたしには分かっていた、この恋が成就する事はないって。
「……こんな可愛い子に好意を持ってもらえて、オレ………嬉しいよ。」
その言葉の後に続くのは間違いなく否定の言葉で。たぶん、色んな経験をしているであろうクロロさんの、相手を傷つけない断り方なんだと思う。
ーーーダメだダメだ、泣いちゃダメだ。クロロさんの記憶に残るのが泣き顔のあたしだなんてダメだダメ。ナターシャも言ってたじゃない、あたしは笑顔が一番だって。笑わなくちゃ。笑顔笑顔。
あたしは涙をぐっと堪えて笑顔を作った。クロロさんには、笑顔のあたしを覚えておいて貰いたい。
最高の笑顔をクロロさんに向けると、クロロさんはやっと困り顔をやめて笑い顔を向けてくれた。そうして、少し近づくと幼子をあやすようにあたしの頭をポンポンと軽く叩いた。
「よく頑張ったね。ご褒美だよ。」
その言葉が聞こえると同時にクロロさんの顔が近づいてきた。ふわりとクロロさんの香りが鼻腔をくすぐる。クロロさんの前髪がふわりと揺れるのが目の端に映ったかと思うと、左頬に温かい何かを感じて、チュッというリップ音が聞こえた。
突然の出来事に体が硬直して思考が停止する。
「ナナシーちゃん、またね。」
クロロさんにキスをされたと頭が理解したのはずいぶんと後で、理解した時にはすでにクロロさんが手を振りながら別れの挨拶を言った後だった。
「………キス、されちゃった………。」
クロロさんが通りを曲がった後、あたしはへにゃへにゃと腰を抜かしてその場に座り込んでしまった。クロロさんがキスをした左頬が熱を持ったみたいに熱かった。
*
クロロさんにキスをされてから3日が経った。この二週間毎日欠かさず来てくれていたのに、あたしが告白した日からピタリと来なくなって、あたしは常連のお客さんたちに「どうしたの?」って聞かれるほど感情がめまぐるしく動いていた。
もしかしたら、あたしが好きって言ったせいで来てくれなくなったのかもしれない。もしかしたら、あたしのことが嫌いになったのかもしれない。もしかしたら、オークションでの仕事が終わって自分のホームにさっさと帰ってしまったのかもしれない。もしかしたら、そのホームには恋人がいるのかもしれない。はたまた、もしかしたら、感動の再会をした妹さんとここではないどこかで暮らし始めたのかもしれない。
もしかしたらもしかしたらの妄想が次から次へと湧いて、その度にあたしは落ち込んだり悲しんだり涙ぐんだりしていた。でも、次の瞬間には3日前のキスをされたとことを思い出してはにやにやしたりしていた。それはまるで感情のジェットコースターのようだった。
それでも一週間経った頃にはマイナスな妄想ばかりが増えていってあたしは日に日に情緒不安定になっていった。
そして8日目の朝、裏のロッカールームで着替え終えてフロアに出たあたしに、ナターシャが声をかけてきた。今まで見たことのない、困ったような苦しいような申し訳ないような複雑な顔をしていたナターシャの手には、一枚の紙がぎゅっと握られていた。
「ごめんね。ナナシーに見せるかどうか迷ったんだけど、ずっと黙ったままではいられないと思って……」
ナターシャがその紙をおずおずとあたしに差し出した。こんな前置きを言いながらあたしに何か知らせてくるなんて、クロロさんに関することだって瞬時に理解した。どくんと心臓が跳ねる。嫌な予感に指先が震える。
「今ネットで拡散されている情報なんだけど……。ナナシー、気を確かにして聞いてね。それ、ヨークシンオークションを邪魔した集団を公開処刑した写真でね…結構グロ写真なんだけど……。その……その中にいる人が………。」
そこまで言うとナターシャは口を噤んだ。それ以上先は言葉にしたくないみたいだった。
この時期、ヨークシンには世界中のマフィアが集まってどこかで秘密裏に闇オークションをやっている。それはこのヨークシン界隈ではあたしも知っているような公然の事実で、この時期に外から来る観光客の何割かはマフィアだったりする。
そして、彼の纏う深くて底の見えない空気とオークション騒動後に姿を消したという事実が、あたしの数ある「もしかしたら」の中の一つを現実のものとしてその輪郭を浮かび上がらせた。
『彼は裏の世界の人間で、姿を消さなくてはいけないようなナニカが彼の身に起こった。』
当たって欲しくない予想に、冷や汗がジワリと噴き出す。
「ねぇ、ナターシャ。今、………何て言った?……こ、公開………処刑……って言わなかった……?」
ナターシャが気まずそうに目を反らした。手がブルブルと震えて、畳まれた紙を開こうとするけど上手に開けることが出来なかった。
「………これ…………まさか……………。」
開いた紙の中で、あたしが目にしたのは男女数人の血みどろの写真だった。そこには、血を流した無残に殺された死体がモザイクもなくあって、その中の一つがあたしの知っている人に思えた。
「あ………カハッ………ハッ………あ…………」
言葉が出なかった。こんなの嘘だ、これがクロロさんのはずであるわけがない。息をしたいのに息をすることも出来なかった。
でも、そこにはあたしがずっと見続けていた男性の姿があって。均整の取れた肉体に、すっと目鼻の通った顔。黒曜石のように黒い瞳に黒い髪。血だらけの姿で目を見開いて力なく壁に寄りかかっていたけれど、それはずっとずっとずっと夢に見るほどに思い続けていたクロロさんの姿に間違いなくて。
「………カハッ………ハッ………あ…………」
脳の許容量を超える衝撃に、頭が真っ白になってゆく。遠くでナターシャが「ナナシー大丈夫!?しっかりして!!」って言っている気がしたけれど、もう何も聞こえなかった。
ーーーこんなの嘘……誰か嘘だと言って……お願いだから……
薄れてゆく意識の中で、あたしはそれだけを必死に繰り返し繰り返し願っていた。
*
ーーーーもし、魂に刻まれた恋というものがあるとしたら、あたしはあの恋がそうだったと思う
*
「ナナシー?」
ふと名前を呼ばれ、あたしはハッと振り返った。すると、そこには心配げな顔で私の顔を見つめるマイクの姿があった。
「どうしたの?ナナシー?そんなぼーっとしちゃってさ。」
「ううん。なんでもないよ。」
力ない声であたしが言うと、マイクはあたしのおでこに手を当ててきた。数か月前から付き合っているマイクはとても心配性で、すぐにあたしのことを心配するのだ。
「熱?……はなさそうだけど。体調でも悪いの?」
「ううん。別に。ーーーーただ、ちょっと思い出しただけ。」
「あぁ、ここナナシーが前バイトしてたカフェに近いもんね。でも、そう言えば、三年以上働いていたのになんで辞めちゃったの?僕、ナナシーの制服姿結構好きだったんだけどな。大学が忙しくなったから?」
「それもあるけど。ーーーもう、区切りをつけようと思って。」
ーーーあれから三年、あたしはクロロさんの事をあのカフェで待ち続けていた。
ナターシャも店長も他のバイト仲間も「もう忘れなよ」って何度も何度も言ってくれたけど、あたしはクロロさんの事を忘れることは出来なくて、ドアのベルが鳴る度に「もしかしたら…」って淡い期待をしてしまっていた。期待をしては絶望するーーそんな日が三年もの間続いた。
高校を卒業しても新しい大学生活が始まってもあたしは待って待って待ち続けていた。けれど、ホントはもう気づいていた。この先一生クロロさんと会えることはないって。
だから、あたしはクロロさんと別れてからちょうど三年経った今年の9月2日に、あそこのバイトを辞めたのだった。ちょうど同時期にあたしの事を好きだとアプローチかけてきたマイクの存在も一役を担ったけれど、このままではいけないっていう気持ちもあったんだと思う。
すっかり木の葉が落ちた冬の並木道を、風がすうっと走り抜ける。ヨークシンの街並みを吹き抜ける冬の風は鋭く冷たいけれど、心に直接語りかけるように吹き込むそれは、あたしの心を慰めてくれた。
風に促されるようにして、あたしはあたしの歩調に合わせてゆっくりと歩いてくれているマイクを見た。あたしの事を可愛い大好きだって言ってくれる優しい優しい彼。まるで砂糖菓子のような甘い甘い愛情をくれる彼だったけれど、あたしの心が、魂が、あの時みたいに燃えることはなかった。
木枯らしの冷たい風がマフラーで隠れていないあたしの頬を撫で上げる。
風で冷えているはずなのに、クロロのさんがキスをしてくれた左頬が軽い火傷の痕のようにじくじくと痛み出した。
ーー頬。左頬。あたしの中の聖域。
そこはこの先誰にも許しはしない、クロロさんにだけ許した場所。まだ熱を持っているその左頬を、あたしはそっと優しく噛みしめるようにして触った。
『魂に刻まれた恋』
あの恋はまさしくそんな恋だった。喜びと悲しみと切なさとーーーそして溢れんばかりの愛しさを教えてくれたあの恋を、あたしは一生忘れない。
それはまるで魂に深く深く刻まれた聖痕のようで、この先一生癒えることはないだろう。
頬に当てていた手をスッと下ろす。久しぶりにあのカフェの前を歩いたせいだろうか。もう枯れたはずだと思っていた涙が、もう過ぎ去ったと思っていた感情が込み上げてきて、鼻の奥がツンとした。
立ち止まり空を見上げる。突き抜けるように青いヨークシンの空と冷たい凍えるような風が、あたしのことを包み込んでくれたような気がした。
[魂の聖痕]
ーーーーーーーーーーーーー
狩人夢企画サイト「くちづけ〜22箇所のキス〜」に「頬:親愛・厚意・満足感」で提出させていただきました。
[ *prev | back | next# ]