
偽りの装い
「エロスな触れ合い」「うなじへのキス」をキーワードに考えた話です。
*
しのぶれど 色に出でにけり わが恋は
ものや思ふと 人の問ふまで
エレベーターの階数表示ランプが音も立ってずに順々と数を重ねてゆく中、なぜかこの間読んだジャポンの文献に乗っていたこの詩が、ふと頭に思い浮かんだ。
あたしの恋は、どうだろうか。『色』に出ているのだろうか。そう思い、ふと顔に手を当てる。顔色に出るようなヘマはしていないはず。平常心を保って彼の望む振る舞いができたはず。ふぅーっと息を吐いて、右隣にいる男の横顔を盗み見た。
黒髪を後ろに撫でつけた、精悍な顔つきの横顔が目に入った。
クロロ=ルシルフル。あたしが本気になっていると知ったら彼はどう反応するだろうか。「面倒だ」と過去の女たちのように切り捨てるだろうか、それともただの仕事の提携相手として、男女関係のない元の関係に戻るのだろうか。
好意以上の感情を持ってはいけない。
知られてはいけないあたしの想い。
あたしのしのぶ恋。
*
「……さま、奥様?」
案内のベルボーイに声をかけられ、ハッと顔を上げた。エレベーターはとうに目的の階に着いていたようだった。いったいいつ止まったのだろう。エレベーターの入り口に立つクロロが、様子を伺うようにこちらを見ていた。
「やはり奥様、お加減が優れないようですね。」そう尋ねるベルボーイに向かってクロロが柔和な笑顔で答えた。
「あぁ、妻は病弱なものでね。今夜のパーティー会場のような所だと、すぐに人に酔ってしまうのだ。」
「左様ですか。お部屋まではあとちょっとですので、もう少しご辛抱願います。」
「ほら、ナナシー、手を」
そう言って、クロロが紳士的に手を差し伸ばしてきた。そう、そうだったわね、まだ仕事中だったわ。そう心の中で呟いて、あたしはその手を優雅に受け取り、しゃんなりと一歩踏み出した。裾広がりのイブニングドレスがゆらりと揺れる。
「お部屋はこちらでございます。」
「そうか、すまないな。妻の加減が良くなるまで、少しこの部屋で休ませて貰おう。」
「はい。マルベール卿も気兼ねなくお使い下さいと仰っておりました。」
「そうか。……これ、少ないがチップだ。」
そう言って、クロロは懐からお札を取り出し、ベルボーイに手渡した。
チップとして多すぎるその量に、ベルボーイが一瞬躊躇するのが見て取れた。
「マルベール卿に、すまないと伝えてくれ。それと、近いうちにお詫びを兼ねて私邸でパーティーを開くのでそちらにご招待したい、招待状はまた後日送らせていただく…と。」
「はい、かしこまりました、ハワード男爵。」
「ふふ、あたしからも、よろしく…とお伝え下さいね。」
胸元を強調するように腕を寄せて上目遣いでそう言うと、まだ若いベルボーイは、強調された豊満な胸元に釘付けになっていた。が、それは一瞬のことで、すぐに目を逸らされた。
「か、必ずお伝えいたします。では失礼いたします。」と、ベルボーイはまだ顔の赤いまま畏まって頭を下げると、そのまま踵を返して来た道を帰って行った。
ーー純朴な青年をたぶらかすのは本当に面白い。いとも簡単に思い通りに動いてくれる。誰かさんと違って。
そう思いちらりと横顔を盗み見ると、去って行くベルボーイに満足気な笑みを送っているクロロが目に入った。
ラフな格好をして髪を下ろしているクロロとも、いつものコートを羽織りオールバックにしているクロロとも違う、正装姿のクロロの姿。斜めに分け、後ろに緩くなでつけた髪から数筋垂れている前髪が凄く色っぽい。初めて見るラフさとフォーマルさが併存するその髪型に、胸がトクンと鳴った。
ーーかっこいい
でも、いけない。今は仕事中だわ。そう思い直し見惚れている自分を叱咤して、あたしは去って行くベルボーイに目を向けた。あのベルボーイはこのまま下のパーティーフロアに戻って、彼がハワード男爵だと疑うこともせずにマルベール卿へ伝言を伝えるだろう。あたしたちは、ただの成り代わりの偽物に過ぎないと言うのに。
ーーーそう、全て、彼の思惑通りに
*
ベルボーイを見送ったあと、あたしたちは重厚な扉を開けて部屋の中に入った。潜入成功。鍵とチェーンをかけて人が入れないようにするけれど、まだ気は抜けないわと、あたしは男たらしなハワード男爵夫人を装ってクロロに話しかけた。
「ふふ、あのベルボーイ、顔を赤くして……可愛かったわ。」
「お前に見惚れていたのだろう。」
「あら、いやだ、そんなつもりなんてないのに。」
会話をしながら"円"をして周囲に人がいないことを確かめる。旅団員の円に比べたら未熟かもしれないけど、今回所用で参加できなかった旅団の金髪女には見劣りたくないと、会話をしながらもあたしは必死にオーラを広げた。そんなあたしを横目にクロロは男爵としての会話を返す。
「全く、思ってもいないことを。」
「思ってもないこと?」
「あの男に見せつけていただろう。」
「見せつけていた?」
「その胸を。」
「あら、ばれちゃったかしら?」
ふふふと笑いながら、懐に隠しておいた小型探査機を取り出して周囲の周波を探る。どうやら不審な周波を発している盗聴器や隠しカメラはなさそうだった。良かった。予定通りパーティー会場上の客室へ潜入出来たわと、あたしは安堵から大きく息を吐いた。
「いいわ。特に不審なものは無いわよ、大丈夫。」と機器をカバンにしまいながら言うと、ソファに腰をかけたクロロがこっちに振り返って、「そうか、では男爵夫妻ごっこも終わりか。」と笑いながら返した。ハワード男爵をたぶらかした娼婦上がりの女と、眉目秀麗で人当たりが良いが嫉妬深く女を片時も手放さない男。それがあたしたちが今回装っていた人物像だった。名残惜しいけど、それももう終わり。
思わず「名残惜しい?」とクロロに尋ねると、「お前の魔性の女っぷりがもう見れないかと思うと、少しな。」と困ったように眉を寄せてクロロが答えた。
「本当かしら?でも、本当なら嬉しい。」
「事実だ。」
「まあ、最大級の褒め言葉だわ。」
「そうか。」
「それに、一つ発見。」
「なんだ?」
「クロロってこういう系統の女が好みなのね。」
「……そうだな、美人でグラマーで性的魅力に溢れた女は、総じて好みだ。」
やっぱりね。薄々そうだと思っていたわ。彼の求めているものが言葉で明確化され、あたしの心が少し痛んだ。それに言葉にはしてないけど『手がかからなくて扱いやすい女』って項目もプラスでしょ?とあたしは内心笑った。
けれど、それを彼に伝える気にはならなくて、むしろあたしのことを『魔性の女』で『美人でグラマーで性的魅力に溢れた女』の系統の一人と言ってくれたのが嬉しかった。
「ご要望とあらば、いつでもやるわよ。」
そう言ってあたしは悪女の誘惑のポーズのつもりで、ソファに座っているクロロに向かって胸を強調したポーズを取った。
「胸を強調したドレスに、こぼれ落ちん程の大きなダイヤ。今日のお前は、男爵をたぶらかして贅を尽くした希代の悪女、ハワード夫人にふさわしい。」
「ふふ、クロロが盗ってきたこの首飾りのおかげよ。浪費家の夫人らしさをより一層演出してくれたもの。」
喋りながらあたしは肩にかけたストールを畳み、ハンガーにかけてクローゼットにしまった。本当に好きな人には本音を伝えられないくせに、こういった言葉のやり取りだけが上手くなって行く。もう、振りなんてしたくないのに。この日のためにクロロが買ってくれたドレスにシワをつけないようにと、あたしはドレスの表面を何度も何度も撫でながら思った。
「それにしても、会場の警備かなりずさんだったわね。」
「そうだな。」
「招待客の個人照会や身体チェックも甘かったし。」
「偽造IDを一通り用意したのにな。」
「あたし、バレやしないかってかなりヒヤヒヤしていたのに……結局使わなかったしね。」
「そうだな。」
「使わないのにソレ作らされたシャル君、可哀想。」
「だが、それがあいつの仕事だ。」
「そうね。それがシャル君の仕事であって旅団の仕事だものね。でも、旅団の仕事があるからこそ、あたしにこうやって提携の依頼が来るのだもの。シャル君にも感謝しなくちゃだわ。」
そう言って、あたしは鏡の前に向かった。10cmのヒールに、ゴージャスなイブニングドレス、胸元と耳に光る巨大なダイヤ。ハワード夫人としては、これ以上ないほど相応しい格好だけど、体調の悪い振りをしてパーティーホールの上の客間に潜入できた今となっては、全て必要ないものだった。
「服、脱いじゃうわね。帰りは窓から逃げるかそのままホールから出て行くか……まだ決まってないけど、とりあえずクロロが仕事を終えるまで二時間近くは暇になるわけだし。」
解放されたい。着るだけなら5分もかからないから、この窮屈なコルセットから解放されたかった。クロロが仕事をしている間は、そこのクローゼットの中にあるガウンを着て過ごすつもりでいたから、この場で服を着替えても問題ない。そう思っていた。
クロロにエスコートされる夢心地の役はもう終わりで、シンデレラの魔法はこの部屋に入った時点で消え去り、あとは王子様がこの部屋を出るのも見送るだけ。そう思ってた。
だから、クロロに色を孕んだ声で名前を呼ばれた時は、心臓が跳ね上がってしまった。
*
「ナナシー」
突然名前を呼ばれて、あたしは下げかけていた背中のファスナーの手を止めた。低く掠れたその声は、ベッドでクロロがあたしを呼ぶ時と同じで、あたしの心臓がどくんと音を立てた。
振り返ると、ソファに座っていたクロロが、不敵な笑みを浮かべながらあたしの方に歩いてくるのが見えた。なにごとかと唾を飲み込んでから、あたしは口を開いた。
「な……なに?」
「なにをそんなに驚いている。」
「だって…」
「それ。」
「え?」
「それ、オレが外してやる。」
「え、いいよ。自分でやるか…」
「いいから。」
そう言うとクロロは強引にあたしの背後に立った。気恥ずかしさを感じながら目の前の鏡を覗くと、こちらを見据えるクロロと目があった。
「ナナシー、この後のタイムスケジュールは覚えているか?」と背中のファスナーをゆっくりと下げながらクロロが尋ねた。もどかしいくらいゆっくりと下げるその手に、背筋が緊張でピンと張る。
「え、えっと、これからクロロが仕事を終えるまで部屋で待機。時間は、最大120分、22:30まで。トラブルがなく終わった場合は、そのままパーティーの終了時間に合わせて二人で正面玄関から退避。」上ずりそうになる声を抑えて、今日のタイムスケジュールを言うと、クロロの手によって落ちるか落ちないかギリギリのところまで下げられたドレスが、あたしの肩に掛けられた。辛うじて肩に引っかかっている今にも崩れ落ちそうなそれに、あたしの動きが制限される。
「それで?」
「そ、それで…トラブル発生時は窓からルートBで揃って退却。終了時間過ぎても連絡がない場合はルートDで一人で脱出…で合ってるわね?」
露わになった肩にそっと手を当てられて、思わず身体がビクンとなった。ただ、肩に手を置かれただけなのに、妙に意識してしまう。
「今日のターゲットは覚えているか?」
あたしの背後に立ったまま、クロロは声色を変えずに事務的な声で話しかけてきた。質問の内容よりも肩に置かれた手と背中からほのかに感じる体温に意識が向いてしまって、反応が鈍くなる。
「えっ…と、ターゲット?ターゲットは…た、確か…ある男で。パーティーの同伴が今回の仕事だから、ターゲットの詳細をしっかりとは覚えていないけれど、男を探して何かを吐かせる所までが、今日の仕事だって……」
あたしの返事を聞いたクロロは低い声で「そうだ。」とただ一声言うと、後ろから指先を尖らせた手で首筋をつつーと撫でてきた。思わず体がビクつく。驚いて顔を上げると、鏡越しにクロロと目があった。
「ターゲットは念の使えない普通の人間だ。"絶"で会場に戻り、怪しい男全てに総当たりで接触する予定……だった。」
「…だった?」
近い。彼の息が首筋に当たってゾクゾクする。鏡越しに、狙うような鋭い目を向けてくるクロロに、まるで、視線だけで拘束されているようだった。紐もロープも何もないのに、動けない。コクン、と音を鳴らして唾を飲み込んだ。
「予定変更だ。もうターゲットは絞られた。」
「え、もう?」
「そうだ。ターゲットの懐に発信機を入れておいた。所要時間はもう15分とかからない。パーティー終了間際まで時間が空くな。
なあ、ナナシー。それまでの間……
何を、しようか?」
意味ありげな瞳で見つめてくるクロロに、胸が高鳴る。
これは、誘われている…の?
今すぐにでも振り返って彼にキスをしたい欲求にかられる。けれど、それは、ダメ。状況を把握していないのに、欲望に負けて誘いに乗るなんて、そんな半人前な反応をクロロの前で見せたくなかった。少なくとも今は仕事のパートナーとして彼の隣にいるのだから。ちゃんと聞かなくては。
大きく深呼吸をした後で、あたしは乾いた口を開いた。
「そんな……いつ」
「ターゲットを絞ったの?」と続くはずだった言葉が途中で消える。
鏡越しのクロロの鋭い視線に、身を射抜かれた気がした。それほどクロロは鋭い目をしていた。まるで獲物を狙う目。
「ナナシー、お前はいつだと思う?」
「ええっ……と。」
今日のパーティーの様子を思い返してみても、いつターゲットに接触したのか検討つかなかった。車で乗り付けてパーティー会場にエスコートされてからずっと、クロロはあたしの側にいた。男好きの夫人と嫉妬深い男爵の役どころでは、別々に行動することは不自然なので、あたしとクロロはこの部屋に入るまで、一瞬と離れずずっと一緒にいたのだ。
「分からないのか?」
そう問われたけれど、首を縦に振りたくはなかった。クロロに分からないだなんて返事はしたくなかった。今日のパーティーでの出来事を思い返して考え込むあたしを尻目に、クロロが口角をにやりと上げた。悪戯な笑い。そして、その笑みを携えたまま、クロロに後ろからギュッと抱き締められた。ふわりと彼の香りに包まれて顔が熱くなる。バクバクバクと心臓が喉から出そうなほど大きく鳴った。
「知り…たいか?」
耳元で囁かれる。クロロの少し掠れた声が、あたしの脳を直撃した。頭がクラクラして何も考えられなくなりそう。
「分からない」「知りたい」と言わせたいのだろうか。それならば、なおさら言いたくないわと、思い直したその瞬間、後ろから耳の上部をカリッと甘く噛まれた。
「あッ…ん……」
思わず、甘い声が鼻から抜けていってしまった。
首に彼の吐息を感じる。
熱い。ぞくぞくする。
甘い疼きが首元から下腹部へと伝わって、足に力が入らなくなった。
「ン………ん、知り、たい。」
先ほどの決心はどこに行ったのか、気づけばあたしは返事をしていた。
その様子を、クロロは満足げな様子で見てから、口を開いた。
「ほら、これだ。」
そう言ってクロロは、後ろからあたしの顎を掴み、くいと正面に向けた。強制的に正面を向かされて、鏡に映っている自分が目に入る。鏡の中には、イブニングドレスを肩まで露わにし頬を赤らめている自分がいた。
ーー恥ずかしい。と思わず顔を逸らすけれど、後ろからクロロにがっしりと顎を掴まれていて、動くことが出来なかった。熱い。体と体の密着度がさらに増し、今ではもう、背中全体で彼の体温を感じていた。心臓の音に気づかれませんように。無駄とは知りながらそう願う自分がいた。
「目を逸らすな。見ろ。」
そう言って、クロロは後ろから鏡越しに鋭い目を向けてきた。心臓が高鳴り、体が熱くなり、頭に霞がかかってきた……もう、全てが限界だった。
「ここだ、ここ。お前は気づかなかったか?
男どもは欲望の眼差しで、この………胸の……谷間を。女どもは、羨望の眼差しで、この……ダイヤを、見ていたことを。」
あたしの胸元に下げられた首飾りを指先で弄りながら、クロロは言葉を続けた。クロロがダイヤの首飾りを触るたびに、あたしの首にも彼の指先が触れた。あたしの首筋を、喉元を、胸元を、指先でつつーとなぞってゆくそのもどかしい動きに、触られた場所がどんどん敏感になっていった。
「そんな……っ……ん……」
「その中で、ただ一人。欲望でも羨望でもない眼差しでここを見ている男が……一人。」
「……ん…」
「そいつは、恨みと怒りの混ざった視線をここに向けていた。」
そこで一旦言葉を切ると、クロロは鏡越しにあたしの顔をジッと見た。言い訳の出来ないくらい赤く上気した顔を見られているかと思うと恥ずかしさで胸がいっぱいになる。そんなあたしに視線を置いたまま、クロロは首飾りの金具を外し、シュルリとそれを抜き取った。肌を伝う金属の質感に、思わず鼻から息が漏れた。
首飾りのなくなり露わとなったうなじをそろそろと指先でひと撫でした後、くろはそこにキスを一つ落とした。チュッ。クロロの温かい唇を肌に感じた。キスされたところから肌が粟立っていく。体全体に広がった甘い疼きに、張り裂けそうな胸の鼓動に、込み上げるこの想いに、もう、耐えられそうになかった。身体が、脳が、心が、あたしの全てが彼を求めていた。
ーーークロロ、クロロ、クロロ、クロロ、クロロ………
「そこまで分かればもう簡単だ。そいつが今日のターゲットだった。あとはすれ違いざまに、発信機を入れ、後は帰り道に一人になったところを襲えば終わりだ。」
そう言うと、彼は外した首飾りをポケットにしまった。完敗だ。
あたしは、そんな視線に気づかなかったし、クロロがいつ接触したのかも分からなかった。もう、全てにおいて敵わない。
あたしは、くるりと体を返してクロロに向き合った。
「さすが、幻影旅団の団長ね。」
はやる心臓を押さえつけ、余裕の笑顔を作り出し、何とか言葉を絞り出した。敵わない。同業者としても、恋の駆け引き相手としても、何もかもが敵わない。全てに白旗を立てて、彼の軍門に下りたくなる。
ーーーでも、これだけは譲れない。たったひとつのあたしの矜恃。
『彼の隣に居続けたい』
そのためなら、あたしの恋心を押し殺しても構わない。
そのためなら、心を偽ることなんか構わない。
そのためなら、本心じゃないことを言っても構わない。
手間のかからない扱いやすい女に落ちて、いつか捨てられるくらいなら
初めから、感情を挟まない手軽な肉体関係だけで構わない。
だから、偽りの装いを身に纏って、あたしは言うのだ。
「ねぇ、クロロ。あたしをこんなに挑発して、どうするつもり?」
ハワード夫人さながらの誘惑の視線を絡ませて、あたしはクロロの唇を強引に奪った。彼は驚いた顔をしたのだろうか?ここからじゃ、確認することもできやしない。
そして、あたしはそのまま答えも聞かずに「責任とってよね。」と耳元で囁くと、彼をベットに押し倒したのだった。
あたしのしのぶ恋。
誰にも見せるつもりはない。
偽りの装いを身に纏い、あたしは『色』を隠すのだ。
FIN
ーーーーーーーー
相互先の「Arche noire」ののある様へ、日頃のご感謝と555555hitをお祝いしてこの小説を送ります。
[ *prev | back | next# ]
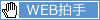
*
しのぶれど 色に出でにけり わが恋は
ものや思ふと 人の問ふまで
エレベーターの階数表示ランプが音も立ってずに順々と数を重ねてゆく中、なぜかこの間読んだジャポンの文献に乗っていたこの詩が、ふと頭に思い浮かんだ。
あたしの恋は、どうだろうか。『色』に出ているのだろうか。そう思い、ふと顔に手を当てる。顔色に出るようなヘマはしていないはず。平常心を保って彼の望む振る舞いができたはず。ふぅーっと息を吐いて、右隣にいる男の横顔を盗み見た。
黒髪を後ろに撫でつけた、精悍な顔つきの横顔が目に入った。
クロロ=ルシルフル。あたしが本気になっていると知ったら彼はどう反応するだろうか。「面倒だ」と過去の女たちのように切り捨てるだろうか、それともただの仕事の提携相手として、男女関係のない元の関係に戻るのだろうか。
好意以上の感情を持ってはいけない。
知られてはいけないあたしの想い。
あたしのしのぶ恋。
*
「……さま、奥様?」
案内のベルボーイに声をかけられ、ハッと顔を上げた。エレベーターはとうに目的の階に着いていたようだった。いったいいつ止まったのだろう。エレベーターの入り口に立つクロロが、様子を伺うようにこちらを見ていた。
「やはり奥様、お加減が優れないようですね。」そう尋ねるベルボーイに向かってクロロが柔和な笑顔で答えた。
「あぁ、妻は病弱なものでね。今夜のパーティー会場のような所だと、すぐに人に酔ってしまうのだ。」
「左様ですか。お部屋まではあとちょっとですので、もう少しご辛抱願います。」
「ほら、ナナシー、手を」
そう言って、クロロが紳士的に手を差し伸ばしてきた。そう、そうだったわね、まだ仕事中だったわ。そう心の中で呟いて、あたしはその手を優雅に受け取り、しゃんなりと一歩踏み出した。裾広がりのイブニングドレスがゆらりと揺れる。
「お部屋はこちらでございます。」
「そうか、すまないな。妻の加減が良くなるまで、少しこの部屋で休ませて貰おう。」
「はい。マルベール卿も気兼ねなくお使い下さいと仰っておりました。」
「そうか。……これ、少ないがチップだ。」
そう言って、クロロは懐からお札を取り出し、ベルボーイに手渡した。
チップとして多すぎるその量に、ベルボーイが一瞬躊躇するのが見て取れた。
「マルベール卿に、すまないと伝えてくれ。それと、近いうちにお詫びを兼ねて私邸でパーティーを開くのでそちらにご招待したい、招待状はまた後日送らせていただく…と。」
「はい、かしこまりました、ハワード男爵。」
「ふふ、あたしからも、よろしく…とお伝え下さいね。」
胸元を強調するように腕を寄せて上目遣いでそう言うと、まだ若いベルボーイは、強調された豊満な胸元に釘付けになっていた。が、それは一瞬のことで、すぐに目を逸らされた。
「か、必ずお伝えいたします。では失礼いたします。」と、ベルボーイはまだ顔の赤いまま畏まって頭を下げると、そのまま踵を返して来た道を帰って行った。
ーー純朴な青年をたぶらかすのは本当に面白い。いとも簡単に思い通りに動いてくれる。誰かさんと違って。
そう思いちらりと横顔を盗み見ると、去って行くベルボーイに満足気な笑みを送っているクロロが目に入った。
ラフな格好をして髪を下ろしているクロロとも、いつものコートを羽織りオールバックにしているクロロとも違う、正装姿のクロロの姿。斜めに分け、後ろに緩くなでつけた髪から数筋垂れている前髪が凄く色っぽい。初めて見るラフさとフォーマルさが併存するその髪型に、胸がトクンと鳴った。
ーーかっこいい
でも、いけない。今は仕事中だわ。そう思い直し見惚れている自分を叱咤して、あたしは去って行くベルボーイに目を向けた。あのベルボーイはこのまま下のパーティーフロアに戻って、彼がハワード男爵だと疑うこともせずにマルベール卿へ伝言を伝えるだろう。あたしたちは、ただの成り代わりの偽物に過ぎないと言うのに。
ーーーそう、全て、彼の思惑通りに
*
ベルボーイを見送ったあと、あたしたちは重厚な扉を開けて部屋の中に入った。潜入成功。鍵とチェーンをかけて人が入れないようにするけれど、まだ気は抜けないわと、あたしは男たらしなハワード男爵夫人を装ってクロロに話しかけた。
「ふふ、あのベルボーイ、顔を赤くして……可愛かったわ。」
「お前に見惚れていたのだろう。」
「あら、いやだ、そんなつもりなんてないのに。」
会話をしながら"円"をして周囲に人がいないことを確かめる。旅団員の円に比べたら未熟かもしれないけど、今回所用で参加できなかった旅団の金髪女には見劣りたくないと、会話をしながらもあたしは必死にオーラを広げた。そんなあたしを横目にクロロは男爵としての会話を返す。
「全く、思ってもいないことを。」
「思ってもないこと?」
「あの男に見せつけていただろう。」
「見せつけていた?」
「その胸を。」
「あら、ばれちゃったかしら?」
ふふふと笑いながら、懐に隠しておいた小型探査機を取り出して周囲の周波を探る。どうやら不審な周波を発している盗聴器や隠しカメラはなさそうだった。良かった。予定通りパーティー会場上の客室へ潜入出来たわと、あたしは安堵から大きく息を吐いた。
「いいわ。特に不審なものは無いわよ、大丈夫。」と機器をカバンにしまいながら言うと、ソファに腰をかけたクロロがこっちに振り返って、「そうか、では男爵夫妻ごっこも終わりか。」と笑いながら返した。ハワード男爵をたぶらかした娼婦上がりの女と、眉目秀麗で人当たりが良いが嫉妬深く女を片時も手放さない男。それがあたしたちが今回装っていた人物像だった。名残惜しいけど、それももう終わり。
思わず「名残惜しい?」とクロロに尋ねると、「お前の魔性の女っぷりがもう見れないかと思うと、少しな。」と困ったように眉を寄せてクロロが答えた。
「本当かしら?でも、本当なら嬉しい。」
「事実だ。」
「まあ、最大級の褒め言葉だわ。」
「そうか。」
「それに、一つ発見。」
「なんだ?」
「クロロってこういう系統の女が好みなのね。」
「……そうだな、美人でグラマーで性的魅力に溢れた女は、総じて好みだ。」
やっぱりね。薄々そうだと思っていたわ。彼の求めているものが言葉で明確化され、あたしの心が少し痛んだ。それに言葉にはしてないけど『手がかからなくて扱いやすい女』って項目もプラスでしょ?とあたしは内心笑った。
けれど、それを彼に伝える気にはならなくて、むしろあたしのことを『魔性の女』で『美人でグラマーで性的魅力に溢れた女』の系統の一人と言ってくれたのが嬉しかった。
「ご要望とあらば、いつでもやるわよ。」
そう言ってあたしは悪女の誘惑のポーズのつもりで、ソファに座っているクロロに向かって胸を強調したポーズを取った。
「胸を強調したドレスに、こぼれ落ちん程の大きなダイヤ。今日のお前は、男爵をたぶらかして贅を尽くした希代の悪女、ハワード夫人にふさわしい。」
「ふふ、クロロが盗ってきたこの首飾りのおかげよ。浪費家の夫人らしさをより一層演出してくれたもの。」
喋りながらあたしは肩にかけたストールを畳み、ハンガーにかけてクローゼットにしまった。本当に好きな人には本音を伝えられないくせに、こういった言葉のやり取りだけが上手くなって行く。もう、振りなんてしたくないのに。この日のためにクロロが買ってくれたドレスにシワをつけないようにと、あたしはドレスの表面を何度も何度も撫でながら思った。
「それにしても、会場の警備かなりずさんだったわね。」
「そうだな。」
「招待客の個人照会や身体チェックも甘かったし。」
「偽造IDを一通り用意したのにな。」
「あたし、バレやしないかってかなりヒヤヒヤしていたのに……結局使わなかったしね。」
「そうだな。」
「使わないのにソレ作らされたシャル君、可哀想。」
「だが、それがあいつの仕事だ。」
「そうね。それがシャル君の仕事であって旅団の仕事だものね。でも、旅団の仕事があるからこそ、あたしにこうやって提携の依頼が来るのだもの。シャル君にも感謝しなくちゃだわ。」
そう言って、あたしは鏡の前に向かった。10cmのヒールに、ゴージャスなイブニングドレス、胸元と耳に光る巨大なダイヤ。ハワード夫人としては、これ以上ないほど相応しい格好だけど、体調の悪い振りをしてパーティーホールの上の客間に潜入できた今となっては、全て必要ないものだった。
「服、脱いじゃうわね。帰りは窓から逃げるかそのままホールから出て行くか……まだ決まってないけど、とりあえずクロロが仕事を終えるまで二時間近くは暇になるわけだし。」
解放されたい。着るだけなら5分もかからないから、この窮屈なコルセットから解放されたかった。クロロが仕事をしている間は、そこのクローゼットの中にあるガウンを着て過ごすつもりでいたから、この場で服を着替えても問題ない。そう思っていた。
クロロにエスコートされる夢心地の役はもう終わりで、シンデレラの魔法はこの部屋に入った時点で消え去り、あとは王子様がこの部屋を出るのも見送るだけ。そう思ってた。
だから、クロロに色を孕んだ声で名前を呼ばれた時は、心臓が跳ね上がってしまった。
*
「ナナシー」
突然名前を呼ばれて、あたしは下げかけていた背中のファスナーの手を止めた。低く掠れたその声は、ベッドでクロロがあたしを呼ぶ時と同じで、あたしの心臓がどくんと音を立てた。
振り返ると、ソファに座っていたクロロが、不敵な笑みを浮かべながらあたしの方に歩いてくるのが見えた。なにごとかと唾を飲み込んでから、あたしは口を開いた。
「な……なに?」
「なにをそんなに驚いている。」
「だって…」
「それ。」
「え?」
「それ、オレが外してやる。」
「え、いいよ。自分でやるか…」
「いいから。」
そう言うとクロロは強引にあたしの背後に立った。気恥ずかしさを感じながら目の前の鏡を覗くと、こちらを見据えるクロロと目があった。
「ナナシー、この後のタイムスケジュールは覚えているか?」と背中のファスナーをゆっくりと下げながらクロロが尋ねた。もどかしいくらいゆっくりと下げるその手に、背筋が緊張でピンと張る。
「え、えっと、これからクロロが仕事を終えるまで部屋で待機。時間は、最大120分、22:30まで。トラブルがなく終わった場合は、そのままパーティーの終了時間に合わせて二人で正面玄関から退避。」上ずりそうになる声を抑えて、今日のタイムスケジュールを言うと、クロロの手によって落ちるか落ちないかギリギリのところまで下げられたドレスが、あたしの肩に掛けられた。辛うじて肩に引っかかっている今にも崩れ落ちそうなそれに、あたしの動きが制限される。
「それで?」
「そ、それで…トラブル発生時は窓からルートBで揃って退却。終了時間過ぎても連絡がない場合はルートDで一人で脱出…で合ってるわね?」
露わになった肩にそっと手を当てられて、思わず身体がビクンとなった。ただ、肩に手を置かれただけなのに、妙に意識してしまう。
「今日のターゲットは覚えているか?」
あたしの背後に立ったまま、クロロは声色を変えずに事務的な声で話しかけてきた。質問の内容よりも肩に置かれた手と背中からほのかに感じる体温に意識が向いてしまって、反応が鈍くなる。
「えっ…と、ターゲット?ターゲットは…た、確か…ある男で。パーティーの同伴が今回の仕事だから、ターゲットの詳細をしっかりとは覚えていないけれど、男を探して何かを吐かせる所までが、今日の仕事だって……」
あたしの返事を聞いたクロロは低い声で「そうだ。」とただ一声言うと、後ろから指先を尖らせた手で首筋をつつーと撫でてきた。思わず体がビクつく。驚いて顔を上げると、鏡越しにクロロと目があった。
「ターゲットは念の使えない普通の人間だ。"絶"で会場に戻り、怪しい男全てに総当たりで接触する予定……だった。」
「…だった?」
近い。彼の息が首筋に当たってゾクゾクする。鏡越しに、狙うような鋭い目を向けてくるクロロに、まるで、視線だけで拘束されているようだった。紐もロープも何もないのに、動けない。コクン、と音を鳴らして唾を飲み込んだ。
「予定変更だ。もうターゲットは絞られた。」
「え、もう?」
「そうだ。ターゲットの懐に発信機を入れておいた。所要時間はもう15分とかからない。パーティー終了間際まで時間が空くな。
なあ、ナナシー。それまでの間……
何を、しようか?」
意味ありげな瞳で見つめてくるクロロに、胸が高鳴る。
これは、誘われている…の?
今すぐにでも振り返って彼にキスをしたい欲求にかられる。けれど、それは、ダメ。状況を把握していないのに、欲望に負けて誘いに乗るなんて、そんな半人前な反応をクロロの前で見せたくなかった。少なくとも今は仕事のパートナーとして彼の隣にいるのだから。ちゃんと聞かなくては。
大きく深呼吸をした後で、あたしは乾いた口を開いた。
「そんな……いつ」
「ターゲットを絞ったの?」と続くはずだった言葉が途中で消える。
鏡越しのクロロの鋭い視線に、身を射抜かれた気がした。それほどクロロは鋭い目をしていた。まるで獲物を狙う目。
「ナナシー、お前はいつだと思う?」
「ええっ……と。」
今日のパーティーの様子を思い返してみても、いつターゲットに接触したのか検討つかなかった。車で乗り付けてパーティー会場にエスコートされてからずっと、クロロはあたしの側にいた。男好きの夫人と嫉妬深い男爵の役どころでは、別々に行動することは不自然なので、あたしとクロロはこの部屋に入るまで、一瞬と離れずずっと一緒にいたのだ。
「分からないのか?」
そう問われたけれど、首を縦に振りたくはなかった。クロロに分からないだなんて返事はしたくなかった。今日のパーティーでの出来事を思い返して考え込むあたしを尻目に、クロロが口角をにやりと上げた。悪戯な笑い。そして、その笑みを携えたまま、クロロに後ろからギュッと抱き締められた。ふわりと彼の香りに包まれて顔が熱くなる。バクバクバクと心臓が喉から出そうなほど大きく鳴った。
「知り…たいか?」
耳元で囁かれる。クロロの少し掠れた声が、あたしの脳を直撃した。頭がクラクラして何も考えられなくなりそう。
「分からない」「知りたい」と言わせたいのだろうか。それならば、なおさら言いたくないわと、思い直したその瞬間、後ろから耳の上部をカリッと甘く噛まれた。
「あッ…ん……」
思わず、甘い声が鼻から抜けていってしまった。
首に彼の吐息を感じる。
熱い。ぞくぞくする。
甘い疼きが首元から下腹部へと伝わって、足に力が入らなくなった。
「ン………ん、知り、たい。」
先ほどの決心はどこに行ったのか、気づけばあたしは返事をしていた。
その様子を、クロロは満足げな様子で見てから、口を開いた。
「ほら、これだ。」
そう言ってクロロは、後ろからあたしの顎を掴み、くいと正面に向けた。強制的に正面を向かされて、鏡に映っている自分が目に入る。鏡の中には、イブニングドレスを肩まで露わにし頬を赤らめている自分がいた。
ーー恥ずかしい。と思わず顔を逸らすけれど、後ろからクロロにがっしりと顎を掴まれていて、動くことが出来なかった。熱い。体と体の密着度がさらに増し、今ではもう、背中全体で彼の体温を感じていた。心臓の音に気づかれませんように。無駄とは知りながらそう願う自分がいた。
「目を逸らすな。見ろ。」
そう言って、クロロは後ろから鏡越しに鋭い目を向けてきた。心臓が高鳴り、体が熱くなり、頭に霞がかかってきた……もう、全てが限界だった。
「ここだ、ここ。お前は気づかなかったか?
男どもは欲望の眼差しで、この………胸の……谷間を。女どもは、羨望の眼差しで、この……ダイヤを、見ていたことを。」
あたしの胸元に下げられた首飾りを指先で弄りながら、クロロは言葉を続けた。クロロがダイヤの首飾りを触るたびに、あたしの首にも彼の指先が触れた。あたしの首筋を、喉元を、胸元を、指先でつつーとなぞってゆくそのもどかしい動きに、触られた場所がどんどん敏感になっていった。
「そんな……っ……ん……」
「その中で、ただ一人。欲望でも羨望でもない眼差しでここを見ている男が……一人。」
「……ん…」
「そいつは、恨みと怒りの混ざった視線をここに向けていた。」
そこで一旦言葉を切ると、クロロは鏡越しにあたしの顔をジッと見た。言い訳の出来ないくらい赤く上気した顔を見られているかと思うと恥ずかしさで胸がいっぱいになる。そんなあたしに視線を置いたまま、クロロは首飾りの金具を外し、シュルリとそれを抜き取った。肌を伝う金属の質感に、思わず鼻から息が漏れた。
首飾りのなくなり露わとなったうなじをそろそろと指先でひと撫でした後、くろはそこにキスを一つ落とした。チュッ。クロロの温かい唇を肌に感じた。キスされたところから肌が粟立っていく。体全体に広がった甘い疼きに、張り裂けそうな胸の鼓動に、込み上げるこの想いに、もう、耐えられそうになかった。身体が、脳が、心が、あたしの全てが彼を求めていた。
ーーークロロ、クロロ、クロロ、クロロ、クロロ………
「そこまで分かればもう簡単だ。そいつが今日のターゲットだった。あとはすれ違いざまに、発信機を入れ、後は帰り道に一人になったところを襲えば終わりだ。」
そう言うと、彼は外した首飾りをポケットにしまった。完敗だ。
あたしは、そんな視線に気づかなかったし、クロロがいつ接触したのかも分からなかった。もう、全てにおいて敵わない。
あたしは、くるりと体を返してクロロに向き合った。
「さすが、幻影旅団の団長ね。」
はやる心臓を押さえつけ、余裕の笑顔を作り出し、何とか言葉を絞り出した。敵わない。同業者としても、恋の駆け引き相手としても、何もかもが敵わない。全てに白旗を立てて、彼の軍門に下りたくなる。
ーーーでも、これだけは譲れない。たったひとつのあたしの矜恃。
『彼の隣に居続けたい』
そのためなら、あたしの恋心を押し殺しても構わない。
そのためなら、心を偽ることなんか構わない。
そのためなら、本心じゃないことを言っても構わない。
手間のかからない扱いやすい女に落ちて、いつか捨てられるくらいなら
初めから、感情を挟まない手軽な肉体関係だけで構わない。
だから、偽りの装いを身に纏って、あたしは言うのだ。
「ねぇ、クロロ。あたしをこんなに挑発して、どうするつもり?」
ハワード夫人さながらの誘惑の視線を絡ませて、あたしはクロロの唇を強引に奪った。彼は驚いた顔をしたのだろうか?ここからじゃ、確認することもできやしない。
そして、あたしはそのまま答えも聞かずに「責任とってよね。」と耳元で囁くと、彼をベットに押し倒したのだった。
あたしのしのぶ恋。
誰にも見せるつもりはない。
偽りの装いを身に纏い、あたしは『色』を隠すのだ。
FIN
ーーーーーーーー
相互先の「Arche noire」ののある様へ、日頃のご感謝と555555hitをお祝いしてこの小説を送ります。
[ *prev | back | next# ]