「ホント、モテるのね、グレイって」
「女ってどうせ顔しか見てねえんだろ」
「そんなことないってば!」
ナツはその場にしゃがんで膝に肘を突いた。心の底からバカにしたような声を出す。
「どうだか。お前だってカッコイイカレシ欲しー、とか思ってんだろうが」
完全に否定できるか、と言われればそうでもない。詰まったルーシィに、ナツは鬼の首でも取ったような顔をした。
「ほら!」
「で…でも!……まだ…よくわかんないよ、そういうの」
「あ?」
同年代の女子達は恋話が好きだ。誰がカッコイイ、誰と誰が付き合ってる――そんな話を聞く度に、ルーシィも少なからず憧れるところはある。しかし、いざ自分に置き換えると、不安のようなものが胸を占めた。
ルーシィは、まだ、恋をしたことがない。
「そりゃ、彼氏とか出来れば良いけど、男の子を好きになるって想像つかないし。今はレビィちゃんと遊んでる方が楽しいっていうか」
出来れば、いつか好きな人が現れるまで、放っておいて欲しい。レビィの言う「恋をしてみない?」というのも、ナツの言う「女は男のことしか頭にない」というのも、両方彼女にとっては焦る要因でしかなかった。
ナツはぽかん、と口を開けて呆然とルーシィを見上げていた。その視線に気付いて、頬が熱を持つ。
「やっ、あたし、変なこと言っ…」
「へぇ…オレと同じだな」
「え?」
にっ、と――それまでと人格が入れ替わったかのように、ナツが笑った。牙のようなものが目立つ口元と、嬉しそうに細められた目が、昼寝中の猫を思わせる。
彼の笑顔を、初めて見たような気がした。
「な、何?」
いきなりのことに声が上擦る。
ナツはこくん、と頷いた。
「女なんて皆一緒かと思ってた。グレイなんかにぎゃーぎゃー喚いて、うっぜえの」
「でも」と繋げて、彼は彼女を真っ直ぐに見上げた。
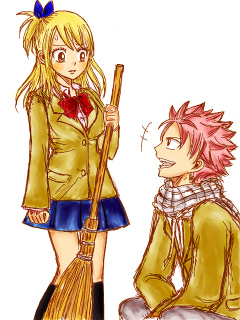
「ルーシィみたいな奴も居るんだな」
「……」
嬉しそう――なのかもしれない。しかしルーシィには、その表情を気に留める余裕はなかった。
「今……」
「ん?」
「…あんたもあたしのこと、呼び捨てにするの?」
「へ?ダメなのか?」
「……ダメってわけじゃないけど」
諦めて、ルーシィは首を振った。意識しすぎだと、思うことにする。
確かにナツは男子だが、あまり異性という感じはしない。もっと言えば、人間という感じさえも薄い。
握り締めていた箒に気付いて、彼女はゆるゆると力を抜いた。ナツ達が放り投げていた箒とちりとりを拾い集める。
「まあ、ハッピーと一緒よね」
「あ?」
「なんでもない」
ナツは驚いたように目を見開いた。
「ルーシィも気付いてたのか?」
「え?何に?」
「ハッピー」
彼はぴ、と校舎の角を指差した。一拍置いて、青い猫が飛んでくる。
「掃除終わったー?」
「おう、今……あ、なんでもねえ。終わったぞ」
「グレイ置いてくつもり!?」
立ち上がったナツに、ルーシィは箒を押し付けた。ホバリングするハッピーと、彼を見比べる。
「あんた、ハッピーが来ることわかってたの?」
「ん、音と匂いで」
「何それ、あんた獣!?」
どう考えても人間業ではない。目を剥くルーシィに、ハッピーが説明してくれた。
「滅竜魔導士の特徴だよ。五感が優れてるんだ」
「へ、へー。て、いうか、その滅竜魔導士って何なの?」
「滅竜魔法は竜も倒せるっていう攻撃魔法だよ」
「竜を倒すって、そんな途方もない」
大体そんな架空の生き物を倒すだなどと、現実味がない。それほど攻撃力が高い、ということなのだろうが。
ナツはふん、と胸を反らした。
「羨ましいだろ!」
「ううん、ちっとも」
「……」
彼はショックを受けたように顔を引き攣らせた。それはとりあえず放っておいて、ルーシィはハッピーに訊ねてみる。
「ねえ、レビィちゃん、まだ教室に居た?」
「あ、一緒に来たんだけど」
「一緒に?でも」
「階段下りるの翼使ったら、ついそのまま置いてきちゃった」
「あんた酷いわね」
「冷酷だ」
「ナツまでオイラを責めるの!?」
項垂れた猫を、ナツが笑いながら撫で回す。
ルーシィがレビィを迎えに行こうかと考える前に、角からその姿が現れた。
「ルーちゃん、お疲れさま」
「レビィちゃん」
何故だか懐かしく感じて、ルーシィはちりとりを握り締めた。
「グレイが戻ってきたら帰れるから、あとちょっとだけ待っててね」
言った途端に、肩が沈んだ。
「帰り、なんか食ってこーぜ!」
温かい。そして重い。
ルーシィはロボットのように首を動かして、肩に乗せられたそれを確認した。瞬時に、振り払う。
「な、何してんのよ!」
「ぶ!?」
ちりとりがナツの顔をべちん、と叩く。彼の持っていた箒が、ばたばたと倒れた。
ルーシィは自分を庇うように両腕を抱き締めた。
「い、いきなり、何!」
「は?だから、帰り、なんか食ってこーぜって」
「それじゃない!」
レビィが唖然と瞬きを繰り返した。
「え、何?そういう仲になったの?」
「違う!」
突然、ナツが腕を回してきたのだ。ルーシィの気持ちなど、どこにもない。
涙目の彼女に、ナツはきょとん、としただけだった。それどころか、さも自分が被害者であるかのように口を尖らせる。