「見て見てー!」
ハッピーが二人を振り返って、左手に乗せた雪だるまを見せ付けた。
「雪だるまー!」
「おっ、もう作ったのか、早ぇな!」
ルーシィには落ちていた雪玉を二つくっ付けただけに見えたが、ナツは感心したように目を丸くした。それに嬉しそうに頷いて、青い子猫は後ろに隠した右手も前に持ってくる。
「しかもダブル!」
「おお!すげえ!」
そこには同じくらいの大きさの雪だるまが乗っている。ハッピーはそれを足元に並べて置くと、両手でもう一つ、小さな雪だるまを掲げてみせた。
「そしてこれが孫雪だるま!」
「子供じゃないの!?」
思わずツッコんだルーシィに、ハッピーが満足そうに笑う。
ナツが勢い良く座って、長椅子を揺らした。
「じゃあオレは後で先祖雪だるま作ってやる!」
「何それ」
「超巨大な奴だよ、当たり前だろ?」
「世代と大きさが比例するの!?」
「雪だるま界ではな」
めちゃくちゃなことを、と思うが、ナツは当然のように言っていて。そんな彼を見ていると、納得しそうな――してあげても良いような、そんな気になってくる。
ルーシィは苦笑に甘さを含ませた。
きっと、今年の――本当の冬も、彼らはこうして雪だるま一族を作るのだろう。容易に想像できて、くすくすと笑いが漏れる。
「んだよ?」
「だってあんたら――」
そうだ。冬にはあのイベントがあるではないか。
ルーシィはぽふ、と手袋を合わせた。
「ねえ、冬になったら、さ」
「あん?」
「一緒に、パーティしようよ。みんなで」
「おっ、良いな!クリスマス!」
ぴ、とナツが人差し指を向けてくる。釣られて人差し指を立てると、彼は小さなハイタッチをするように指の腹を合わせた。
「美味いもん、いっぱい食うぞー!」
ナツらしい笑顔がルーシィの心を擽る。クリスマスの食卓を彩る食べ物が本当に楽しみに思えてきて、彼女は目を細めた。
「そうね、七面鳥にローストビーフ、フライドチキン、ミートローフ、ブッシュドノエル……」
「おいやめろ、腹減ってきた」
会場はどこにしたら良いのだろう。考えを巡らせるルーシィの横で、ナツの声が大人しくなった。
「あ…グレイの奴には……オレから言っとくか?」
「あはは、気が早いって怒られそうよね」
「そんなん、オレが黙らせてやんよ!」
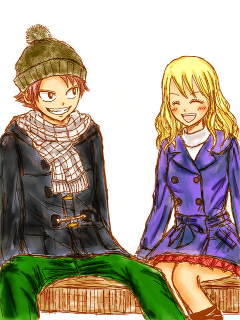
カキ氷の注文は一つだけではなかったらしい。器を氷で作ったグレイが、点検するようにそれを裏返しているのが見えた。また性懲りも無く服を脱いでいる。
「パーティって夜だよね?」
ハッピーが小さな手で雪を弄りながら振り向いた。
「オイラ、昼間は用事があります」
「用事?」
「え、ちょ……まさかあんた、デートとか言うんじゃ」
青い猫の頬がぽっ、と赤く染まる。
ぱかん、と口を開けたルーシィとは対照的に、ナツは「あー」と思い出したような声を上げた。
「あの白い猫か」
「えへへ……まだ誘ったわけじゃないけど、多分」
「ちょっ、ちょっと!あたし聞いてないわよ、そんな相手が居るなんて!」
「どう言って誘おうかなあ」
「話聞いてる!?」
ハッピーは上の空でころころと雪を転がしては、ぺちぺちと表面を叩いて固めている。よほど思考に没頭しているのか、その視線がこちらを向く気配はなかった。
「……ナツ、どんな子?って、子で良いのかしら?」
「ネコだからコには違いねえな。白くて、えーと……猫の集会で会ったって言ってた」
「野良なの?ていうか、普通の猫なの?」
「よく知らねえ。オレも遠目で見ただけだし」
「放任主義ね……」
ナツは雪を捏ねるハッピーを数秒だけ見つめて、ルーシィに視線を戻した。
「じゃあオレらもどっか行くか」
「へ?」
「暇だろ、夜まで。ハッピー居ないし」
「え…え?」
「約束な!」
「それって」
クリスマスの予約など、彼氏居ない歴=年齢のルーシィにはもちろん初めてのことだった。それをまさか、ナツにされるとは。
赤と緑に飾られた街中。聴こえてくるクリスマス・ソング。寄り添う。腕を組む。イルミネーションを見上げる。キレイダネ。キミノホウガキレイダヨ――。
「だああ!昼間だってば!イルミネーションはない!」
「うお!?なんだよ、ビックリすんじゃねえか」
びくり、とナツが跳ねる。その真ん丸になった瞳には電飾の光どころか、真夏の太陽が映っていた。
バカらしいくらいに、元気に明るく。
きっと当日も、甘い雰囲気など欠片もないだろう。クリスマスに対しても、デートに対しても、淡いとは言え憧れが台無しだ。
でも。
「ん?」
「ううん……なんでもない」
(まあ良いか――)
落胆はなかった。
彼と一緒なら、楽しいに違いないから。
そしてそれこそを、楽しみにしている自分にも気付いてしまっているから。
「……グレイにも、声かけとくか?」
「え?ん、んん、ジュビアが怖いから」
「そ…か」
ルーシィはナツから目を逸らした。実を言うと、そんなことただの言い訳だった。レビィを誘おうという気も、彼女にはない。
そこに明確な理由が見付けられずに、後ろめたさだけが圧し掛かる。ルーシィは彼がレビィは、と言い出すのが怖くて、息を詰めた。
ナツはそれまでの会話を忘れたかのように声を弾ませた。
「あ、雪だ。まだ降らせるんだな」
「ホント……」
胸の鼓動に名前を付けるとすれば、これは確かにときめきなのだろう。
ルーシィは舞い下りる白い結晶を見上げて、頬を手で覆った。