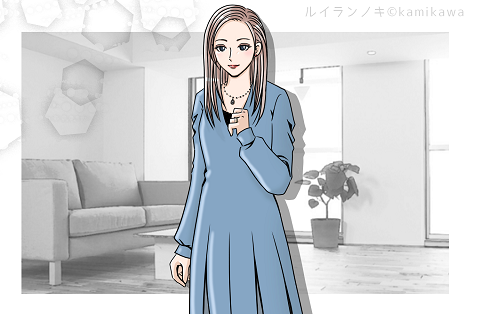voice of mind - by ルイランノキ |
アーテの館6…『陽月』 ◆
「それだけを書いたのですか?」
と、ルイは紙切れに書いた内容を聞いて驚いた。
「うん。知っていたら向こうからなにかアクションがあるかなと思って」
「なるほど」
「あれこれ書いていないほうが見てもらいやすいし、気になるでしょ?」
と、アールも立ち上がり、スーが戻ってこないか気に掛けた。
それから10分ほどして、会場にアナウンスが流れた。
《落し物のお知らせです。会場にお越しの、アール・イウビーレ様。会場にお越しの、アール・イウビーレ様。落し物が届いておりますので、館内までお越しください》
「私だ……」
と、ルイを見遣る。
「なにか落としましたか?」
「名前を書いてるものなんて落としてないよ。ケータイもポケットにあるし」
と、ポケットの中の携帯電話を見せる。
「もしかしたら」
と、ルイ。
「あ……そうかも」
もしかしたら、“アクション”があったのかもしれない。
まだ人が多くいた、ルイはアールに付き添って、館内へ向かった。
──誰かに心を奪われて、できるだけその人の側にいたいと願う
その人のことが好きだから。大好きだから。
その人の側にいると幸せだなって思えるから。
少しでもその人の声を聞いていたいから
少しでも同じ時間を過ごしていたいから
一緒に笑い合える時間が沢山あったらいいよね
そんな風に互いに互いを想って、必要として、愛した。
私が生まれた世界とこの世界を繋げてしまったことから全ては始まったんだ
そうして生まれた一つの愛が引き裂かれて消えてしまった。
繋がらなければ出会うこともなかったのに
それでも面影を探して生き続けたのはそれほどの愛がそこにあったから。
それをなかったことにして出会わなければ良かったなんて思えないのは
私もよく知っている
痛いほど、えぐられるほど知っている
アールを待っていたのは、黒いスーツに身をまとった男だった。アールは彼が自分を待っていたとわかったのは、彼の胸ポケットからスーが平たく顔を出していたからだった。
「スーちゃん?」
「あなたが、アールさん?」
と、男が訊く。
「はい……」
「そちらの方は?」
と、アールの後ろに立っているルイに目をやった。
「一緒に旅してる仲間です」
「すみませんが、彼女だけ通すよう言われていますので、あなた様はこちらでお待ちいただけますか」
「はい」
アールはその男に連れられて建物内へ。その途中、男は自分がエイミーのマネージャーであることを伝えてきた。そしてエイミーが待つ楽屋にたどり着くと、ノックをし、エイミーの返事を待ってからドアを開けた。
アールは酷く緊張していた。エイミーのことは詳しいわけではなかったが、興味を持ち始めてからは何曲かサビだけなら歌を口ずさめるくらいにはなっていたし、どれほどの人気があるのかも目の当たりにしたばかりだ。それになにより、こうして呼んでくれたということは陽月についてなにかしら知っているに違いないと思ったからだ。
「失礼します……」
緊張の面持ちで楽屋に入ると、エイミーが立っていた。
思っていたよりも落ち着いて見えるのは私服だからだろう。カジュアルだけど女性らしい服装は、目鼻立ちが整っている彼女の美しさを引き立たせていた。
「はじめまして。アールさん」
と、エイミーは丁寧に頭を下げた。
「はじめまして」
と、アールも頭を下げた。「メッセージ、見てもらえたんですね」
「えぇ。とりあえず、ソファにどうぞ」
ソファに座ると、目の前のテーブルには熱いお茶と和菓子が用意されていた。エイミーは向かいのソファに座り、ペットボトルの水を飲んだ。そして、ゆっくりと語り始めた。
「私は、この日が来るのをずっと待っていました。半信半疑だったけれど、きっと、祖母がそう信じていたように、祖母を知っている人が会いに来てくれるこの日を」
「祖母?」
「陽月は私の祖母です」
「え……?」
と、身を乗り出した。
「あなたは少し遅かった……。祖母は1年前に亡くなったんです。いつか、自分が生まれた世界から必ず誰かが自分を訪ねて来てくれる、迎えに来てくれるはずだと言っていました」
「待ってください……私が知っている陽月は、20代です。あなたと同じ年くらいの……」
「…………」
エイミーは小さく首を傾げた。アールもまた、考え込んだ。同じ名前の、違う人物なのだろうか。“自分が生まれた世界”というキーワードが出てきた時点でそうとは思えない。アールはこれまでの経緯を話すことにした。一部、伏せて。
「えっと……私は、ココモコ村という場所で、ミラという女の子と出会いました。その子が口ずさんでいた歌が陽月の歌だったんです」
そう説明しながら、自分の事をどこまで話していいのだろうかと頭を悩ませる。別世界から来たと話せば何故と帰ってくるだろう。そうすればこの世界が終わりへと近づいていることを話すことになる。変に不安にさせるわけにもいかない。
「その歌はこの世界には存在しないはずの歌なんです」
「その歌をあなたが知っているということは、あなたは私の祖母、陽月と同じ世界から来たということですね?」
「……違います」
と、顔を伏せた。「私ではなく、私の仲間が」
「え? じゃああなたはその歌をその仲間から聞いて知っていたということ?」
「はい」
「……だったら、その人と話がしたいわ。呼べませんか?」
「呼べません。その人は……亡くなっているので」
「……そう。ごめんなさい」
と、肩を落とした。「その方の名前を伺っても?」
スラスラと嘘が出る。
ふと我に返ったときに、いつの間にこんなにうまくなったんだろうって思う。その内、自分でも何が嘘で何が本当なのかわからなくなりそうで、怖くなった。
「良子、です」
「リョーコさん? その方は男性ですか?」
「いえ。女性です」
「女性……」
と、考え込むように呟いた。
「どうかしましたか?」
「いえ。あなたが聴いたその歌は、祖母が生きた証として娘に伝え、孫の私へ伝えられました。ミラに会ったのは私です。私が彼女に教えたんです」
エイミーは、時間が許す限り陽月という女性のことを話してくれた。
「祖母から聞かされた話ですが、あるとき突然見知らぬ世界に来たと言うのです。それまでは自分の世界で歌手として活動をしていたと。その時にある男性と出会い、互いに恋に落ちたと言っていました。けれど、突然、彼は祖母の前から姿を消してしまった。別れの言葉もなく、原因もわからず、食事が喉を通らなくなって憔悴しきってしまった。自殺を考えたそうです。そして、実行した」
「え……」
アールの脳裏に浮かんだのは、タケルだった。
「でも気付いたらこの世界にいたと言うんです。でも誰も信じてはくれなかった。頭でも打っておかしくなったのだろうって、みんな白い目で見てきて。途方に暮れていたけれど、一度死のうとした身として、生きていることに意味があるのなら生きようと思ったそうです。そして、この世界を受け入れた。祖母はこの世界になら彼がいると考えたんです」
「お付き合いしていた男性ですか?」
「はい。なんの根拠もないけれど、でも、突然いなくなったんですよ? そんなときに自分もいなくなるように別世界へやってきた。そうなるとこの世界にきっと彼がいるって思うのもわかる気がします」
「私も……陽月さんの立場だったら他に頼れる人もいないし、夢を見るかもしれません」
と、お茶に手を伸ばした。妙に喉が渇く。
「この世界で彼を捜しながら生きていくと決めた彼女は強かった。なにもわからない、知っている人がいない場所で、彼女がまず最初にはじめたことは何だと思います?」
「…………」
アールは無言で首を振った。
「歌を歌ったんです」
「歌を……」
「そう。その歌を聴いた人々は忽ち彼女の歌声の虜になった。──って、祖母が言っていたことなので、話を盛られている可能性もありますけどね」
と、エイミーは可愛らしく笑った。
[しおりを挟む]
[top]
©Kamikawa
Thank you... |