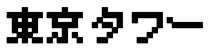
東京行きの新幹線の中で、俺は不機嫌を表に出してコンビニ弁当を食っていた。関東で一番有名な花火大会に視察という名目でやってきている。地元での準備だって急ピッチで行われているのに、俺だけつまはじきにされるように都会へ飛ばされた。
(ちぇっ、トンネルが多くって電波が通じねえや)
視察による上京の話は、実はコサカさんの提案だった。日帰り出張と花火大会が重なったのを機にどなたかご一緒しませんか、とオヤジさんづてに俺らの職場に呼びかけたのだ。
電子機器を鞄にしまい、背もたれに体重を預けて目をつむる。次に目を開けた瞬間、もう東京についていた。
(ちょっと寝ただけだと思ったが……)
この都市と地元とが、近いのか遠いのかわからないまま東京駅で乗り換え、俺らを乗せた電車は地下を潜っていく。たまに地上に出た窓に映る狭い空の隙間から、かの有名なタワーが見えた。東京タワーごときではしゃいでは田舎根性丸出しな気がして素っ気ないそぶりをしてはみたが、東京にいるんだという実感が急に湧いてくる。
人が行き交い街は変容し、この塔は東京の何を知っただろう。もし塔に人の言葉がわかるなら、俺は是非とも聞いてみたかった。「自分を残していくつもの命の灯火が消える瞬間を、君はどんな気持ちで見ているのか?」と。
東京には何度か行ったことがあった。修学旅行だったり友達との旅行だったり、用事は様々だったが、いつ来てもこの都市に用のある人間が多すぎると思う。すれ違う人々が皆俺の知らない人なんだと思うと、他方で全くこの街と縁がないであろう俺の地元の年寄りたちを思うと、日本は十分広い国だと考えざるをえない。
「や、お待たせ」
目印になる派手な看板を背に立っていると、見覚えのあるスーツの男が近づいてきた。
「お疲れ様です、コサカさん」
「やあ、もともと大した出張じゃなかったし、スムーズに事が運んだからよかったよ。じゃあ向かおうか」
花火大会の会場へと近づきながら、先ほど電車で見た東京タワーについてコサカさんに話した。
「東京タワーとスカイツリー、どっちがお好みで?」
俺は少し考えてから答える。
「うーん、どっちもちゃんとよく見たことがないんで直感ですけど……スカイツリーの方が好きですね。単純にでかいし、ちゃんと働いてるし。アナログ放送が終わった東京タワーは、ただ綺麗なだけの建物になっちまったような感じがするんです」
夕暮れが塔のライトアップを誘う。紅白の模様に少し橙色がかかったその様は、”ただ綺麗なだけ"という俺の失礼な発言を撤回させようという意思さえ感じた。
「僕は好きだねえ、東京タワー。役目は終わってしまったかもしれないけど、特別にお疲れ様って感じがするよ」
コサカさんの顔もほんのり灯りに照らされたように赤くなっていた。
「見ている人を懐かしい気持ちにさせるような、温かい気持ちにさせるような、あんな光の使い方ができるようになりたいなあ……」
ほぼ同い年のこの人はいつも仕事のことばかりだ。それなのに、友人の誰よりも楽しそうに生きている。会えば僕を心配してくれて、近頃は離れていても彼の名前を人づてに聞くようになった。
一生懸命生きて、そしてたくさんの人に「お疲れ様でした」と言われる、そんないつかの将来さえもこの人の背後に見えてくるようだった。
都会に来て夜闇に浮かぶ赤い塔をじっと見つめて、自分の仕事とコサカさんの仕事のことについて考えていた。真っ白なキャンバスに絵筆を走らせるように、星だけを散らばせた夜空に一瞬の光を振りまくのが俺たち。それを見に来てくれる観客の皆さんをより楽しませられるように趣向を凝らすのがコサカさん。コサカさんがいなければ、俺たちのやっていることは炎色反応の実験に過ぎない。
「この世界のすべての爆弾が花火に変わって、戦争が無くなりますように──いつしかそう祈られながら花火が上がるようになって……」
俺は話さずにいられなかった。
「昔は花火が嫌いだっていう人もいたそうですよ。自分が経験した空襲を思い出すからって。でもそんな苦情は年々減って、今となってはほとんどなくなりました。たぶんこれって、日本が平和になったことを象徴してるんだと思います。
でも、俺の親父は花火で死んだ。
この事実に俺はいつも考えさせられます。当時の俺は、きっともう花火なんて見ないんだと思いましたし、見ても事故のことしか思い出さないんだと思っていました」
コサカさんの表情に幾らかの悲しみが宿った。暗い話をして申し訳ないという思いが、俺に赤く輝く塔を強く見つめさせた。
「次の年の同じ日、俺は花火を見ていました。
親父のことを、親父の背中を、親父の花火を、ただ思い出していました。
もし花火っつーもんが、この東京タワーみたいにいつまでも同じ場所で光り続けるものだったら、俺は花火師なんかなってなかったんじゃないかなって……今、そんな気がしてきました」
実質的に追悼の意味を失った花火を、誰が見るんだと思った。だけど俺自身がそうであるように、顔も知らない誰かにとっては、毎年同じ日に同じ場所で上がる、輝いては消えていくあの彩りが何にも代えがたいものだったりするんだろう。
そんな人に余すところなく渾身の一発を、一つでも多く打ち上げたい。
そのためにも俺はこんなところになんかいられないのに。
「テレビにだって新しい時代の風が吹いたんだ」
“テレビにだって"――そのニュアンスの意味するところに俺は自身の迷いを投影した。
「変わらないために、失われないために、変わることが必要な時はある。家族の形は時代によって多様になっているかもしれないけれど、家族を思う気持ちに時代は決して動かされない。変わっていくものをちゃんと見極めて、それでいて変わらないものを忘れない」
ふうーっと細く長く、コサカさんがため息をついた。花火大会でよく聞く、美しいものを目の当たりにした時に出るため息だった。
「それが新しい時代を作る人間の根本的なあり方なんじゃないかなあ。時間をかけて学べる機会はいつもあるわけじゃないんだよ」
アナウンスとともに、一発目の花火が上がる。消えるとわかっていても、その光はどうしてか俺を泣かせようとする。”ただいま”という言葉が頭の中を駆け巡って、涙を誘った。
移動の途中に買ったつまみ菓子をつまみながら、しばらく会話もなくただ花火を見上げていた。
「君は知ってるかい」
実に楽しそうに、誰も知らないような秘密を打ち明けるかのように、コサカさんが急に声を潜めて俺に囁く。
「デジタルもね、光の信号なんだよ」
「そ、それくらい知ってますよ」
「つまりこの世界を作ってるのは光だ」
花火の光が空を彩るスピードと、家庭に電波が届くスピードが同じということ。
知っているけど忘れかけていた、それはすごく大切なことのように感じた。
「新しい時代が来ても、世界が変わるわけじゃない。変わるのは時代で、僕らは変わらない」
そういえば、話したことなかったねえ。そう言ってコサカさんが語り始めた。
「見えない光に現実を惑わされている人があまりに多いから、幻想的な世界を作り出す目に見える光が美しいと思ってこの仕事と出会ったんだ。あの輝きは化学があって物理学があって天文学があって、それでいて芸術であって哲学なんじゃないかって、僕は思ってる。宇宙の誕生も、地球の誕生も、人類の誕生も、あの光は知っている。
見えないものが消えてもね、人間っていうのは忘れちゃうんだよ」
消えるのがわかっているけれど、花火は目に見える光だ。だから誰かの心に、記憶に残っているのだろうか。
「……俺、どんだけ頑張ってもコサカさんにはかなわねえっす」
「頑張らなくていいんだよ、楽しんでやればなんだって上手くいく……ほら、始まるよ」
同じ材料で同じ花火を作っても、作る人・上がる瞬間・見る角度……様々な要因で違った花火を楽しめる。天を目指して手を伸ばし、花開いて儚く散っていく花火。人が花火を見るように、東京タワーが人間を見ていたのなら、少しは美しかったのだろうか。
いつかすべての人を感動させる大きな花火を作りたいけれど、今はただ一人でも俺の花火に心を動かしてくれる人がいればいいと祈りながら彩り豊かな夜空を見つめていた。