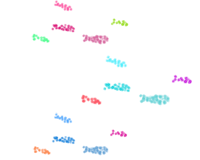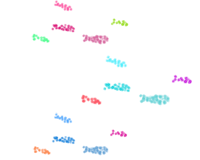
しもよ
急に泣いて、真っ赤になった目。勢いよくかまなくてもいいのに、めいっぱいかむから赤くなった鼻。それらがわからなくなるくらい、真っ赤な顔で伝えられた言葉に目の前で何かがちかちかとはじけた。
「賢二くんのことが、好きです!」
なんとなく気付いていた。なんでそんなことになったんだ、なんて思ってたくらいだ。ほかの女になら、俺のこと好きでしょ、なんて吹っかけて終わらせることも簡単だったはずなのに。いつから、だなんて聞いても無意味か。オレだって、水谷サンのことを好きになったのだって気付いたらそうなっていたんだ。いつ、とか何で、とか細かいことなんてわからない。もし、紗希乃のその気持ちがここ最近からのものでないのだとしたら、こいつはオレを励ました裏で嫌な思いもたくさんしたんじゃねーのか。
「オレは…」
お前の気持ちに応えてやることはできない。そう言おうとしたのに、なぜか紗希乃がぐっちゃぐちゃの顔のまま、にっこりと笑顔を作っているせいで言葉を続けて言えなかった。なんで、そんなに笑ってるんだ?
「知ってるよ」
「は、」
「賢二くんが、水谷さんのこと諦めないで頑張ってたこと、知ってるよ」
「……なんで、オレを励ますようなこと言ったりすんの」
「すきだから」
「…」
「ちょっとだけウソ。半分は、賢二くんに自分を重ねてただけ」
「だったらお前はずっと嫌な思いしてたんだろ、それなのに何であきらめねーんだよ」
「簡単にあきらめられるなら、最初から好きになんかなってないよ」
オレは何を当たり前のことを言ってんだ。それを体感したばかりだろうが。
「賢二くんの答えはわかってる。だって、もし、わたしが賢二くんだったら答えはひとつだもの。だけどね、ずるい奴って思われてもいいから…」
諦めないで好きなままでいてもいいですか。
笑ってるのに、涙でぐちゃぐちゃの顔。また涙が出そうになるのを頑張ってこらえてるのか、きつく結んだ口元が震えてる。なんでこいつが諦めたくないのか、こんなに泣いてまでオレを好きでいるのか理由なんて明白だ。
「オレも、諦めなかったんだ」
「うん」
「まだ忘れてなんかない」
「…そうだね」
「きっと、これからも完璧に忘れることなんてない」
「……うん」
でも、となりにいてほしいと望んだ水谷さんの代わりにお前を置いておくことはしたくない。
「わか、ってるよ」
「…もう泣くなよ。泣かしてんのオレだけどさ」
「うん…」
やっぱり、笑顔を無理やり作っていたのが崩壊してぼろぼろ泣き始めた。泣くなよ。泣かせたいわけじゃねーんだよ。今、もしも紗希乃の思いをすぐに受け入れたとしても結局は泣かせてしまうことになるだろうし、何よりそんなの嫌だ。そんな風に扱えない。お前はやっぱりオレの幼馴染で、そこらへんの女友達とはわけが違う。まあ、そいつらは泣かせないよううまくやれる自信がある。けど、紗希乃を泣かせない自信はない。だってこいつ、小さい頃はよく泣いてたんだ。最近は知らないが、この様子だと今でも変わらないんじゃないか。
「なあ」
「ぐすっ、な、なに、」
「オレは今おまえが望む答えを出すことはできないけど、ひとつだけ確実にできることがある」
「けんじくん…?」
「前みたいにしてきていい」
「は、」
「転んだとか、ぬいぐるみ汚したとか、虫がくっついてきたとか言ってこい」
「……わたし子供じゃないんだけど」
「そういうことじゃねーよ」
「じゃあなに!」
「何かあってもなくても連絡よこせばいいし、会いたきゃ呼べ。まあ、アメリカにはオレは行く気はないから呼ばれても行けねーけどな」
「な、なんで?わたしに応えれないんじゃあ、」
「オレらは幼馴染だろ」
「…」
「変な期間が空いたせいで、何の関係なのかわかんなくなってたけど、幼馴染だったんだ」
「うん」
「今は、お前の気持ちに応えられないけど、だからってもう疎遠になったりしねーよ。…まあ、そっちがもう関わりたくないっていうならそうするけどね」
「…メール、していいの?」
「アドレス知ってんだろ」
「電話、電話も!」
「時差あっても平気ならな」
「平気だよきっと」
「オレの方も考えろ」
いつのまにか流れていた涙も止まって、やたらとてかてか光ってはいるけど、紗希乃は自然に笑うようになってた。
「やっぱり、賢二くんは優しいんだね」
優しいだけだったら、こんな中途半端なことはしねーよ。