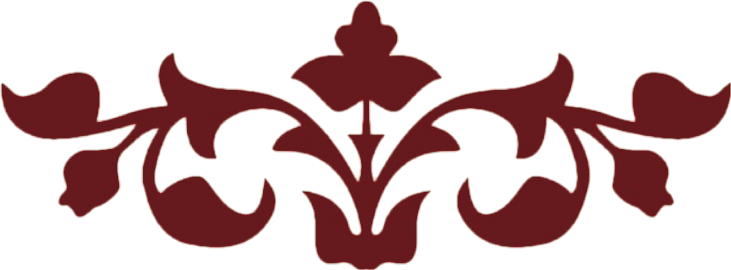
This story ends…?
東京の地に降り立ち、人の多さに噎せ返る。自分の乗りたい路線がどこにあるのかも定かではなかったけれど、看板を頼りになんとか電車に乗ることができて、とりあえず一安心。徹は今日、練習を終えたらオフだと言う。これは、徹といまだに親交の深い岩泉君からの情報だ。新幹線の中で彼に辿り着くために必死だった私が真っ先に頼ったのが岩泉君。大学時代に何度も会ったことがあり、コイツを頼む、と言ってきた人だ。岩泉君は徹と違ってバレーボール選手にはならなかったけれど、今でも頻繁に連絡を取り合っているというのは聞いていた。
平日の午前中なんて仕事で忙しいに決まっているから反応が返ってくるかどうかは賭けみたいなものだったけれど、幸運にも、メッセージはすぐに返ってきた。岩泉君はひどくすんなりと、自分が知っている情報を全て私に教えてくれたから、私の突然の連絡に何の疑問も抱いていないのかなと思ったけれど、ありがとう、とお礼を言うと、何があったのかは知らねぇが早く折り合いつけろよ、と言ってきたから、何かしら勘付いているのだろう。深くまで追求してこないあたり、とても彼らしいし有り難い。
オフの時は家かジムに行っていることが多いと聞いた私は、先に教えられたジムにやってきた。けれどもそこに徹の姿はなく、私は徹の家を目指すことにした。岩泉君によると徹の家はジムからそれほど離れていないらしいので地図アプリを頼りに歩いていた私だったけれど、こんな時に限って靴ずれしてしまったようで、休憩がてら近くのベンチに腰掛ける。
こんなヒール、履いてくるべきじゃなかったかな。でも、徹に会うなら少しでも綺麗な姿で会いたいという乙女心が勝ってしまったのだ。少し休めば痛みも和らぐだろうし、きっと家まではもう少しなはず。そう思って、足元に向けていた視線を上げた時だった。
「名前……?」
聞きなれた声が私の名前を呼んで、まさかと思いながらも通りすがりの人物に目を向ける。
「とお、る…?」
「お前…なんでこんなところにいるの…?」
なんという偶然だろう。徹の家の近くとはいえ、こんな形で遭遇できるなんて思いも寄らなかった。驚愕の表情を浮かべているのは徹の方も同じだけれど、その驚きは私よりも何倍も大きいだろう。そりゃあそうだ。私が東京に来ていること自体知らなかったのだから。
「徹に、会いに来たの」
「…なんで?」
「どうしても確認したいことがあって」
大きな瞳を僅かに見開き珍しく動揺の色を見せた徹は、私の隣に座った。ぶわりと生温かい風が吹いて、白いスカートが揺れる。暑さを物語るように蝉の鳴き声がBGMと化す中、私は徹へ視線を向けて口を開いた。
「自惚れかもしれないけど、片想いの相手って私…?」
「テレビ、見てたんだ」
「うん。だから来たんだよ」
徹は困ったように笑う。そっか、と。それだけ言って沈黙を貫く徹に、私の緊張は高まるばかりだ。違うなら違うとはっきり言ってほしい。馬鹿な女だと笑ってほしい。沈黙が、一番怖い。答えてよ、徹。返事を催促するようにそう言えば、携えていた笑みが更に柔らかさを増した。
「お前以外に、誰がいるの」
「…好きだなんて、ちゃんと言ってくれたことなかったのに?」
「言わないようにしてたんだよ」
「どうして…?」
「安っぽいかなと思って」
好きだよ、なんて言葉で表現できるほど、軽い気持ちじゃないつもりだったから。
別れてからそんなに甘ったるいセリフを吐き出す徹は、やっぱり卑怯だ。だってほら、徹のこととなるとおかしくなってしまう涙腺が、既に緩み始めてしまっている。
「じゃあ、どうして簡単に別れを受け入れたの?」
「縋りつく男ってカッコ悪いでしょ。まあ…フラれた時点でカッコ悪いんだけどさ」
「そんなの…勝手すぎるよ…、私が、どれだけ徹のこと、想ってたか…ッ」
ごめんね。
いつかと全く同じ言葉を囁くように落として。徹はゆっくりと私の身体を抱き締めた。もう泣かないと決めていた筈なのに、そんな決意を呆気なく打ち砕く温もりに、また涙が溢れ出す。折角の化粧も剥がれおちてしまって、元々整っているわけでもない私の顔は、相当ブサイクだろう。
徹はそんな私の頬に指を這わせて涙を拭ってくれた。あの時は触れられもしなかったのに、今はこんなにも優しく触れてくれる。たったそれだけのことでまた涙腺が緩むのだから困ったものだ。
徹は、ぽつりぽつりと今まで思っていたことを話してくれた。何人もの人と付き合ったことがあるのに、私に対しての距離感は図りかねていたこと。それが本気で好きになると言うことなんだと気付いてからは、私の気持ちを優先させようとしすぎて自分から連絡を取ることも躊躇っていたということ。そんな思いを抱えていたせいで容易に触れることもできなかったこと。
あんなにスマートで何でもできる徹が、私のような女のことでこんなにも頭を悩ませてくれたのだと思うと、それまでの不安なんてあっという間に吹き飛んでしまって、私って単純だなと思わずにはいられなかった。
「迎えに来てくれるって言ったけど、」
「うん」
「私、そんなに待てないから、迎えに来ちゃったよ」
「はは、男前なお姫様だね」
もう離れたくないという気持ちを込めて、見た目よりずっと逞しい身体にしがみ付く。腰にぎゅっと腕を回せば、大丈夫だよとでも言うかのように頭をゆるりと撫でられるのが心地良い。そして既に感極まっている私にとどめをさすのは、いつだって徹なのだ。
「好きだよ、」
「…っ、今言うのは、ずるいよ…」
「うん。知ってる」
「これからはもっと徹の気持ちきかせて」
「分かった」
言葉なんて安っぽくて陳腐だ。その気になれば嘘でも言えてしまうその言葉に、私は一体どれだけ飢えていたのだろう。夢を抱いていたのだろう。単純な女だと思われるかもしれないけれど、私は徹からそのたった2文字を聞いただけで、息が詰まりそうなほど胸がいっぱいになるのだ。
まだ日暮れ前の道端にあるベンチで、有名人である徹に抱き付いたままどれぐらい経過したのだろう。我に帰った私は、唐突に、家を出てくる前に見たカレンダーの日付を思い出した。
「徹、」
「ん?」
「お誕生日、おめでとう」
「……あ、そっか。今日…」
「うん。徹の誕生日でしょ?たまたまだけど、運命かもって思っちゃった」
そう。今日は徹の誕生日。付き合い始めてからなんだかんだで毎年お祝いしてきた大切な日だ。別れて復縁する日が今日だなんて、どんな神様の悪戯だろうか。けれど、先ほど徹にも言ったように、運命かも、だなんて浮かれている自分がいることも事実だ。
さすがにそろそろ離れようかと徹の胸板を押し返そうとしたところで、その距離は強引に埋められてしまった。きつく抱き締める腕の力は、これでもきっと手加減してくれているのだろう。慈しむように、ありがとう、と耳元で囁かれ、背中がぞくりと粟立つ。
「誕生日プレゼント、買いそびれちゃったからまた今度渡すね」
「いらない」
「え、でも…」
「名前以外、いらないよ」
ここが公共の場だとか。徹は有名人だからとか。全く頭に過らなかったわけではない。けれど、そういうことは全て無視して。私は、重ねられた唇に酔いしれることを選んだ。キスなんて初めてじゃないのに、初めてするみたいにドキドキするのはどうしてだろう。唇が離れてから至近距離で笑い合う空気の甘さも、たまらなく幸せだ。
きっとね、私の王子様は最初から徹しかいなかったんだよ。もう何があっても離れないから、どうかずっとこのまま、徹だけのお姫様でいさせてね。
「そういえば名前、なんでここに座ってたの?俺の家、すぐそこだけど…」
「ああ…靴ずれしちゃって…」
「こんなヒール履かなくても可愛いのに。俺のためにオシャレまでしてきてくれたの?」
「そりゃあ…まあ…」
「じゃあ今から俺の誕生日祝い、してくれる?」
「わあっ…!?」
私をひょいっと抱き抱えた徹はそのままスタスタと歩きだした。通りすがりの人に振り返られて恥ずかしいことこの上ないし、これで身体を痛めでもしたら大変だ。だから先ほどから何度もおろしてと言っているのに、徹は無視を決め込む。その顔はなんとなく満足そうで、私は諦めざるを得なかった。
まあいいか。今日だけは特別に、恥ずかしさなんて忘れて甘えてしまおう。私は徹の首に腕を回してぎゅっと抱き付くと、言い忘れていた2文字をそっとプレゼントした。