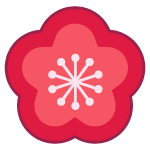
あいするひとへ
パチパチパチ、とまばらな拍手が響き渡った。夕日が差し込む二人きりの教室。教壇の上で向かい合う私と煉獄先生。十分すぎるほどのロマンチック。
「卒業おめでとう」
「ありがとうございます」
体調不良で前日の卒業式を欠席した私は、こうして担任の煉獄先生から一人卒業式を催してもらっていた。
「体調はどうだ?」
「おかげさまですっかり元気です」
にやりと笑いながら問うその表情は、私の仮病になどとっくに気付いているとでも言いたげだった。だって仕方ない。こうでもしないと煉獄先生と二人きりで話す機会なんて、もう二度とないだろうから。
「卒業証書と、卒業記念品と……これは俺からだ」
煉獄先生からだというその花束は一抱えもあるほどの豪華なもので、それなりの重さに私は少々面喰う。
「花束って人生で初めてもらいました」
そう返して煉獄先生を見ると、感慨深げに何度か頷いているその顔と目が合う。
今日で先生ともお別れだ。
私は高校に入ってからのことを思い返した。
高校に入学してすぐに、私はクラスの男子に恋をした。彼は歴史が好きだったこともあり、よく煉獄先生と話をしていた。そして日本史の成績はいつも学年一位だった。
私はといえば、その煉獄先生が授業を教えるのが抜群にうまかったこともあり、苦手だった日本史の成績が伸び始めた。理解が進むとどんどん興味がわいてきて、私も煉獄先生とよく話すようになったし、積極的に補習を申し出るようになった。先生はいつでも笑顔で引き受けてくれ、どんどん接する機会が増えるようになった。やがて私は日本史の成績で学年一位を取るようになった。好きだった彼を差し置いて。
その時の彼の驚愕と落胆ぶりといったらすごかった。次第に彼は私につらく当たるようになり、陰口をたたくようになった。その頃には、彼を好きだという気持ちはとっくに消え失せていた。
代わりに私の恋心が煉獄先生に向かったのは自然な流れだった。ある日の放課後の補習中、私は先生にこう訊ねた。
「私が先生のこと好きって言ったら、困りますか?」
煉獄先生はいつもの笑顔を少しだけ崩して、
「……困るな」
と小さく答えた。そのらしくない様にはちょっとだけ笑えた。
「どうしてですか? 先生と生徒だから?」
「そうだ」
「じゃあ、生徒じゃなければ付き合えるの?」
「それは答えられん」
「……もしも可能性があるのなら、私は今すぐ学校を辞めます」
その頃、好きだった彼から私への嫌がらせや陰口はひどくなっていて、正直に言うと少しつらい時期でもあった。学校を辞めるのもありかな、とぼんやり思っていたところだ。
私の言葉に、煉獄先生は少し厳しい表情をした。
「君は、もしも俺が君との色恋に浮かれて学校を辞めるということになったら嬉しいのか?」
私は黙って首を振った。
「例の彼が今、君に厳しく当たっていることは知っている。何人もの先生方が指導を繰り返しているし、俺もその内の一人だ」
「ありがとうございます」
「力が及ばず不甲斐ない。しかしそんな中でも君が俺を信頼し、好意を寄せてくれていることは非常に嬉しい。だが、教師と生徒という立場を壊すわけにはいかない」
「わかっています。困らせてしまって、すみません」
私は教師の立場を貫いた煉獄先生を尊敬した。しかし同時に、これ以上彼を困らせてはいけないこともわかっていた。その日以来、私は一度も煉獄先生に補習は申し込まなかったし、意識して距離を置いていた。二者面談の時ですら、事務的な態度を貫いた。それでも日本史の勉強は三年間しっかり続けて、先日、日本史を専攻とする第一志望の大学に無事合格した。先生方の指導の賜物なのか、とっくに彼からの嫌がらせも止んでいた。それがいつ止んだのかわからないほど、私は勉強に没頭していた。
そして今日、卒業証書を受け取っている。
「こんなに豪華な花束もらっちゃったら、もう誰からもらっても喜べないかも」
私は花束を抱え直して先生に微笑む。先生は私に微笑み返して意味深な言葉を放った。
「それは心配には及ばん」
その意味を問おうとした時、私の携帯が鳴った。母からの電話だった。出てみると、もう車で迎えに来ているということだった。
「それでは煉獄先生。お世話になりました」
私が去ろうとすると、煉獄先生は腕をぐっと引き、ぎゅっと強く抱き寄せてきた。
初めての感覚に体中が熱くなる。煉獄先生の腕の中。服越しに感じる心音、体温、匂い。わかっている、これが最後の餞別だってこと。今だけ、もう少しだけ、この時間が続けばいいのに。
煉獄先生は、私を抱きしめていた腕を解くと、今度は私の左手を取ってそのまま手の甲にキスをした。
唇が触れた箇所から熱を持ち、あまりのことにブルブルと震える。何故、先生、どうして。
煉獄先生は手の甲に口づけたまま視線だけを私に寄越す。その視線からは卒業を祝っている以外の何かが読み取れそうな気がして、でもそれは私の都合の良い勘違いかもしれなくて……私は真意を測り損ねながら、煉獄先生の燃える目を潤む瞳で見つめた。
「煉獄先生……わたし」
濡れた声で呼ぶと、煉獄先生は私の両手首を壁際に押し付け、唇を奪った。先生、先生。どういうつもりなの? 私に思い出をくれてるの?
初めてのキスに困惑していると、煉獄先生の舌が口づけたままの私の唇を味わうようになぞった。その感触にぞわりと快楽が走り、力が緩む。その瞬間を狙って煉獄先生の舌が私の口内に侵入すると、もう後は好きなように犯されるだけだった。
放課後の教室に響き渡る欲情した息遣い。唾液の絡む音。互いに角度を変えて何度もキスを送り合いながら、それでも私は煉獄先生の気持ちがわからない。
しかしその時間は突然終わりを告げる。再び鳴り響いた携帯の音で、急速に現実に立ち返った私たちは、見つめ合ったまま何も言わなかった。やがて私は荷物を手に教室に背を向け、勢いに任せて廊下をバタバタと走った。
もういいんだ、忘れるんだ。恋は叶わなかったけれど、先生のおかげで私の人生は大きく変わった。それだけでもう十分。私は先生の連絡先も知らないし、きっともう一生会うことはない。先生に恋する、なんて甘酸っぱい青春の思い出。卒業の日に夕日の差し込む教室で大好きな先生とキス。うん、いい思い出だ。大学生活でも定番の恋の話としてきっと私は話すだろう。そうしていつか、思い出に変わるのを待つのだ。この胸の痛みが風化した頃、素敵な人と出会って恋に落ちて……やがて忘れるのだ。
「お母さん、お待たせ」
私は涙を拭って、母の待つ車へと乗りこんだ。助手席に腰かけてシートベルトをカチッと嵌める。母は笑って、私の髪を優しく撫でた。
「卒業おめでとう。煉獄先生にはご挨拶できたの?」
「うん」
「それにしても……あんた、ずいぶん豪華なのもらってきたわね」
母が私の荷物を見て心底驚いたように言った。
「うん、この花束、本当凄いよね。びっくりした」
「花束もそうだけど、そっちの紙袋よ。超高級ブランドのじゃない。何が入ってるの? お母さんの時なんか紅白饅頭だけだったわよ」
「そうなんだ。じゃあ、高級な紅白饅頭なのかな」
母と笑って、私は花束と卒業証書を後部座席に置いた。そして、母が高級ブランドだと指摘した紙袋の中を開いていく。
中にはメッセージカードとラッピングされた小箱が入っていた。まずはカードを開いてみる。
「何て書いてあったの?」
車を発進させた母が横目で問う。
「……うん。卒業おめでとう、って」
母の言葉に内心の動揺を隠しながら答える。確かにメッセージカードにはそう書かれていた。ただし、差出人は「煉獄杏寿郎」となっている上に、連絡先が書かれている。
急激に胸が高鳴り始める。私は今日、先生への気持ちからも卒業しようと決めていたのに。
小箱の中身は腕時計だった。上質なシルバーに丸い盤面。十二時と六時に宝石がはめ込まれている。私の誕生石だった。
何気なく裏を見ると、何やら英語が刻印されていた。一瞬苦手意識に苛まれるが、それは受験を終えてすっかりなまった頭でも容易に理解できるような、ありふれた愛の言葉だった。
「……ねぇお母さん」
「んー?」
赤信号の時を狙って話しかける。私の熱くなった頬に、母は気付いているだろうか。
「学校の先生と恋愛するのって、どう思う?」
少しの沈黙の後、母は何かを察したようにさっぱりと言った。
「別にいいんじゃない? もう卒業したんだし」
「……そうだよね」
桜が散る街路樹を車窓から眺めて、私はそれきり黙った。
「あんた、学校戻る?」
見かねた母の提案に、私は口許の緩みを隠しながら大きく頷く。チラリと見ると、母の方がニヤニヤしているようだ。
「……うん」
母がウインカーを出して車を右の車線に寄せる。
――私は今日、高校を卒業した。