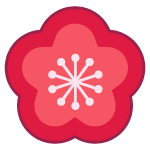
あまのじゃくに恋して
「おい、醜女。こっちを手伝え」
仏頂面で私に命令するのは考えるまでもなく愈史郎だ。もはや慣れたその呼び名に今更反応するまでもなく、「なに?」とこちらもいつも通りの無表情で問い返す。
「珠世様が必要と言っているんだ。さっさとこの荷物を地下に運べ」
愈史郎が指さしたのはいくつもある木箱だった。結構な大きさだが、持ち上げてみると意外に軽い。だがいかんせん量が多い。一人ではとても難しそうだ。
「これね、わかった。でも、愈史郎も手伝ってよ。一人じゃこの量は……」
「手伝うだと?」
愈史郎の眉がぴくっと動く。ギクッとした。何か地雷を踏んだだろうか。
「いいか。珠世様を一番に支えているのはこの俺だ。つまり、下っ端はお前の方なんだよ。俺がお前の手伝いなどするか」
「……はいはい」
何こいつ、ウザ……と思うが、いちいち言い合いをしていては時間がもったいない。まぁ、私たち鬼には時間はたくさんあるけれど。
「さっさとお前も来い!」
そう言ってテキパキと率先して荷物を抱える愈史郎。そう、わかりにくいが、今のは「手伝わない」と言ったわけではなく、「俺の方がたくさん運ぶから手伝っているのはお前の方」だと言っているのだ。本当にめんどくさい男である。
珠世様に鬼にしてもらってどれくらいの歳月が経っただろう。私は鬼にされたことを恨んでなどもちろんないし、珠世様を敬愛している。研究にも役立ちたいから、できることもできないことも何でも進んで申し出ている。珠世様が大好きだ。
しかしそれは彼も同じで、私より長く珠世様といる分、愈史郎の思いの方がずっと強い。「珠世様!」と呼び掛けてはハートを飛ばしている姿の時だけは、私より幼くして鬼になった彼の表情を年相応に見せかけた。
「はい、これでおしまい……と」
「二人とも。疲れたでしょう。今日はもうお休みなさい」
珠世様が私たちを気遣って顔を出してくださる。いえそんな、と言いかけた私を遮ったのは、やはり愈史郎だった。ドン、と突き飛ばされて思わずよろける。こいつ。
「いえ、珠世様! 俺はもちろん、こいつなんてもっともっとこき使ってやればいいんですよ」
もう怒った。私も愈史郎を思いきり突き飛ばす。私以上に愈史郎が吹っ飛ぶ。いい気味だ。
「そうです、珠世様! 私はまだまだ働けます! 愈史郎よりもお役に立てます!」
「何だと、この醜女が!」
「愈史郎〜!」
ギリギリと睨み合う私達に珠世様はおろおろするばかりだ。しかし、私にはとっておきがある。それを思い出した私はふふん、と笑い愈史郎を見下した。
「愈史郎、そんな態度でいいと思ってるの? あの言葉言っちゃうよ?」
「なっ……ま、待て……」
途端に愈史郎が狼狽し始める。愈史郎は私の「奥義」を知っている。いつもならここで許すけれど、今日の私は止める気はなかった。
咳払いしてほんの少しだけ声色を変える。愈史郎はわなわなと震えて恐怖の表情を貼り付けた。
「愈史郎。あなたのことが嫌いです。今すぐ出てお行きなさい」
「なぁっ……!」
ガーン、という効果音が背後に見えそうなほどに絶望した愈史郎がとぼとぼと部屋に戻っていった。その後ろ姿を見送り、少しだけ優位な気持ちになる。
珠世様が額に手を当て、やれやれと言った様子で私を嗜めた。
「いけませんよ、名前。愈史郎に意地悪をしては。私に似た声を悪用するんじゃありません」
「……はーい」
珠世様に軽く叱られて舌を出す。本当に、珠世様の言う通りだ。
私の声は珠世様にとても似ていた。それはあの愈史郎ですら認めるところでもある。愈史郎が調子に乗った時には、こうした「奥義」で彼を黙らせていた。
しかし、不思議なものだ。人間だった頃の私の実年齢は愈史郎よりも大人だったし、つまらない喧嘩などしない性格だった。気が小さかったり弱かったりしたわけではないけれど、誰かと争うことは特別なかったと思う。
それが、愈史郎相手だとどうしてかこうなってしまうのだ。きっと愈史郎が特別独占欲の強い性格だからなのだろう。全く、厄介な男もいたものだ。
「それでは、珠世様。私もそろそろ休ませていただきます」
「わかりました。私は今夜から出かけます。愈史郎のことを頼みましたよ」
「はーい」
愈史郎は私なんかに世話を頼まれたくないだろうな、と思いながら、珠世様の儚げな背中を見送った。最近、珠世様は外出が多い。元より何かとお忙しい方だ。
明日になったら愈史郎が嘆くのは目に見えていた。
翌日になって珠世様がいないことを知った愈史郎は、思った通り、あからさまにがっかりしていた。
「あぁ……珠世様……ご無事だろうか。今頃どこに……」
昨日とは別人のようにうじうじした姿にイライラする。こいつは私の神経を逆撫でする天才なのか。たった一日出かけているくらいで。
「別に大丈夫だよ。珠世様はしっかりされているし。ちゃんと用事で出て行ったんだから」
「お前に何がわかる、醜女。珠世様はあの美しさだぞ。お前は醜いからわからないかもしれないが、あの美しさで何もない方がおかしいんだ」
「何かあってほしいのかほしくないのかどっちなのよ」
呆れて思わず息を吐く。本当に、珠世様のことばかり。
そんな愈史郎のことは放って、私はひたすら屋敷の中を掃除した。愈史郎はというと、頻繁にため息を吐きながら箒で床を掃いている。その陰鬱さといったら、掃除しているそばから空気が汚れそうなほどだった。
その姿を見ていたら、さすがにちょっと可哀想かな、と思い始める。今なら普段の狂暴さもなりを潜めているし、少しくらい特別扱いしてあげようという気持ちになった。
「ねぇ、愈史郎。珠世様の声が聞きたい?」
「当たり前だろ……声が聞きたい。姿が見たい。あぁ、珠世様ぁ……」
「……いけませんよ、愈史郎。そんなことでは」
「珠世様!?」
私の言葉に愈史郎がパッと瞳を輝かせる。しかし声の主が私だと知ると、少しだけ落ち込んだ様子をして見せた。
「なんだ、お前か……」
「まぁまぁ、元気出してよ。何かご希望があれば言ってあげようか?」
「そうだな……」
うーむ、と少し考えた様子をして見せる。元気が出たみたいでよかった、と私は少し安堵した。
「試しに愛の言葉を囁いてみてくれ」
「えー……」
まさかの要求にドキッとした。涼しい顔してなんて強欲なんだ。仕方ないな、と呟いて咳払いする。珠世様の愛の言葉なんて聞いたことがないし、ここは適当に捏造するか。
「愈史郎、愛していますよ。これからも私達は一緒です。……こんな感じ?」
適当に取り繕った台詞に、愈史郎は口をポカンと開けて固まった。あんまり珠世様っぽくなかったかな?
「……何赤くなってんの?」
「は!? なってないだろ! お前、目が腐っているんじゃないのか!?」
「もう言わないからね! これ以上の変な要求は珠世様への侮辱になる!」
「お前が言い出したんだろ! 変な要求なんかするか!」
それから少しだけ上機嫌になった愈史郎と掃除をしたが、目に見えて効率が良くなった様には私も呆れたほどだ。本当に、珠世様のことが大好きなんだなぁ。
「私だって……」
「何か言ったか、名前?」
何となく面白くなくて呟くと、耳聡く聞きつけた愈史郎が寄ってくる。思いの外至近距離に寄ってきたものだから、思わずびっくりして後ずさった。油断していたが、愈史郎は意外に端正な顔立ちをしていたりするのだ。
「……別に」
「……ふん」
愈史郎が私を名前で呼ぶのは、本当に上機嫌の時だけだ。
珠世様を真似ただけの言葉で、そんなに元気出ちゃうわけ? 本人が言ってるわけでもないのに、馬鹿みたい。
なぜだかわからないけど、さっきまでの愈史郎よりも更に元気をなくした私は、早々に掃除を切り上げて部屋に戻った。
それからも愈史郎は、珠世様が数日外出して寂しさが募った時に限って、私に声真似をねだるようになった。
「珠世様がもう三日も戻って来ない……おい名前。いつものやつだ」
「愈史郎。名前を困らせてはなりません。仲良くしなさい」
「ぐぅっ……珠世様ぁ……!」
馬鹿みたいな話だが、明らかに発言しているのは私なのに、愈史郎はこれで結構言うことを聞くようになった。
だけど、最初に調子に乗って愛の言葉を言わせて以来、愈史郎はその類の言葉を一度も要求しなかった。本人が言ったり思っていないことを声の似た私に口にさせるのは珠世様への侮辱になる、ということを彼なりにわかっているのだろう。
「以前よりも二人の仲が良くなったようですね」
ある日、私が倉庫で荷物を整理していると珠世様が微笑みながらそんなことを仰った。確かに言い合いは少なくなったかもしれないが、果たして仲良くなったと言えるだろうか? 私は首を傾げながら答える。
「確かに、前よりは喧嘩は減りましたけど……」
「素晴らしいことです。二人が仲良くしてくれて私は嬉しいですよ」
「え、ほんとですか……?」
「もちろんです」
私たちが仲良くすることが珠世様の喜びにつながる。こんな当然のことに、どうして気が付かなかったのだろう。
お役に立てた喜びでニヤけながら、私は愈史郎の元へ急いだ。確か今は部屋にいたはずだ。
「ねぇ、愈史郎!」
資料を読み耽る愈史郎が視線だけを私に向けた。足を組んで頬杖をついたその姿は、意外に様になっていた。
「なんだ?」
「珠世様、私達が仲良いと嬉しいんだって。だからもっと、仲よくしよ?」
私の言葉に愈史郎はなぜかむっとした表情をして見せた。今の発言からは想像できない反応に私は目を見開く。
「……ああ」
たっぷりの沈黙の後、愈史郎は一言だけそう言った。そしてそれ以上は何も言わずに資料に目を戻した。もう私に用はない、という意思表示なのだろう。
珠世様の嬉しい話なら、せっかく喜ぶと思ったのに……。少し残念な気持ちになる。機嫌が悪かったのだろうか。それにしても、あんなに冷たい態度取らなくたって……。
残念を通り越してむしろ悲しい気持ちだ。私は涙をこっそり拭って、倉庫の整理に戻ったのだった。
「今日も珠世様、お出かけだね」
「ああ」
本棚を整理する愈史郎に声をかける。彼は手も止めずに先日通りの素っ気ない態度で頷いた。
あれから愈史郎はずっとこんな態度だ。以前とは違い喧嘩にはならないものの、そっちの方がずっとましだったと思うほどの冷たい態度。どんなに考えてみても何も思い当たらない。むしろ、仲良くなったと珠世様に褒められたばかりだったのに。その矢先にこれだなんて。
「愈史郎、また寂しいの?」
「寂しいに決まっているだろ」
「じゃあ、あれやろっか?」
私はなんとか愈史郎の機嫌を取りたかった。癪なことだが、いつまでも気まずいままでは調子が出ない。
しかし彼は、
「今日はいい」
と冷たく私をあしらった。
「え、何で?」
「今日は気分じゃない」
「……ふーん? あのさ、なんか最近、変じゃない? 珠世様も喜ぶし、もっと仲良くしようよ」
思い切って素直に言うと、愈史郎は私をキッと睨みつけた。彼の持っていた本が床に叩きつけられる。私はびっくりして身をすくませた。
「お前は、珠世様が喜ぶから俺と仲良くするのか?」
「えっ?」
なぜ愈史郎が怒っているのかわからなかった。どことなくバツが悪そうなその表情に、はじめは呆気にとられたが、だんだんと怒りが湧き上がってくる。何故、こんな態度を取られなければならないのか。先ほどの愈史郎と同じように彼を睨みつけることで勢いをつける。
「何で怒ってるの? それは愈史郎も一緒じゃん! いっつも私のこと邪険にして!」
「最近はしてないだろ!」
「それは私の声が珠世様に似てるからじゃん!」
「あのな……!」
愈史郎は何かを言おうと口を開いた。しかしすぐにハッとしたように口を閉じ、言葉を飲み込んでしまう。
「今、何か言おうとしたでしょ?」
「してない」
「気になるから言ってよ!」
「うるさい! さっさと手を動かせ!」
結局いつもの展開だ。どうしてこうなるんだろう。私は別に愈史郎と喧嘩したいわけじゃないのに。確かに私は、愈史郎と珠世様の二人の世界に入り込んだ邪魔者だ。最初から私を気に食わないのはわかる。それでも私は仲良くしようとしてるのに。
これからもこんな日々が続くのかと思うと、もううんざりだった。
「……もういい。私、出てくね。今までお世話になりました」
投げやりになって宣言し、愈史郎に背を向けて部屋を出――ようとした。
「……なに、この手は」
右手ががっしりと掴まれ、それ以上一歩も進むことができない。私は振り返らなかった。今更何だというのだろうか。
「離して」
「……悪かった」
「そんなこと思ってもいないくせに。私が出ていったら珠世様に叱られるから、仕方なく止めてるんでしょ?」
愈史郎は答えなかった。やはり、そういうことなのだろう。少しでも否定してほしいと思ってしまった自分の愚かさをあらためて感じる。
「別に愈史郎のせいにはしないから。珠世様には手紙書いていくし……それならいいでしょ? 早く離して」
私の言葉とは反対に、掴まれた腕の力がどんどん強くなる。痛みを感じるほどだった。
「痛いよ、愈史郎」
「こっち向けよ」
「何でよ」
「いいから向けって」
涙目になりながら振り返る。私の涙に愈史郎はたじろいだ。男なんて古今東西、女の涙に弱いんだ。くだらない。悔しい。やり返してやりたい。
私は咳払いして、声の調子を整えた。使ってやる、奥義を。度肝を抜かれて傷つくがいい。ものすごく酷いことを言ってやる。
私は愈史郎を睨みつけてから息を吸った。
「愈史郎。あなたのことが」
ギクリとした様子で腕の力を緩めた愈史郎が、顔を引きつらせて私を見る。
「好きです」
珠世様に酷似した声でそう言うと、愈史郎の顔がみるみる真っ赤になる。ポカンと口を開けた間抜け面。この前と同じだった。
「……珠世様はそんなこと仰らない」
愈史郎が顔を真っ赤にしたまま虚しいことを呟く。……どうして彼は気付かないのだろう。
「そんなことありませんよ。愈史郎のことが大好きです」
「珠世様は、珠世様は……」
パクパクと口を開け閉めして間抜けに繰り返す愈史郎に、私はふっと息を吐いた。
「……そうだよ。珠世様はこんなこと言わないよ。残念だけどね」
「そんなことはわかってる」
私は声を戻して意地悪く返答した。そう、所詮こんなのは捏造だ。声がいくら珠世様に似ていても、言っているのはこの私。
「だから俺にはその言葉を……お前が……名前が言っているように聞こえる」
なんて鈍い男なのだろう。だけど私も素直じゃないから、そうだよ、なんて絶対言ってやらない。
愈史郎は私を掴んでいた手を放すと、壁際に私を突き飛ばした。そのままじりじりと寄ってくると、今度は私の顔のすぐ横をドン、と平手で叩き、私を覗き込むように見下ろしてくる。耳のすぐ横で鳴り響いた音に、私は抗議の意味で顔を上げた。向こうも相変わらずの仏頂面で見返してくる。少しだけ赤面しているのがいい気味だった。
やがて私は愈史郎を睨みつけたまま、
「どうかな」
とだけ冷たく返して、目の前の唇に噛みついた。