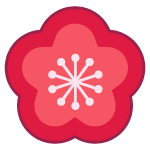
愛で餌付けする
体育館裏に呼び出されるといったら、何を想像するだろうか。その一、告白される。その二、ヤキを入れられる。その三……は、私にはあまり思い浮かばない。実はその三があろうがなかろうがどうでもいい。その二すら私にはどうでもいい。私への呼び出しは、100%が「その一」だからだ。外れたことは一度もない。
だから今日、体育館裏に呼び出されても、既に頭の中は「何と言って断ろう」だった。相手はバスケ部のエースの一つ先輩。面識は……ない。
「苗字さん……君のことが好きなんだ」
「ごめんなさい」
即答した私に、バスケ部エースは口を開けたまま固まった。恐らくこれから、「初めて見かけた時から」とか、「委員会での真面目な姿で」とか何とか私を好きになってくれた理由で告白の詰めに入る予定だったのだろう。
告白を断る時には、少しでも迷った素振りを見せないことにしていた。そうした逡巡は気を持たせることになるからだ。高校生になっても一度も人を好きになったことがないのはおかしいだろうか? もしそうだとしても、焦って好きでもない人と付き合いたくはない。好きでもない人を好きだとは言いたくない。だから素直に「ごめんなさい」に限る。
「そっ……か……」
「お気持ちは嬉しいです。これからも部活、頑張ってください。さようなら」
私は彼の未来へエールを送り、さっさとその場を切り上げた。気持ちが嬉しいのは嘘ではない。何で私を好きになってくれたのかはよくわからないが、とてもありがたいのは事実である。
放課後の廊下は人が少ない。荷物を取りに教室へ戻った私がドアに手をかけた時、中から男女の話し声が聞こえた。まだ誰か残っているのかな、と思いながらも迷いなく扉を開けると、クラスメートの男子と隣のクラスの女子生徒がいた。女子生徒が男子生徒に抱き着いている。
これは邪魔したな、と思う。気まずいながらも私は廊下側の自席にあった荷物を無言で掴み、教室を出た。
男子生徒の名前はわかる。クラスメートの嘴平伊之助。いっつも制服を着崩している上に、学校に弁当しか持ってこないふざけたやつだ。そのくせ顔だけはいいからやたらとモテている。女子生徒は選択授業の調理実習で同じクラスだが、名前は知らない。早速明日の調理実習で彼女と顔を合わせることを思うと、なんだか少し気まずい思いがした。
翌日になり、午前中の2時間の選択授業を受けるために私は調理室へ向かった。私は料理部でもあるため、調理室は学校の中でもなじみ深い。黒板には先生が指定した毎回変わる班分けと、下ごしらえの手順が書いてあった。私は自分に割り当てられた窓に近い調理スペースに行った。机の上にはいくつかの食材と調味料が並べられている。私はそれらを手で弄びながら、窓の外をぼんやりと見つめた。体育を選択している生徒たちが楽しそうに駆け回っているが、何をしているのかはよくわからなかった。
調理室近くの水道に何人かの男子生徒が水分補給に訪れていた。その中には嘴平くんの姿も見える。昨日の光景が脳裏に蘇り、なんだか気まずい気持ちになった。あらためて彼の顔を見てみる。確かに顔はかっこいい、かもしれない、けれど。
「おい、苗字」
水道から顔を上げた嘴平くんが声を上げた。目が合ってしまう。私に声をかけているのは明らかだった。
「え、なに?」
「これから飯作んのか?」
どうやら私ではなく手の中の食材に用があるらしい。さすが弁当しか持ってこない男。
「そうだよ。調理実習だからね」
「何作るんだ?」
「今日は鶏のから揚げとか」
「後で俺に食わせろ!」
「えっ、やだよ! 何で?」
まさか初めて話すクラスメートに食事を要求されるとは思わなかった。びっくりして少々声が大きくなってしまう。
「はぁーん? 食いてぇからに決まってんだろ! それ以外にあるかよ!」
それはそうなんだろうけれど、と行動が読めない彼に首をひねっていると、私の背後から可愛らしい声が聞こえた。
「じゃあ、私が作ったのをあげるよ」
思わず振り返ると、昨日、嘴平くんに抱き着いていた女の子が立っていた。今日はこの子と同じ班なのかな、と冷静に考える。
その女の子は可愛らしい声で続けた。
「伊之助くん、食べるの大好きだもんね?」
「……お前のはいらない」
少しだけ低い声でそれだけ言うと、嘴平くんはグラウンドに駆けて行ってしまった。
女の子はふぅ、とため息を吐いて、何事もなかったかのように私の隣に座る。
「昨日、嘴平くんにフラれちゃったんだ」
「あ……そ、そうなんだ……」
よくよく思い返してみると、確かに昨日の彼は彼女を抱きしめ返してはいなかった。きっと、彼女の一方的な片思いだったのだろう。それならあの警戒した様子も少しはわかる気がする。
「食べ物で釣ればいけると思ったんだけどなぁ」
「彼のどこが好きだったの?」
思わず気になって聞いてしまう。まるで餌付けでもしようかというその態度に、果たして愛はあるのか?
彼女はうーん、と少し悩んだ素振りを見せてから、
「……どこだろう?」
と言った。
「顔は普通にかっこいいし、ワイルドで素敵かなって思って」
「そっか。フラれちゃったのは残念だけど、元気出してね」
「ありがと。もう次の人探してるから大丈夫だよ」
その発言に私は唖然とした。イマドキ女子は積極的だな、なんて年寄りのような考えが脳裏を過ぎる。
チャイムと同時に先生が入ってくると、今日の調理の手順を軽く説明した。残りの一人も班に加わり、私達は三人で唐揚げ作りにとりかかったのだった。
なかなかおいしくできた唐揚げを食べながら、実習後の後片づけをする。私と彼女はあれきり喋らなかった。もう一人の班員も寡黙な女子だった。私達はただ職人のごとく黙々と唐揚げを作った。まるで唐揚げ屋の店員のようだった。
廊下が騒がしくなる。体育を早めに終えた生徒たちが調理室の扉を開けた。先生も寛容だから、「量が多い班の子は分けてあげて」なんて言っている。私はそんなつもりはなかったので、聞こえないふりをして唐揚げをいくつかつまんでいた。
「おい、苗字」
ガタガタと椅子を動かして、誰かが私の前に座った。いや、確認しなくてもわかる。嘴平くんだ。唐揚げを奪いに来たのだ。
「食うからな!」
「だめっ」
「なんでだよ!」
唐揚げの山の中から勝手に一つ取ろうとする。すると彼は律義に手を止めた。少し意外だった。
「……こっちの方がおいしいよ」
そんなに食べたいのなら、と親切心が顔を出す。
もう一つの揚げたての山を指差し、私は自分でも食べようと箸で一つのから揚げをはさんだ。しかし間もなく口に入ろうかというその瞬間、
「じゃあ、それ寄越せよ」
と言った嘴平くんが、私の唐揚げを奪い去ってしまった。それも、口で。
「えっ……」
私は驚いて慌てて椅子から立ち上がった。私が動じたのは至近距離で見た嘴平くんの顔が思いの外綺麗だったからだけではない。ほんのわずかに唇同士が触れてしまったからだ。
え、キスしたの、私? ファーストキスって唐揚げ味なの?
調理室中がざわつき、色めき立つ。「あの二人、付き合ってたの?」という誤解も甚だしいたくさんの声が鼓膜を震わせる。
しかし嘴平くんは素知らぬ顔で唐揚げを咀嚼していた。
「うめぇ! 苗字、なかなかやるな! 俺様の子分にしてやってもいいぜ!」
歓喜の声を上げた彼は更に唐揚げに手を伸ばす。
私は数秒遅れて、カチャン、と箸を取り落とした。
「なぁ、今日は何作んだよ?」
放課後の人がまばらな教室。嘴平くんはわざわざ私の席まで来て訊ねた。もう教室に残っている生徒は少ないから、声が無駄に響いて仕方ない。私はここしばらく、こうした彼の言動に頭を抱えている。
あれから私が料理部だと知った嘴平くんは、ことあるごとに纏わりついてくるようになった。おかげで、私達が付き合っているという噂は調理室に留まらず、そこかしこで流れるようになった。言いふらしているのは、この前嘴平くんにフラれたばかりのあの彼女だ。
その噂は私の親しい友人の耳にも入っており、なんと「名前、嘴平くんと付き合ってたんだね」、「だからいつも告白断ってたんだ」、「早く教えてくれたらよかったのに」なんて口々に言われてしまった。例のバスケ部エースの先輩でさえ、「苗字さん、彼氏がいたんだね。お幸せに」とわざわざ私の教室まで言いに来た。違うと言ったのに全く信じてくれない。彼は本当に私のことを好きだったのだろうか。
「今日はカップケーキだよ」
「甘いものも悪くねぇな! 早速食いに行くぜ!」
「あげるなんて一言も言ってないけど」
私がそう言うと嘴平くんは、はんっ、と笑った。何だかんだで彼が調理室に現れたら作ったものを分けずにいられない私に、彼は気付いているのだろう。なんだか手の平の上で転がされているようであまりいい気分ではない。
「あのね、あなたと私が付き合ってるって噂になってるの」
ここらできちんと釘を刺しておこうと、嘴平くんの目を見てはっきり告げる。嘴平くんは二、三回瞬きをしてから首をひねった。
「それが何だよ」
「え……何っていうか、迷惑……」
あっけらかんとした物言いに、私がおかしいのではないかと口ごもる。
「迷惑してるってのか?」
頷きかけた首が固まる。私は迷惑しているのだろうか? いや、冷静になってみるとそうでもないかもしれない。何しろ噂のおかげであれだけ断るのに苦労していた告白が激減したのだから。むしろ迷惑どころか大感謝だ。特に好きな人がいるわけでもないから、誤解されたくない男子などいない。つまり私は、別に困ってなどいない。
「迷惑、してなかった」
考えた末にポツリとつぶやく。
「じゃ、噂なんて放っとけよ。くだらねぇ」
「……うん」
嘴平くんは二人分の荷物を持って、さっさと調理室へと歩き出した。
調理室に着くと、部長に適当に班分けされた。エプロンをつけて手を洗い早速調理に取り掛かる。先ほど彼に宣言した通り、今日はカップケーキを作ることになっていた。嘴平くんは物珍しいのか調理室の隅であちこち視線をさまよわせている。子供みたいで可愛い。
「ね、名前。今日も彼氏一緒だね。超ラブラブで羨ましい」
同じ班になった友人が私をからかう。こういう時はやっぱり少し迷惑かもしれない。
「……そういう感じじゃないけどね」
私はそうお茶を濁したが、友人はなおも追撃してくる。
「そう? さっきだって荷物持ってくれてたし、愛されてるって感じだよ」
「愛されてる……?」
顔をしかめながら、凡そ私達の関係とは似つかわしくない言葉を復唱した。そもそも、私達って一体どんな関係なんだろうか。
それからも和やかに調理が進み、カップケーキがうまく焼きあがった。この後は生クリームやチョコスプレ―等で簡素なケーキを飾りつけて、色とりどりのケーキへと変身させる。途中、部員の何人かがSNSに写真を投稿していた。料理部は何かとウケがいいらしいとどこかで聞いたことがある。
「名前! 早く食わせろ!」
焼きたてのいい匂いにつられて馴れ馴れしく呼びかけてきた嘴平くんが私の元へやってくる。何勝手に呼び捨てしてるんだ、と思いながらよくできたケーキを一つ差し出した。周りの部員が私達をニヤニヤと見ている。
「はい、どうぞ」
「おう!」
渡したカップケーキは一口で嘴平くんの口の中に消えた。せっかく綺麗に飾り付けたというのに、なんて儚いことだろうか。あーあ、と思いながら私もケーキにフォークを入れ、自らの口へと運んだ。うん、おいしい。我ながらよくできている。
私が一つのケーキを大切に味わっている頃、嘴平くんはといえば私の焼き上がり分を全て平らげてしまっていた。気付いたときには手遅れだった。いくつもあったケーキは姿を消し、空のトレイが残っているだけ。私は愕然となりながら嘴平くんに向き直る。
「全部食べちゃったの!?」
「もちろん、食ったぜ!」
当然だろ、というような声音と表情に、私は小声で抗議する。
「ちょっとくらい残してくれても……」
「うまかったんだから仕方ねぇだろ!」
「全然、仕方なくないよ!」
「腹減ってたんだよ! 悪いか!」
「他の班からももらってくればいいじゃない! 何で私のばっかり食べちゃうの!?」
だんだんヒートアップした私を見ても全く動じず、嘴平くんは堂々と言った。
「名前のが食べたいんだからしょうがねぇだろ!」
その開き直りようといったらなかった。私は食べ物の恨みからつい声を荒げてしまう。
「せっかくおいしくできたのにひどい! 謝って! 謝らないなら、もう他の誰からも一生食べ物もらわないで! そんなに私の料理が気に入ったってことだもんね!?」
私の大声に部員たちがざわつきながら振り向く。その妙な雰囲気に気付けるほど、私は冷静ではなかった。
「わかった」
嘴平くんはあっさり頷いた。つまり彼は謝らないということなのだ。食い意地の張った彼が、他の人からの食べ物を犠牲にしてでも謝りたくないということが、私には全く理解できなかった。
どうしても気が治まらなかった私は、具体的に駄目押しをしていく。
「本当にいいのね? ハロウィンもバレンタインも誕生日も私以外からもらっちゃダメだからね! きっとみんなたくさんおいしいものくれようとするだろうけど、絶対に受け取っちゃダメだから。それが無理なら謝って!」
「わかったっつってんだろ!」
怒鳴り返した嘴平くんを睨みながら、私は憤然と椅子に座った。私は自分のケーキの残り一口を口に放り込む。ほら、こんなにおいしいのに。もう一個もないなんて。
「もう名前からしか食い物はもらわねぇよ」
恨みがましく嘴平くんを見遣ると、彼が何かに気付いたように目を見開いた。私の唇に視線が注ぐ。
「おい、チョコついてんぞ」
その言葉と同時に、嘴平くんが私の唇をぺろりと舐めた。その意味を理解するまでに私の脳が数秒を要する。ようやく脳が演算を終えた時には、私の頬はとても熱くなっていた。
ああ、唐揚げの時と同じだ……。こうして私は彼に振り回されちゃうんだ。きっといつかこのドキドキに釣られて、何もかも全部許しちゃうんだ。
そんな予感がして、少し前の自分の爆弾発言にも気づかないまま、私は深く深くため息を吐いた。
餌付けられたのは、私と彼のどちらだろうか。