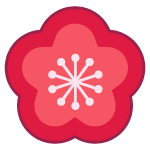
雷鳴と心音
最近、幼馴染の我妻善逸はかなり調子に乗っている。
「なんかさぁ、俺、最近急にモテ始めたんだよね」
こうして一緒に学校に行っている今も、自慢気に私を見ながら言う。思いきり否定してやりたいけれど、実はこれがあながち的外れでもない。何故だか善逸は、最近、上級生から急激にモテ始めていたのだ。
「あ、ねぇあれ、我妻くんじゃない?」
「我妻くん、こっち見て!」
「あ、ほらほらこっち向いてくれた! やだ、超可愛い!」
そう、まさかの善逸は「可愛い系」としてもてはやされているのだ。
何で? 善逸、可愛いか? どこが? みんな、春だから浮かれてるの?
私は上級生のお姉様たちの気持ちを全く理解できなかった。そして、善逸も別に可愛い系を目指しているとは思わない。モテれば何でもいいのか? 君にプライドはないのかい?
「あのさぁ、可愛いって騒がれてるみたいだけど、本当にそれでいいの?」
私が呆れてため息を吐くと、善逸が心外というような表情でこちらを見る。
「さすがに自分が可愛いとは思わないけどさ、こんな俺でも好きって言ってくれる人がいるわけじゃない。そりゃ、どんな理由でも嬉しいでしょうよ」
「へー……」
「だって、どこかの誰かは、俺が好きって言っても全く靡いてくれないし?」
その一言に私はぐっと詰まった。突然のカウンターパンチ。
「その子さぁ、小さい頃からずっと好きだって言ってるのに全く振り向いてくれないんだよ? 酷いと思わない?」
「……そうなんだ。酷いね」
「あの、名前のことなんだけど……」
「……わかってるよ!」
私は叩きつけるように言ってから、善逸を差し置いて学校まで走って向かった。何かわからないけどすごくムカついた。だけど、善逸が上級生からモテ始めているのも、私がずっと告白に返事をしていないのも、事実じゃないか。一体、何が腹立たしいというのか。
しかし、私の気持ちは朝から全くおさまる気配がなかった。なぜなら、最近の善逸のモテ具合といったら本当に半端ないのだ。ついには上級生が休み時間ごとに教室に押しかけてきて、善逸を見てキャーキャー騒ぐようになってしまった。今までの私の人生で、こんな光景は目にしたことがなかった。そしておそらく、善逸の人生史上でもなかったことだろう。案の定、善逸はデレデレとしている。満更でもなさそうだ。元より女好きのあの性格だから、当然といえば当然なのだが。
あらためて、善逸の顔をよく見てみる。私が見慣れていて何も感じないだけで、実は善逸はいつの間にかとんでもないイケメンに成長していたとか……? はたまた母性を刺激するようなアイドル系の顔立ちなのか? どんなに凝視してもそのどちらでもなさそうだった。となれば、私の美意識がおかしいとでもいうのだろうか。
しばらく善逸を凝視していると、視線に気づいた善逸と目が合った。調子に乗っているその顔に口だけで「バーカ」というと、何故か嬉しそうにへらりと笑って手を振ってくる。こういうところが可愛いとか、思ったり思わなかったり。
次の土曜日、私と善逸は映画に行く約束をしていた。約束の一時間前に、私は善逸の携帯にモーニングコールをする。彼の寝起きはすこぶる悪い。
「もしもし、善逸? もう起きてる?」
「……寝てる……」
「今日、映画行くんでしょ? もう起きないと間に合わないよ」
「うん……」
「一時間後に行くから。もし起きてなかったら今日は出かけるのなしね」
今までも善逸の寝起きが悪くて出かけられなかったことは何度かあった。このため、映画や美術館等へ出かける時もいつもチケットは現地で購入する。
私は電話を切って、念入りに身支度を整えた。仮にも休日に会うのだから、いつもと違うところを見せて何とかあっといわせてやりたい、というくだらない見栄のためだ。
そうこうしている間に約束の一時間後が迫りくる。私は自分の姿を鏡で最終チェックし戸締りを確認した。最後の窓を閉めようと何気なく外に目をやれば、隣の玄関からちょうど善逸が出てきたところだ。珍しく私より早く出かける準備が整ったらしい。
しかし、どうやらそれは違ったようだ。善逸はインターフォンに反応して出てきたのだった。よくよく見ると、中等部の制服を着た女の子が善逸に話しかけている。何やら真っ赤になって手紙を差し出しているではないか。これは、もしかしてもしかしなくても、告白では。
愕然とした私は、善逸が本当にモテているという事実をあらためて目の当たりにしたのだった。上級生が興味本位で騒いでいるならまだしも、中等部の女子にまでモテているなんて、これはもう本当のモテ期だ。え、何で急にモテてるの。一体彼が何をしたというの。
私が困惑していると、今度は我が家のインターフォンが鳴った。時計を見ると、約束の時間になっている。
私は荷物を持って外に出ると、インターフォンの主に曖昧に微笑んだ。
「準備、早かったね」
「そう? 時間ちょうどだよ」
「あ、そっか、そうだよね」
「……もしかして、名前、さっきの見てた?」
私の様子がおかしいことにいち早く気づいた善逸が、気まずそうに切り出す。私は内心の動揺を隠すように努めて明るく振る舞った。
「見てたよ、見てた! 善逸、下級生にもモテてたなんて知らなかったな」
「あー……どうやって断ろうかねぇ……」
善逸が困ったように呟く。
「断るの?」
「うん、当然だよ」
「なんで?」
「何でって……名前、それ訊いちゃう……?」
それは、私を好きだからだ。考えればすぐにわかることなのに、私はあまりに無神経な言葉を発してしまった。
気まずい雰囲気で映画館に到着し、今日の上映予定をあらためて確認する。ちょうど今から十分後にお目当ての映画が上映開始するらしい。しかし、生憎満席になってしまっていた。その次の上映時間は三時間も後だ。
「満席? これってそんなに人気だったっけ?」
善逸が驚いたように声を上げる。私も同じ気持ちだった。
「あ、そういえば今日は映画が安い日だからかも」
「そっか、忘れてたよ。どうする?」
「うーん……今日は別のにしない? 三時間後のも結構埋まっちゃってて、微妙なところしか空いてないし」
「わかった。観たいのある? 俺は何でもいいから合わせるよ」
「じゃあ、あれにしない? ホラーだけど面白そう。もうすぐ始まるみたいだし」
「ホラー? 大丈夫なの? 名前、そんなに得意じゃないんじゃない?」
「なんか今日は大丈夫な気がするの」
「オッケー」
軽い気持ちで目についたホラー映画をチョイスする。善逸がさっさとチケットを買いに行く間に、私は携帯で映画の評判を調べた。かなり怖いという意見が大半を占めている。しまった、という気持ちになるがもう遅かった。善逸が二枚のチケットを片手に一瞬で戻ってくる。
「はい、買ってきたよ」
「ありがとう、善逸。お金……」
「その前に席座っちゃおう。もう入場できるみたいだし」
「あ、うん」
善逸は館員に二枚のチケットを提示すると、私を振り返って言った。
「先に行っててくれる?」
私が頷く間もなく、善逸は私に一枚のチケットを押し付けてどこかへと姿を消した。
飲み物とかが欲しかったのだろうか、と思うが、私たちは映画の時にあまり飲食するタイプではない。まあいいか、と私はチケットの示す座席へ向かった。スクリーンからの距離は真ん中より少し後ろの右端の席だった。善逸らしい席の決め方だと思った。
予告が始まるギリギリになって、善逸は私の隣の席に座った。
「はい、ひざ掛け持ってきたよ」
「ありがと」
小声で言うと、善逸は私の頭をポン、と軽く撫でた。
宣伝が流れ、面白そうな映画がいくつも目に入る。あれも観たい、これも、と思いながらタイトルをできる限り記憶した。またこうして善逸と観に来ることになるだろうな、と頭の隅で考える。
いよいよ始まった映画は、ジャパニーズホラーなので日本特有の怨念だとか幽霊だとか、そういった怖さのある内容だった。レビューで確認した通り、確かになかなか怖い。いや、かなり怖い。善逸が叫び出すんじゃないかとハラハラしながら横目で見る。しかし、意外にもストーリーがしっかりしていたためか善逸は真剣な表情でスクリーンを見つめていた。
あ、善逸は意外に大丈夫なんだ、と思ったのも束の間。スクリーンに突如として出現した霊に驚いたのは私の方だった。私は小さく声を上げ、びくりと肩を跳ねさせた。
声が出るほどびっくりしてしまって、かなり恥ずかしい。でも本当にかなり怖いのだ。ひざ掛けを握る手に力が入る。すると、その上にそっと手が添えられた。善逸の手だ。さっきとは別の意味で驚いて善逸を横目で見ると、素知らぬ顔でスクリーンを観ていた。
二時間の上映が終了し、終演のアナウンスが流れるまで、善逸はずっと私の手を握ってくれていた。
「善逸、ありがと。もう大丈夫だから」
素直な気持ちで善逸にお礼を言う。善逸はいつも通りへらっと笑って手を離した。
「いやぁ、結構怖かったよね」
「うん」
私たちは立ち上がって映画館を後にした。どこかでお茶でも、と話すが、何だか雲行きが怪しい。一雨きそうだ。それなら、と善逸の提案で近くのケーキ屋に寄り、一つずつケーキを買った。これから善逸の家で食べるのだ。結局チケット代を払い損ねた私が支払いをしたが、それでもまだまだ払い足りないくらいの金額だった。
あのシーンがどうだ、このシーンが怖かった、と二人で盛り上がりながら帰っていると、向かいから見覚えのある少女がやってきた。誰だっけ、つい最近見たような、と考えてすぐに思い当たる。出かける前に、善逸にラブレターを渡していた中等部の子だ。
「あ……」
少女は善逸を見つけて一瞬嬉しそうな顔をしたが、すぐに隣の私を見つけてシュンとなった。
「あ、こ、これはその……」
善逸が至上最低の浮気男のように慌てふためくが、どう見ても完全な邪魔者は私のようだった。
「その人と、よく一緒にいますよね。お付き合いされているんですか?」
可愛い上に礼儀正しい彼女に、私は心底感心した。しかし同時に、何故だか焦りが生まれてくる。私に勝ち目はない、と急速にそんな気持ちが芽生えだしたのだ。
「付き合ってないよ。ただの幼馴染なんだ」
善逸がゆっくりと諭すように少女に語り掛ける。ただの事実の羅列が、私の心をひどく痛めつけた。
「そうですか、よかった。じゃあ、私も可能性ありますよね」
ホッとしたように微笑む彼女のことを、百人中百人が可愛いと評するだろう。善逸がいくらモテ期だといっても、こんなに素敵な女の子はこれから一生現れないに違いない。間もなく彼は肯定の意を示すだろうと、簡単に予測がついた。
「ごめんね。俺、君とは付き合えないよ」
しかし私の予想に反して、善逸は彼女の告白をきっぱりと断る。えっ、という表情で、私と少女は同時に善逸を見た。
「どうしてですか?」
「付き合ってはないしただの幼馴染だけど、俺は彼女……名前のことが好きなんだ。だから……」
もう一度優しく、ごめんね、と言った善逸に、少女は小さく頷いて去っていった。
「……よかったの?」
「え? なにが?」
「だって、あんなに可愛い子なのに……」
「あのさ、今日二回目。それ、訊いちゃう?」
映画を観る前と全く同じ台詞を私に零した善逸は、さっさと家への道を歩き出した。ケーキの箱をぎゅっと握って、私も彼に続いて我妻家の門戸をくぐる。善逸の部屋に入るのももはや当たり前になっていた。私たち以外不在の我妻家で、私はお皿とフォークを出して、紅茶まで入れることができる。
「雨、降ってきたね」
ソファーに並んで座りながら善逸に語り掛けた。私の言葉に、善逸はショートケーキを食べながら頷く。
「今日、雷もひどくなるって」
「え、嘘……」
言ったそばから、物凄い轟音が鳴り響く。危うく紅茶を零しそうになるほどの爆音だ。
「びっくりした……」
驚きのあまり心臓がどきどきしている。呆然としていると、善逸が私の手を握った。
「こうしてれば、大丈夫でしょ」
「……うん」
その手の熱さに、もう潮時だな、なんて私は思う。もういつまでもこんな曖昧な関係を続けてなんていられない。いつまでも逃げていないで、そろそろはっきりさせなくては。
「……ついでにキスしてもいい? ……わけない、よね」
「いいよ」
「……え」
冗談めかした善逸の目を見て答えると、彼の瞳が動揺する。
「え、な……いやいや、だめでしょ……」
「いいよ。キスして」
「……じゃ、じゃあ……目、瞑って……」
コクリと頷きゆっくり目を閉じると、善逸が私の手を握り直した。そして少しの沈黙の後、唇と唇がゆっくり触れる。
「……キス、したよ」
「うん」
わかってると思うけど、と前置きして、私は善逸に思いの丈をぶつけた。
「映画館の座席の決め方が好き」
「……うん」
今日はたまたまそうしたけれど、私は元からホラーがそこまで得意ではなかった。いざとなったら出られるように、善逸は端の席を選んでくれていた。
「さりげなくお金を受け取らないところが好き」
「うん」
「あと、善逸は全然可愛くなんてないから。そこは勘違いしないで」
「うん」
「善逸は、かっこいいよ」
上級生の人たち、何もわかってない。私がそこまで話したところで、善逸は私をぎゅっと抱きしめた。私もいつの間にか随分と広くなったその背に腕を回す。小さい頃から長らく一緒にいるけれど、抱き合ったことは初めてだった。
「俺は、とっくに気づいてたけどね。名前の気持ち。いつ言ってくれるのかと思ってたよ」
どうやら私も気付かない内から私の気持ちはバレバレだったみたいで、善逸は随分余裕に構えていたそうだ。
ライバル登場に焦っていたのは私だけだったな、なんてしてやられた気持ちになりながら、その腕の中で雷の音をやり過ごした。