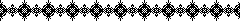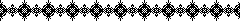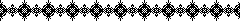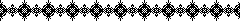
虎に成る
ぽんぽん、と頭に乗せられた大好きな手。
他人との触れ合いを良しとしない彼がそうしてくるのは、わかっている限り自分だけ。
彼が自分を許してくれているのだと、そのたびに嬉しくなる。
人とは違う。自分だけ。むくむくと胸のうちで育つ心地好い感情が俗に言う優越感なのだと初めて知った。
彼に頭を撫でられることへの純粋な喜びと、そうされる自分を見遣る幾人かの羨望の眼差しへの優越感。普段ならばそればかりが胸を支配するというのに、今日はそこに、なにやら穏やかでないものが混ざっていた。
彼はいつもとなんら変わりない。自分にだけ向ける穏やかな表情で、頭を撫でてくれている。
自分だって、いつもとなんら変わりないはずだ。それなのにこの、胸につかえる違和感はなんなのか。
もっともっと、と抱き着く腕の力を強くして、頭をぐりぐり押し付ける。
まったく、と呆れたような、だけど甘く優しい声が降ってきて、撫でる手が髪をすくう。
満たされているはずだ。
けれど違和感は、拭いきれなかった。
虎に成る
「−−って、俺様にそんなこと言われてもねえ」
幸村がかの西軍総大将、石田三成にどうしようもなく懐いていることは、西軍ではもはや知らぬ人などいないであろうほどの、周知の事実であった。もしかすると東軍にだってなんらかの噂は流れているかもしれない。
しかしさらに驚きなのが、これが一方通行ではない、ということだ。
いつでも切羽詰まったような三成が、他人のことなど顧みないような三成が、何故だか幸村だけはまともに相手をする。
始まりはなんだっただろうか。
記憶を辿ろうとしても、明確なそれは思い出せない。気づいたら、そこにあった。やたらと仲良くなった、幸村と三成が。
とにかく最近では、人目も憚らずに幸村は三成に抱擁をほどこす始末で、三成も三成でそれを振り払おうとしないのだから、目のやり場に困ってしまう。
さらに幸村が西軍の利益になるような成果をあげようものなら、よくやったとそのいつでも厳めしい表情を綻ばせ幸村の頭を撫で褒めるのだから、たまったものではない。
誰とは言わないが、実は三成に想いを寄せる人間がちらほらと混ざるその場において、錯綜する殺気がもはや尋常ではないのだ。いっそ東軍とやりあう前に内から崩壊してしまうのではないかと、佐助あたりは真剣に危惧している。
−−で、心配事の主な原因である幸村本人はそんなこととは露知らず、先から佐助に"胸のうちにつかえる違和感"がなんなのかを問うている。
アンタ暗殺されてもおかしくない立場にいるってこと、気づいてる?
佐助はそう言いたいのをやっとのことで我慢して、だけど出てきたのはなんとも投げやりな言葉だった。
いくら佐助が優秀な忍でも、他人の心まではわからない。
−−いや、付き合いの長い幸村のことだ。幸村の言いたいこと、そして欲しているだろう答えは、なんとなくわかるような気もする。
ただ心底面倒だと、その気持ちが先行してしまっているだけで。
「しかし佐助、三成殿は俺にこんなにも良くしてくれているのに、このようなはっきりしない気持ちで向き合うのは失礼というものだろう?」
佐助はため息を押し殺して、幸村に向き合った。
結局のところ、このどうしようもなく真っ直ぐな主に佐助は甘い。
「じゃあ聞くけど、」
面倒の二文字をどこかへ無理矢理押しやって、幸村に問うた。
「大将はさ、石田の旦那とどうなりたいの?」
「……は?」
その内容に、幸村は目を丸くする。
佐助にとってするべき当然の質問は、幸村にとってはかなりの想定外であるらしかった。
「まあ今でも十分それっぽいけどさ……どうなの?」
「そ、それっぽいとは?」
「だからあ、恋仲になりたいのかって聞いてんの」
「こっ…!?」
しかし佐助にしたらその反応は十二分に想定内のことで、気にせず先を続け、あっというまに核心へと触れる。
幸村相手に遠回しな話術は通用しないことなどとうの昔に承知している。
すると幸村は真っ赤になって、そんな破廉恥な、と慌てだすものだから、佐助はますます真剣な顔をしてみせた。
「ちょっと大将、俺様真剣なんだけど」
「あ、う……し、しかし、だな…」
そうすればもじもじと落ち着かなさそうにしながらも、なんとか姿勢を正す幸村。
その様を見ながら、散々それっぽいことを公衆の面前でやらかしてきたくせにと、佐助は頭が痛むような錯覚にとらわれた。
そもそもこの耐性の無さはなんなのか。幸村の育ちを考えたら、多少の知識に欠けるだとか、そういうことは仕方のないことなのかもしれないが、しかしこれは、普通、ここまで純粋に育てるものなのか。
改めて尊敬の念が入り混じり始めた佐助を前に、相も変わらずもじもじしている幸村が、ぼそぼそと話しだす。
「さ、佐助?俺は、その、三成殿とこ、ここ恋仲になりたいなどと、そんな大それたこ、ことを思ったことは、ない」
「でしょうね」
というより、自分が三成に向ける好意がそういう類いのものであることなど、気づいてもいなかったのだろう。
「しかし、しかしだぞ?三成殿が微笑まれると、それをずっと見つめていたい…けれど他の者には見せたくないだとか、」
「うん」
「三成殿が俺に構ってくださっているときの、他の者への、その…」
「優越感?」
「う、うむ。それがひどく心地好く感じたり、だとか……もっと、と欲深く思ってしまうのはつまり、」
「そういうことだと思うけど」
「………」
羞恥心が限界に近いのか、ぷるぷると体を震わせながら俯いてしまった幸村に、今度はため息も我慢しなかった。
「ようするにさ、大将は現状に満足してないってことだよ。今だって恋仲っぽいっていえば近いけど、どちらかというと兄弟みたいだしね」
「きょうだい…」
「そ。ああ、飼い主と愛犬って感じもするかも?」
「あいけん…」
理解はしていなくとも、本能はわかっていた、ということらしい。
確かに三成は、幸村に甘い。これは他者にはない甘さだ。それは間違いない。
しかしその甘さは幸村が知らず知らずに心の底で望んでいたような、恋仲の者同士の甘さではないのだ。言うなればそう、家族。親しい身内に向ける、それに近い。
「……どうしたらよいのだ、」
たった今恋の戦士へと成り上がった幸村は、早速頭を抱えた。
今までこれでもかと言うほど、真っ直ぐに三成への好意をあらわしてきた幸村だ。そのおかげで今の関係がある。
けれど更にその先へ行くには一体どうすれば。どうすれば弟や愛犬のようだと思われなくなる。
今までと同じでは、ダメなことは明白で。
そんな悩める恋の戦士幸村の背を、佐助はそっとおしてやる。
「まあ、漢らしく大人らしく、いけばいいんじゃないの?」
「……」
それはレベル1の幸村にとっては、更なる混乱を招くだけのシロモノであったが。
さて、三成にこれでもかと言うほどべったりだった幸村が、今まで何故、密かに三成に想いを寄せる人間から暗殺されずに済んでいたかと言えば、それは単純に、安心していたからだろう。
三成が幸村に心を許していることは確かだし、幸村の行動が親密さを増すほど大胆になってきていたのも事実。
けれどそれ以上はない、という安心だ。
幸村が自分の気持ちに自覚がなく、またそういうことに対する耐性がないことも、周りはちゃんと承知していたのだ。
だから人前でべったりされれば、やはり自分の想い人に他者がいいように触れているのは腹がたつが、事を起こすほど重大ではないと、見ていたのである。
もちろん幸村はそこまで考えていないし、気づいてもいないのだろう。三成という人間の競争率の高さなど−−まあ、知らぬが仏という言葉もあるから、そのままでもいいだろうが。
しかし幸村の身辺警護にはこれまで以上に注意を払っておくかと、佐助は忍隊へと密かに指示を出す。
まさか本当に恋の嫉妬で暗殺部隊を繰り出してくるような人間はいないだろうが、備えるに越したことはない。
時は戦国、おそらくこれまでに経験したどの戦よりも大規模なものになるだろう戦を控えているというのに、何故こんなところで気を揉まなければいけないのだろう。
佐助は最近多くなったため息をまたついて、今日も幸村のために奔走する。
ところ変わって、ここは月山富田城。尼子の戦力を西軍に引き入れるべく、元親がその軍をつれて訪れており、幸村もその加勢にと、共にその地に立っていた。
三成は自分が行くと言い張ったのだが、これまでもかなりの速さで進軍しており、三成は連戦に次ぐ連戦を強いられていた。これはさすがに休ませなければいけないと、吉継や元就が反発。なおも言い張る三成に、幸村が「ならばこの幸村が、三成殿のかわりに槍を奮って参りまする!」と場をおさめたのだった。
三成は幸村に弱い。
張本人である幸村以外からすれば気に入らない事実もこの時ばかりは役にたった。
「屠ること烈火の如く…真田幸村、参る!」
「おうおう、甲斐の虎はいつになくやる気じゃねえか」
そして幸村は、三成に約束した言葉以上の働きを見せている。
これじゃあ尼子さんも歩が悪いねえと、元親は笑む。
元親は、この暑苦しい男がどうしても嫌いにはなれなかった。密かに三成に想いを寄せる元親にとっては恋敵であるはずなのに、どうしても。
「佐助が言っていたのだ!」
「ああ、アンタのとこの忍か」
「うむ!三成殿に恋仲として認められたくば、漢らしく振る舞えと!」
「…っ、」
漢らしく、それすなわち何人にも負けぬ最強の武人と心得たり。
そう叫びばったばったと敵兵を薙ぎ払っていく幸村に、元親は頭を思い切り殴られたかのような衝撃を受ける。
恋仲がどうのと、聞き捨ててはならないことは百も承知。ついに幸村も自分の気持ちに気づいてしまったのかと、警戒しなければいけないことは、よくわかっている。
いるけれど、それ以上に笑いをこらえることが先決だ。
確かに進んで戦場に赴き、武勇を飾ることは三成の好感度をあげることに繋がるだろう。
だけど多分佐助が言う漢らしくとは、もう少し毛色が違うことだと、元親は思う。
「しかし長曾我部殿」
「…な、なんだ?」
「考えてもどうしてもわからないのでござる。佐助がもう一つ言っていた大人らしく、とは一体どういうことでござろう?」
二槍を奮う手をはたと止めて、幸村は元親を振り返った。
その目はひたすらに真剣だ。
元親はこれがどうしようもなく面白い。真剣なのもひたむきなのもよく伝わってくるのに、空回り。
だけどそれと同時に恋敵だというのに放っておけない理由は、そこにあるのかもしれない。
助言は自分のためにならないし、元就あたりには余計なことをとお叱りを受けるかもしれない。わかっているが、元親はにかっと笑った。
「まあ俺から言ってやれるのは」
「!」
「戦に勝って最強を目指すってーのは、今までと変わらねえんじゃねえか?」
「………」
「難しいことは俺にもわからねえ。だけどアンタの忍が言う漢らしくは、多分、石田への接し方を言ってんじゃねえかな?」
「…な、なんと!某はとんでもない思い違いを!?」
しかし漢らしく接するとはどういうことなのだ、と考え込みはじめる幸村の肩を叩く。
「何はともあれ、今は勝たねえと元も子もないぜ!」
「う、うむ!そうでござるな!」
それに大人らしさがわからないと言うのなら、あとで元就あたりにでも聞いてみるといいと、余計な助言もこっそり付け加えて。
無事に尼子軍を降伏させた元親と幸村が大阪城に戻り、三成に報告を済ませる。
休息を半ば無理矢理とらされいささか機嫌の悪い三成がそうかと頷いて、幸村は脊髄反射のように三成に抱き着きそうになるのを、はっとして止めた。
漢らしくとは、三成に対する接し方のことだと元親は言った。となると、大人らしくというのもおそらくそういうことなのだろうと、幸村は考える。
つまり普段の幸村の三成に対する接し方は、そのどちらでもないということ。それもそうだ。佐助に言わせれば、幸村は三成の弟や愛犬のように見えるらしいのだから。その二つはどうしたって、漢らしさにも大人らしさにも繋がりそうもない。
ということは、ここで抱き着いて頭を撫でてもらうようではいつまで経っても恋仲にはなれないということ。三成に一人の男として見てもらえないということだ。
容易に触れられなくなることは三成から遠ざかってしまうことのように感じるが、時には我慢することも必要なのだろう。これこそなんだか、大人っぽい気も、しなくなはない。
とにかく幸村は笑ってその場を後にした。
その後幸村は元親に言われたように元就のところを訪れ、大人らしさとはなんなのかを問うた。しかし我が知るかと一蹴され、早一月。
どうも普段の接し方がよろしくないのだということはわかった。
だから以前のように手を握ってみたり、抱き着いてみたり、そういうことはしないように心掛けていた。
だけどそうしていないと何故か三成との距離が遠くなってしまうような気がして、それは嫌だからと、たびたびお茶や散歩、鍛練などに誘い出してはいた。
とは言え三成も幸村も暇ではない。その回数は限られていて、三成との距離はどんどん離れていくような焦りにかられる。三成の手はどんな温度で、どんな心地がしただろうか。それすら曖昧になりだして、幸村はむうと唸る。
焦りだけが先行する。けれどいまだ漢らしさも大人らしさもわからない。どうすれば弟やら愛犬やらの立場から抜け出せるのかなど見当もつかない。
鍛練場にて槍を奮うことにも飽いた幸村は、手ぬぐいで額の汗を拭いながら空を仰いだ。
「やれ、今日も精が出る」
小さく針に刺される程度だったはずの違和感は、今や幸村の胸を真綿で絞めるかの如く大きく、膨れ上がっている。
否、これは違和感ではないと知った。これは幸村の願望、欲だ。三成ともっと親しくなりたいと、三成にちゃんと男として見てもらいたいという、欲。
それが試行錯誤しているうちに、三成に触れられないことへの不満や、前よりも遠く感じる距離への焦りを纏い、幸村を苦しめる。
今や鍛練ですらままならず、こうして声をかけられるまでその気配に気づくこともできなかった。
「お、おおお大谷殿っ!?」
「そこまで驚くこともなかろ」
振り返ると、そこには輿をふわりと浮かせた吉継がいた。
吉継と言えばだいたい、書庫や私室にて政務をこなしているか、元就と碁をうちながら今後の動きについて模索しているかで、同じ西軍とは言え滅多なことでは幸村は会うことはない。
三成が最も信頼している人物。幸村にとってはそれ以上でもそれ以下でもなく、けれどこうして改めて向き合うと、その纏う雰囲気に圧倒される。
思わず背筋をぴんと伸ばし、肩にかけていた手ぬぐいを背の後ろで組んだ手の中に隠すと、吉継は肩を揺らして笑った。
「ヒヒッ…そう堅くなるな」
「もっ、申し訳ござらん!」
幸村はひとしきり慌てて、けれど結局、もとの直立の姿勢に落ち着いた。
「し、して大谷殿!某に何か御用でござりましょうか?遣いであればこの幸村、すぐにでも発てまするが」
「何、そうではない。ただ…随分と迷うておるなと思うてな」
「……?」
吉継がわざわざ幸村のところへやってくるのだから、それは大層な用があるのだと思ったのだが、どうやら幸村が想像していたようなものではないらしい。
吉継の言葉の意味がわからず幸村がわずかに首を傾げると、吉継はまた、独特な笑い声をもらした。
「考え込むなど、ぬしらしくない。一つ聞くが…」
「なんでござりましょう?」
「三成に、直接言葉で伝えようとは、思わぬのか?」
ぬしならば先ずそうすると思っていたが。
そう言う吉継に、これがなんの話であるのか幸村はようやく気づく。
「…、言葉で?」
「然様。ぬしが望むものになるには、必要なことであろ?」
そしてこの一月悩んでばかりであった幸村に、助言をしてくれていることにも。
言葉で伝える。確かにどうして今まで気づかなかったのだろう。
漢らしく、大人らしく。それは例えば元親や元就、目の前の吉継を見習えばいいのだと考えたこともあるが、どれもうまくいかなかった。
結局深みにはまっては焦っての悪循環。
それを打破したいのであれば、そうか、直接伝えればいい。
もしかすると畏れていたのかもしれない。弟のようにしか思えないと言われることを。
しかしそれさえも、今こうして足止めをくらって前に進めないでいることよりは明るいことのように思える。
「大谷殿!」
「……」
「某は、三成殿と向き合う覚悟を致しました!」
「…なれば、ゆけ」
応、と吠えて幸村が走る。
少し行って足を止めると吉継に一礼して、また走る。
ばたばたと忙しないその背中に、吉継はふうと息をついた。
「三成もぬしも、まこと手のかかる…」
これ以上三成にかような顔をさせてくれるなと、ぽつり呟いて。
「たのもー!」
中からの返事を待たずして、幸村はそう叫んで三成の私室の障子をすぱんと開け放つ。
いつだったか、西軍にくだるべく大阪城の門を叩いたのと同じだ。
あの時はまさか、その総大将たる三成にこんな想いを寄せるなどとは思ってもいなかったが。
「っな、!?」
「三成殿!!」
机に向かっていたらしい三成は、突然のことに肩をびくりと揺らして振り返る。
その拍子に手に持っていた筆からぽたりと墨が垂れたが、三成も幸村も気づかない。
幸村は振り返った三成に、これでもかというほどの勢いで体当たりをかます、否、抱き着いた。
「三成殿!某は三成殿にお話があって参りました!」
「な、なんだ!?いいからまず、この手を離せ!」
「それはお断り致す!」
三成はそれを解こうと筆を投げ出して奮闘するが、ぎゅうとかたく三成の腰に絡み付くその手は、三成の腕力では振り切れそうもない。
三成は潔く諦めて、幸村の好きにさせることにした。
「…それで、話とはなんだ」
「三成殿、某は三成殿のことを好いておりまする」
「!?」
そしてこのような体勢でする話とは何かと訝しがりながら先を促すと、首に埋めていた顔をぱっとあげた幸村は臆することなくそう告げた。
面食らったのは三成だ。
けれど言いたいことはそれだけではないのだと、言葉を続ける。
「だからこうして三成殿に抱き着いたり、頭を撫でてもらえることが何よりも嬉しかったのでござりまする。三成殿が某を受け入れてくれていることが、何よりも」
「……」
「しかし、」
しかしいつからか、そこに違和を感じはじめた。
幸村はもとより、それに応えている三成も相手に心を許していることは明白。けれど幸村と三成の感情の重さには、決定的な違いがあるのだと。
それに気づかず満足していた過去。もはやそれでは満足できない現在。幸村の三成を想う気持ちは確実に育っている。
「佐助に言われ申した。こうして三成殿に抱き着く姿、三成殿が受け入れてくださる姿は、まるで兄弟のようだと」
「兄弟…?」
「某はそれでは我慢できませぬ。兄、弟ではなく、一人の男として、某を見ていただきたい」
だからこの一月幸村なりに試行錯誤してみたのだが、結局うまくはできなかったのだと。こうしている今も、端からしたら弟(幸村)を慰める兄(三成)のように見えているのだろうかと、幸村は苦笑いした。
「馬鹿者めが」
そんな幸村に、三成はそう呟いた。そして空いている右手で無防備なその後頭部をはたく。
ぱしんという音があまりに軽快だった。
「…誰が貴様を兄弟のように思った」
「…え?」
「貴様の思い込みと他者の言うことで勝手に話を進めるな、この馬鹿者が」
それから両手で幸村の頬にすくうように手を添えて、逃げられないように固定する。
キッと睨みつけるように、きょとんとした瞳を見た。
「私は貴様を、そのように思ったことはない」
「三成殿、」
「好きだ」
嘘も偽りも嫌う、三成らしい真っ直ぐな言葉だった。それにかああああ、と顔を赤らめたのは幸村のほうだ。
しかし顔はしっかり三成に固定されていて背けるに背けられない。
どうしたものかと口をぱくぱくとさせる幸村に、三成は柔らかく笑んだ。
「この一月、貴様は妙に私を避けた。そして避けたかと思ったら、機嫌をとるかのように私を誘い出した。もはや前までのような気持ちはないが友好関係だけは表向き築いておきたい、そういうことなのかと……裏切られたのかと思ったが、そうではないのだな……」
「っ、」
「!」
久方ぶりに見る、三成の笑顔。
そのあまりの美しさに、知らず知らずに体が動く。それはもはや衝動だった。
ゆうるりと弧をえがく口元に、幸村は噛み付くように唇を寄せる。口づけの仕方などわからない。だけどそうしたいと思ってしまったのだから仕方がない。
拙いであろうそれを気が済むまで施して、幸村は泣きそうになりながら叫んだ。
「この幸村、何があろうと三成殿を裏切ることなど決してござらん!!」
美しくも悲しい笑み。そんなものは見たくないと幸村は思う。
自惚れかもしれない、驕りかもしれない、けれどこの一月、もしかするとこんな顔ばかり三成にさせていたのかと思うと、それが自分のせいなのかと思うと、自分を情けなく思う。
幸村の言動は漢らしくも大人らしくもないのかもしれない。だけど三成にこんな顔をさせるのは、それ以上に漢らしくも大人らしくもない。
幸村は後悔して、それから決意した。
「もう二度と迷いませぬ、某は三成殿と釣り合うようには見えないかもしれませぬ、時に不安を抱えることもあるかもしれませぬ、しかしかような時でも、某は三成殿のそばから片時も離れは致しませぬ!!」
「真田、貴様…」
そしてすっかりいつもの熱血漢に戻った幸村が、めらめらと炎を燃えたぎらせる。
ぎゅうとしがみついてくる様は、なるほど、言われてみれば幼い弟のように思えなくもない、かもしれない。だけど弟を相手に、こんな気持ちは抱かない。
三成は呆れたように笑った。
「もう十分に、漢らしいぞ」
もちろん熱血"漢"らしいであるが、そう言えば目を輝かせて喜ぶ幸村に、大人らしさは今ひとつだと意地悪を言っておく。
だって悔しいじゃないか。
三成だってずっと、自分と幸村の抱く"好き"では重みが違うのではないかと違和を覚えていたというのに、その不満を吐く機会はすっかり失われてしまったのだから。
- 53 -
[*前] | [次#]
ページ: