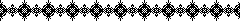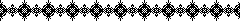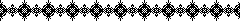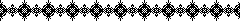
あの子に惚れなきゃ嘘じゃない?
か細い体躯で疾風のように戦場を駆ける三成。しかし、その風が吹き抜けた後には、まるで鬼神が通り過ぎたかのような光景が広がる。
一瞬にして数多の敵を薙払う太刀さばきを、幸村は憧憬の眼差しで見ていた。しかし自分に指南願いたいと何度申し出ても、三成はまったく取り合ってはくれない。根っからの体育会系の人間である幸村は、「三成殿の剣術は教えるものではないと!己の目で見て自ら体得せよと!」そう思い込み、日々三成について回っていた。そして、「人知れずどこかで鍛練を積んでいるに違いない」と、隠れて彼の様子を窺うなどとちょっと困った行動さえ起こし始めていた。
「…大将、熱心なのはいいけど、あんまり度が過ぎると“すとーかー”になっちゃうよ?」
「酢、投下??俺はそんな迷惑な真似はせぬ!」
「違うよ、“すとーかー”ってのは一方的に付きまとったりして相手に迷惑を掛けること。まぁお酢の投下も大概迷惑だけどね。」
今日も今日とて三成の背中を付かず離れずで追う幸村を、佐助がたしなめる。彼にストーカー紛いのことを始めて結構になるが、分かったことはそう多くなかった。しかし、三成はとにかく想像以上に食わぬ眠らぬで、世間一般からは考えられない生活をしていた。佐助は「強さの秘密を探る」どころではなく、三成の世話を焼くために幸村の行動に付き合っている節があった(無茶をし始めたら即座に飛び出すためである)。
そしてもう一つ分かったことは、彼は雨が降ると一人でどこかへ行ってしまうということ。以前、「雨は嫌いだ」と言っていたのだが、雨天の度に必ず姿を消していた。そんなときは、尾行を試みても佐助でさえ三成を見失ってしまっていた。
ぽつ。
鉛色の空から雨粒が落ちて来た。とうとう泣き出してしまった空を見上げて、三成は一つ息を吐いた。親友である吉継にも何も言わずに、彼は臙脂色の傘をさして城を出た。その様子を見送り、今日こそは行く先を掴んでやる!と幸村と佐助は三成の後を追った。
しとしと。
尾行するのに傘は邪魔だが仕方がない。民家の塀などに身を隠しながら、二人は気取られぬよう三成の足跡を追う。通り過ぎる町民達には変な目で見られるが、構ってなどいられなかった。
ふと、三成が足を止めた。
「あ、止まった…。」
彼の視線の先、道路の隅には雨に打たれて蹲る灰色の毛並みの子猫がいた。
こと。
その子猫の傍らに、三成は躊躇することなく自分の傘を置いた。そして何事もなかったかのように再び歩き出したのだ。
―きゅん!
「ん?今変な音がしなかったか?」
「犬でも鳴いたんじゃないのか?」
……いいえ、通りすがりの商人の方々、今のは幸村と佐助が胸をときめかせた音です。
(みみみみ三成殿〜っ!!)
(石田の旦那……っ!)
体を濡らしながらも歩みを止めない三成を本当ならば放っておきたくなどなかったのだが、二人は声をかけるのをぐっと堪えた。彼がいつもどこに向かっているのか、それが知りたい一心だったのだ。しかし、
「真田、猿飛。出て来い。」
三成にはバレていたようだ。くるりと振り返り、二人が隠れている木の影を睨み付ける。
「……気付かれちゃったか。」
「も、申し訳ありませぬ三成殿……。」
抵抗は無駄であると、二人は素直に姿を見せた。そして幸村は三成に駆け寄り、自分の傘を差し出した。
「傘が二本もあれば、分からぬはずもない。私に何の用だ?」
三成は、怒っていると言うより呆れている様子だった。
「用と、言うか……。」
ばつが悪そうにどもる佐助。だが「私は嘘が嫌いだ」とぴしゃりと言い放たれ、幸村は正直に話すことにした。
「三成殿は、雨天になると必ずいずこかへと消えてしまうので、いつもどちらへ向かっているのかと……。尾行などと姑息な真似をして、申し訳のうございました!!」
深々と頭を下げ、二人は三成に謝罪する。
「……そんな理由か。仕方がない、こうまでして来た貴様らの執念に免じて教えてやろう。」
三成は面倒臭そうに溜め息を吐いて、ゆっくりと口を開いた。
「………秀吉様と、半兵衛様のところに行っていた。」
「二人の、お墓に…?」
「雨が降ると思い出す。いや、忘れてはいけないのだ。私の……無力さを。」
三成は幸村の傘をすり抜けると、元来た道を帰って行く。
「石田の旦那、お墓参りはいいの?」
「貴様らを連れて行く気はない。」
既に濡れ鼠と化してしまった三成を、幸村達は慌てて追いかけた。
- 29 -
[*前] | [次#]
ページ: