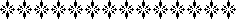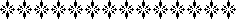三成、頑張る②
「……ってことがあってよ~…。」
「はぁー、石田の旦那らしいねぇ……。」
城に帰るなり、元親は先ほどあったことを佐助に話していた。三成を気にかけ面倒を見る者同士、二人は茶飲み友達のような間柄になっていた。
「別に嫌とは思わねぇけどよ、石田のお守りは骨が折れるぜ…。」
「…はは、確かに~。」
「………。」
吉継に薬を渡し終えた三成は、たまたま二人の会話を聞いてしまった。融通が利かず傲慢とも取れる態度ばかりを取る三成だが、彼は本当は純粋で心根の優しい青年だった。
(…私は皆に、迷惑ばかりかけているのか……。)
元親と佐助の他愛ない愚痴が、真っ直ぐな三成の心に深く突き刺さった。
その晩、元親達に夕食の給仕をしたのはなんと三成だった。
「三成殿!?」
「石田!?」
「石田の旦那!?」
幸村、元親、佐助は驚いたが三成は顔色一つ変えず椀物を運んで来る。彼は着物の上に、どこから購入して来たのかと言うようなふりふりの白い割烹着を着ていた。どちらかと言うとエプロンに近いそれは、三成の腰の辺りで大きなリボンを作っていた。その後ろ姿が何とも可愛らしい。
肝心の給仕のし方はと言うと、豊臣の教育の賜物かなかなか様になっていた。だが、慣れない格好と所作のせいかつんのめって転びそうになっていたのだった。
「み、三成殿、お気をつけて!」
幸村は彼の身を案じていたが、元親と佐助は
((ドジっ子萌え!))
と密かに身悶えていた。
それからと言うもの、三成は例の新妻ルック(?)にて「背中を流す」と湯殿に現れたり「汗を拭け」と手拭い片手に鍛練場に現れたりとかいがいしく世話を焼き、佐助達を驚かせた。いじらしいまでの彼の姿を見て、兵士達は「三成様イイなぁ~!」「俺も尽くされたいっ!」とふにゃふにゃした顔で噂をしていたのだった。元親と幸村も最初は唖然としていたが、三成なりの気遣いを有り難く思い、喜んでいた。
「助かるぜ、石田!」
「三成殿、ありがとうございます!」
「………ああ…。」
笑顔で礼を述べると、三成は照れながら返事をくれる。そのことが何より、二人は嬉しかった。彼らの役に立てているようで、三成も快い気持ちでいたのだった。
今日は吉継、元親、幸村、佐助の四人に得意の茶を点てると、三成は朝から張り切っていた。どの茶器にするかと棚に手を掛け悩んでいたところ、背後に急に気配を感じた。
「…猿飛か。」
「あらまたバレた。」
「貴様、よくそれで忍をやっていられるな。」
三成が振り返ると、佐助がばつが悪そうに苦笑いを浮かべていた。
「石田の旦那が特別凄いせいもあるけど?
まぁそんなことより、何か手伝うことない?」
「無い。」
「あらバッサリ。」
三成は再び、棚の方を向いてしまった。真後ろから見る彼の白いうなじは、なんとも色っぽかった。まるで花の甘い芳香に誘われた蝶のように、佐助は三成の色香に誘われその細い腰を抱き寄せた。
「ねぇ石田の旦那。」
「………。」
三成から返事はない。
「その新妻みたいな格好、すっごく似合っててみんなにも評判いいんだけど……。俺様以外の前でそんなに可愛い格好されちゃあ嫉妬しちゃうって言うかさぁ、なんか面白くないよ。」
佐助が耳元でそう言うと、くすぐったいのか三成が身動いだ。
「私は別に、貴様らを労うために…。」
「そりゃ分かってるけど。恋人が自分以外にも優しいってのは、やっぱ複雑なんだよ。この男心分かってよね。」
「……私も男だが。」
佐助と三成は、周囲に内緒の恋人だった。二人きりの逢瀬などはほとんどできないが、二人のお互いを想う気持ちは本物であった。だからこそ、ここ最近の三成の振る舞いは、佐助にとってあまり面白いものではなかった。
「……貴様は、特別だ……。」
蚊の鳴くような声で三成が言う。
「うん、じゃあ特別賞ちょうだい。」
佐助は甘えるように三成の首筋に額をくっつけた。
「貴様は欲張りな忍だ。真田が『高い禄を要求されて困る』とぼやく訳だな。」
「それは大将がケチなだけだって!」
心外だ!と顔を上げると、佐助は頬に柔らかい何かが触れるのを感じた。それが、三成から贈られたキスであったと気付いたのは彼が腕の中からすり抜けてからだった。
「満足か?」
ふふん、と口の端を吊り上げ、三成が見せた笑顔は小悪魔のそれ。
「もっと、って言いたいけど、それにはもっと働けって言うんでしょ?」
「よく分かってるじゃないか。」
「あ゛~……。石田の旦那、大将と気が合う訳だわ。」
あなたには敵いません、と佐助は肩を竦めたのだった。
「まぁ、真田達とおとなしく待っていろ。最高の茶を点ててやる。」
そう言ってふわりとほほ笑んだ三成。彼のこのような表情は、佐助にしか見せないものだ。佐助はきゅんと胸を高鳴らせると同時に、茶室で待つ主達に言い様のない優越感を覚えたのであった。
だが三成は既に佐助などどうでもいいのか、茶会の準備を再開して上等な茶碗をいくつか並べていた。
そんな彼の、お尻の上でふわふわ揺れる割烹着のちょうちょ結びに佐助の独占欲が刺激される。
(やっぱ、複雑だなぁ……。)
俺にだけ甘えて、俺にだけ迷惑かけて、俺にだけ優しくしてくれればいいのに。
「ま、あの人のお茶は独り占めしたら悪いか。」
無理な願望を胸にしまって、佐助は音もなくその場を後にした。
その後の茶会にて佐助に出された薄墨色の碗は、三成の一等のお気に入りであることを……佐助は知らないのであった。
[ 7/22 ][*prev] [next#]
[mokuji]
[しおりを挟む]