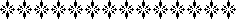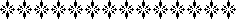六月の花嫁②
三成が帰宅して三十分後、ガチャガチャと鍵の開く音がした。清正が到着したらしい。玄関の方に、ひょこっと顔を覗かせる三成。
「思ったより早く着いたな。」
「飛ばしたからな。」
危ないだろう、と渋い顔をして咎める恋人に、清正はコンビニの袋を差し出した。
「杏仁豆腐買って来た。お前好きだろ?」
三成はその中身を確認すると、プラスチック製のスプーンが二本と、自分が良く口にしている赤いラベルの杏仁豆腐が一つ。それと、清正が好きなメーカーのプリンが入っていた。
…先ほど三成が買った商品と全く同じ物だ。三成は思わず吹き出し、それから高らかに笑い出した。
「み、三成?」
滅多に見ない彼女の大笑いに、清正は少々驚いた様子だ。
「これ、俺がさっき買って来た物だ。」
三成は冷蔵庫を空けて、例のプリンと杏仁豆腐を彼に見せた。
「お前が言う通り、俺達は運命なのかも知れんな。」
白い歯を見せて、三成が笑った。釣られるように、清正も声を出して笑った。
「三成。」
レポートを書くために、宣言通り三成のパソコンを占拠している清正。そんな彼が、液晶画面に向かいながらちょいちょいと三成を手招きした。
「ちょっと手伝ってくれ。」
「何だ?建築は俺の専門外だぞ。」
飲んでいたホットコーヒーをテーブルに置いて、三成は清正の隣りに移動した。
「いや、日本語を教えてくれ。こっちの資料をうまいことまとめたいんだが、どう文章を組み立てたらいいか…。」
「…なるほど。俺の出番だな。」
流石文官、頼りになるぜ、と茶化しながら、清正は胡座をかいた自分の膝の上に三成を乗せてパソコンに向かわせた。
カタカタと音を立てて、三成が発光する画面上に文章を紡いで行く。少々堅苦しい気がしなくもないが、分かりやすい文面だった。キーボードを軽快に叩く白くて美しい指。そこで光る指輪を見て、清正は昼間見た光景を思い出した。
「大学から実家帰るときに、教会の前を通るんだけどさ。今日、そこで結婚式やってた。」
「ふぅん。」
三成は、文字を打つ手を止めずに、さして興味もなさそうに返事をした。
「新郎も新婦も、すごく幸せそうだった。」
「そうか。」
「ウェディングドレスが日光に反射して、綺麗だった。…ジューンブライドって、お前も憧れたりすんのか?」
「……清正。」
キーボードから手を離し、三成が清正を見上げた。
「そんなに慌てることはないぞ。」
「慌てる、って、俺はそんな……。」
確かに清正は焦っていた。三成と一緒になりたい気持ちは日々大きくなるばかりなのに、自分はまだ学生の身分でそれは現実的ではない。彼女は自立してるが自分は子どもで。そんなジレンマに、どこか気持ちに余裕がなくなっていたのだった。
「俺は今すぐでなくていい。いつか、本当の家族になれればそれで。」
清正にもたれて三成が言う。
「籍を入れるだけでも十分だが、できればお前の隣でドレスが着たい。」
ふわっと優しくほほ笑む三成を、清正は強く抱き締めた。ちょっと自分がかっこ悪いと思ったから、顔を見られないようにした。
「白無垢も、きっと似合うだろうな。」
「お前は、洋装より和装の方が似合いそうだな。」
「じゃあ両方着るか。両方見たい。」
「そんな真似をしたら、費用が幾らになると思っている。この馬鹿。」
何年先か分からぬ将来のことを考えて、二人はほほ笑み合った。
「まぁ、まずはしっかり単位を取って卒業することだな。」
「…三成先生の文章力を分けて頂きたい。」
三成は再び文字を打ち込み始めた。彼女の構成力を目の当たりにし、「はぁ」とか「なるほど」とか感心して声を上げる清正は若干間抜けな感じだった。
(俺は今でも十分幸せだ。これ以上を望めば、罰が当たりそうだからな…。)
ゆっくりで構わない。きっとこいつ以上に、俺を幸せにしてくれる人物なんていないのだから。
三成は、背中に感じる体温に小さく笑みを零した。
[ 10/22 ][*prev] [next#]
[mokuji]
[しおりを挟む]