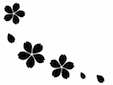モノクロの先にある世界・前編
※全体的には赤黄ですが、モブ(お父様)赤で近親相姦(のようなもの)な描写もあるので何でも許せる方のみお読みください。
小さい頃母が他界してしまってから、全てが狂い始めた。
母が自分の全てだと言うほどに愛して愛して、愛し合っていた父は、その日から仕事以外では部屋に閉じこもるようになった。頻繁に会話をするような一般的な親子関係を築いてはいなかった赤司は、そんな父に意見する事も心配して部屋へ様子を伺いに行くこともしなかった。子供の自分が何を言ったところで変わるような人ではないと幼いながらも理解していたからだ。時間をかけて傷を癒して、その内またいつも通りの、近づく事を躊躇うような威厳と風格の溢れる父に戻ることだろう。そう考えていた。勿論赤司自身も母を亡くし身が引き裂かれるような痛みを胸に抱えていたが、己とは比べ物にならない父の憔悴ぶりを見ていると冷静になれた。
けれどそれが1ヶ月ほど続いたある日。なんの連絡もなく唐突に父が赤司の部屋の扉を開け放った。1ヶ月振りに見た父は病的な痩せ方をしていて、目の下も隈が酷くまるで別人のようだった。
そもそも父が赤司の部屋に来たのは初めてで、今まで用がある時は使用人を通して赤司が呼び出され父の部屋へと赴いていた。だから自分の足でわざわざ赤司の部屋に来たことに不思議に思い、それ程大事な用があるのかと扉の横で立ち尽くす父へと視線を持っていくと、目が合った父はこれでもかと濁った赤い瞳を見開いた。はくはくと口を開閉させ、こちらをじっと見る光のないその目から涙がこぼれ始める。見たことの無い父の涙にぎょっ、としたのもつかの間。駆け出した父に勢いよく抱きしめられた。驚いて何も言えない赤司をいい事に暫く痛いくらいに強く抱きしめられていたが、ふと絞り出したかのような父の声が耳元で聞こえてどうにか意識を浮上させた。母の名前だった。愛しくて堪らないというような聞いたことの無い蕩けた声音で母を呼び、やっと父の体が離れていくと思った瞬間、視界がぶれる。目の前には赤。自分と同じ色の髪。口に当たる感触。何故自分は父親にキスをされているのか。混乱する赤司は固まり、声さえも出せなかった。ただただ色のある瞳で自分を見つめる父を見開く瞳で見つめ返す事しかできなかった。名残惜しそうに離れていった唇がまた母を呼ぶ。何を言っているのか。どうして俺を見て母の名を呼ぶのか。理解したくはなかったが、自分の優秀な脳は答えをすぐに引き出す。父は自分と母を重ねて見ているのだ。
「ずっと…ずっとお前を探していたんだ…1ヶ月もどこに行っていた…」
赤司の頬を撫でながら言われた言葉に眉を寄せる。感触を確かめるように執拗に撫でてから、鳥肌が立ってしまう程の甘い声で囁かれる。
「…愛してる。もう俺から離れていかないでくれ」
俺は母ではない。そう言おうと開いた口をまた父に塞がれた。それどころか舌までも侵入してきて流石に抗議するように父の胸を叩く。しかしその腕を捕まれ、押し倒され、体をまさぐられ。まだ小さい子供だった赤司に大人の父を跳ね除ける力はなく、求められるままに体を好き勝手に触られた。とうとう後ろにまで伸びてきた父の手に、赤司は一層暴れる。
「父さん!!俺は母さんじゃない!!」
「ああ、泣かないでくれ。泣いている詩織も可愛いが、俺はお前を愛したいだけなんだ。俺の愛を受け止めてくれ」
「父さん…っ!!!」
赤司の声など少しも聞こえていないのか、視線の交わっているはずの父からは歪んだ笑顔しか返ってこなかった。絶望する赤司を慈しむように撫でながら、父の手が本人も触ったことの無い場所へ入り込む。母がいなくなってから、父は狂ってしまった。狂った父は母を求めるあまり、顔立ちの似ている赤司に母の幻想を重ねてしまった。痛みで滲む視界で父を見る。自分に覆いかぶさり色情の溢れる表情で赤司を愛おしそうに見つめる光なんて一切感じないその目には、もういないはずの母しか映っていないのだろう。自分の中に入ってくる異物を感じながら、赤司はそこで考える事を放棄して瞳を固く閉じた。
世界はこんなにモノクロだっただろうか。
その日から、父の赤司に対しての対応ががらりと変わった。用がなければ視界にさえ入れずに、長い時では同じ家に居ながらも1ヶ月顔を合わせないなんてことが赤司と父にとっては普通であった。けれど今は毎日のように赤司の部屋へ来ては愛を囁き、体を求め、女のように扱う。女性物の服や化粧品を渡された時には既に、赤司は思考を停止させてしまっていて、何もかもがどうでも良くなっていた。父の好きにさせて満足すれば帰ってくれる。早くこの毎晩続く地獄のような時間が終わって欲しい。着替えさせられ、メイクさせられ、元々母親似で中性的で整っていた赤司は、より一層女性のような、まるで母を思い出す美しさになった。赤司の真っ赤な唇を、真っ白な肌を、上品でいてしかし可愛らしいワンピースを眺めながら、いつもの様に愛の言葉を囁く父。そしてそれを何の色もない顔で聞き、押し倒される赤司。
もう、何もかもが、心底どうでもよかった。
そんな生活が続いたまま、中学に上がった赤司はバスケ部に入り、そして生まれて初めて恋をした。
自分とは違う意味で何かと有名らしい黄瀬涼太。人気モデル、運動神経抜群で色んな部活から助っ人を頼まれている等々、一人歩きしていた噂だけは赤司の耳にも届いていたがさして気に止めてもいなかった。学年は同じでも、クラスもちがければ部活も違う、黄瀬涼太との接点など1つもない。関わる事も無いだろうと頭の隅に追いやっていた。
それは土砂降りに近い雨の日だった。部活が終わり先輩に頼まれた戸締まりも終わり帰ろうと下駄箱に行った時。何時もなら既に校舎に学生は残っていない時間であるのに、下駄箱の前で座ってどこか詰まらなそうに携帯を弄っている黄色が目に入った。丁度そこは赤司の下駄箱の前だった事もあり素通りは出来ず、イヤホンをして俯いている所為で赤司に気付いていない黄色に近寄った。あと1歩の距離まで近づいてもまだ気付かないらしく軽く声もかけてみたが一向に気づく気配がない。ここまでくればもしやわざとなのかと携帯と睨み合う彼と同じ目線になる様にしゃがみ込み、両手で頬を挟んで少し強引に顔を自分の方へと向けた。
「…え…?」
目の合った蜂蜜色の瞳は徐々に大きく見開かれ、それに比例して口も間抜けにあの形でカパリと固まった。片方のイヤホンが落ちたことにも気づいて無さそうなその抜けた表情に無視していた訳では無かったと悟り男にしては滑らかなその頬から手を下ろす。普通なら何とも不細工な顔になっているであろう表情も、目の前のさらさらと触り心地の良さそうな柔らかな金髪の持ち主はそれすらも1枚の絵画のように見惚れる美しさであった。こんなに綺麗に整った容姿は初めて見たかもしれない。
「なに、え…、誰?」
いきなり眼前に現れた赤司に心底困惑した視線がこちらに向く。綺麗な瞳をパチパチと瞬かせ、真っ直ぐに赤司を見つめるそのとろりと甘そうな蜂蜜に目を奪われた。
「…そこ、俺の下駄箱があるんだ。退いてくれるか」
「えっ、あ、ごめん!」
ハッとした彼は直ぐに立ち上がりその場から退いて道を開けてくれた。此方を伺いながら隅に寄り、再度そこで腰を下ろす。それを横目で見ながら上履きと自分の靴を交換し履き替えて、鞄から折り畳み傘を取り出した所で未だに下駄箱の前から動こうとしない彼が気になった。ここに座って一体何をしているのか。いつもの赤司なら通り道に人が座っていたところで視界にすら入れないのだが、どうしてだか眩しくキラキラと自分の視界に映る黄色から目を離せなかった。だかららしくも無く知り合いでも何でもない彼に声をかけてしまったのだ。
「どうかしたのか」
「…ん?俺?」
「そうだ。今俺の目の前にはお前しかいないだろう」
「あ、いやそうなんだけどさ。まさか話しかけられるとは思わなくて。…えっと、ここの下駄箱って事は同級生、だよね。名前、聞いてもいい?」
「赤司征十郎だ。此方も名前を聞いても?」
「あ、うん、黄瀬涼太、です。赤司君って呼んでもいい?」
「好きに呼んでくれ。で、黄瀬はどうしてこんな所で座ってるんだ?」
「傘、忘れちゃって。今家族に迎えに来てもらおうかと連絡してるところなんだけど、繋がらなくて」
「今日の降水確率は90%だっただろう」
「いやぁ、朝寝坊しちゃって急いでたから天気予報見てなかったんだよね」
気恥ずかしげに頬をかく黄瀬涼太と名乗った彼に、何処かで聞いた名前だなと一瞬考えを巡らせる。そういえば、女子生徒の間で騒がれていたモデルの名前が確かそんな名前だったような。走って帰るしかないかなぁ、と外に目を向けながら呟き、黄瀬がゆっくりと立ち上がる。走って帰る。この土砂降りの中を?
「家、近いのか」
「全然。でもこのままここに居るわけにもいかないし、腹くくるしかないかなって」
屈伸し始めた黄瀬に、本気で走って帰ろうとしているのだと分かった。特に知り合いでも友人でもないのだから雨に濡れようがそれで風邪を引こうが関係ない。だから放っておけばいいのだ。気をつけて帰れよ、と一言労い、黄瀬を残して帰ればいい。後は帰るだけ、なのに。
「…この傘で良ければ使ってくれ」
無意識に動いた自分の口が紡いだ言葉に、表情には出さなかったが赤司自身驚いた。俺は目の前に困ってる人がいるからと、進んで手を差し出すような性格だっただろうか。否。それが親しい友人や家族、親族など、助けて此方に利益がある相手であれば助けるだろう。しかし会ったばかりの他人に近い人間であれば助けない。迷いなく見捨てる。自分はそういう冷めた性格だったはずだ。
「いやいや、そうしたら赤司君がずぶ濡れになっちゃうじゃん。借りられないよ。傘2つ持ってる訳ではないんでしょ?」
赤司の提案に黄瀬も驚いたのか、両手を大袈裟にぶんぶんと振った。
「ああ。だが俺は迎えの車が来てるから校門まで走ればそんなには濡れないよ。繋がるか分からない連絡を待つより確実だと思うけど」
興が乗っただけ。瞬時に自分の珍しい行動をそう判断する。黄瀬は少し考える素振りを見せた。小さく唸って悩んでいるその手を掴み赤司の黒1色のシンプルな折り畳み傘を乗せれば、申し訳なさそうに眉を下げて笑みを作った。
「じゃあ、お言葉に甘えて貸してもらおうかな。でも校門までは一緒に傘入っていってよ。男二人じゃ狭いだろうけど、傘の持ち主を雨に濡らすなんて俺が嫌だから」
ね?と隣に立った黄瀬は人好きのする笑顔で赤司を見やった。その笑顔に赤司の胸が小さくコトリと音を立てる。聞いたことの無い軽い音だった。1度だけしか鳴らなかったが、もう少し聞いていたくなるような心地のいい音。
「…分かった。隣、失礼するよ」
傘を広げて赤司を待っていた黄瀬に小さく笑いかけ、肩の触れる距離で隣を歩く。
「相合傘ってやつだね」
「そうだな」
「俺相合傘したの初めてかも」
「奇遇だな。俺も初めてだ」
「じゃあお揃いだね」
悪戯っぽく言ってくる言葉に笑みを返し、校門までの短い距離をぽつぽつと雑談しながら歩いた。あまり他人に心を開くことの無い赤司だったが、黄瀬の隣はとても居心地がよかった。初対面の筈なのに少しの距離も感じさせない黄瀬のコミュニケーション能力の高さと空気を読んだ場の繋ぎ方には感心しきりだった。今まで話したことのある誰よりも肩の力を抜いて話すことが出来た。まるでまだ元気だった頃の母と話しているかのような。赤司が1番気を許している同じバスケ部の仲間達でさえまだここまでの感情は向けていないというのに、たった数分話しただけで赤司の関心を引いてしまった。確かにこれは、周りに騒がれる人材かもしれないな。隣で微笑んで身振り手振り話を降ってくる黄瀬を見ながら、そんな事を考えた。
次の日の昼休み。昼食をとりに学食へ行こうと席を立とうとした時、教室内が少しザワついた事に気づいた。出入り口には女子の群れが出来ており、その中心にいたのは昨日知り合った黄瀬涼太だった。女子にヘラヘラと手を振って愛想を振りまいて、ドアの横から教室内をきょろきょろと見回していた。暫くさ迷っていた視線が赤司を見つけると、途端に愛想笑いからぱあっと花が咲いたような笑顔になってニコニコと早足で赤司の机に近寄ってくる。
「やっと見つけたよ赤司君。昨日はありがとう!おかげでずぶ濡れにならずに済みました」
軽く頭を下げて、綺麗に折り畳まれた傘と何やら沢山の小袋が入ったコンビニ袋を手渡される。
「…これは?」
「ん?昨日借りた傘」
「そっちじゃない」
「お菓子の詰め合わせの方?傘借してくれたお礼。貰ってくれると嬉しいな」
「お礼、…。姿と名前しか知らない相手を探すのは大変だったろう。そのまま捨ててくれても構わなかったんだけどね、傘」
「そんな訳にはいかないっしょ。なんかこの傘ブランド物っぽいし。…もしかして食べられないお菓子とかあった?」
しげしげと物珍しげにお菓子を取り出し眺めていると、不安そうな声が向けられる。お菓子の袋から黄瀬に目線を戻すと、少し眉を下げて小首を傾げたどこか子犬を思い出させる可愛らしくさえある姿が目に入る。これだけ顔が整っているとどんな表情や仕草でも様になるなと思わず感心してしまった。
「いや、こういうものを食べた事がないから珍しかっただけだ。ありがとう、後で頂くよ」
「えっ?!お菓子食べた事ないの?!」
「焼き菓子や生菓子ならたまに食べるんだが、こういったものはないかな」
「…昨日も少し思ってたんだけどさ、赤司君ってもしかしていいとこのお坊ちゃん?」
「…まあ、黄瀬達のような一般的な家庭でない事は確かかな」
「そっか。…赤司君も大変なんだね」
「ん?」
「いや、なんでもない!赤司君これからお昼どうするの?俺学食行こうかと思ってるんだけど、もし同じだったら一緒にどう?折角知り合えたんだしもっと赤司君と話したくて」
「俺も今日は学食だから是非ご一緒させてもらおうかな」
「良かったあ!じゃあ早く行こ!」
周囲に花が散りばめそうな様子で赤司の腕を取り、楽しげな足取りで学食まで引っ張られる。それをどこか微笑ましい気持ちで眺めながら大人しく黄瀬に案内される事にした。
それから黄瀬はほぼ毎日のようにわざわざ赤司の教室へ足を運んではお昼一緒に食べようと誘ってくるようになった。そんな黄瀬に付き合っている内に赤司の中で黄瀬の存在がどんどんと大きくなっていく。今まで赤司に構おうとしてくる友人らしい友人がいなかったからかもしれない。コロコロと変わる表情も見ていて飽きない。モデルという芸能界にいるからか、黄瀬の話はどれも聞いているだけでもとても興味深くとても楽しかった。黄瀬と一緒にいる時間は何かと忙しい赤司にはとてもいい息抜きになっていた。
「あの黄瀬と最近随分と仲が良いらしいな。どういう風の吹き回しなのだよ」
こちらも恒例になりつつある部活仲間の緑間との将棋の最中。何時もなら勝敗が決まるまで雑談などしようとしない目の前の見慣れた仏頂面が珍しく口を開いた。
「別にどうともしないけどね。ただ普通に友人関係を築いているだけだよ」
「…お前がか?」
「俺が友人と仲良くすることがそんなに可笑しいか?」
「自分のテリトリーに他人を入れる事を誰より嫌うお前が、性格も趣味も真逆だろう黄瀬と、か?」
「あいつはそこまで馬鹿ではないよ。成績は…まああれだけど、ちゃんと色々考えてる。踏み込んでいいラインを理解して会話を弾ませてくれる。芸能界で揉まれてる所為か黄瀬はかなり大人だよ。社交性は俺以上だしな。というより、お前が黄瀬を知ってる事に驚きだ。お前ら接点あったか?」
「…最近噂になっているのだよ。噂話の類に興味のない俺にまで届く始末だ。赤司と黄瀬が毎日のように昼を共に過ごし、楽しげに会話をしているとな。入学当時から色々と有名だったお前達が急に親しくなれば誰だって気になるだろう。品行方正を絵に書いたようなお前と、浮ついた噂の絶えない黄瀬とでは、どうあっても合いそうには見えないからな」
一理ある。あの雨の日に偶然黄瀬と会い、たまたま興が乗って自ら話しかけなければ、黄瀬とはずっと他人同士だっただろう。同学年ではあるからもしかしたら廊下ですれ違ったりはしたかもしれないが、それだけだ。すれ違うだけでお互いを認識はしない。ここまで親しくなれたのは、あの日赤司が用事があるらしい先輩に体育館の戸締りを頼まれて帰りが遅れ、黄瀬が傘を忘れて下駄箱の前で立ち往生していて、そんな黄瀬が気になり珍しく赤司から声をかけた。色んな偶然が重なったからだ。
「…まあ確かに、偶然が重なって黄瀬と知り合わなければ、あいつと顔を合わせる事も話す事もなかっただろうな 」
「偶然?」
「雨の日に傘を忘れた黄瀬に、俺が傘を貸したんだ」
「それは…」
なにやら難しい顔で黙り込んだ緑間を無視して手元の盤に目を戻す。大方「お前が人助け?明日は嵐か?」とか失礼な事を考えているに違いない。駒を置けば、少しして盤に視線を戻していた緑間も駒を動かした。
「…黄瀬とはどんな話をしているのだよ」
「お前も気になるのか。そうだな、天気とか
当たり障りのない会話から、最近食べて美味しかった店、面白かった出来事、モデルの仕事の話もよく聞いたかな。あとは恋の話とかもたまにするか」
「恋の話?!!?!」
急に大声を出した緑間は、まるで化け物でも見てる様な顔で穴があくほどに赤司を凝視した。その声に驚き手に持っていた駒を落とした赤司は恨めしげに緑間を睨む。
「なんだいきなり。盤を挟んだ至近距離で大声はやめろ。びっくりするだろう」
「驚いたのはこっちの方だ。お前が恋の話?好きな相手でも出来たというのか?」
「そういう訳じゃない。それにお前が考えているような内容の話ではないよ。黄瀬がされて驚いた告白内容だとか、執拗いストーカーの話とか、芸能界のドロドロした恋愛模様だとか。そういう類のものだ。俺は大体聞く側に徹してる。というか基本黄瀬の話を聞いて相槌打ったり聞かれた事に返事するくらいだ」
「そうか、…そうか」
赤司の言葉を聞いて緑間が疲れたような安心したような、そんな深いため息を一つつく。眼鏡を人差し指と中指で持ち上げすぐにいつもの調子に戻った緑間は、落とした駒を拾っている赤司にすっかり仏頂面に戻った顔を向けた。
「聞く側に徹しているお前と話していて、それで黄瀬は楽しいのか?毎日クラスの違うお前を誘いに行く動力に見合った利益ある会話を出来ているのか?」
「…それは、どうだろう。あいつはいつも楽しそうに率先して色んな話をしてくれるから、俺が話すより黄瀬の話を聞いている方が盛り上がるんだ。俺の冗談は笑えないとお前もよく言うだろう。だが、言われてみれば聞いてるだけでは駄目かもしれないな」
話のレパートリーが多い黄瀬は、いつも楽しげに会話を振ってくれていた。黄瀬も喋る事が好きだと言っていたから、赤司から話を振ることが少なくてもさして気にしないだろうと思っていた。黄瀬の耳によく通る心地のいい声を邪魔したくないという気持ちもあり毎回少しの相槌を打つだけにしていたのだが、やはり最低限の会話のキャッチボールは必要だろうか。
「明日も昼一緒に食べる約束をしているから、ちょっと聞いてみるか」
「本人に聞くのか…。お前は黄瀬との時間を楽しんでいるんだな」
「ああ。黄瀬と話す時間はとても楽しいよ。俺の知らない色んなことを知っているから、毎回何かしらを教えてもらってる。今日はクレープという食べ物の事を知ったよ。黄瀬の薦める菓子はいつも美味しいから今度食べてみようと思ってる」
「…クレープ」
「それに、あいつといると心が軽くなる。世界の色が鮮やかに見える。今まで俺の周りにはいなかったタイプの人間だよ。黄瀬が周りから沢山の好意を向けられるのは、見た目の善し悪しだけじゃなくあのちょっと抜けた構いたくなる性格も関係しているんだろうね。見ていてとても面白い。綺麗なものを手元に置きたがる心理というものが今は手に取るようによく分かるよ」
赤司の話を黙って聞いていた緑間がまた何か言いたげな顔をしだしたのを見ないふりをして、最後の一手を打つ。
「王手、だ」
パチリ。子気味のいい音を立てながら赤司が盤の上に置いた駒から手を離す。完璧なまでの勝利だった。
「…ありません」
「ありがとうございました」
いつもなら今回も勝てなかったと人きしり悔しがるところなのだが、今はそれよりも目の前の目に痛いくらいの鮮やかな赤色が発した言葉を頭の中でループさせることに忙しかった。先程の黄瀬の話をしている時の赤司は、恋や愛というものに滅法疎い緑間でさえ勘ぐってしまう程の甘い空気を醸し出していた。この男には似合わない優しげな微笑みと、言葉の節々から匂ってくる春の気配もセットで黄瀬について語る様はどう見ても。
「…先程の自分が、どういう顔をしていたのか、気づいているか」
「顔?いつも通り普通の顔をしているだろう。なんだ、不細工とでも幼稚な罵倒がしたいのか?勝負に勝てないからと俺に当たるな」
「…はあ」
頭が痛い。思わず額を抑えると目の前の赤色は違うのか?と首をかしげ出す。
まさか赤司が黄瀬に恋愛感情を抱いているとでも言うのか。あの赤司が恋。しかもどちらも同じ性別の男で、相手が黒子ならまだしも黄瀬は赤司より背も高ければ体格だってどう見ても女子の代わりには…いや、考えるのはよそう。これはきっと自分の考えすぎだ。見当違いだろう。きっとそうだ。そうに決まってる。
「…先に帰らせてもらうのだよ」
「検討はいいのか?」
「今日はいい。済まないが先に失礼する」
片付けを頼むと一言残して、緑間は早足で部屋から出ていった。出ていく直前に見えた緑間の顔は部活の後よりも随分と疲れていると分かる表情だった。緑間の考えなど分かるはずもない赤司は調子が悪かったのか等と全く見当違いな答えを導き出していた。
「お前は俺と一緒にいて飽きないのか?」
「え?どうしたのいきなり」
次の日の昼休み。昨日緑間に問われた内容を飾らずにそのまま黄瀬に投げかけた。珍しく赤司から話を振ったこともあって黄瀬は少し驚いた顔をしてこちらに振り向いた。
「性格が真逆で合わないだろうと周りから思われてた俺と黄瀬が最近よく一緒にいるからか、変に噂になっているらしい」
「あー、そういえば少し前からそんな噂流れ始めてたなぁ」
「気づいてたのか」
「まあね。というか俺と赤司君が一緒に居る時結構周りからの視線感じてたし気づかない方が可笑しいって」
「そうなのか」
「…え、まさか気づいてなかったとか?」
「昔から自分が色々と目立つ部類だと自覚はあったからね、いちいち周りの目を気にするのは疲れるから視界に入れないことにしてる。今回の事も部活仲間から聞いたんだ」
「ほぇー、流石赤司君。…あ、もしかして、俺と一緒にいるの、疲れる…?」
急にトーンの下がった声音で、赤司を伺うように問われる。向けられている視線はどこか悲しげに垂れ下がっていた。赤司の次の言葉を怖がっているようにも見えて、どうしてそんな顔をするのかとこちらまで悲しくなる。
「どうしてそうなる」
「や、だってほら、自分で言うのもなんだけど俺っていい噂と同じぐらい変っていうか悪いっていうか、そういう噂も多いでしょ?けど赤司君は殆どが憧憬や羨望の噂で、あったとしても妬みの類だけじゃん。俺といる所為で赤司君まで俺の悪い噂かぶることになってたら、赤司君でなくても誰だって迷惑だと思うだろうし疲れるかなって」
「俺は好まないと感じる人間にははなから同じ空間にいる事を許可しないよ。黄瀬の悪い噂というのも聞いた限りでは全て虚言妄言の類じゃないか。お前が意外と真面目で真っ直ぐな奴だとはこれだけ共にいる時間が増えれば誰でも気づくさ。黄瀬との時間を俺は存外気に入ってるんだ。噂話の一つや二つ、今更増えたところでどうとも思わないよ。寧ろお前との噂なら大歓迎かな」
黄瀬の根も葉もない噂は、仲良くなってから無意識に耳に入れるようになった。赤司自身の噂は毛ほども興味が持てないのに、黄瀬の噂はどこからか聞こえてくる度に耳を澄ませて聞いてしまう。何故かとても気になった。黄瀬は周りからどう思われているのか、どんな噂があるのか、その噂の中に赤司の知らない黄瀬がいるかもしれないと思うと、聞かずにはいられなかった。
「…ありがとう。そう言ってくれて、すごく嬉しい」
「そもそもさっきも言ったが自分の噂は気にするだけ面倒だから全て聞かずに無視してる。だから増えたって気づきすらしないよ」
「あはは、確かに。赤司君は大物だなぁ」
先程までの不安に揺れていた視線は柔らかく細まり、黄瀬らしい爽やかな笑顔でくすくすと笑い出す。そんな楽しそうな黄瀬の顔をずいと覗き込んだ。まだ赤司の問に答えを貰っていない。
「で?」
「ん?え?」
「お前は俺と一緒にいて飽きないのか?無口という訳では無いが、俺はお前のように話し上手でもないだろう。いつも黄瀬の話を聞いてるばかりで、お前の方が疲れないのか」
「そんなの伝わってると思ってた。俺赤司君と話せるこの時間が凄く好きだよ!そもそも誘ってるのも毎回俺なんだから、嫌だったら最初から誘わないって。俺も赤司君といれる時間が今は1番好きだし、最近はこの昼休みのために学校来てるって言ってもいいくらい。赤司君って変に気を使ったり特別な事求めたりしないでしょ?だから赤司君の隣ってすっごい居心地がいいんだよね」
「…そうか」
「俺、思ってたより赤司君の事めちゃくちゃ好きかも。こんなに友達と頻繁に会いたくなるの初めてだよ。もう俺たち親友って言ってもいいんじゃないかな…!ね!」
少し興奮しながら「実は親友ってのにずっと憧れてたんだあ」とそわそわ赤司の返答を待っている黄瀬の頭をわしゃわしゃと撫でる。それに一瞬きょとんとした後、ふわりと甘く笑った。気持ちよさそうに目を細める姿はとても微笑ましく愛らしい。
(友達…。好き、か)
友人としては最高に嬉しい事を言ってもらえた筈なのに、赤司の心はキリキリと痛みを発するばかりだった。分かってしまったのだ。黄瀬の好きと、赤司の好きは種類が全く違うことに。黄瀬は暖かい春の日差しのような感情を、赤司は砂糖を煮詰めて密のようにとろとろにした甘く、そして重い感情をお互いに向けていた。俺はどうやらいつの間にか、黄瀬に心底惹かれてしまっていたらしい。持て余すばかりのこの感情に名前をつけるならば、恋以外にはないだろう。
(…せめて、気づきさえしなければ、そうしたらまだ…)
ずっと恋愛など自分とは一番縁のないものだと見向きもしていなかった赤司は初めての感情に戸惑い、そして人生二度目の絶望を味わった。
頭のどこかで狂った父を軽蔑し嫌ってさえいた自分が初めて好きになったのは同性の男で、その事実があの父と同じで自分も狂っているのだと思い知らされた。父のようにはならないと全てを完璧に真っ直ぐ歩いてきたはずなのに、俺は一体どこで間違えたのだろうか。
この感情は気の所為だとどんなに足掻いても、視界に入る眩しい黄色はそんな赤司の小さな抵抗を馬鹿にするかのように近づいてくる。無邪気な笑顔が自分に向く度に乱される心は、理性を少しずつ崩していった。
どんな宝石よりもきらきらと綺麗な蜂蜜色の瞳が愛おしい。耳に入る心地の良いまだどこかあどけない声が愛おしい。さらさらと癖のない、しかし触ればふわりと手に絡む髪が愛おしい。手入れをしているのか潤った薄い桃色の形のいい唇が愛おしい。手に吸い付く白く滑らかな肌が愛おしい。綺麗に鍛えられた長い手足が愛おしい。
どこまでも自分の気持ちに真っ直ぐで一直線で、裏表のない眩しいくらいの黄色。ああ、欲しい。自分のモノにしたい。
頭のてっぺんから足の先まで、黄瀬の全てが赤司を魅了した。ころころと変わるあの顔を自分だけに向けてほしい。他に何も考えられなくなるくらい自分の事で頭をいっぱいにしてほしい。どうしたらこちらを見てくれる。どうすれば。
どうすれば。
そして2年になり、まるで運命のように黄瀬はバスケ部へと入部してきた。
─END─
次の後編で終わります…多分!!