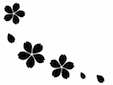5
「…あ、黒子っち!火神っち!」
部活が終わりいつも通り校門へ行くと、少し先の方から明るい声が僕達を呼んだ。
周りにいる女子の群れの中から、笑顔の黄瀬君が顔を出した。
「久しぶりっス!二人共!」
手を振りながら目の前まで走ってくると、勢いをそのままに思い切り抱きつかれる。
予想してなかったために勢いに飲まれて倒れてしまいそうになったけれど、どうにかよろけるだけに留めて黄瀬君を自分から引き剥がした。
「…っ、危ないじゃないですか黄瀬君」
「久しぶりなんだしいいじゃないっスか!」
何がいいのかさっぱりだが、とにかく話を聞くために近くのファミレスに入ることにした。
最初は邪魔だろうと思って火神君は帰ろうとしていたが、黄瀬君がそれを止めて二人で話を聞くことになった。
僕の隣に火神君、テーブルを挟んだ前の席に黄瀬君が座る。
そして注文をしたところで黄瀬君が口を開いた。
「…俺、青峰っちのこと、諦めることにしたっス」
ニコリと音がしそうな笑顔でそう告げる。
無理をしてると分かる、そんな笑顔で。
「…青峰君と、何かあったんですか?」
「ううん、何も。ただ、自分の中で1つ賭けをしてたんだよね」
「賭け…ですか?」
テーブルに置いてあるコップをカラカラと鳴らしながら、黄瀬君の顔が少しずつ曇っていく。
「この間、IH準決勝で青峰っちと俺対戦したよね?でね、もしその試合に勝てたらまた青峰っちに想いを伝えようって決めてたんス。負けたらきっぱり諦めようって。…で、結果は二人も知ってるっスよね」
「…負けてしまったから、諦めるってことですか?」
「そういうことっス」
それに、もう潮時かなって思ってたところだったしね。
僕が心配そうな顔をしたのを気にしてしまったのか、すぐにそう付け加えられる。
暫く重い空気が流れていたのだが、僕の隣から少しおずおずとした口調で火神君が疑問を投げかけた。
「…あのさ、ちょっといいか?諦めるとか諦めないとか、何の話だ?」
「あ、そういえば火神っちにはまだ言ってなかったっスね。俺、青峰っちが好きなんスよね。ライクじゃなくてラブの方の」
「…へぇ」
「…へぇって、それだけ?」
もっと驚かれると思ったのだろう黄瀬君は、反応の薄い火神君に逆に驚いている。
当の火神君は特に気にする素振りもなくちょうど店員さんが持ってきてくれた料理を食べ始めた。
「それだけってなんだよ」
「…もっと驚くか引くかのどっちかだと思ってたから」
「男同士なんて、アメリカにいた頃結構周りにいたからなぁ」
両頬をリスのように膨らませて食べながら、昔を思い出しているのか目を瞑り話す。
「俺だって向こうにいた頃、付き合ってたヤツいたし。ていってもほんの2週間くらいだけどな」
そんな爆弾発言に、僕も黄瀬君もガタンと椅子を揺らした。
「えっ?!まじで?!?」
「おう。まじで」
何でもないと言うふうにあっけらかんと答える火神君に、開いた口が塞がらない。
そんなまさか。
火神君に恋愛方面で先を越されているなんて。
というか、恋人がどういうものなのか分かっているかも怪しいというのに。
「えっと、恋人ってどう言う人の事をいうのか、ちゃんと分かってますか?友人と恋人は違うものですよ?」
「黒子お前、どれだけ俺の事バカにしてんだ。それぐらい分かってるに決まってるだろ」
「本当ですか?ただ好きなだけではなく、手を繋ぎたいとか、キスしたいとか、そう思える相手の事ですよ?」
「だから分かってるっつーの!!その可哀想なものでも見るような目で言うのやめろ!」
いつの間にか平らげられていたお皿を横に移動させながら眉を寄せる火神君。
心底心外だと言わんばかりのふくれ面だ。
ちらりと向かいの席に視線を向ければ、そこにはキラキラとして楽しそうな表情をした黄瀬君がいた。
「どういう経緯でお付き合い始めたんスか?!どっちから告ったの?!」
「相手からだな。俺が日本に行くまででいいから付き合ってほしいって言われて、普通に好きだったしいいかなって」
「何かそれ火神っちはその人の事恋愛の方での好意は無かったって聞こえるんスけど?!」
「まぁ、そうだな。どっちかと言えば友達として好きだっただけだな」
まるで女子の会話の内容の様で何だか入りにくい。
さっきまでの暗い空気は嘘だったかの様にキャッキャと周りに花が咲いている。
聞く側に徹しようとジュースを飲みながら2人の会話に耳を傾けた。
「じゃあ火神っちは友達とヤレるの?!セックスしたんスか?!ちょっと見損なったっス!!」
「ぶっ!?」
セックスという単語に思わず飲んでいたジュースを吹き出しそうになる。
ジュースが器官に入り、ゴホゴホと噎せてしまった。
「わぁ?!黒子っち大丈夫!?」
「…黄瀬君、ここはファミレスですよ。僕達の他にもお客さんいるんですから、そういった単語を大声で言うのは控えてください」
「あ…そういえば…」
忘れてたのかよ、と笑う火神君に、火神っちの所為っスよ、と軽く睨む黄瀬君。
しかしすぐに笑顔に戻り、そわそわしながら火神君の服の袖を少し摘み無邪気な声で問うた。
「ねぇねぇ、来週の日曜日って空いてる?」
「日曜か?あー、部活確か無かったよな?」
「無かったと思いますよ」
「ホントっスか!?じゃあさ、良かったら俺の家来ない?その日仕事も無いし、話詳しく聞きたいんスよ!」
こんなに眩しいキラキラとした笑顔で誘われて、断れる人は中々いないだろう。
ここまで楽しそうな黄瀬君はいつぶりだろうか。
最初は渋っていた火神君だったが、最終的に黄瀬君の押しに負けたようで、連絡先の交換をしていた。
2人が楽しそうに話している姿を見てるのは辛いから、出来れば遠慮したかった。
「黒子っちもおいでよ!」
けれどそう子犬のような顔で、ね?、と小首を傾げられてしまい。
2人に気付かれないようそっと息を吐き、窓の外に視線を移す。
あんなに青々と晴れていた空は、僕の心を代弁するかのような曇天へ変わっていた。
‐END‐
6に続く