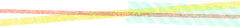
※生々しい表現があります
※主人公が援助交際しています
純粋って、私からほど遠い言葉だなあ。
360ミリリットルのはちみつ容器を見て、ナマエはそんなことを思う。
水分の含有量が低いはちみつを俗に「純粋はちみつ」と呼ぶらしい。人間は60%ほどが水分だから、はちみつに照らし合わせれば誰もかれも純粋ではない。
だから自分も今シャワーから出てきた男も、ホテルの受付の男もすれ違ったカップルも、みんな純粋ではない。
くだらない考えに、ナマエは自分を嗤って、ビニールに包まれたままのはちみつとコンドームの箱を枕の上に放った。
どうかしたのかいと尋ねる男になんでもないのと答え、ナマエは肩にかかっているだけだったバスローブをはらりと落とす。
膨らんだ乳房が揺れ、すこし肉がついた腹と太ももを水滴が滑り落ちる。真白な肌は健康そのものだが、これから行われる行為は不健康そのものだった。
「光ちゃん」
「あ、ナマエ! おせーぞ!」
「ごめんね。用意に時間かかっちゃって」
「まぁいいけどさ。よーし、んじゃ行くか!」
「うん」
サイドアップの髪を揺らし、仁礼が拳を突き上げる。
ナマエはその様子を愛おしく思いながら見つめて、自分も少しだけ腕を上げた。
若者に人気のテーマパーク。
隅々まで意匠を凝らした施設は見事で、よく雑誌やテレビにも取り上げられる。しかし、同様にアトラクションや食事の値段も高い。
ボーダーとして通常のアルバイトよりも稼ぐ仁礼には問題がない程度だが、ボーダーではないナマエにはなかなか手が出ない。
アルバイトも親が禁止していたため、金を手に入れる手段は親からの雀の涙ほどの小遣い。
「てか、大丈夫だったのか? 親御さん金くれた?」
「うん。次のテストで1位とるからって約束したら、楽しんできなさいって」
「そんな宣言できるミョウジがすげーよ……。アタシ今回赤点でさー。次も赤点だったらやべーわ」
「じゃあ、私が教えてあげようか?」
「マジで! お願いするわ!」
だからナマエは初めての春を、どこの誰とも知らない中年の男に捧げた。
1回で3万円。
3回で、遊ぶ金とテーマパークのホテル代、遊びに行くための服やバッグが調達できた。
はちみつを使ったプレイが好きだという、金払いのいい男が言うままに、体に粘つく液体を塗りつける。まるで台本を読むように喘いで卑猥な言葉を口にする。
それで仁礼の近くにいられるのならと、ナマエは気持ち悪さを呑み込んだ。
友人と来られたのが嬉しいのか、仁礼は子供のようにはしゃいでいる。あまり来たことのないナマエは、仁礼に倣ってテーマパークを楽しんだ。
コーヒーカップが目の回るものとは知らずに乗って酔ったり、ジェットコースターで思い切り悲鳴をあげてみたり。
アトラクションはもちろん楽しかったが、にこにことまぶしい笑顔を振りまく仁礼の隣にいられたことが、何より嬉しかった。
ナマエは仁礼のことが好きだった。
一通りの乗り物を楽しんで、仁礼とナマエは並んでベンチに腰を下ろした。
気温は低いというのに、はしゃいだのとあちこち歩き回ったのとで、二人の頬は赤くほてっている。
「はー、一旦休憩! やっぱ1日で制覇はムリだな!」
「そうね。ねえ、光ちゃん。さっきの、振り子の。もう1回後で乗りたいな」
「ああ、バイキングな。んじゃその後でもっかいコーヒーカップ乗っていいか?」
「回しすぎないでね。吐いちゃうから」
「ゼンショするゼンショする。よし、じゃあどっかで腹ごしらえだ!」
「うん」
言われて立ち上がると、仁礼が突然ナマエの方を振り向いた。
はっきりとした目鼻立ちの顔が近くなり、どきりと胸が高鳴る。仁礼はナマエの首元に鼻を近づけると、すんすんと匂いを嗅いだ。
心音が聞こえてしまわないかとどぎまぎするナマエをよそに、仁礼はぱっと笑顔を浮かべる。
「なんかナマエ、はちみつの匂いすんな?」
「えっ」
はちみつ、の言葉に、先ほどとは別の意味で心臓が鳴る。
ナマエを買う男はいつもはちみつを使いたがる。今日は会っていないとはいえ、体にはちみつの匂いが染みついているのかもしれない。
「もしかして、あれ使ってんの? 最近CMしてるボディソープ! あれはちみつ使ってるとかやってたよな」
しかし、それを知らない彼女は、無邪気にCMのテーマソングなどを歌ってみせる。
ナマエはそのCMもボディソープも知らなかったが、そうだと頷いた。はちみつ入りならばそこそこの効果なのだろうと、肌がすべすべになるよとも口にする。
仁礼はすっかり信じたようで、いいなあアタシも変えよっかな、と楽しげに悩みながら歩き出した。
ナマエはほっと息をつきながら、仁礼を騙したことにわずかに罪悪感を覚えていた。
「……はちみつの匂い、するかな」
髪をひとつまみ鼻の前に持ってきて匂いを嗅いでみるが、わからない。仁礼はいつも、甘い果実の匂いがするのに。
夕方、テーマパークを心行くまで楽しんでから、2人は提携しているホテルへ向かった。
女子高生にはやや豪華すぎる部屋だが、せっかくだからとその部屋を選んだ。
いつもナマエが行くホテルとは違い、可愛らしいキャラクターがそこら中を飛び跳ねている。
「すっげーー! ベッドがダブルだ、あははっ」
仁礼は荷物を置くなり、ベッドにダイブした。大きく弾むベッドにさらに笑い声を立てて、ナマエを誘ってくる。
幼いころから絶対にダメと教えられてきたナマエにとって、それは大きな勇気を要することだったが、結局はベッドに飛び込んだ。
体をやさしく受け止めるベッドは確かに心地良い。
「あーあ、明日は帰るだけかぁ。名残惜しいなー」
「仕方ないよ。明日は任務なんでしょ? ボーダーの」
「そうだけどさー……ま、いっか。また来ようぜ、ナマエ!」
「うん、来たい。次はお化け屋敷も行きたいな」
「うげ! それは勘弁しろよ! アタシお化け屋敷は……」
リリリリ。
仁礼の言葉を遮るように、ナマエの携帯が鳴った。
ソファに置いたカバンの中から、軽やかな電子音が流れている。
ナマエはベッドから降りると、携帯を取り出して通話ボタンを押した。
仁礼に聞こえないよう、窓からバルコニーに出る。耳にあてると、はちみつのように粘つく声が聞こえてきた。
『ナマエちゃんかい?』
「はい。はちみつ、買っていきますか?」
『ああ。明日、頼むよ。ゴムはこっちで用意するから。3万でいいんだよね?』
「はい。それでは、明日」
早く仁礼のもとに戻りたいと、いつもよりだいぶ早く通話を切る。
せっかくの楽しい気分に、噎せ返るようなはちみつの匂いは似合わない。くるりと踵を返すと、先ほどまでベッドにいたはずの仁礼が、ソファに陣取っていた。
こちらを見透かすような鋭い視線に、思わずナマエはたじろぐ。
「今の、誰だ?」
常よりもいくぶんか低い声に、さらにナマエは戸惑う。何かまずいことでもしてしまったのだろうかと、今までの自分の行動を思い返してみるも、なかなかこれというものがない。
「習い事の……先生。明日の時間が変更になったって」
「はちみつ買ってくとか聞こえたけど、それは?」
「お茶会するの。生徒が、お菓子とかそういうの持ち寄って……私ははちみつの係」
でたらめな嘘だ。
先ほどのようには信じてくれなかったが、ひとまずは納得したようで、そっかと仁礼は頷いた。
携帯の電源を切ってからカバンにしまい、ナマエは再びベッドに飛び込む。その上から仁礼が乗り上げてきて、甘い果実の香りの中、ナマエは破裂しそうな鼓動を押さえ込んでいた。
楽しい時間は夢のように過ぎ去り、朝には仁礼とナマエはテーマパークを後にした。
ナマエが家に戻ると、母親は出かけているのか留守だった。
友達の家に泊まると嘘をついていたが、どうやらバレなかったようである。
荷物を下ろし、仁礼と買った土産物は新聞紙にくるんで捨てる。服とバッグも新聞紙にくるみ、クローゼットの奥に押し込んだ。
仁礼と遊んだ記憶は幾重にもくるまれて、奥深くに封じ込められる。
母親に見つかりでもすれば、どこで買ったとうるさい。それに、高価なバッグを少ない小遣いで買えるはずもなく、そこからナマエの秘密がわかってしまうかもしれない、ということも怖かった。
ただ一つ、仁礼とお揃いで買ったストラップだけは残し、飾り気のない携帯につけることにした。
「……光ちゃん」
どこを見ているかわからないキャラクターの目が面白くて買ったけれど、今こうして部屋で見ると、何も面白くはない。
ナマエはそっと目を閉じ、小さなストラップにキスをする。
父親と同い年の男に肩を抱かれ、はちみつに塗れ、汚らわしいもので中を暴かれ、得たものはこの小さなストラップ。
それなのに、ナマエはたとえようもなく幸福だった。
午後には男に会う。あの時間を我慢すれば、仁礼との思い出が手に入る。それを考えればなんでもないことだ。
ナマエは自分にそう言い聞かせ、出かける準備をし出した。
午後5時、コンビニで360ミリリットルのはちみつを購入し、手から下げて、待ち合わせ場所に立つ。
帽子をかぶってメガネをかけ、いつもは着ない派手な洋服を身に着ければ、誰もナマエとは気が付かない。遠くの景色を見るようにぼうっとしながら待っていると、上等の上着を着た男が歩いてくる。
手に持つバッグの中にまさかコンドームが入っているなんて、通行人の誰もが思いもしないだろう。
「お待たせ」
「いえ。行きましょう」
男の手が肩に回る。芋虫のような指が動くのも、生臭い息がかかるのも、もう慣れたことだ。
あとは流れに身を任せておけば、仁礼との思い出が手に入る。
ホテルへ向かうための路地に足を踏み入れた、その時に、ナマエの腕をつかむものがあった。
ぎょっとしてナマエが振り向くと、ナマエと別れたままの服装をした仁礼がいる。
いよいよ攻撃的な色を見せる目を見知らぬ男に向けていた。
「おいオッサン、あんた何してんだよ!!」
「何って、君こそ一体……」
「ナマエのダチだよ! つーか、んなこたぁいいだろ! あんたが何なんだよ!」
「光ちゃん……!」
思わず、変装しているのも忘れて仁礼の名を呼ぶ。
その拍子に仁礼に引き寄せられ、柔らかな胸に抱きしめられる。こんな状況だというのに、ナマエの胸は甘くときめいた。
仁礼は獰猛な犬が唸るかのように男に鋭い視線を向けるが、それをどうとらえたのか、男はすぐにいやらしい笑みを浮かべた。
「そうか、ナマエちゃんの友達か。なら、2人合わせて7万でどうだい? やってみたいことがあってな」
「……!」
瞬間、血が沸騰するかのような錯覚をナマエは抱いた。
手にしていたはちみつを、男の顔面めがけて投げつける。腕力が足りなかったのか、はちみつは壁にぶつかり跳ね返った。
仁礼をナマエと同じく、体を売る少女と思ったのだろう。
それは何よりも許しがたいことだった。
「光ちゃんのことを、そんな目で見ないで! この子は違う!!」
そうだ、違うのだ。顔で笑って心で見下す、そんな女ではない。口は悪いが、裏表のない、こざっぱりとした少女。
だからナマエは強く惹き付けられた。
仁礼の腕から抜け出して、庇うように立つ。
先ほどまで胸の奥に追いやっていた嫌悪感が沸き上がり、その心のままに男に言い放った。
「もうあんたとは会わない。いつもいつもはちみつ塗られて、気持ち悪いのよ!」
男はまるで核弾頭でも撃ち込まれたような顔をしていたが、構わずナマエは仁礼を連れてその場を離れた。
大声で言い合いをしたせいで、注目が集まりつつあった。
7センチのヒールを鳴らしながら、ナマエは必死で走る。
仁礼の手を掴んだままだったことに途中で気が付いたが、なぜか手が離せず、そのまま走り続けた。
仁礼の手には、ドラッグストアの袋が下げられていた。
息を弾ませながら走り、ようやく人気のなくなったところで、ナマエたちは立ち止まった。重苦しい沈黙が仁礼との間に満ちて、言葉が出ない。
いっそあの時知らないふりをすればよかったと、ナマエが後悔し始めた頃、仁礼が強くナマエの手を握った。
「、光ちゃん、」
「アタシの家。近いし、今誰もいないはずだから」
「え……」
「いいから、来い!」
いつになく機嫌の悪い仁礼に何も言い返せず、ナマエはただその言葉に従った。無言のままの仁礼は、ナマエと一緒にいた男について問いただすことも、あの後何をしようとしていたのかと尋ねることもなく、無言で足を動かした。
近い、という言葉通り、10分ほど歩くと、仁礼の表札が掲げられた家にたどり着いた。
仁礼はポケットからカギを取り出してドアを開けると、靴も脱がずに上がりこむ。ナマエは引きずられるまま、なぜか風呂場へと連れていかれた。
脱衣所に立たされて、どうしようもない居心地の悪さに身をよじる。
「あ、の、光ちゃん……」
「脱げ」
「えっ」
「その服脱げ。靴も帽子もメガネも下着も、全部。全部脱げ!」
「は、はい!」
目を吊り上げ、足を踏み鳴らす仁礼。
彼女の怒ったところなどついぞ見たことのないナマエは、その剣幕にすっかり気おされて、まずは靴と帽子を抜いだ。
続けて派手なワンピースを脱ぎ、震える手で畳む。そっと仁礼を見上げると、じっとナマエを見下ろしていた。
仕方なく下着も脱いで、畳んだ服の間にしまい込んだ。
一糸まとわぬ姿となったナマエの腕を仁礼が再びつかんで、湯船の中に突っ込む。冷え切った水にすくみあがると、続けて今度はぬるい湯が頭上から降ってきた。
容赦なく目と鼻を襲う湯の勢いに負けそうになりながら薄目を開けると、仁礼はドラッグストアの袋の中から何かを取り出していた。
シャンプーの詰め替えのような形は視認できたが、何と書いてあるかまでは読めない。
切り口を乱暴に引きちぎると、湯と水でずぶぬれになったナマエにその中身をぶちまけた。
ほのかにはちみつのような匂いが漂う。
昨日彼女が言っていたはちみつのボディソープだと、気づくまでにさほど時間はかからなかった。
「ひか、光ちゃん、な、なに」
「あんな、あんな豚男に、なんであんな知らねーヤツに触らせんだよ!」
叩きつける湯で、ボディソープが泡立つ。仁礼は吠えながら、泡風呂に沈められたナマエの体を、自分の服が濡れるのも構わず犬でも洗うかのように、手とスポンジで泡を塗り付ける。
細い首、仁礼よりも大きな胸、ややふくよかな腹とふともも、柔らかいふくらはぎ。
柔らかく香るはちみつの匂いと水音、仁礼が吠えながら泣く声。
しばらくして、きゅ、とそれらを遮るように、水道がひねられた。
ナマエがそこでようやく濡れた髪をかきあげ、顔を上げると、涙とボディソープの泡でぐしゃぐしゃの顔で、仁礼が泣いていた。
ずきりとナマエの胸が痛くなる。
「ナマエ、なんで……」
「……ごめん、なさい」
「う、うぅ」
仁礼は泡まみれのナマエの胸に顔を埋める。
この濡れた手で仁礼に触れていいのかと、ナマエはしばし戸惑ったが、やがて背中に手を回す。
自分ができうる限り優しく抱きしめると、仁礼は顔をあげて、しゃくりあげながら、リップグロスの落ちた唇を開いた。
「ナマエ、好きだ」
「……えっ」
「あんな、ひっく、あんなやつにナマエの体触らせるなんて、う、絶対、絶対嫌だ」
「ひ、光ちゃん、」
「あいつに、やるくらいならっ、アタシにくれよ、金が要るっていうなら払う、いくらでも払うから!」
だから嫌だあんな奴に触られるなアタシに全部ちょうだい絶対もうあいつと会うないくらなんだ7万か10万か15万か一生使ってでも払うからお願いおねがいおねがい。
懇願とも脅迫ともとれないその言葉に、ただただナマエは呆然とするだけだった。
絶対に届かない、受け入れてもらえないと思っていた。だから傍にいるために、束縛だらけの日々の中でどうにか見つけた、金を手に入れる方法。
それを断ったのは仁礼で、しかし一緒にいたいのも仁礼で、一番傷つくのも仁礼で。
展開についていけずに、ナマエは呆然としていた。
「……光ちゃん」
「ひ、っく、ぅうう、えっぐ」
「光ちゃん、……私で、私でいいの?」
やっとのことでそれを尋ねると、仁礼は勢いよく顔を上げて、いっそう幼くなった顔でナマエを見る。真っ赤な目と鼻が痛々しくもあり、愛おしくもある。
「ナマエじゃなきゃ、嫌だ。金なら払う、全部払うから、」
「お金は、いらない」
沈んでいた手をあげて、そっと仁礼の頬にあてる。
不安はまだあるが、目の前に吊り下げられたチャンスをわざわざ逃すほど、ナマエは鈍重ではない。
自分の目からも涙があふれるのを感じながら、ナマエは仁礼に言った。
「光ちゃんが欲しいなら、いくらでも私をあげる。だから、……私にも、光ちゃんをちょうだい」
たった一欠けらでもいいから、ただそれだけが欲しかった。
その言葉に応えるように、仁礼はナマエの唇にかみついた。
はちみつの香りがした。
