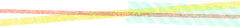
※三角関係注意
初めて彼女を見た時の印象は「綺麗な人」であった。
防衛任務も学校もない、オフの日のことであった。
黒江双葉はその日、ちょっとした買い物をするために町へ出掛けていた。
女性向けの服飾店などが並ぶ、三門市の中でもお洒落な街道を歩いている最中、一軒のオープンテラスのカフェによく見知った姿を見掛けて、黒江は近付き、その人物に声を掛けた。
「あら」と少し驚いた表情の彼女は手にしていたカップをソーサーの上に置く。
席には他の人の姿はない。
「加古さん」
「はぁい、双葉もお出掛けかしら?」
黒江はそれに頷いて「加古さんもお買い物ですか?」と問うた。
生身の彼女は、大人らしい落ち着いた服装で、休日の買い物の最中のように見えた。
しかし、加古はそれを軽く笑って否定する。
彼女は「座ったらどう?」と促し、黒江も大人しくそれに従った。
加古が飲んでいるコーヒーの匂いがつん、と鼻を刺激する。
「いいえ、待ち合わせよ。ナマエとね」
「ミョウジさんとですか」
ミョウジナマエという名前は、黒江も何度か聞いたことがあった。
加古や二宮達と同じ、三門市の大学に在籍している女性で、加古にとっては恋人に当たる人物らしい。
ボーダーには所属していないが大学生組と仲が良く、頻繁に彼らの話題に出るので面識のない黒江でも名前は憶えていた。
恋人同士の語らいに邪魔ではないだろうか、と黒江が顔を強張らせるが、加古は「気にしないで」と軽く手を振る。
「前々から言ってたのよ、あの子。双葉と会ってみたいって」
「あたしと…?」
黒江が首を傾げる。
会ってみたいと思われるような心当たりは特になかったが、加古がなにか自分の話を聞かせているのだろうか。
疑問符を浮かべていると、「子ども好きだから」加古がそう続けた。
なるほど、確かに加古と同い年だという女性からすれば13歳の黒江は子どもという分類に入るだろう。
恋人の部下ということで興味もあるのだろうし。
失礼のないようにしないとな、黒江は背もたれにつけていた背中を伸ばし、身なりを正す。
なんだか娘の結婚相手を紹介される父親のようなそわそわ振りに、加古が形の良い唇に微かな笑みを浮かべた。
と、黒江に向けていた瞳を、加古がその頭上の辺りへ逸らした。
なんだろうか、と黒江も釣られて振り返る。
とくん。胸の奥で微かに鳴った音。
「遅かったじゃない、ナマエ」
「ごめんね、ちょっとバイトが長引いちゃって」
言葉と裏腹に責め立てる心づもりの全くない加古の声も、彼女と加古の会話も全く耳に入らず、黒江は目を開いた。
困ったように目尻の垂れた瞳が、薄い赤を差した唇が、白く絹のような肌が、全てが黒江の視線を釘付けにして止まない。
風呂で上せた時と同じ、けれどそれよりもずっと心地良い熱が顔に溜まっていくのが分かった。
黒江が座っている席の後ろに立つ女性が、穏やかな瞳を黒江へと向ける。
どくん。今度は警鐘ほどに大きく、打たれる鼓動。
「望ちゃんのお友達?」
「ほら、以前から話してたでしょう。私の隊の子よ、黒江双葉」
「あぁ、あの双葉ちゃん!」
加古の言葉に、女性の顔にパッと花が咲く。
そのたおやかな表情に、熱が更に高まっていくのを感じた。
真向いに座る加古と黒江の間の席に座って、会釈をする女性。
その仕種は大人のそれで、目の前の人物が自分よりもずっと年上なんだということがありありと伝わる。
「望ちゃんや二宮君から話は聞いてると思うけど、ミョウジナマエって言うの。よろしくね」
「く、黒江双葉ですっ」
ミョウジにされた自己紹介に意識を取り戻した黒江が、身体を棒のように固くして頭を下げた。
その様子に「あら……」と手で口を隠して驚いた表情を浮かべた加古。
「望ちゃん?」首を傾げるミョウジに加古は「ごめんなさい、気にしないで頂戴」と黒江にもしたように手をひらひらと振った。
火が着いたようにかっかと熱くなる頬。
恋や愛など興味もなければ経験もない黒江だったが、ここまでの熱とあれば自覚せざるを得なかった。
「もー、望ちゃんってばそういうことならLineとかしてよ。双葉ちゃんと会うならもっとお洒落して来たのに」
「ふぅん、私とのデートじゃお洒落する必要はないってことかしら?」
「そうじゃないけど……」
けれど、目の前で仲睦まじく話し込む二人を見ればこの幼い初恋が実る可能性なんてないと分かってしまって。
しかもミョウジの恋人はよりにもよって尊敬する加古望その人である。
加古から奪うなど黒江にとっては絶対に有り得ないことで、それがなくともミョウジを奪えるだけの魅力が自分にあるとはとても黒江には思えなかった。
火照る頬と跳ねる鼓動とは裏腹に、掻き毟られるようなジリジリとした痛みが黒江のまだ幼い心を甚振っていた。
次に抱いたのは、「加古さんとお似合いの人」という印象だった。
今度は、ミョウジと初めて会った日から一か月ほど経った頃だった。
確か、防衛任務の終わった後のことだったと黒江は記憶しているが、正直そんなことはどうでもよかった。
大切なのは、本部から自宅に帰る道の途中にミョウジと加古の2人を見掛けたことであった。
大分季節も秋めいてすっかり暗くなってしまった道中、黒江はとある駐車場で見知った車を目にした。
あれは加古の車だと、黒江はランク戦のために残った自分よりも先に帰った隊長を思い出す。
本部にも一般人立ち入り不可の駐車場があるはずなのに、何故わざわざ料金を払ってあんなところに停めているのか、黒江は不思議に思ったが、遅くなってしまうと足を速めようとして―――そして立ち止まった。
息を呑むとは、こういうことなのだろう。
車内には、運転席に座る加古と共に助手席にミョウジの姿が見えていた。
2人が、口づけを交わしていた。
辺りは街灯の頼りない灯り以外は真っ暗で、黒江以外には人影もなかった。
その中で、幸せそうに唇と唇を交わす2人。
心地の良さに瞳を閉じるミョウジを見詰めて、加古が何度もキスを落とす。
まるでそこだけスポットライトが当たっているのかと勘違いするほどに、黒江にはその様子がよく見えた。
唇の合間からわずかに覗く真っ赤な舌や、その間を繋ぐ水飴みたいに光る液体。
それを喜んで受け入れるミョウジの表情が、嫌でも目に入って、つららを突き刺されたような、底冷えする痛みが胸に広がる。
ぎゅうと、黒江は制服の胸元の辺りを皺になるほど強く握りしめた。
見たい訳ではないのに、目を逸らしたくて仕方がないのに、まるで動くことを拒否しているかのように視線はそこで固定されていた。
瞬間、
「、あっ」
思わず黒江が小さく声を上げた。
加古の緑色の瞳が、黒江の瞳とばちりと合って、一瞬驚きに見開かれる。
しかしすぐに悪戯に細められた。
なんだかミョウジへの未熟な恋心も、加古への忠誠心も全てを見透かされているようで、身体がかっと熱を持った。
金縛りに掛かっていた脚を無理に動かして、黒江は走り出す。
とにかく、今は少しでもあの二人から離れたかった。
気が付けば自室のベッドの上にいた。
玄関で驚いた母親に声を掛けられたような気もしたが、今はそんなことはどうでもいい。
脳裏に浮かぶのは、加古に身を任せて快感に蕩けたミョウジの表情と、全てを見透かす加古の瞳ばかり。
今度熱を持ったのは、自身の瞳で。
黒江は身を焦がすような感情を抑えつけることを止めた。
「ふ、っく……ひっ、」
分かり切っていることだったじゃないか。
今更何を泣くことがあるんだ。
あたしの入る余地なんてないと、分かっていたじゃないか。
それでも、ミョウジの幸せそうな表情が、加古の悪戯な瞳が、黒江の胸を痛めつけて堪らない。
三番目に感じた印象は、覚えていない。
あの日からどれほど経った頃だったか。
ある時、黒江は加古に車で送っていくと声を掛けられた。
チーム単位のランク戦があった日で、13歳が一人で歩いて帰るには大分遅い時間帯だったので、黒江はその言葉に甘えることにした。
あれから、ミョウジについての話は加古としていない。
意図的に避けている黒江の態度を加古も汲んだのか、自分から話を振るようなことはしなかった。
あの日見た、加古のお気に入りの車の助手席に腰を下ろす。
大人の女性らしい、甘い香水の香りがして、ずき、と胸の辺りをささくれ立たせる。
ミョウジもあの日、ここに座っていた。
「ねぇ、双葉」
「なんでしょうか」
黒江がシートベルトをするとほぼ同時に、加古がアクセルをゆっくりと踏み込んだ。
運転の上手い彼女の技術のおかげで、振動はほとんどない。
「あの日、見てたでしょ」
「…………」
突然の言葉に、黒江は面食らった。
目の前の信号は赤で、加古はあの時と同じ悪戯な瞳で微かに笑っている。
なんと返すべきか、考えてみたところで答えは出ない。
俯きながら、黒江は小さく首を縦に振った。
どうやら意外と脳は冷静なようだ。
「すみ、ません」
「謝る必要なんてないわよ」
「むしろ、教育的に悪いとこ見せちゃって双葉のご両親から怒られないかしら」なんて加古はからからと笑った。
その姿が、黒江にはない大人の余裕というものなのだろうか。
「あの、あたしっ」
「私に義理立てしなくてもいいのに」
黒江の言葉を遮って、加古は言う。
その表情は、自身の恋人が横恋慕させていることに対してなんとも思っていない様子で、どちらかと言うなら自分に気を使う黒江に対して拗ねているようだった。
「本当に好きなら、誰かに気を使っちゃ駄目よ」
子どもを嗜めるような、優しい口調で加古は言った。
否、実際に子どもを嗜めているつもりなのだろう。
酸いも甘いも知り尽くしているであろう加古にとって、隊長に遠慮して恋心に蓋をしようとしている黒江など、青くて仕方がないに違いない。
その言葉により自分の幼さを思い知って、黒江が窓ガラスの外へと視線を逸らす。
加古もミョウジも、子どもの自分には眩しいくらいに大人に見える。
「モールモッド一体、駆除しました」
オペレーターに一言報告し、黒江は間に合ったことにまだ成長段階の胸を撫で下ろした。
今日も防衛任務であった。
いつもと違うのは、講義の課題が迫っている大学生組が不在である点。
時間のある隊員同士で即席で作った混成部隊での任務だった。
最近は近界民が現れる門の誘導が上手くいっていないらしく、今回もまた、警戒区域以外でモールモッドが現れたのだった。
民間人の女性が一人襲われる直前だったようで、自身の機動力を活かしてなんとか最悪の事態を避けることが出来た。
未だに地べたに座り込んでいる女性に、黒江が声を掛けようと振り返った時、女性から声を掛けてきた。
「双葉ちゃん?」
「っ、ミョウジさん」
「ナマエでいいよ。そっか、双葉ちゃんもボーダーの人だったもんね」
「びっくりしちゃった」なんて困ったように笑うミョウジ。
その表情にまたとくんと心臓が高鳴って、それでも、あの時彼女が加古さんに向けた愛に溢れた瞳を思い出し、黒江は頭を振る。
加古がなにを言おうと、彼女は加古の恋人だ。
それを奪おうなんて、彼女にも加古にも無礼なことで、決して考えてはいけない。
この気持ちは、抱いてはいけないものだ。
「大丈夫ですか、怪我とかは……」
「うん、大丈夫、っ……」
黒江がそう問えば、ミョウジは安心させるためか勢い良く立ち上がった。
しかし、眉を顰めて声を漏らすミョウジの様子を見てはいそうですかと返すほど黒江は鈍くはなく。
ミョウジに本部への同行を申し出たのだった。
「捻りましたか?」
「ごめん、そうみたい」
「本部にお連れしますので、そこで治療をしてもらいましょう」
「ん……じゃあ、お願いしてもいい?」
「はい」
そこではた、と黒江は気付いた。
本部へ連れて行くということは、つまり、記憶消去の処置も受けるということだ。
恐らく、そこでミョウジは記憶を消される。
今日この場で近界民に襲われた記憶を。
―――今日この場で起きた記憶を。
古い、アニメや漫画なんかである心の中の天使と悪魔が頭上で言い争う図。
あの光景が、今黒江の頭でも繰り広げられていた。
相手は怪我人で、今の自分はトリオン体だ。
抵抗なんて、無いに等しい。
ミョウジに差し出した手が、一体何の想いからか震えていた。
どうせ、ここで起こったことは忘れてしまう。
加古にも、ミョウジ本人にも知られない。
それなら、少しぐらい。少しぐらいなら。
いや、それでも、例え知られなくとも本当にそれでいいのか。
バレないからとそんなことをするなんて、人として最低な行為ではないのか。
最悪の裏切り行為だと思わないのか。
良心や後ろめたさがジリジリと熱を帯びる身体を突き刺す。
それでも、悪魔は囁きを止めない。
黒江が行き着いた答えは―――
「え?」
最後に記憶にあるのは、目を見開いて驚くミョウジの表情だった。
「あ、望ちゃん」
「大丈夫?骨にヒビが入っていたんですって?」
わざわざ講義を休んで車で迎えに来てくれた望ちゃんに、礼を言って、私達は車へ乗り込んだ。
慣れない松葉杖は歩きにくくて、タクシーかなにかで帰ろうと思っていたからすごく有難い。
私の荷物を後部座席へ置いて、扉を閉めると望ちゃんが「それにしても、」と声を漏らした。
「不運だったわね。轢き逃げだなんて」
「そうだねぇ、脚だけで済んだからいいけど」
にへら、と笑えば望ちゃんは「ちょっとは怒りなさいよ」と私の鼻に軽くデコピンした。
「あいたっ」顎を晒して、私は声を上げる。
運転中に余所見するのは私の事故の二の舞になるから止めてほしいな。
「あら…………」
「どうかした?」
望ちゃんはその綺麗な瞳を瞬かせて、私の顔の辺りを凝視する。
もしかして、傷でも残ってた?
私が聞くと彼女は自分の喉を指先でトントンと叩いて示す。
「喉の辺り、赤くなってるわよ」
「えっ?……あれ、ホントだ」
鏡を使っても見れない位置だから、スマートフォンのカメラ機能を使って見てみた。
彼女の言う通り、虫刺されのようにぽつり赤くなっている。
どこかに打ったのかなぁ?いや、でもどうやってぶつけるんだろこんなところ。
「ふふっ」
望ちゃんが悪戯な瞳をしている。
こういう顔をする時は、好奇心をくすぐられているかなにか面白いものを見つけたかのどちらかだ。
「なぁに?」と再び問えば、望ちゃんは楽しそうにこう返した。
「面白いことになりそうだと思っただけよ」
くすくす笑う彼女に、とくんと温かく心が高鳴った。
