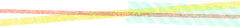
早く、と急かす声が聞こえて、雑貨屋さんのショーウィンドウを滑らせていた視線を前に向けた。あのバッグ可愛いなぁ、とか、新しい洋服が欲しいなぁ、とか。そういう気持ちは置き去りにして、歩調を早める。くるりとこっちを振り返った光ちゃんは、わたしが追いついたのを確かめて、もう一度すたすたと歩き始めた。足取りは軽い。きっと、嫌いなテストから解放されて嬉しいんだろう。わたしだって、好きか嫌いかで聞かれたら後者を選ぶ。大人しく座ってお勉強することよりも、こたつで寝そべって漫画を読んでいるほうが好きな光ちゃんにはさぞ苦痛な時間だったことだろう。
テスト終わるまで防衛任務禁止とか、ほんとありえないだろ。ぶつくさと不満を零す光ちゃんに曖昧な相槌を打ちながら、足元に視線を落とす。光ちゃんのチームメイトは、彼女ほどではないにしろ学業優秀とは言い難いらしい。ボーダーの偉い人たちは、そんな彼女たちを心配しているんだろう。でもわたしは、光ちゃんと一緒に居られる時間が増えて、嬉しかったよ。口をつきそうになった言葉を飲み込んで、苦笑いと共に空気へ溶かした。テストは午前中で終わって、今日までは半日授業。こんな風に放課後を一緒に過ごすチャンスは、明日からはきっと減ってしまうんだろう。だって、光ちゃんはボーダーのお友達のこと、大好きだから。チームメイトはみんな男の子だけど、光ちゃんは随分と仲良くしているみたいだ。同じ学校の影浦先輩や北添先輩のことは、わたしも知っている、けれど。あんまり、好きじゃない。だって、光ちゃんと、仲良しだから。それが汚い感情だっていうことも、そんなことを思ってしまうのも悪いことだって、わかってる。だから、これはわたしだけの秘密だ。光ちゃんに知られちゃいけない、大事なひみつ。嫌われたくなんか、ないんだもん。
「光ちゃんは、夕方から用事があるんだっけ?」
「ん?ああ、まあな!」
今日は久しぶりに防衛任務だからな!と楽しげに笑った光ちゃんに相槌を打って、ひとつだけ溜息。光ちゃんは、よっぽど久しぶりの防衛任務が楽しみなんだろう。終わったらカゲの家でお好み焼き食うんだ、と笑う彼女に気付かれないように唇を尖らせて、それが見えてしまわないようにそっと顔を背けた。どうにも、いやなことばかり考えてしまう。せっかく、光ちゃんと二人で遊んでいるのに。楽しいはずなのに。嬉しい、はずなのに。おなかのあたりがもやもやして、心臓がきゅうっと苦しくなる。息苦しさを忘れようと深く息を吸って、それからいつも通りの態度を取り繕った。上手に出来ているか少しだけ不安だったけど、光ちゃんは気にしていないようだった。だから、きっと大丈夫だ。
「お好み焼き食べるなら、今からクレープ食べないほうがいいんじゃない?」
「別にどっちも食えるからダイジョーブだって」
「量は大丈夫だろうけど」
カロリー的に、ね?光ちゃん、昨日だってファミレスで勉強してたときパフェもケーキも食べてたじゃない。わたしの軽口が痛いところに刺さったのか、光ちゃんは露骨に顔を顰めて、それからなんとも形容し難い表情で低く唸った。ひょっとすると、テスト勉強のストレスからくる暴食のカロリーを一生懸命計算しているのかもしれない。光ちゃんは細いんだから、そんなにカロリーとか気にしなくてもいいのに。口をつきそうになった言葉をのみこんで、代わりにちょっとだけ意地の悪い言葉を吐く。ムッとした顔も、葛藤している顔も、かわいい。だけど、わたしが一番好きなのは、やっぱり、楽しそうな顔だから。意地悪言ってごめんね、と謝って、それから光ちゃんの表情を窺う。案の定拗ねた様子の彼女は、じっとりとした恨めしげな視線をわたしに向けてツンと唇を尖らせている。不機嫌さをしっかりと表現したその顔は、けれど、ひどく子どもっぽくて。ついつい、小さく噴き出してしまった。また、光ちゃんの眉がキューっと吊り上がる。慌ててもう一度ごめんねと付け加えたときには、もう手遅れだった。
「なんだよ!自分だって昨日はワッフル食べてただろ!」
「そ、それは……まあ、そうだけど……」
「ほら!じゃあおあいこだろ!」
「で、でもわたしは今日お好み焼き食べないし!」
反射的に吐き出した反論は、随分と子供じみていた。なんというか、自分が仲間はずれにされているみたいで、拗ねている、というか。べつに、光ちゃんとそのチームメイトに紛れてお好み焼きを食べられないことが不満なわけではないのに。受け取り方によっては、きっとそういうふうにしか聞こえないだろう。しまった、と即座に自分の発言を取り下げようとしたけれど、先程とは打って変わってにやにやとした表情の光ちゃんには、即席の言い訳など通用しそうになかった。ふぅん、なるほどねえ。そんなふうに笑った光ちゃんが、くるりとわたしを振り返る。じゃあ、今日の19時にカゲの家に集合な。場所わかんなかったら連絡しろよ、と一方的に約束を取り付けた光ちゃんは、有無を言わせない態度でびしりとわたしを指差した。人を指差すのはお行儀が悪いよ、なんて場違いな言葉しか出てこない。光ちゃんは、当然のようにそれを無視した。
でも、わたし影浦先輩たちのこと知らないし、向こうだって知らないでしょ。いきなり来たってビックリするよ。頭の中の冷静な部分をかき集めて作り上げたもっともらしい言葉さえ、光ちゃんはあっさりと笑い飛ばしてしまう。カゲたちにはよく話してるし、もう知り合いみたいなモンだって。投げ返された言葉にがつんと頭を殴られたみたいで、内容が上手に噛み砕けない。え、と間抜けな声を零したわたしの手を強引に取った光ちゃんが、したり顔で笑っている。アタシの親友だって言ってるから、大丈夫だって。カゲたちも見た目はまあアレだけど、取って食ったりなんかしねえよ。笑って吐き出された言葉が、悪意なく心臓を貫く。ああ、そうだ。光ちゃんにとってのわたしは友達で、わたしは、彼女がこうして「親友」という立場を与えてくれるだけで、満足していたのに。それなのに、どうしてこんなにも痛いんだろう。ちくちくとささくれだった心臓が、馬鹿みたいに泣き喚いている。当たり前なのに。わたしはおんなのこで、光ちゃんも、おんなのこ。わたしのほうが、きっと、ふつうじゃないんだ。わかってる。わかって、いるのに。目測、3センチ。彼女までの距離が、ひどく遠い。繋がれた手を握り返す勇気なんて、わたしには1ミリも持てなかった。
