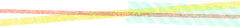
才能って残酷だ。
ナマエには恋人がいる。恋人の名前は香取葉子という。香取は器用な子供だった。勉強でも運動でも、これといった積み重ねがなくとも、人並み以上にそつなくこなせた。けれど、それだけだった。自分の能力を驕り、努力を惜しんだ香取は、天才になり損なったただの器用貧乏だった。
ナマエは、ボーダーとしての公式の記録ではB級下位のチームに属する、香取より下のランクの戦闘員だった。しかし、ランク上位の面々からは、それを疑問視する声が度々上がっていた。特に、A級唯一のガールズチーム、加古隊の隊長の固執ぶりは群を抜いていた。度々ナマエの前に現れては、ナマエを自身の隊へと勧誘するのだ。しかし、ナマエは頑としてその申し出を受け入れなかった。それどころか、名誉とも言えるその誘いの話を、口外しないようにまで言い含めていた。
最初に断ったとき、何故、と問う加古に、ナマエは理由を告げなかった。しかし加古には、なんとなくだがその理由が分かっていた。
ナマエは、彼女の恋人である香取葉子に気を使っているのだ。香取は以前から、自身の苗字のイニシャルがKであるにも関わらず、加古から声がかからないことを気にしていた。プライドの高い香取のことだ。自分より弱いと思っているナマエが、自分を差し置いて加古に目をつけられているなどと知った暁には、癇癪を起こして暴れるのが目に見えている。そして同時に、ナマエの優しくて、愚かで、つまらない嘘がバレてしまうことになる。そうなったらきっと、ナマエは香取の側にはいられなくなる。それだけは嫌だった。
ナマエは香取より強い。ナマエはまぎれもない天才で、そして、人並みに努力だってする。香取に危険が迫った時、守れるように。けれど、その時が来ない限りは、それを表に出すことはないだろう。実力が明るみに出れば、きっと香取はナマエを捨てる。嘘がバレれば嫌われる。
香取の隣にいられるのならば、地位も名誉も必要ない。香取の笑顔を誰よりも近くで見られるのなら、世界中の人間に嫌われたっていい。ナマエは、香取のことを愛している。だから、自分のすべてを嘘で塗り固めた。
ナマエは偽りだらけの人間だ。香取の隣にいる時も、本当のことなどほとんど口にはしない。すべては香取に嫌われないため、好きでいてもらうため。罪悪感に押し潰されそうな心の中で、ただ一つ、香取を好きな気持ちだけが、本物だった。
何度目かの加古の誘いを断り、その隣にくっついて来た黒江に睨まれたナマエは、申し訳のなさと純粋な恐怖に顔をうつむかせた。加古は苦笑しつつそのうな垂れた頭に手を置き、優しく撫でる。
「本当に好きなのね、あの子が」
「好きです。葉子ちゃんは、わたしの大切な人ですから」
「でも、あなたのしていることは、あの子を侮辱することと同じよ」
「…わかってます」
理解しているのだ。これがただのエゴでしかないことを、ナマエはよく分かっている。香取の自尊心を傷つけないようにと言えば聞こえはいいが、その実はただの自己防衛だ。加古にはもちろん、幼い黒江にさえも、それを見透かされている。だから黒江は、ナマエのことがあまり好きではない。加古がナマエのことをいたく気に入っているため、はっきりと口にすることはないが。
「そうねえ。そこまで入りたくないのなら、もうこの話はいいわ。なかったことにしましょう」
「え、いいんですか…?」
「ええ。ナマエを困らせたいわけではないもの」
ナマエがホッと息を吐く。このところ、ナマエが加古のスカウトを受けているという噂が実しやかに囁かれ始め、焦っていたのだ。本人が諦めてくれるのなら、これほど都合のいいことはなかった。
しかし、安堵に弛緩したナマエの頬は、次に放たれた加古の言葉で凍りつくことになる。
「その代わり、私と付き合いなさい、ナマエ」
「……は」
これには隣にいた黒江も驚きを隠しきれなかった。目を丸くして加古を見上げている。当然ながら、当事者のナマエはそれ以上の困惑を見せていた。
「もう嘘をつくのは疲れたでしょう? 私が楽にしてあげる」
加古の誘いを、いつものようにすぐ断ることはできなかった。それは、加古の瞳が存外真剣な色を湛えていたからか、それとも、加古の言葉が、ナマエの心を覗いたかのように的を射たものだったからか。
ナマエは加古の視線から逃れようと目をそらした。しかし、そらしたところで、加古の追求が止むわけではなかった。
「私は、ナマエが私より強くなったとしても突き放したりしない。むしろその成長を自分のことのように喜ぶことができるわ。自分を偽る必要なんてないの。もう他者に遠慮する必要もない。ナマエ、私と、お互いを高め合える関係を作りましょう」
差し出された手を取ることはできない。けれど、きっぱりと断ることもできなかった。ナマエは押し黙り、そして数十秒後、絞り出すような声で、考えさせてください、と言った。加古は満足そうに笑っていた。黒江は、最後まで不満そうなのを隠すことなくナマエを睨みつけていた。
返事を保留にしたまま、しばらく経った頃、ナマエは香取と久しぶりのオフを共にしていた。ビーズクッションに身を沈めてスマートフォンを弄ぶ香取は、いつも通りどこか不機嫌そうな顔で、会話の節々に皮肉めいた言葉を並べている。
この様子を見るに、きっと香取は、加古と自分のことなど一切聞き及んでいないのだろう。ナマエは安心しきっていた。加古になんと返事をするか、このところそればかりで頭を悩ませていたが、その答えも決まった。やはり自分は香取のことが好きで、香取以外の隣に立つことなど考えられない。今この瞬間も、罪悪感は相変わらずナマエの心を蝕んでいるが、香取と共に過ごすことで得られる安らぎは、それをも上回っていた。
このままでいい。この当たり前が、ずっと続けばそれでいい。ナマエが望むのは、それだけだった。それだけ、だったのに。
「ねえナマエ」
「なに?」
「加古さんに誘われてんでしょ。なんて返事すんの?」
「………え」
唐突に投げられた言葉に、ナマエの心臓が一瞬止まる。間の抜けた声を漏らせば、香取がため息を吐きながらスマートフォンを床に置き、ゆっくりと立ち上がった。ナマエの視界が、香取の陰に覆われる。顔を上げることができなかった。その先の香取の表情を、確かめることができなかった。
「アタシが何も知らないと思ってたの? あんたが言わないから聞かなかっただけよ」
何か言わなければ、と思うのに、緊張と恐怖で引きつった喉はうまく言葉を発してくれず、漏れるのは情けなく震えた息だけだった。
嫌われる。捨てられる。懸念が脳内を駆け巡る。
死んでしまいたい。消えてしまいたい。渇求が、胸中に浮かぶ。
不安と絶望が、涙となって視界を濡らす。目尻から溢れて頬を湿らせるそれを拭うことすらできない。
「なんで泣いてんの。てか泣きたいのはアタシの方なんだけど」
香取がその場にしゃがみ込んで、ナマエの頬に指を滑らせた。暖かい親指が、乱暴に涙を拭う。優しい手つきだった。
「なんか勘違いしてるみたいだけど、別にアタシ、怒ってないから。そりゃ、人からそれ聞いたときはムカついたけど。でもそれは、あんたがアタシを差し置いて加古さんに誘われたから、とかじゃなくて……あー、もうっ。……アタシがムカついてんのは、あんたがアタシを疑ったことよ」
すぐには理解できなかった。疑う、とは、どういう意味だろう。それに、ナマエが本来の実力を偽っていたことに関しては、特になんとも思っていないのだろうか。
予想外の反応に、ナマエの戸惑いは尽きない。疑問や不安が次から次に湧いて出る。
そんなナマエの惚けた態度に、香取は心底呆れたように息を吐いた。まるでこちらの意図を汲み取らない、いつまで経っても自己解決ばかりの恋人に、香取の苛立ちは募るばかりだった。
けれど、だからこそ、言葉にして伝えなくてはならない。元来、素直とは程遠い性格の香取だが、この局面でそれを渋り、大切なものを取り零すほど愚かではない。
「ナマエがアタシに嫌われたくなくて嘘ついたみたいに、アタシだってナマエに嫌われたくないって思ってる。アタシの実力はともかく、アタシの、ナマエへの気持ちをなめるな。ナマエがアタシより強いからって、その程度のことでナマエのこと嫌いになるわけないっての」
香取が真っ赤な顔で言い放ったことをナマエが咀嚼して飲み込むまでには、だいぶと時間がかかった。苦労して理解したそれを、すぐに信用することもできなかった。けれど。
「こんなこと、一生言うつもりなかったのに…。このアタシにここまで言わせたんだから、きっちり責任とりなさいよ」
もはや泣きそうに顔を歪めた香取を見た瞬間、ナマエの体は無意識に動いた。香取の華奢な体を抱きしめると、香取もおずおずと背中に腕を回し、ナマエを抱きしめ返した。
「葉子ちゃん、ごめんね…。葉子ちゃんは、信じてくれてたのに、わたし…」
「もういいわよ…。でも、あんたってずるい女よね。それでも嫌いになれない自分がむかつくわ」
ず、と鼻をすすりながら、香取は苦々しく笑った。
「は? 告白された…? ちょ、それいくら相手が加古さんでも許容できないんだけど。てかあんたが隙だらけだからそういうことになんのよ。ちょっとは警戒心持ちなさい」
理不尽な文句を言いながら、香取はナマエの頬を思い切り引っ張った。ナマエは痛みに若干涙を滲ませながら、それでも幸せそうに笑っていた。
余談ではあるが、後日、意気揚々と加古に模擬戦を挑んだもののぼろ負けして落ち込む香取を必死に慰めるナマエの姿が、複数のボーダー隊員に目撃された。
