傷も今では愛しくて
前へ 次へ
あの日、あのとき。
花宮くんから別れの言葉を切り出されて、それから、彼は朝まで帰ってこなくて、そのまま朝を迎えて、私がアルバイトに出かけた。そして、帰宅すると花宮くんの荷物はなくなっていて、部屋には布団がたたまれて置いてあるだけだった。
私はその場にへたり込み、泣いた。
お父さんも、お母さんも、私のところからいなくなって、花宮くんまでいなくなってしまった。
また独りぼっちになってしまった。
誰も憎くない。恨んでない。だから、私のところに帰ってきて欲しい。
でも、そんな願いは叶うはずもなくて。
私は傷を負ったまま、大人になった。
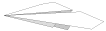
「みょうじさーん、この資料お願い」
「はーい! すぐやります」
あれから10年後。私は27歳になった。
風の噂によれば、花宮くんは奨学金を借りて有名国立大学を卒業し、今は外資系の企業に勤めているらしい。
私は平凡な大学を卒業して、建築会社に就職した。
まるで立場が違いすぎる。
また会えるだなんて思っていないけれど、ましてや、会ってもどうこうするだなんてことはないと思うけれど、でも、それでも、少しだけ期待してしまっている自分がいる。
たとえば、横断歩道の向こう側を、花宮くんが歩いていたりだとか――
「! 花宮くん!」
夕方の帰り道。人通りも車通りも多い中で、私は見つけてしまった。
どうして。今は日本に居ないと、瀬戸くんが言っていたのに。
名前を呼んだけれど、彼はこちらに気が付くこともなく、歩いて行ってしまう。
「花宮くんっ……!」
振り絞るように叫ぶと、道路向かいを歩いていた彼の足が止まった。
そうして、ゆっくりと振り返る。
花宮くんの目が、大きく見開かれる。
ああ。ああ。
なんてことだろう。
10年前よりもずっと大人になった彼が、今、目の前に――
すぐに信号が青に変わったので、私は花宮くんの方に駆けていく。
「花宮くん……」
「……みょうじ」
花宮くんは私の名前を呼んで、目を伏せた。
これは彼の癖のようなものだ。
なにか隠し事をしたいときや、やましい事があるときは、こうして目を伏せるのだ。
「どうして今、目を伏せるの?」
「……みょうじに会わせる顔なんてなかったから」
「そんなの、花宮くんが決めることじゃないよ」
ああ、違うのに。
なにも責めたいわけじゃない。
私はただ、「久しぶりだね」って、それだけ、一言だけ言えればよかったの。
「……ひ、久しぶり、だよね」
「そう、だな」
「どう? 元気だった?」
「ああ……みょうじは?」
「元気……うん、元気だよ。ずっと」
嘘を吐いた。元気なわけない。
花宮くんと会えなくなってから、私はずっと元気だったときなんてない。
会話はそこで途切れた。
「えっと……」
私は無理やり話題を引き出そうとする。
すると、急に花宮くんが私の手首を掴んで、自分の方に私の体を引き寄せた。
つまり私は今、花宮くんに抱きしめられた。
「逢いたかった」
花宮くんはそう一言だけ言った。
「……うん」
私も花宮くんの背中に手を回す。
ああ、花宮くんって、本当にわがままだなあ。まったく、仕方がないんだから。
花宮くんが言ったんだよ。一緒にいたいって。それに、花宮くんが言ったんだよ。別れの言葉も。
そうして、ずっと会うことも話すこともしなくて、今こうして偶然、街角で出逢って、逢いたかっただなんて……私、どうしていいかわかんなくなっちゃうよ。
「花宮くん……あのね、私、すっごくすっごく、逢いたかったよ。昔みたいに話したかった」
「ああ」
「私、あれから頑張ったんだよ。独りで、頑張ったんだよ」
「……ああ」
「花宮くんが傍にいないのに、頑張れたの。想い出だけで、生きてきたの」
「……ごめんな」
「う、うっ……うう……花宮くん……」
「……なんだ?」
「私、まだ花宮くんのこと、好き」
「そうか、俺もだよ」
「え……?」
「俺も、みょうじが好きだ。ずっと。家を出ていったときだって、ずっとずっと、好きだった」
「じゃあ、どうして……」
「俺とお前のためにならないと思った。俺たちはあまりにも子供だった。大人になるまで、待たなきゃ行けないと思った」
花宮くんは、そう言って強く私を抱きしめた。
「……大人になったよ、私。花宮くんも、大人になった」
「ああ」
「じゃあ、花宮くん、私と結婚してくれる?」
「当たり前だ。……すまなかった、ずっと、独りきりにして」
嬉しい。なんて言葉にしたらいいのだろう。
私、待ってて良かったんだ。
花宮くんを待ってて、良かったんだ。
待っててよかった。
「また俺と、一緒に暮らそう」
傷も今では、愛しくさえ思える。
「……はいっ」
(愛のコップが満たされた)
20200406
花宮くんから別れの言葉を切り出されて、それから、彼は朝まで帰ってこなくて、そのまま朝を迎えて、私がアルバイトに出かけた。そして、帰宅すると花宮くんの荷物はなくなっていて、部屋には布団がたたまれて置いてあるだけだった。
私はその場にへたり込み、泣いた。
お父さんも、お母さんも、私のところからいなくなって、花宮くんまでいなくなってしまった。
また独りぼっちになってしまった。
誰も憎くない。恨んでない。だから、私のところに帰ってきて欲しい。
でも、そんな願いは叶うはずもなくて。
私は傷を負ったまま、大人になった。
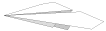
「みょうじさーん、この資料お願い」
「はーい! すぐやります」
あれから10年後。私は27歳になった。
風の噂によれば、花宮くんは奨学金を借りて有名国立大学を卒業し、今は外資系の企業に勤めているらしい。
私は平凡な大学を卒業して、建築会社に就職した。
まるで立場が違いすぎる。
また会えるだなんて思っていないけれど、ましてや、会ってもどうこうするだなんてことはないと思うけれど、でも、それでも、少しだけ期待してしまっている自分がいる。
たとえば、横断歩道の向こう側を、花宮くんが歩いていたりだとか――
「! 花宮くん!」
夕方の帰り道。人通りも車通りも多い中で、私は見つけてしまった。
どうして。今は日本に居ないと、瀬戸くんが言っていたのに。
名前を呼んだけれど、彼はこちらに気が付くこともなく、歩いて行ってしまう。
「花宮くんっ……!」
振り絞るように叫ぶと、道路向かいを歩いていた彼の足が止まった。
そうして、ゆっくりと振り返る。
花宮くんの目が、大きく見開かれる。
ああ。ああ。
なんてことだろう。
10年前よりもずっと大人になった彼が、今、目の前に――
すぐに信号が青に変わったので、私は花宮くんの方に駆けていく。
「花宮くん……」
「……みょうじ」
花宮くんは私の名前を呼んで、目を伏せた。
これは彼の癖のようなものだ。
なにか隠し事をしたいときや、やましい事があるときは、こうして目を伏せるのだ。
「どうして今、目を伏せるの?」
「……みょうじに会わせる顔なんてなかったから」
「そんなの、花宮くんが決めることじゃないよ」
ああ、違うのに。
なにも責めたいわけじゃない。
私はただ、「久しぶりだね」って、それだけ、一言だけ言えればよかったの。
「……ひ、久しぶり、だよね」
「そう、だな」
「どう? 元気だった?」
「ああ……みょうじは?」
「元気……うん、元気だよ。ずっと」
嘘を吐いた。元気なわけない。
花宮くんと会えなくなってから、私はずっと元気だったときなんてない。
会話はそこで途切れた。
「えっと……」
私は無理やり話題を引き出そうとする。
すると、急に花宮くんが私の手首を掴んで、自分の方に私の体を引き寄せた。
つまり私は今、花宮くんに抱きしめられた。
「逢いたかった」
花宮くんはそう一言だけ言った。
「……うん」
私も花宮くんの背中に手を回す。
ああ、花宮くんって、本当にわがままだなあ。まったく、仕方がないんだから。
花宮くんが言ったんだよ。一緒にいたいって。それに、花宮くんが言ったんだよ。別れの言葉も。
そうして、ずっと会うことも話すこともしなくて、今こうして偶然、街角で出逢って、逢いたかっただなんて……私、どうしていいかわかんなくなっちゃうよ。
「花宮くん……あのね、私、すっごくすっごく、逢いたかったよ。昔みたいに話したかった」
「ああ」
「私、あれから頑張ったんだよ。独りで、頑張ったんだよ」
「……ああ」
「花宮くんが傍にいないのに、頑張れたの。想い出だけで、生きてきたの」
「……ごめんな」
「う、うっ……うう……花宮くん……」
「……なんだ?」
「私、まだ花宮くんのこと、好き」
「そうか、俺もだよ」
「え……?」
「俺も、みょうじが好きだ。ずっと。家を出ていったときだって、ずっとずっと、好きだった」
「じゃあ、どうして……」
「俺とお前のためにならないと思った。俺たちはあまりにも子供だった。大人になるまで、待たなきゃ行けないと思った」
花宮くんは、そう言って強く私を抱きしめた。
「……大人になったよ、私。花宮くんも、大人になった」
「ああ」
「じゃあ、花宮くん、私と結婚してくれる?」
「当たり前だ。……すまなかった、ずっと、独りきりにして」
嬉しい。なんて言葉にしたらいいのだろう。
私、待ってて良かったんだ。
花宮くんを待ってて、良かったんだ。
待っててよかった。
「また俺と、一緒に暮らそう」
傷も今では、愛しくさえ思える。
「……はいっ」
(愛のコップが満たされた)
20200406
前へ 次へ