逃れられない悲しみに
前へ 次へ
「なまえちゃんの、旦那さんになりたいかな」
瀬戸くんが口にした言葉は、意外にも意外すぎるものだった。
風が、私たちの肌を撫でて去っていく。
「え、と……」
私は言葉に躓く。
どうしよう。どうするのが正解だろう。なんて答えて欲しいのだろう、瀬戸くんは。
そりゃ、こういうシーンだ。私も瀬戸くんのお嫁さんにして、と言えば、瀬戸くんは喜んでくれるのだろうけれど。
でも、私にはそう答えられない理由がある。
すると、しばしの沈黙ののち、瀬戸くんはくすりと笑ってこう言った。
「冗談だよ、困らせてごめんね」
冗談……なら、いいのだけれど。
でも、瀬戸くんって、他人を困らせるような冗談を言うような人だったっけ。いや、違う。彼はそんな人じゃない。
きっと、嘘だ。
冗談だという嘘をついたのだ、きっと。
私の出方を見て、確かめて、私が迷ったから……
「あのね、瀬戸くん」
「ん、なに?」
瀬戸くんも、私と同じように、バルコニーの柵に前のめりに寄りかかって、こちらに視線をやった。
「私、昔からずっと、花宮くんのことが好きだったんだ」
「好きだった、って、過去形?」
「ううん、現在進行形」
「……そっか」
「うん」
「ちなみに、それってさ」
「なあに?」
「俺じゃ、代わりになれないよね」
「……うん、なれない。花宮くんが、私のことどう思ってるかはわからないけれど、私は花宮くんのことしか考えられない」
「そうだよね。うん、わかった」
ごめんね――
瀬戸くんは一言そう言って、遠くを眺めた。
町の全部が見渡せる場所。
私の住んでいたあの家。花宮くんとの秘密基地。そして、このバルコニー。 私の知る限り、町を一望出来る場所は、この三つだけ。
大切な場所が、また一つ増えた。
「今日はさ、なまえちゃんに今言ったことを伝えたくて呼んだんだ」
「夜中ってあたりが瀬戸くんらしいなって思ったよ」
「俺ってそんな風に思われてるの?」
「あ、ううん、違うの。いつも夜までバイトしてる私のこと、気遣ってこの時間を選んでくれたんだろうなと思って。だから、人を思いやれる瀬戸くんらしいなって」
「ああ、そういう意味か。……別に、この時間を選んだのは、特に深い意味はなかったよ」
「そういう善意の誤魔化しも、瀬戸くんらしい」
「……負けたよ」
「ふふ。勝っちゃった」
瀬戸くん。瀬戸健太郎くん。
私の大切な、友達。
私たちは、しばらくバルコニーで雑談をして、日が昇る少し前に、自転車で家へと帰った。
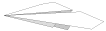
家に着いたあと、私は一息つくためにお風呂に入った。冬場のどうしても寒いときにしか、基本的に湯船には浸からないけれど、今日は例外。
とりあえず、ゆっくり癒されたかった。
ああ、私、なんの考えもなしに、花宮くんのことが好きだって言っちゃったけど、大丈夫かな。瀬戸くんは他人に言いふらすようなタイプじゃないから、まあいいか。
湯船に浸かりながら、私は花宮くんのあの言葉を反芻した。
「〝俺は愛に囚われているからな〟……」
あれって、本当にどういう意味で言ったんだろう。私みたいに、なにかしらの愛を注がれた思い出に囚われて、前に進めない……とか、だろうか。
でも、そんなこと……花宮くん、あったかな。
私が知らないだけ、かな。
「……花宮くん」
私の知らない花宮くんがいる。
そんなの当然のことなのに、改めて考えると、なんだか悲しくなってしまった。いや、寂しい、と言った方が適切か。
花宮くんは小さいころ――厳密に言えば、小学三年生のときまで、お父さんと一緒に住んでいた。花宮くんのお父さんと言うのが、これまた暴力的で、酒にギャンブルに女と、最低最悪の人だったらしい。
お母さんのパート代と生活保護費で生計を立てていたのだと、中学生のころに本人から聞いた。
高校生になったころ、家庭に不和が生じた私とは違って、幼いころから不幸せだったのだ、彼は。だから、過去の愛に囚われているということは、ないと思う。たぶん。
それならいったい、どう意味で……
そんなことを考えていると、浴室の外――居間の方から、スマホの鳴る音がした。
急いでお風呂を済ませて発信元を確認すると、画面には〝花宮真〟の文字があった。
どうしよう。かけなおそうか。それとも、かかってくるのを待とうか。いや……急用だったらなんだし、かけなおして、用事を聞こう。
こんな日の出から電話をかけてくるなんて、ただごとではない可能性がある。
なんだか、厭な予感がする。
――プルルルル、プルルルル……
発信音が三回ほど鳴ったころ、花宮くんは電話に出た。
「もしもし、花宮くん?」
「みょうじ……」
「どうしたの、なにかあった?」
私が食い気味に訊ねると、花宮くんは急に電話口で泣き出し、嗚咽した。
「花宮くん?」
しばらく泣いたのち、花宮くんは一言、
「母さんが、冷たくなってる」
と言った。
ああ、厭な予感が当たってしまった――
(今日は、悲しい日だ)
20200403
瀬戸くんが口にした言葉は、意外にも意外すぎるものだった。
風が、私たちの肌を撫でて去っていく。
「え、と……」
私は言葉に躓く。
どうしよう。どうするのが正解だろう。なんて答えて欲しいのだろう、瀬戸くんは。
そりゃ、こういうシーンだ。私も瀬戸くんのお嫁さんにして、と言えば、瀬戸くんは喜んでくれるのだろうけれど。
でも、私にはそう答えられない理由がある。
すると、しばしの沈黙ののち、瀬戸くんはくすりと笑ってこう言った。
「冗談だよ、困らせてごめんね」
冗談……なら、いいのだけれど。
でも、瀬戸くんって、他人を困らせるような冗談を言うような人だったっけ。いや、違う。彼はそんな人じゃない。
きっと、嘘だ。
冗談だという嘘をついたのだ、きっと。
私の出方を見て、確かめて、私が迷ったから……
「あのね、瀬戸くん」
「ん、なに?」
瀬戸くんも、私と同じように、バルコニーの柵に前のめりに寄りかかって、こちらに視線をやった。
「私、昔からずっと、花宮くんのことが好きだったんだ」
「好きだった、って、過去形?」
「ううん、現在進行形」
「……そっか」
「うん」
「ちなみに、それってさ」
「なあに?」
「俺じゃ、代わりになれないよね」
「……うん、なれない。花宮くんが、私のことどう思ってるかはわからないけれど、私は花宮くんのことしか考えられない」
「そうだよね。うん、わかった」
ごめんね――
瀬戸くんは一言そう言って、遠くを眺めた。
町の全部が見渡せる場所。
私の住んでいたあの家。花宮くんとの秘密基地。そして、このバルコニー。 私の知る限り、町を一望出来る場所は、この三つだけ。
大切な場所が、また一つ増えた。
「今日はさ、なまえちゃんに今言ったことを伝えたくて呼んだんだ」
「夜中ってあたりが瀬戸くんらしいなって思ったよ」
「俺ってそんな風に思われてるの?」
「あ、ううん、違うの。いつも夜までバイトしてる私のこと、気遣ってこの時間を選んでくれたんだろうなと思って。だから、人を思いやれる瀬戸くんらしいなって」
「ああ、そういう意味か。……別に、この時間を選んだのは、特に深い意味はなかったよ」
「そういう善意の誤魔化しも、瀬戸くんらしい」
「……負けたよ」
「ふふ。勝っちゃった」
瀬戸くん。瀬戸健太郎くん。
私の大切な、友達。
私たちは、しばらくバルコニーで雑談をして、日が昇る少し前に、自転車で家へと帰った。
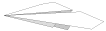
家に着いたあと、私は一息つくためにお風呂に入った。冬場のどうしても寒いときにしか、基本的に湯船には浸からないけれど、今日は例外。
とりあえず、ゆっくり癒されたかった。
ああ、私、なんの考えもなしに、花宮くんのことが好きだって言っちゃったけど、大丈夫かな。瀬戸くんは他人に言いふらすようなタイプじゃないから、まあいいか。
湯船に浸かりながら、私は花宮くんのあの言葉を反芻した。
「〝俺は愛に囚われているからな〟……」
あれって、本当にどういう意味で言ったんだろう。私みたいに、なにかしらの愛を注がれた思い出に囚われて、前に進めない……とか、だろうか。
でも、そんなこと……花宮くん、あったかな。
私が知らないだけ、かな。
「……花宮くん」
私の知らない花宮くんがいる。
そんなの当然のことなのに、改めて考えると、なんだか悲しくなってしまった。いや、寂しい、と言った方が適切か。
花宮くんは小さいころ――厳密に言えば、小学三年生のときまで、お父さんと一緒に住んでいた。花宮くんのお父さんと言うのが、これまた暴力的で、酒にギャンブルに女と、最低最悪の人だったらしい。
お母さんのパート代と生活保護費で生計を立てていたのだと、中学生のころに本人から聞いた。
高校生になったころ、家庭に不和が生じた私とは違って、幼いころから不幸せだったのだ、彼は。だから、過去の愛に囚われているということは、ないと思う。たぶん。
それならいったい、どう意味で……
そんなことを考えていると、浴室の外――居間の方から、スマホの鳴る音がした。
急いでお風呂を済ませて発信元を確認すると、画面には〝花宮真〟の文字があった。
どうしよう。かけなおそうか。それとも、かかってくるのを待とうか。いや……急用だったらなんだし、かけなおして、用事を聞こう。
こんな日の出から電話をかけてくるなんて、ただごとではない可能性がある。
なんだか、厭な予感がする。
――プルルルル、プルルルル……
発信音が三回ほど鳴ったころ、花宮くんは電話に出た。
「もしもし、花宮くん?」
「みょうじ……」
「どうしたの、なにかあった?」
私が食い気味に訊ねると、花宮くんは急に電話口で泣き出し、嗚咽した。
「花宮くん?」
しばらく泣いたのち、花宮くんは一言、
「母さんが、冷たくなってる」
と言った。
ああ、厭な予感が当たってしまった――
(今日は、悲しい日だ)
20200403
前へ 次へ