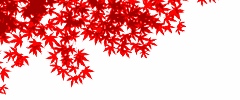 ‖掌から温もりを "綺麗な刀…あの人の魂に等しいんだものね、貴方は" 俺の刃に映り込んで、微笑んだ桜色の口元と長いおさげの赤い髪を覚えている。 あの時代には異国人のように珍しい色だったから、俺の主は最初は警戒していたんだ。 初めてその赤い髪に出会った日、主は赤い髪の持ち主の喉元に俺を突きつけていたっけ。 だけどいつからかその赤いおさげ髪は、主の背後で護られて揺れていた。 時にはその赤が俺の刀身を横切って、飛び出していった時もあった。 いつからだったか。 主独特の握り手から警戒心が消えて、赤いおさげ髪の彼女に対しての愛おしさが、主から流れてくるようになったのは。 「(…絹姫様の、よく似た赤髪は偶然なんだろうか)」 膝の上で眠る、この小さな主の髪に触れると、元の主の想いに感化されそうになる。 あの人を手本に、俺は形をとっているからだろうか。 「(刀の俺が抱くような想いじゃねぇ。それにあの赤い髪の彼女は、あの人のもんで、あの人と一緒に死…)」 「兼さん、絹姫様は…あ、お昼寝中ですか」 「!…国広か」 「兼さん、ほんとに絹姫様にべったりですね」 「しっかり見てねーとじいさんにどやされるだろ?」 「…本当にそれだけですか?兼さん」 「……お前も覚えてたか…」 勿論ですよ、と国広が眉を下げて笑った。 「トシさんの最後の想い人ですから、赤い髪の彼女は、紬さんは」 「…」 「そっくりですよね姫様は。紬さんはもう少し大きかったですけど」 「…人間には、生まれ変わりってのはあるのかもしんねぇな」 「…刀でもあるかもしれませんよ、魂の一欠片でも主の…彼の想いが残っていたら」 「…馬鹿言え。俺はあの人にはなれねぇよ。俺は、どこまでいってもただの刀だ」 もし絹姫が、主の愛した紬の生まれ変わりならば きっとまた俺たちの主の魂を持った男と、出会う日が来るのだろう。 「だからそれまで、俺はあの人の刀として絹姫様を護るだけさ。未来のためにな」 「…なら、僕もお付き合いします」 「おう」 「(…兼さん。トシさんも、桜が似合うと彼女に言われていたのは、忘れているのかな)」 終 [ 前 * 4/4 * 次 ] [ LIST / TOP ] |