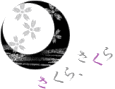――……えで…、…の声を聴け…、……が喚びかけに応えろ……!
「…くら、おいさくら、さくらー、どこ逝っちゃってんだー。戻ってこーい」
肩を激しく揺すられてハッと我に返ったさくらは、それまで焦点が合っていなかった瞳を目の前の者に向けた。
「…え…?蒼空(そら)?どうしてここに…、なにしてるの?」
「俺がここにいる理由はたった今、奉納試合が終わって帰るところだから。何してるかというと、ひとりでふらふら歩いてる巫女さんを見つけたから追いかけて来たの。捕まえてみるとその巫女さんは何かに獲りつかれちまったみたいにぼんやりしてて、呼んでも答えない」
「あ…」
「そんな格好して、こんなとこでぼんやりしてどうしたんだ?」
剣道着と袴を着け、防具を背負った短髪長身の蒼空と呼ばれた若者は、口調の軽さには似合わない真剣な眼差しでさくらと呼んだ娘を問い詰めた。
「ごめん…。私、心配かけちゃったみたい?」
「まあな。何かお前の様子、普通じゃなかったし。それに巫女さんになってるし」
蒼空はさくらが着ている巫女の装束を顎で指す。
「これは今日だけのバイトなの。人手が足りないからって颯矢(そうや)に頼まれて」
「なるほどな」
色白にセミロングの黒髪が映えるさくらに紅い袴はよく似合っている。
「なんか…、蒼空とお揃いみたいだね」
無垢に笑うさくらは普段のさくらだ。さっきは少し焦ったが、とりあえず蒼空は一息ついた。
今日は、ここ珠羽(たまはね)神社の祭りだ。縁結び、恋愛成就の神社として名が通っているため、年始や祭りの日は地元の人間だけではなく遠方からも誰かと縁を結びたいと願う人がやってくる。
さくらは神社の倅で見習い神主をしている幼馴染の颯矢に『一日巫女さん』を頼まれたのだった。
蒼空は警官だ。村の剣友会は毎年の祭りで奉納試合を行っている。蒼空は奉納が終わって帰る途中で、人のにぎわいの中からひとりでふらふらと神社の外れに行こうとする巫女姿のさくらを見つけたのだった。
「お昼からずっとお守り売ってて、人も多いしちょっと疲れちゃって。颯矢が少し休憩してきていいって言うから人がいないところへ行こうと思ったら…」
――……えで、…声を聴け………!
あの声が聞こえたのだ。
いや、聞こえたというよりは、頭の中で響いたという感じだった。声は微かで何を言っているのかはよく分からなかったが、何か、胸が締め付けられる思いがして切なくて、気が付くとこんな外れまで来ていて蒼空に肩を叩かれていた。
「さくら?」
「ううん、何でもない。人に酔っちゃったんだと思う」
たぶん、あの声も気のせいだ。でなければ、近くにいた誰かが言った声が祭りの太鼓や笛の音に重なって、あんなふうに聞こえただけだろう。
「人酔いか。うちの村、年始と祭りの日限定で人口が十倍になるからな」
珠羽神社に祀られている松風(まつかぜ)の神様に祈願すれば良縁に恵まれる、というのは一昔前の言われ方で、最近になってからは好きな人とキスができる、キスのカミサマ、との夢言が若者たちの間で流れている、らしい。
「しかも、今年は千年祭と重なってるからさらに倍の人出だ」
珠羽神社の歴史は古く、松風の神が祀られてから今年でちょうど千年になる。
「うちの神様って若い人にすごい人気なのね…。こんなにも好きな人とキスしたいと願う人たちがいるなんてちょっと驚き…」
さくらにとって、キスのお守りを求めて次々とやってくる若者たちの光景はかなりの衝撃だった。
「お守りを買ったところで叶うものだとも思えないけど…」
「おいおい。巫女さんがそんなこと言っちゃ、みもふたもないだろう」
「あ、そうね。颯矢に怒られちゃう…。今の、聞かなかったことにしてね!」
両手を合わせて願うさくらに、分かったよ、と蒼空は笑う。
「でもね、この間颯矢から聞いたんだけど、この神社に祀られている松風の神様は悲恋の果てに悲しい最期を迎えた人なんだって…」
「ああそれ、村に伝わる有名な伝説だ」
「…私は聞いたことなかったの!この村で生まれたのに、その伝説、今まで一度も…!」
さくらはぷーっと膨れて蒼空を睨んだ。
「べつに知らないから悪いってわけでもないし…、」
何をそんなにムキになってる、と蒼空。
「だって…」
千年も前の悲恋を知った時、胸が痛くてたまらなくなった。無意識に涙がぽろぽろ零れて、颯矢を驚かせてしまったぐらいだ。
「まあ…、どこにでもあるような話なんだけど――」
・
・
昔は珠羽領と松風領のふたつに分かれていた領地が統合したのが今の珠羽村だ。千年の昔、松風には二人の皇子がいて珠羽には姫がひとりいた。二人の皇子は同じ珠羽の姫を愛し、二人が姫を我が妻にと望んだ。
だが、幼い頃からふたりの皇子と親交を深めていた姫は、どちらかひとりなど選べず、思いつめた挙句に自害してしまい、皇子たちは打ちひしがれた。
このことが切欠となり、珠羽と松風は戦になった。兄はその戦いのさなか、乱心の末に大量の血を吐いた。弟は姫が死んでから自暴自棄になり行方知れずとなり。
やがてふたりは姫の死を受け入れられないまま、それぞれ非業の死を遂げ、松風は滅んだ。
その後、天変地異、疫病、飢饉などの禍が続けて起こるようになり、嵐の中で哭き吼えるふたりの皇子が頻繁に目撃された。人々は皇子たちの報われない魂が死んでもなお、愛しい人を求めて泣いているからだと考えた。
そこで人々は社を建て、姫の形見と共に皇子たちの御霊を祀った。すると禍は嘘のように止み、松風と珠羽はひとつの村になって豊かな土地になっていった。
・
・
「――恋愛経験ゼロのさくらにしてみれば、かなりろまんちっくな伝説かもなぁ」
蒼空は軽い調子でさくらをからかうが、さくらの方は何かに傷ついたような顔を蒼空に向け、
「………蒼空のばか」
と、小さく呟く。
「な、なんだよ?」
「どうせ私は蒼空と違って恋愛経験ゼロだもん…」
「蒼空と違って…って、なんだか棘がある言い方だな」
「……知らない」
「なになに?なんで怒ってるんだ?」
本気でおろおろする蒼空が少し可哀想になってしまい、さくらは、何でもない、と笑顔になった。もともと、蒼空がさくらに何かをしたわけではない。さくらが自分の気持ちの中で勝手に拗ねてしまっているだけのことだ。
さくらに笑顔が戻り、何が何だか分からなかったが、とりあえず蒼空もホッとする。
「やれやれ…」
「神社にいる松風の神様はひとりよね。どっちの皇子様なんだろう」
「いきなり話が戻ったな」
わけわかんねー、と蒼空。
「え?」
「いや。初めはふたりの御魂を祀ったんだろう。けど、長い時が経つうちにふたりがひとりのカミサマになったんだと思うぜ。そこら辺は颯矢の方が詳しいんじゃないか」
「そういえば颯矢言ってた。神様は後々の人の想いが作るものだって…」
悲恋に散った皇子たちの悲しみが人が誰かを愛する想いに溶かされて次の願いを叶える、その巡りを信じる人の心が縁結びの神様を造りだした――、
「――って」
「それが今じゃ、どういうわけかキスのカミサマとか言われて村おこしの道具にされてるけどな」
初めにそれを言い出したのはこの神社で祈願をして、たまたまそれが叶ったという若者なのだろう。若者が使う様々なツールから妄想や創作が加わった情報が広まり、それが話題になって雑誌に取り上げられ今に至っている一種の麻疹現象だ。過疎に加えて寂れる一方だった村は、これ幸いと“キスのカミサマ”を担ぎ上げて村を興しているのだ。
「にんげんってあさましい」
蒼空が単調につぶやくとさくらも、そうだね、と同意しながら、気になっていることを口にした。
「キスは神様に頼ってするものなの?」
「は?」
「好きな人とキスできますようにって、蒼空は神様にお願いしてするの?」
「はぁ!?」
突拍子もないさくらの問いかけに蒼空はうろたえるが、訊いたさくらは真面目に答えを待っている。
「なんで、そんなこと訊くんだよ」
「なんとなく…」
「お、俺は、カミサマより本人に願うんじゃねーかな。そーゆー雰囲気になってればの話だけど…、って、なんで真面目に答えてんだよ、俺は…っ」
じゃあ、あの時は相手の人に願ってキスしたんだ…、とさくらはぽつりとつぶやいた。
「あの時?」
怪訝に眉根を寄せる蒼空にさくらは、なんでもない、と首を振る。
「私はどうなのかな…。やっぱり、そういう相手がいたら、神様に願うのかな」
「し、知るか。そんなの俺に訊くんじゃない!」
「颯矢はどうかな…」
「って、颯矢にも訊くんじゃねーぞ、そんなこと!」
どうして?と無垢に首を傾げるさくらに、蒼空は盛大なため息を吐いた。この二つ年下の幼馴染の恋愛に関する認識は良く言えば純粋無垢であり、悪く言えば鈍感。キスは神様に頼ってするものなのか、なんて子どもでもしないような質問を真顔でするのだから。
「まったく…」
蒼空はさくらの両肩に手を置いて、無垢な瞳をじっと覗き込んだ。
「どうしたの?」
「さくらに願う。俺、おまえにキスしたい」
「……え?」
背中に定規を突っ込まれたように真っ直ぐ固まってしまったさくらの顔に、蒼空はゆっくりと自分の顔を近づけていった。瞳を伏せ、長いまつ毛を震わせてゆっくりと。そして、唇と唇が触れ合う寸前で止まる。剣道着から汗が混じる蒼空の匂いがふわりと香った。
「お前の唇に俺の唇で触れたい…。いいか…?」
「そ、蒼空?!」
真っ赤になってあわあわするさくらに、だが蒼空はにやり、と笑った。
「なーんてな!冗談だよ冗談」
「………っ!!」
「本気にした?ちょっとは本気にしたか?」
「し…、信じられない!蒼空のバカ!!」
蒼空の背中に真っ赤な開いた指の跡がついたのは言うまでもない。
マジでぶつことないだろー、蒼空が悪いんでしょー、とさんざんじゃれ合った後。
「でも……、蒼空はキスとか恋愛とか慣れてそうだよね…」
再び、ぽつりとさくらが呟いた。
「慣れてるわけないだろ。俺が女たらしみたいなこと言うな!」
「だって…、昔から蒼空って女の子にモテるし、この前も女の人と一緒にいる蒼空を見ちゃったもん…」
いつだ、それ!?と、蒼空は狼狽えた。
「最近…。すごく仲好さそうにくっついてた…」
覚えがあるようなないような蒼空は、必死に最近の記憶を手繰り寄せた。さくらの目を見れば、じいっと、まるで責められているような眼差しでこちらを見ている。
「そ、それはたぶん、道訊かれて案内してただけだ!と思う!いや、絶対そうだ!」
ふうん…、とさくらはあまり信用していない目を蒼空に向ける。
「人も歩いていない夕暮れの木陰で道を訊かれたんだ…」
「そういうこともある!」
蒼空は無駄に胸を張って言い切る。
「……ふうん」
「疑ってる…?」
「うん…。道案内であんなにくっつかないと思うもん…」
遠目ではキスしてるように見えた、とさくら。
「神様のおひざ元で好きな女の人に願ってキスできてよかったね」
単調に台詞を読んでいるようなさくらの言葉に蒼空はごくりと生唾を呑んだ。さっきからさくらの様子がおかしかったのは、もしかしたらこれが理由なのか――と。
「マジで、絶対、それはお前の見間違いだぞ!」
盛大すぎる誤解を解こうと必死になる蒼空の目が真摯にさくらを捕らえた。
「さくらにひとつ教えてやる。キスってのは、ある意味一番神聖なんだ。本気で惚れた相手としかできないんだぞ」
本気で惚れた相手――という蒼空の声と言葉にさくらの胸がどくんと跳ねる。
「……そうなの?」
「そうなの!」
「えっちはできるのに?」
「おい!えっちはできるって、なんだそれ!?」
「男の人は好きじゃない女の人とも欲情だけで平気でえっちしちゃうセッスクマシーンなんだって、大学の友達が言ってた」
「せ、せっくすましーん…っ!?」
だぁぁと叫んで蒼空は頭を抱えた。
確かに男とはそういう生き物かもしれない。胸を張って自分は違います、と言えないのがカナシイが、さくらの無垢な口からセックスマシーンなんて単語は飛び出して欲しくない。
「今どきの女子大生って恐ろしい。なんてこと話してんだよ」
「そう?」
「さくら、おまえ意味分かってそういう会話に混ざってるのか?」
「……ぜんぜん。えっちのやり方とか友達がよく話してるけど、私は意味が分からないから」
「やーめーろー!えっちのやり方とか言うなー!」
蒼空は真っ赤になって叫んだ。
「お前はな、まだそーゆーことに興味持たなくていいんだぞ?!間違ってもえっちのやり方とか誰かに教わったりするなよ!知りたくなった時は俺が教えてやるから!」
「蒼空が…?」
教えてくれるんだ…、とさくら。
「あ、いやその…っ」
つい、口から出てしまった己の失言に気がついて蒼空は今度はみるみるうちに蒼白になった。
「………」
さくらがじいっと見ている。
その、無垢な視線に耐え切れなくなって、
「と、とにかくだ!えっちのことは置いといて!キスってのはえっちよりも神聖なの!だから、キスのカミサマに人が願うのは、キスすることそのものよりも、結局は好きな相手の心が欲しい、相思相愛になりたいってことなんだよ。たぶんな」
蒼空は強引に話を元に戻してほっと一息ついた。
「はい、よくできました」
蒼空が必死になって話し終えた時、どこからかパチパチと拍手が聴こえた。蒼空とさくらが顔を向けたところに立っていたのは、法衣を着けた若き神主見習いだ。
「蒼空にしては立派な講釈だったよ」
「颯矢、いつから聞いてやがった」
「蒼空がさくらの肩を叩いて、戻ってこーいって言ってる時から、かな」
「最初からじゃないか!」
「そうだね。俺もさくらのこと追って来たんだけど、先に蒼空が声をかけてたから出てくるタイミングを逃してさ。その後、ふかーい話が始まっちゃったから余計に出られなくなった。もし蒼空がほんとにさくらにキスしてたら容赦なく滅してやったけどね」
あぁぁと叫んで蒼空は再び頭を抱えた。
サラサラの髪を風になびかせてニコニコ笑って話す颯矢だが、その笑顔の下にどす黒いものがチラチラと見えるのは気のせいではない。
「さて、さくら。そろそろ戻ってもらってもいいかな?」
「うん。休憩が長くなってごめんね」
「いや、それはいいんだけど」
「じゃ、俺は帰るぜ。せっかくの祭りだからさくらに水風船釣ってやりたかったけど、まだ終わらないんだろ、巫女のバイト」
「水風船って…、蒼空は私のこと子ども扱いしてるでしょ…」
立派な子どもじゃないか…、と蒼空はため息を吐いた。
「水風船は後で俺が釣ってやるよ。さくらの好きなピンク色のやつをさ」
「颯矢までそんなこと言うの?」
「だって、祭りでいつも俺たちに釣って釣ってーって言ってたじゃない」
「そうそう。さくらは祭りといえば水風船だったよな」
釣った水風船を落として割れて泣いた、
ピンクが欲しいのに黒いの釣って泣かれたことがあった、
と、蒼空と颯矢は幼い頃のさくらを思い出して笑いあう。
「もう!ふたりともヒドイ!私、そんなに泣いてばかりいないよ」
さくらを挟み、ははは、と声をあげる蒼空と颯矢。それは幼い頃から変わらない、三人の日常的な光景だった。
「…くら、おいさくら、さくらー、どこ逝っちゃってんだー。戻ってこーい」
肩を激しく揺すられてハッと我に返ったさくらは、それまで焦点が合っていなかった瞳を目の前の者に向けた。
「…え…?蒼空(そら)?どうしてここに…、なにしてるの?」
「俺がここにいる理由はたった今、奉納試合が終わって帰るところだから。何してるかというと、ひとりでふらふら歩いてる巫女さんを見つけたから追いかけて来たの。捕まえてみるとその巫女さんは何かに獲りつかれちまったみたいにぼんやりしてて、呼んでも答えない」
「あ…」
「そんな格好して、こんなとこでぼんやりしてどうしたんだ?」
剣道着と袴を着け、防具を背負った短髪長身の蒼空と呼ばれた若者は、口調の軽さには似合わない真剣な眼差しでさくらと呼んだ娘を問い詰めた。
「ごめん…。私、心配かけちゃったみたい?」
「まあな。何かお前の様子、普通じゃなかったし。それに巫女さんになってるし」
蒼空はさくらが着ている巫女の装束を顎で指す。
「これは今日だけのバイトなの。人手が足りないからって颯矢(そうや)に頼まれて」
「なるほどな」
色白にセミロングの黒髪が映えるさくらに紅い袴はよく似合っている。
「なんか…、蒼空とお揃いみたいだね」
無垢に笑うさくらは普段のさくらだ。さっきは少し焦ったが、とりあえず蒼空は一息ついた。
今日は、ここ珠羽(たまはね)神社の祭りだ。縁結び、恋愛成就の神社として名が通っているため、年始や祭りの日は地元の人間だけではなく遠方からも誰かと縁を結びたいと願う人がやってくる。
さくらは神社の倅で見習い神主をしている幼馴染の颯矢に『一日巫女さん』を頼まれたのだった。
蒼空は警官だ。村の剣友会は毎年の祭りで奉納試合を行っている。蒼空は奉納が終わって帰る途中で、人のにぎわいの中からひとりでふらふらと神社の外れに行こうとする巫女姿のさくらを見つけたのだった。
「お昼からずっとお守り売ってて、人も多いしちょっと疲れちゃって。颯矢が少し休憩してきていいって言うから人がいないところへ行こうと思ったら…」
――……えで、…声を聴け………!
あの声が聞こえたのだ。
いや、聞こえたというよりは、頭の中で響いたという感じだった。声は微かで何を言っているのかはよく分からなかったが、何か、胸が締め付けられる思いがして切なくて、気が付くとこんな外れまで来ていて蒼空に肩を叩かれていた。
「さくら?」
「ううん、何でもない。人に酔っちゃったんだと思う」
たぶん、あの声も気のせいだ。でなければ、近くにいた誰かが言った声が祭りの太鼓や笛の音に重なって、あんなふうに聞こえただけだろう。
「人酔いか。うちの村、年始と祭りの日限定で人口が十倍になるからな」
珠羽神社に祀られている松風(まつかぜ)の神様に祈願すれば良縁に恵まれる、というのは一昔前の言われ方で、最近になってからは好きな人とキスができる、キスのカミサマ、との夢言が若者たちの間で流れている、らしい。
「しかも、今年は千年祭と重なってるからさらに倍の人出だ」
珠羽神社の歴史は古く、松風の神が祀られてから今年でちょうど千年になる。
「うちの神様って若い人にすごい人気なのね…。こんなにも好きな人とキスしたいと願う人たちがいるなんてちょっと驚き…」
さくらにとって、キスのお守りを求めて次々とやってくる若者たちの光景はかなりの衝撃だった。
「お守りを買ったところで叶うものだとも思えないけど…」
「おいおい。巫女さんがそんなこと言っちゃ、みもふたもないだろう」
「あ、そうね。颯矢に怒られちゃう…。今の、聞かなかったことにしてね!」
両手を合わせて願うさくらに、分かったよ、と蒼空は笑う。
「でもね、この間颯矢から聞いたんだけど、この神社に祀られている松風の神様は悲恋の果てに悲しい最期を迎えた人なんだって…」
「ああそれ、村に伝わる有名な伝説だ」
「…私は聞いたことなかったの!この村で生まれたのに、その伝説、今まで一度も…!」
さくらはぷーっと膨れて蒼空を睨んだ。
「べつに知らないから悪いってわけでもないし…、」
何をそんなにムキになってる、と蒼空。
「だって…」
千年も前の悲恋を知った時、胸が痛くてたまらなくなった。無意識に涙がぽろぽろ零れて、颯矢を驚かせてしまったぐらいだ。
「まあ…、どこにでもあるような話なんだけど――」
・
・
昔は珠羽領と松風領のふたつに分かれていた領地が統合したのが今の珠羽村だ。千年の昔、松風には二人の皇子がいて珠羽には姫がひとりいた。二人の皇子は同じ珠羽の姫を愛し、二人が姫を我が妻にと望んだ。
だが、幼い頃からふたりの皇子と親交を深めていた姫は、どちらかひとりなど選べず、思いつめた挙句に自害してしまい、皇子たちは打ちひしがれた。
このことが切欠となり、珠羽と松風は戦になった。兄はその戦いのさなか、乱心の末に大量の血を吐いた。弟は姫が死んでから自暴自棄になり行方知れずとなり。
やがてふたりは姫の死を受け入れられないまま、それぞれ非業の死を遂げ、松風は滅んだ。
その後、天変地異、疫病、飢饉などの禍が続けて起こるようになり、嵐の中で哭き吼えるふたりの皇子が頻繁に目撃された。人々は皇子たちの報われない魂が死んでもなお、愛しい人を求めて泣いているからだと考えた。
そこで人々は社を建て、姫の形見と共に皇子たちの御霊を祀った。すると禍は嘘のように止み、松風と珠羽はひとつの村になって豊かな土地になっていった。
・
・
「――恋愛経験ゼロのさくらにしてみれば、かなりろまんちっくな伝説かもなぁ」
蒼空は軽い調子でさくらをからかうが、さくらの方は何かに傷ついたような顔を蒼空に向け、
「………蒼空のばか」
と、小さく呟く。
「な、なんだよ?」
「どうせ私は蒼空と違って恋愛経験ゼロだもん…」
「蒼空と違って…って、なんだか棘がある言い方だな」
「……知らない」
「なになに?なんで怒ってるんだ?」
本気でおろおろする蒼空が少し可哀想になってしまい、さくらは、何でもない、と笑顔になった。もともと、蒼空がさくらに何かをしたわけではない。さくらが自分の気持ちの中で勝手に拗ねてしまっているだけのことだ。
さくらに笑顔が戻り、何が何だか分からなかったが、とりあえず蒼空もホッとする。
「やれやれ…」
「神社にいる松風の神様はひとりよね。どっちの皇子様なんだろう」
「いきなり話が戻ったな」
わけわかんねー、と蒼空。
「え?」
「いや。初めはふたりの御魂を祀ったんだろう。けど、長い時が経つうちにふたりがひとりのカミサマになったんだと思うぜ。そこら辺は颯矢の方が詳しいんじゃないか」
「そういえば颯矢言ってた。神様は後々の人の想いが作るものだって…」
悲恋に散った皇子たちの悲しみが人が誰かを愛する想いに溶かされて次の願いを叶える、その巡りを信じる人の心が縁結びの神様を造りだした――、
「――って」
「それが今じゃ、どういうわけかキスのカミサマとか言われて村おこしの道具にされてるけどな」
初めにそれを言い出したのはこの神社で祈願をして、たまたまそれが叶ったという若者なのだろう。若者が使う様々なツールから妄想や創作が加わった情報が広まり、それが話題になって雑誌に取り上げられ今に至っている一種の麻疹現象だ。過疎に加えて寂れる一方だった村は、これ幸いと“キスのカミサマ”を担ぎ上げて村を興しているのだ。
「にんげんってあさましい」
蒼空が単調につぶやくとさくらも、そうだね、と同意しながら、気になっていることを口にした。
「キスは神様に頼ってするものなの?」
「は?」
「好きな人とキスできますようにって、蒼空は神様にお願いしてするの?」
「はぁ!?」
突拍子もないさくらの問いかけに蒼空はうろたえるが、訊いたさくらは真面目に答えを待っている。
「なんで、そんなこと訊くんだよ」
「なんとなく…」
「お、俺は、カミサマより本人に願うんじゃねーかな。そーゆー雰囲気になってればの話だけど…、って、なんで真面目に答えてんだよ、俺は…っ」
じゃあ、あの時は相手の人に願ってキスしたんだ…、とさくらはぽつりとつぶやいた。
「あの時?」
怪訝に眉根を寄せる蒼空にさくらは、なんでもない、と首を振る。
「私はどうなのかな…。やっぱり、そういう相手がいたら、神様に願うのかな」
「し、知るか。そんなの俺に訊くんじゃない!」
「颯矢はどうかな…」
「って、颯矢にも訊くんじゃねーぞ、そんなこと!」
どうして?と無垢に首を傾げるさくらに、蒼空は盛大なため息を吐いた。この二つ年下の幼馴染の恋愛に関する認識は良く言えば純粋無垢であり、悪く言えば鈍感。キスは神様に頼ってするものなのか、なんて子どもでもしないような質問を真顔でするのだから。
「まったく…」
蒼空はさくらの両肩に手を置いて、無垢な瞳をじっと覗き込んだ。
「どうしたの?」
「さくらに願う。俺、おまえにキスしたい」
「……え?」
背中に定規を突っ込まれたように真っ直ぐ固まってしまったさくらの顔に、蒼空はゆっくりと自分の顔を近づけていった。瞳を伏せ、長いまつ毛を震わせてゆっくりと。そして、唇と唇が触れ合う寸前で止まる。剣道着から汗が混じる蒼空の匂いがふわりと香った。
「お前の唇に俺の唇で触れたい…。いいか…?」
「そ、蒼空?!」
真っ赤になってあわあわするさくらに、だが蒼空はにやり、と笑った。
「なーんてな!冗談だよ冗談」
「………っ!!」
「本気にした?ちょっとは本気にしたか?」
「し…、信じられない!蒼空のバカ!!」
蒼空の背中に真っ赤な開いた指の跡がついたのは言うまでもない。
マジでぶつことないだろー、蒼空が悪いんでしょー、とさんざんじゃれ合った後。
「でも……、蒼空はキスとか恋愛とか慣れてそうだよね…」
再び、ぽつりとさくらが呟いた。
「慣れてるわけないだろ。俺が女たらしみたいなこと言うな!」
「だって…、昔から蒼空って女の子にモテるし、この前も女の人と一緒にいる蒼空を見ちゃったもん…」
いつだ、それ!?と、蒼空は狼狽えた。
「最近…。すごく仲好さそうにくっついてた…」
覚えがあるようなないような蒼空は、必死に最近の記憶を手繰り寄せた。さくらの目を見れば、じいっと、まるで責められているような眼差しでこちらを見ている。
「そ、それはたぶん、道訊かれて案内してただけだ!と思う!いや、絶対そうだ!」
ふうん…、とさくらはあまり信用していない目を蒼空に向ける。
「人も歩いていない夕暮れの木陰で道を訊かれたんだ…」
「そういうこともある!」
蒼空は無駄に胸を張って言い切る。
「……ふうん」
「疑ってる…?」
「うん…。道案内であんなにくっつかないと思うもん…」
遠目ではキスしてるように見えた、とさくら。
「神様のおひざ元で好きな女の人に願ってキスできてよかったね」
単調に台詞を読んでいるようなさくらの言葉に蒼空はごくりと生唾を呑んだ。さっきからさくらの様子がおかしかったのは、もしかしたらこれが理由なのか――と。
「マジで、絶対、それはお前の見間違いだぞ!」
盛大すぎる誤解を解こうと必死になる蒼空の目が真摯にさくらを捕らえた。
「さくらにひとつ教えてやる。キスってのは、ある意味一番神聖なんだ。本気で惚れた相手としかできないんだぞ」
本気で惚れた相手――という蒼空の声と言葉にさくらの胸がどくんと跳ねる。
「……そうなの?」
「そうなの!」
「えっちはできるのに?」
「おい!えっちはできるって、なんだそれ!?」
「男の人は好きじゃない女の人とも欲情だけで平気でえっちしちゃうセッスクマシーンなんだって、大学の友達が言ってた」
「せ、せっくすましーん…っ!?」
だぁぁと叫んで蒼空は頭を抱えた。
確かに男とはそういう生き物かもしれない。胸を張って自分は違います、と言えないのがカナシイが、さくらの無垢な口からセックスマシーンなんて単語は飛び出して欲しくない。
「今どきの女子大生って恐ろしい。なんてこと話してんだよ」
「そう?」
「さくら、おまえ意味分かってそういう会話に混ざってるのか?」
「……ぜんぜん。えっちのやり方とか友達がよく話してるけど、私は意味が分からないから」
「やーめーろー!えっちのやり方とか言うなー!」
蒼空は真っ赤になって叫んだ。
「お前はな、まだそーゆーことに興味持たなくていいんだぞ?!間違ってもえっちのやり方とか誰かに教わったりするなよ!知りたくなった時は俺が教えてやるから!」
「蒼空が…?」
教えてくれるんだ…、とさくら。
「あ、いやその…っ」
つい、口から出てしまった己の失言に気がついて蒼空は今度はみるみるうちに蒼白になった。
「………」
さくらがじいっと見ている。
その、無垢な視線に耐え切れなくなって、
「と、とにかくだ!えっちのことは置いといて!キスってのはえっちよりも神聖なの!だから、キスのカミサマに人が願うのは、キスすることそのものよりも、結局は好きな相手の心が欲しい、相思相愛になりたいってことなんだよ。たぶんな」
蒼空は強引に話を元に戻してほっと一息ついた。
「はい、よくできました」
蒼空が必死になって話し終えた時、どこからかパチパチと拍手が聴こえた。蒼空とさくらが顔を向けたところに立っていたのは、法衣を着けた若き神主見習いだ。
「蒼空にしては立派な講釈だったよ」
「颯矢、いつから聞いてやがった」
「蒼空がさくらの肩を叩いて、戻ってこーいって言ってる時から、かな」
「最初からじゃないか!」
「そうだね。俺もさくらのこと追って来たんだけど、先に蒼空が声をかけてたから出てくるタイミングを逃してさ。その後、ふかーい話が始まっちゃったから余計に出られなくなった。もし蒼空がほんとにさくらにキスしてたら容赦なく滅してやったけどね」
あぁぁと叫んで蒼空は再び頭を抱えた。
サラサラの髪を風になびかせてニコニコ笑って話す颯矢だが、その笑顔の下にどす黒いものがチラチラと見えるのは気のせいではない。
「さて、さくら。そろそろ戻ってもらってもいいかな?」
「うん。休憩が長くなってごめんね」
「いや、それはいいんだけど」
「じゃ、俺は帰るぜ。せっかくの祭りだからさくらに水風船釣ってやりたかったけど、まだ終わらないんだろ、巫女のバイト」
「水風船って…、蒼空は私のこと子ども扱いしてるでしょ…」
立派な子どもじゃないか…、と蒼空はため息を吐いた。
「水風船は後で俺が釣ってやるよ。さくらの好きなピンク色のやつをさ」
「颯矢までそんなこと言うの?」
「だって、祭りでいつも俺たちに釣って釣ってーって言ってたじゃない」
「そうそう。さくらは祭りといえば水風船だったよな」
釣った水風船を落として割れて泣いた、
ピンクが欲しいのに黒いの釣って泣かれたことがあった、
と、蒼空と颯矢は幼い頃のさくらを思い出して笑いあう。
「もう!ふたりともヒドイ!私、そんなに泣いてばかりいないよ」
さくらを挟み、ははは、と声をあげる蒼空と颯矢。それは幼い頃から変わらない、三人の日常的な光景だった。