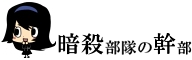そう言えば、以前任務から帰って来た少女を連れて食事に行った事があった。ほんの気まぐれだった。二人で夜の街を出掛けたのだ。彼女は声には出さなかったが、とても喜んでいて、今にも泣き出しそうだったのを覚えている。
確かこの時、普段は全く口を開かないカナタが、珍しく色々喋っていた。多少鬱陶しかったものの、相手は子供だと言う事もあったし普段は見せない様子だったので面白くもあり、ザンザスは文句を言わず相手をしてやったのだ。
「……あ」
間の抜けた声が漏れる。カナタが勢いよく顔を上げた。期待を含んだ眼差しをザンザスに向けてくる。
「おい待て、あれは今の話と関係ねぇだろ」
言えば、カナタは首を激しく左右に振る。いや、関係ない。絶対に。だってあの時した約束は。
「関係あるんです。私決めたんです。その時が来るまではお名前で呼ぶのは控えようって」
「あん?」
「願掛けみたいなものです! わ、分かってます。ボスにその気が全然無かった事なんて! でも、私あの時からずーっとそれだけを夢見てたんです。生きがいなんです。ボスがいない間もずっとずっと願ってたんです」
「アホかテメェは」
「あっ、アホで良いです……私頑張ります、頑張りますから。だからいつか、その時が来たら、前みたいにお名前で呼ばせてください」
何というアホな女だろう。
夢見てた? 願ってた? あんなくだらない、馬鹿馬鹿しい話を? 八年間も?
――ああ、でも。どうしてだろう。
不思議とザンザスの気持ちが晴れていく。先程までは不愉快だった、その女性らしい振る舞いも、よそよそしいと感じた態度も、途端に悪くない気持ちになってしまう。
彼女の変化は、全て変わっていない証なのだと言う事が分かったから。
「私、飲み物、取ってきます」
居心地の悪さを感じたのだろうか、カナタが逃げるようにザンザスに背を向ける。露出した肌が赤い。
足を踏み出した彼女の肩が、大きく震えた。恐らく、ザンザスが手を掴んだからだろう。
「許可なくうろつくんじゃねぇ」
「あ、いえ、の、喉がかわいたなぁと」
「だったら、これでも飲んでろ」
背を向けたままのカナタに、ワイングラスを差し出す。気配でそれを感じたのか、彼女は赤い顔でゆっくりと振り返った。
「私お酒は」
「テメェ幾つだ。もう19だろ」
「日本ではお酒は20歳からなんです」
「ここは何処だ」
鼻で笑えば、カナタは渋々と言った感じでそれを受け取った。カナタは妙に困った顔をしながら、ワイングラスを睨みつける。意を決したように口をつけようとした所で、ザンザスが口を開いた。
「約束は帳消しだ」
「えええっ!?」
カナタがワイングラスから顔を離し、泣きそうな顔でザンザスを見てくる。
「元々俺は、そんな面倒なもんはいらねぇ。だから約束を守るつもりもはなからねぇ」
「そ、そ……そんな」
カナタの赤かった顔が、みるみる内に血の気が引いて青くなっていた。その瞳は直ぐにでも涙がこぼれおちそうなくらいに、潤んでいる。
「文句があるならもっと上を目指せ」
「は?」
「テメェは欲が無さ過ぎる」
「え」
前を見据えてそう言えば、カナタはよく理解出来ていないのか黙ってしまった。横から視線を感じながら、ザンザスは柱にもたれかかり、ぼんやりとパーティ会場を眺める。
掴んでいたその小さな手が、次第に熱を帯びて来た頃だろうか。
「しょ、精進します……」
か細い声が耳に届いた。横目で見ればカナタは、俯いていて表情は見えない物の、再び全身を真っ赤にしていた。
そう言えば、八年前のあの時も、彼女は赤くなっていたなと、思い出す。
『大人になったら、ザンザス様の愛人にしてください』
何処でそんな言葉を覚えたのか。まだ十一歳の少女は、真剣な表情で訴えて来た。ガキに興味はねぇと答えれば、泣き出しそうな顔をしたので、面倒くさくなって答えたのだ。
『……良い女になったら考えてやっても良い』
吐き捨てるように告げた言葉なのに、カナタはえらく喜んでいた。それがまさかここまで本気だとは知りもしなかったけれど。気がつけば一瞬で大人になるのだから、困ったものである。
大体、何故愛人なのか。妻ではなく、妾を望む。全く可愛げのない。そんなもの、子供が夢見るような事でも、願い続けるような事でもない。
馬鹿な女。
本当に馬鹿で愚かな女だ。
しかし何故か怒りは湧かない。
馬鹿で愚かか。それも、悪くない。
初老の男の目が、穏やかに細められた。その瞳には賑わうパーティ会場から少し外れた所で、手を握り合ったまま佇んでいる男女二人を捉えている。
「九代目?」
「ああ、すまないね」
声を掛けられ、男は視線を二人から離した。その表情は、木漏れ日のように暖かでいて柔らかい。
時間が止まったかのような、不思議な空気が会場を包んでいた。
輝く星々の下、船は進むのを止めない。穏やかな夜は更けていく。
星空は見ていた
(2011.06.18)