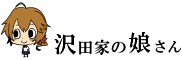朝7時。
いつも通り起床。目をこすりつつカーテンを開けば、太陽の光が部屋に差し込んでくる。
「おはよう」
「おはよう、ソラちゃん。今日から夏服でしょ? 制服そこに出してあるからね」
「はーい」
リビングへ入ると母さんの笑顔が飛び込んできた。いつもの事ながら、よくもまあ朝から元気でいられるもんだと感心してしまう。
私はソファの上に制服が置いてあるのを確認し、食卓へついた。ツナはまだ寝ているのか、席にはいない。
笹川君の事が好きになった春から、あっという間に時は過ぎて行き、気づけばもう衣替えの季節である。
そして非常に残念なことに、私と彼の間には特に何の進展もないままだったりする。
だって仕方ないじゃない。クラスも違うし。用もなく話しかけるのも、何だか恥ずかしい。大体笹川君は廊下でくだらない話をだらだらするようなタイプでもない。さらに言えば私も行動的なタイプではないのだ。
そんな訳で。私が出来る事と言えば、運よく登校中に笹川君を見かけたら声を掛けて一緒に登校してみたり、運よく廊下ですれ違ったら挨拶する事くらいだった。しかも笹川君は大体突っ走っているので、引き止められる確率も低い。と言う事で、私が笹川君との仲を進展させるのは非常に困難な事だった。
いっそのことボクシング部に入部してマネージャーをしたり、ガンガン追いかけてアタック出来ればいいんだけど、やっぱり色々考えちゃって出来ないんだよなあ。本当、私ってチキンだ。悔しい程にチキンなのだ。
食事を終え、部屋で着替えながら溜息をつく。今日は笹川君と話せると良いなあ、なんて思いながら部屋を出る。この際だ。せめて顔が見られればそれだけでも良い。
「ツッ君! ほーら、起きなさい」
ツナの部屋からは母さんの声。いつも通りツナは寝坊しているらしい。この光景も春からずっと変わらない。
「じゃあ、母さん、いってくるね」
「はーい、いってらっしゃい、ソラちゃん! 気をつけてね」
ツナの部屋に向かって声をかけてから、私は階段を下りた。
「ちゃおっす」
「……え?」
玄関まで進めば、そこには見知らぬ赤ちゃんが立っていた。うちは私とツナの二人姉弟だ。当然、こんな小さな子がいるはずはない。ではこの子は一体誰だろう。
「ぼく、どこの子? どうしてうちのいるのかな?」
赤ちゃんの前にしゃがみ込み、目線を合わせて伺ってみる。そしてその姿をはっきりと確認すると、胸がきゅんきゅんしてきた。だってこの子、すっごく可愛いのだ。赤ん坊だというのに、いっちょまえに黒スーツにネクタイをしめている。そのアンバランスさが、たまらなく可愛い。あまりの可愛さに思わず頬が緩んでくる。
「オレは家庭教師のリボーンだ」
「はい?」
予想外の単語に私は固まった。すらすらと喋れたのにも驚きだけど、何よりも今この子は家庭教師、と言った事に驚いた。こんな赤ちゃんが、一体誰の家庭教師をするっていうのだ。
もしかして今そういう遊びが流行っているのだろうか。
「って……遅刻しちゃう! ぼく、ごめんね。お姉さん学校に行かなくちゃ。またね」
「おう。またな、ソラ」
色々と気になる事はあったけれど、こうしていては遅刻してしまう。
私が慌てて立ち上がれば、赤ちゃんは手を上げてそれを見送ってくれた。
家から出ると、熱い日差しが私を出迎える。今日も良い天気だ。
それにしても、どうして赤ちゃんがうちにいたのだろうか。母さんは何もいってなかったけど、近所の子を預かったのかな。またな、とか言っていたし、もしかして今日一日預かる予定なのだろうか。
って、あれ? さっきの子、私の名前呼んでたような。私、名乗ったっけ。
首を捻りつつ、歩を進めていると前方に見慣れた人影を発見する。その姿を発見した瞬間、考え事なんて一気に吹っ飛んでしまった。シャドーボクシングをしながら走っているのは、言わずもがな。
「笹川君、おはよう!」
見失う前にと、その背に声を掛ければ笹川君は勢いよく振りかぶるように、こちらに向き直った。彼は些細な動作にも常に全力投球なのだ。
「おお、沢田か! 今日も極限に良い天気だな! 絶好のボクシング日和だ!」
「本当に良い天気だよね、今日は暑くなりそう。もうすっかり夏って感じ」
ボクシングって室内競技だから天気は関係なくない? なんていう話はこの際置いておく。朝から笹川君に会えたのだ。そんなツッコミを入れるなんて野暮な事この上ない。
笹川君と肩を並べて歩ける。これに勝るものなんて、今の私には何もないのだ。
「うおおおおおおおおおおおおおおお!」
上機嫌でスキップしそうになるのを必死に抑えながら歩いていたら、背後から聞き覚えのある声がした。そして、同時に激しい地響き。その二つが、段々とこちらに迫ってくる。
その異様な雰囲気に、恐る恐る振り返ろうとした瞬間、私の横を風のような速さで何かが通り抜けた。
あまりの速さだった為か、すれ違っただけだというのに、髪とスカートがばさばさとなびく。
えーと……。
「何だ、今の男は!?」
「っていうか今通り過ぎた人、裸じゃなかった!?」
一瞬の間を置いて、私は驚嘆の声を上げた。私だけではなく、横では笹川君も足を止め目を見開いている。当たり前だ。たった今、服を着てない少年が凄まじい勢いで通り過ぎて行ったのだから、誰だって驚く。
というか……今走り抜けて行った人、一瞬しか確認出来なかったけど、見覚えがあった。まさかとは思うけど、考えたくも無いけど。声も、見た目も、私の知る人にそっくりだったのだ。
「どうした、沢田。まさか今の男、知り合いか!?」
「い、いやいやいや、まさかあ! 知らない、絶対知らない!」
そうだ、まさか。あれが弟のツナな訳ない。ツナはあんな奇声を上げながら、裸で、突っ走るような子ではない。寧ろそんな人を白い目で見て、例え知り合いでも遠ざかっていくような子だ。幾らなんでもありえない。
そうだ、あれがツナな訳はない。あんなのと弟の姿を重ねるなんて、私は酷い姉だ。
一瞬でもツナだと疑ってしまった自分を恥じていると、再び前方から激しい足音が聞こえて来た。
「あれは先程の男!」
「えっ……」 笹川君の声と共に、前方の曲がり角から顔を出したのは、いつも見ている、あの、顔だった。
「や、やっぱりツナ……!」
信じたくはないが、真正面から走ってくるのは、やはり私の知っているツナだった。こうして正面からはっきりと見たのだ。流石に見間違えるはずが無いが、その尋常ではない様子にやはり別人ではないのかと疑ってしまう。普段のツナを考えると、結ぼうとしても結びつかない程に、様子がおかしいのだ。
「おい! 待て! 危ない!」
笹川君が叫んだ。その声に私は考えるのを止め注意を周囲に向ければ、右方向からトラックが向かってきていた。しかしツナはそれに気づかないのか立ち止まる様子は無い。すさまじい形相で叫びながら一直線にこちらに向かって走ってきている。お互いこのままの速度では間違いなく衝突してしまうだろう。
「駄目、待って! ツナ! 止まって!!!」
あれがツナだろうが、ツナじゃなかろうが、流石にまずい。慌てて制止を求め叫ぶが、遅かった。
トラックも、ツナも、徐行する事無く、交わる。
聞いた事もない大きな、衝突音。
何事も無かったかのように通り過ぎて行くトラック。
そして、目の前には――。
「あの熱血野郎、どこに行った?」
「……へ?」
誰もいなかった。