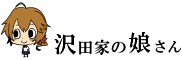じりじりと照りつける太陽。コンクリートは熱を帯びて鉄板のように熱くなっている。その熱さと言えば、黙って突っ立っていたら身が焼かれるのではないかと疑ってしまうくらいだ。
そんな暑さの中、外で体育の授業を終えた私は完全にへばっていた。
汗は拭っても止まらず、着替えた制服が肌にぺっとりとくっついてしまい気持ちが悪い。
早く教室に戻って涼もうと思ったものの、教室はクーラーがきいているとはいえ、人が多い為かあまり涼しさを感じられない。まあ、こうして廊下にいるよりはマシなのだろうが。
しかし、こんな調子ではお昼なんて食べられる気がしない。体育は嫌いではないけれど、夏の4時間目に外で体育をさせる神経はどうかしていると思う。食欲がごっそりとはぎとられるのが分からないのだろうか。
「だらしねえな、ソラ」
覚束ない足取りで廊下を歩いていると、子供の声が耳に届いた。顔を右に向けてみると、壁がシャッターのように開き、そこからリボーン君が出てくる。
突っ込まない。突っ込まないぞ。どうして学校にいるのとか、何勝手に校舎を改造しているのとか、言いたい事は色々あるけれど、私は断固として突っ込む気は無い。そもそも彼に突っ込んでいたらきりがない。今後も極力スルーしていく方向でいくつもりだ。
「放っておいてよ。元々私は運動得意な訳ではないんだから」
私が口をとがらせると、リボーン君は「だらしねえな」と繰り返した。
「まあ良い。午後の授業に差し支えると困るからな。俺が涼しい場所に案内してやるぞ」
「涼しい場所?」
私が首を傾げると、リボーン君が飛んでくるのでそれを抱きとめる。暑いけれど、リボーン君は可愛いし抱き心地が良いので、まあ良い。
「向こうだ」
リボーン君に促されるままに、私は廊下を進んでいく。
彼はこの学校の生徒でも無いのに、どうしてこんなに校舎の事に詳しいのだろうか。いや、そんな事を疑問に思う前に、リボーン君の存在自体疑問に思った方が早いのかもしれない。
最近はどんな事でも「リボーン君だし」で解決出来るようになってきている時点で色々と問題だと思う。
「ここだぞ」
「ここだぞって……応接室しか見えないんだけど」
「ああ。ここなら人もいないし教室よりも狭いからクーラーのききも良い。涼むなら絶好の場所だぞ」
「え、あ、いや、応接室って確か、風紀委員の」
「そこで何してるの、沢田ソラ」
「何って、リボーン君に連れてこ……」
そこで、第三者の声が割って入って来ていた事に気づき、私の体は固まる。
この声は。言わずもがな。
「よう、雲雀」
「やあ、赤ん坊」
悠々と挨拶を交わす二人と反して、私の心中は穏やかではない。どうして最近はこう、いつもいつも危険地帯に飛び込む事態に陥っているのだろうか。
「ご、ごめん。直ぐ帰りますので、うん」
「何言ってんだ、ソラ。応接室で涼んでいくんだろ」
「へえ、そうなの、沢田ソラ」
「いやいやいやいやいや!?」
手短に会話を済ませ立ち去ろうとしているというのに、リボーン君が余計な事を言ってくれる。彼は私をどうしたいのだろうか。単に面白がって意地悪しているだけなのだろうか。
「こいつ暑がってへばっちまってな。教室のクーラーじゃ涼しさを感じないから、もっと涼しい場所に連れてけよガキってうるさくて」
「言ってないよ。絶対そんな事言ってないよ、私」
「ワオ。君って案外傲慢なんだね」
「信じないでよ、雲雀君」
つい突っ込みを入れてしまい、私は口をつぐんだ。
恐る恐る雲雀君を見ると、彼はいつも通り涼しげな笑みを浮かべている。良かった、怒ってはいないみたいだ。
「ま、そういう訳だから雲雀。応接室で昼飯食わせてもらうぞ」
「はあ!? 何言ってるの、リボーン君! 大体私のお弁当は教室にあるから」
「だから俺が持ってきてやったんだぞ、有難く思え」
リボーン君は、何処からともなくお弁当の包みを出す。間違いなく私の物だ。しかし、一体今まで何処に収納していたのだろうか。というより、何で私のお弁当箱をリボーン君が持っているんだ、この子は。
私が当惑していると、雲雀君が鼻を鳴らす。
「まあ、良いよ。勝手にしたら」
「ほら、雲雀君も駄目って言って……はい?」
私が雲雀君の方を向けば、彼は応接室のドアを開けて中に入ってしまう。
え。今、勝手にしたらとか聞こえたんだけど。
「さ、飯食うぞ。ソラ」
「え……ええええ?」
てっきり追い払われると思ったのに、どういう事なのだろうか。状況に頭が付いていけない。
呆気に取られて立ちつくしていると、急かすようにリボーン君が私の腕を叩いて来た。止むを得ない状況にいる事だけは理解出来たので、私は応接室へと踏み込むことにした。
閉じかけたドアを開けば、ひんやりとした空気が漏れてくる。その冷気は火照った体には、とても気持ちが良い。確かにこれは、多少危険を冒してでも入室すべきなのしれないと思えてくる。
入口で突っ立っていると、奥にある椅子に腰かけた雲雀君がじろりと見て来た。
どういう意味の視線なのか分からなかったけれど、何か言われる前に慌ててソファに座る。そうすると彼は私から視線を外して窓の外を見やった。よ、良かった。これで合っていたらしい。
しかし、落ち着いて応接室内を見ていると、何かおかしい。普通応接室ってソファとローテーブルくらいかと思うのだけれど、どうして書斎机やら本棚やらが置いてあるんだろうか。幾らなんでも風紀委員だからって何でもあり過ぎやしないだろうか。まあそれを本人に言う勇気なんて、私は微塵も持ち合わせていないのだけれど。
「えっと、じゃあ、ここで食事しちゃっても……?」
確認の為、雲雀君に伺う。
「すれば。僕の気が変わらないうちに」
急いで食べよう。気が変わったらどうなるのかは考えない方向で。
暑いからではなく、別の意味で流れてくる冷たい汗を背中に感じつつ、私はお弁当の包みを開いた。
そこでふと、ある事に気付く。
箸を取る手を止めて、私は雲雀君の方へ視線を投げた。彼は相変わらず、窓の外を眺めている。
「雲雀君はご飯食べないの?」
「食べたよ」
けろりと雲雀君は言ってのけた。
いやいや。食べたよって。私達のクラス、今まで体育だったじゃないか。
そうは思ったけれど、相手は雲雀君だ。彼が真面目に授業を出る所はまだしも、この暑い中体育を楽しむ姿なんて想像が出来ない。
ここは深く追求すべきではないと判断し、私はお弁当に箸をつけた。