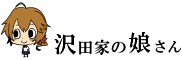「あ、そうそうソラちゃん。ちゃんとお礼しなきゃダメよ」
夕飯で食卓を囲んでいる最中、突然母さんが言った。とっさの事で何の話か分からなかった私は、ツナと一緒に首を傾げる。
「なに、ソラ姉なんかあったの?」
「それがねぇ! 聞いてよ、ツッ君! ソラちゃんったら今日ね、体調が悪いとかで学校の男の子に送ってきてもらったのよ」
「ちょっと母さん!」
その話か、と気づいて慌てて箸を置き間に割って入る。
実を言うと笹川君に送ってもらっている時に、運悪く帰路についていたらしい母さんと鉢合わせしてしまったのだ。不幸中の幸いに、ツナは母さんと並んで帰るのは恥ずかしいとかで母さんとは別々に帰っていたから遭遇しなくて済んだのに、ここでバラされてしまっては意味が無い。
とはいえ、やたら楽しそうに盛り上っちゃってる母さんの口は、止まりそうもなかった。
胸の前で両手を合わせ、うっとりとした表情で虚空を見つめるその姿は、まるで恋する乙女のそれだ。
「すごく逞しくて元気で素敵な男の子でねー、ソラちゃんの事軽々抱えちゃっててすごかったのよぉ」
「へえ〜」
「へえ〜じゃないわよ、ツッ君。もしかしたら将来ツッ君のお義兄さんに」
「なっ、なりません! ただの同級生だから!」
声を張り上げると、意外にも母さんは素直に聞き入れ黙った。しかしその顔は楽しげに輝いている。
ああ、駄目だ。完全に勘違いしてる。確かに、あの時はどきどきしてしまったけれど、私は笹川君にどうこうするつもりは別にない。
とはいえ、母さんはそんな事は知る由もない訳で、説明した所で聞く人ではない。こうなってしまったら、母さんの誤解は簡単には解けないだろう。
「とにかく、お礼はちゃんとしなくちゃ駄目よ? 分かった?」
「分かったってば……」
瞳を輝かせる母さんに、半ば投げやりに返事をして私は茶碗を持ち直した。
二日後の昼休み。
母さんに言われたからというのもあるけれど、私としても笹川君への感謝の気持ちは強いのもまた事実。
と言う訳で私は今、例の“お礼”を持って笹川君の教室前にいた。
「笹川君いますか」
教室に入ろうとしてる女子を捕まえて、笹川君を呼んでもらう。
丁度お弁当を食べ終えたらしい笹川君が、お弁当箱を片付けてから元気良くこちらに走ってきた。明るい表情が、いやに眩しい。そんな彼を見ていたら、何故だか段々と手が汗ばんでくる。
お礼をするだけだというのに、何を緊張してるんだ、私は。頭ではそう分かっているものの、ひとたび彼を意識してしまった私の体はどんどん強張ってしまう。一体どうしたっていうの。
「どうした、沢田! 俺に用か!」
いつの間にか目の前まで来ていた笹川君が、元気よく言った。その声はびっくりする程に大きく、教室はおろか、廊下にいる生徒までこちらに注目しだす。
「いや、あの、えっと」
やだ、どうしよう。ただでさえ緊張してると言うのに、周囲からの視線で余計に緊張してきた。
しかし笹川君は周囲なんて全く気にしていないようで、不思議そうにこちらを見つめてくる。この人の頭の中はどうなってるんだろう。一度で良いから覗いてみたい。
「なんだなんだ告白か〜?」
私がもじもじとしていると、何処からともなく、そんな野次が飛んできた。
一気に顔に熱が集まる。まずい、信じられないくらい顔が熱い。鏡を見なくても分かる。私は今、すごく顔が赤くなってるに違いない。
でも駄目だ。このままこうしていたら、どんどん周囲に誤解されてしまう。別に私は笹川君が好きとかいう訳じゃない。ただ単に助けてくれたお礼が言いたいだけなのだ。そう、それだけ、それだけなんです。
大丈夫、簡単な事でしょ。後ろ手に持っている、この包みを笹川君に押しつけて、一昨日はありがとう!助かった!じゃあね!って言えば全部終わりなんだから。
なんだ、本当に簡単じゃないか。そうと決まれば早く本題に入りさっさと教室へ帰ろう。
そう決意し、勢いよく顔を上げる。
「笹川君! 一昨日は……」
しかし。
意を決し顔を上げた視線の先にいたのは、顔はおろか耳まで真っ赤にした笹川君だった。
それは予想外の反応で。
驚きのあまり、私は口を開けたまま、次の言葉が出てこなくなってしまった。
「こっ、こここっ、告白だと!? そうなのか沢田!?」
「ち、違うよ! 告白じゃないから!」
笹川君の放った大きな声で我に返り、私も負けじと周囲に聞こえるように声を張り上げる。
笹川君は顔を赤くしたまま、さらに上をいく声を出してきた。
「じゃあ何だ!?」
「いや、えっと、大した事じゃないんだけど、何かギャラリーが多すぎて言いにくいというか!」
つられてさらに大声になってしまう。そんな私を見て笹川君は目を見開いた。あ、何か嫌な予感がする。
「分かったぞ、沢田! 勝負か!? 俺とボクシングで勝負したいんだな!」
「ええ!? 違う! 全然違うよ、笹川君!!」
「よし! ならば付いてこい!!」
「えええ!? だから違うの、ちょっと待って!!」
言うが早いが笹川君は壮絶な誤解をしたまま、走り出してしまう。分かってはいたが、本当に人の話を聞かない人だ。そして気がつけば、私は考えるよりも早く体が動き出していた。ぼんやりしていると姿を見失ってしまいそうなくらいの速度で走る笹川君を必死に追いかけている私がいる。
ああ、私、何しに来たんだっけ。なんでこんな事になってるんだろう