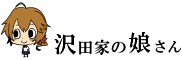「それは強いの?」
雲雀君の訳が分らない問いに首を傾げる。
「ソラは戦えねーぞ。手は出すな」
リボーン君が答えた。どうやら、私の話らしい。雲雀君は不機嫌そうな顔になる。構うことなくリボーン君は続ける。
「ソラは、お前のクラスメイトだぞ。知らないのか」
「へえ。そうなの。初めて知ったよ」
うわ。やっぱり。分かってはいたけれど、こうもあっさりと知らないなんて言われるとは。流石、雲雀恭弥だ。ショックを受けると言うよりも、納得してしまう。
「そうか。じゃあこれからは忘れるな。覚えておけ」
ぴくり、と、雲雀君のこめかみが動いた。私は思わず汗ばむ手を堅く握った。
明らかに、雲雀君は怒っている。
そりゃそうだ。今のはリボーン君がおかしい。いや、普通ならクラスメイトの顔も知らない方がおかしいけれど、相手は雲雀君だ。一般的な道理が通るような人じゃない。大体雲雀君が私を人間として認識しているのかも怪しいくらいだ。
「気に入らないね。僕は人の指図は受けない」
「そうか。じゃあ良い」
意外な事に、リボーン君はあっさりと引いた。
「俺に用がある時はこいつを通して貰おうと思ったんだがな。嫌なら良い」
「えええ?!」
「今まで通り、お前からは俺にアポイントメントを取る事は出来ないままだが、仕方ねえよな」
「ええええええ!?」
ちょっと待て。私、そんな話は聞いてないぞ。
目を白黒させる私に、当然雲雀君は不機嫌丸出しな顔を向けてくる。そんな顔をされても、困る。私だって出来れば辞退したい。
「これと仲良くしろって言う訳?」
「そんな事は言ってねえぞ。ソラはただの連絡役だ」
「じゃあ痛めつけても構わない訳だ」
「傷つけたら今後一切、お前とは会わない」
有無も言わさぬような、凛とした声でリボーン君は言い放った。理不尽としか言えないその言葉に、雲雀君は顔を歪ませる。
「それは肉体的な意味で?」
「傷つけたら許さない」
「……それを僕に言う訳?」
「じゃれ合う程度なら大目にみるぞ」
場の空気を読まず、リボーン君が明るい調子で言った。顔を覗きこむと、にやりと楽しそうに笑っている。この状況で。この子は。
「気に入らない」
再び、否定的な言葉。とはいえ、私だって、雲雀君と同意見だ。こんな理不尽な話、雲雀君に通るはずが無い。っていうか、怖いから辞退したいんだってば。
「僕に指図する奴なんて、赤ん坊。君くらいだ」
「だろうな」
「君ってずるいよね。僕の選べる答えを一つしか用意してない」
「まあな」
「でも、良いね。気に入らないけど、僕に対して、こんな事言うの君だけだ。ますます君に興味が沸いたよ」
雲雀君は、楽しそうに口角を上げた。
「君、なんだっけ」
「え?」
「名乗りなよ。覚えてあげるから」
雲雀君が、真っ直ぐ私に視線を合わす。こういった目を向けられるのは、多分、今日、初めてだと思う。
「あ、ええと、さ、沢田ソラです」
「沢田ソラね。分かった」
もう夏へと差し掛かっていると言うのに、クラスメイトと自己紹介するという不思議なやり取りをする。
タヌキにばかされているんじゃないだろうか、という奇妙な気持ちで、雲雀君の顔を見た。すると先程とは打って変わって、雲雀君の表情が柔らかい物になっているのが見て取れる。どうやら、雲雀君はリボーン君のむちゃくちゃな提案を受け入れたらしい。
本当に、リボーン君って何者な訳。
「そうだ。これ、返すぞ」
リボーン君がトンファーを出す。そうそう。私達はこれを返しに来たのだ。
しかし雲雀君は、ゆるゆると首を振った。
「いらない。スペアだから」
「す、スペア?」
「うん。分かってて持って行かせた」
雲雀君が笑うと、リボーン君もふん、と鼻を鳴らした。
「知ってる」
「えええ?!」
私がその発言に驚いていると、雲雀君も同じなのか、軽く目を見開いていた。
「やっぱり君、面白いね」
機嫌良さげに、雲雀君は笑った。
どうやら、トンファーを返す事など、目的ではなかったらしい。私も雲雀君も、リボーン君に踊らされていたようである。
「食事をお持ちしました」
ひと段落着いた所で、草壁君の声。
ふすまが開かれると、着物を着た女の人達が食事を運んでくる。お手伝いさんの人だろうか。所謂、メイドって奴?
決して華美ではなく、けれど高価そうな食器に盛り付けられた食事が、目の前に並べられていく。その配膳の仕方は完璧に形式ばったものだったので、私は再び委縮した。
和食は食べ慣れているが、正式な作法なんて、私は覚えてない。当たり前の話だが、海外のテーブルマナー同様、和食にもテーブルマナーは存在する。私だって箸の持ち方くらいは分かる。が、私の年齢くらいだと意外と知らない人も多い。持つだけならまだしも、使い方にも当然正解がある。下の箸は動かさず上の箸だけを動かすのが正しいように、マナーというものは細かく設定されているのだ。
辛うじて箸の事は分かるけれど、他はそうもいかない。刺身ひとつにも、食べ方は存在するし、お椀の開け方だってある。先程上げた箸だって、取り方があるし置き方もある。
けれど、そんなの聞いた事があるだけで、さっぱり覚えて何かいない。
「食べれば」
さっさと食事を始めていた雲雀君が、言い放つ。
私はおろおろとしながら、お箸を持ち彼を見た。
雲雀君は流れる様な手つきで食事を進めている。それは私が普段食べているような動きとはかけ離れていて、上品で綺麗だ。恐らく、しっかりとした作法で食べているのだろう。
待って。この場所で、この人と、こんな状態でどう食事しろと。
「普通で良い」
「え」
「君には欠片も期待してないし興味も無いから、普通に食べなよ」
「は、はい」
私の気持ちを察したのか、どうでも良さそうに雲雀君が言った。
リボーン君が、ぽんぽんと私の膝を叩いてくる。
「ソラ。俺、あのピンク色の奴が食いたいぞ」
「はいはい」
相変わらずマイペースなリボーン君の言葉に、幾分か気が和らぐ。まあ、くつろいで食べるとまではいかないけれど、先程よりはましだ。
急かすリボーン君の言う通りに、食事を箸で切り分けてリボーン君の口へと運ぶ。私も好きな物をとって食べると、なるほど美味しかった。
「次はあれが良いぞ」
「はいはい」
「早くしろ」
「もー、分かったから急かさないでよ」
「……ふーん」
雲雀君が意味ありげに声を漏らしたので、私は顔を上げる。
「な、何か?」
「別に」
質問を許さないような返事が戻ってくる。やっぱり私には気を許してはいないらしい。私の視線を無視して食事を再開してしまったので、私も同様に食事を続けた。
食事はとても上品な味で、私には勿体ないくらいだった。